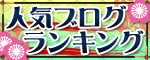黒澤明監督の『7人の侍』という映画がありました。この映画の中で面白い話があります。村人がいて、一生懸命作物をつくります。その村は惣村(そうそん)といって、独立している村だったのです。
このような惣村(そうそん)は、領主と契約をしたのです。領主がいきなり惣村(そうそん)に税金をかけたのではなくて、村長が領主と話をつけて、「今月は、これくらい税金を納めればよいですか?」と聞いて、話し合いで税金を決めたのです。
そのような独立した村を惣村(そうそん)と言ったのです。領主に税金を納めて「これで安心だ」と思うと、野伏(のぶし)という野武士がやってくるのです。「ヒヒィ~~~ン」と馬に乗り惣村(そうそん)を襲ったのです。
すると、「うわー、のぶせりが来た!」と農民は逃げたのです。惣村(そうそん)の中に野伏が馬でやってきて、「村長はいるのか?」と行くと、「私が村長です」というと、「食べ物はあるのか? 全部出せ!」というのです。
「いや~、領主様に税金を納めた後なので、残っていないのです」というと、「なんでもいいから残ったものはすべて出せ!」と野伏が言って、税金を取っていくのです。「領主に税金を納めて、野伏にも税金を取られてしまって、大変だな。これで終わればいいのだがな」と思うと、野伏がまたやってくるのです。
野伏は村長に向かって、「おい、税金を出せ」というのです。「いや、みんな盗られた後で、何もないですわ」と村長が言うと、「そんなことはないだろう」と野伏がゴミあさりをすると、「ほら、まだこんなにあるではないか。米ももらっていくぞ。娘もいるじゃないか、もらっていくぞ!」ともっていくのです。
これが黒澤明監督の『7人の侍』のストーリーです。これと同じことが戦前の満州国でも行われていたのです。満州には、7つの馬賊がいたのです。一つの村に馬賊が襲ってきて、「おい、税金を出せ」というのです。
泥棒だとは言いません。「税金を出せ」というのです。村人が「いや、勘弁してください」と言っても、「うるさい!」と言って、蔵をあさって、残っているコメなどをかっぱらい、「また来るぞ」というのです。
「これで終わった」と思うと、他の馬賊がまた来るのです。「おい、税金を出せ」というのです。村長が「みんな盗られてもう何もないですわ」というと、「そんなことはないだろう」と言ってごみあさりをすると、「酒も米もあるじゃないか」と言われてとられてしまうのです。
それが、3回も4回も5回も来るのです。たまりかねて満州の人たちは、「ここに国を造ってくれ」と大日本帝国軍人に頼んだのです。満州は、国がないから税金を取りに馬賊の集団が何回もやってくるのです。
日本に愛新覚羅 溥儀(あいしんかくら ふぎ)が泣きついて、「私はかつて、大清帝国の皇帝だった。私は女真族であり、清国の皇帝は私なのだ。助けてください」というのです。
その話に乗ったのが、陸軍の石原莞爾です。「そうか、そんなにひどい状態なのか。国がないということは、そのようなことになってしまうのだな」と言って、国を造ったのです。それが満州国です。満州国は、愛新覚羅 溥儀(あいしんかくら ふぎ)に頼まれて造った国です。
日本軍が満州国を造り、後釜に入った瞬間に馬賊のゴロつきは、村人を襲うことはできなくなったのです。「満州国に入ったら、大変なことになる。日本軍が出てくる」とわかったのです。日本軍は強かったので、馬賊ではとても敵いません。
それで、満州国は安定して、五族協和の国を造ったのです。五族とは、日本人、朝鮮人、漢人、満州人、蒙古人です。五族が協和して作った国が満州国です。
この話を見ていると、本当によくわかります。税金とは、どのようなものでしょうか? 誰だって税金など払いたくありません。
天智天皇、または、天武天皇の御代に、奈良の平城京に向かって、5千キロのハイウエィが造られたのです。ものすごく立派なハイウエィです。道幅は、13メートルです。
道路には、木炭が敷かれて、水分を吸収するようにして、アスファルトを敷いて、5千キロにわたる古代のハイウエィを完成させたのです。それが、奈良時代です。
何のためにそのような道路を造ったのでしょうか? 答えは簡単です。その道路を造ったのは、全国から税金を納めるためです。
各地方には、豪族がいたのです。「天皇に税金を納めるならば、俺に納めろ」ということです。豪族が途中で税金を取ってしまうのです。それを天皇は嫌ったのです。「すべての税金は、直接、私のところへもってこい!」ということです。
平城京に税金を全国から納めるためには、道がありません。全国に通じる道を造ったのです。九州から、東北までの5千キロのハイウエィをつくったのです。これは、見事な道路だったと思います。
「わっせ、わっせ」と、人間が台車を引いてきたのです。その荷台には、お米や海産物などがたくさん詰まっていたのです。
それが毎日、送られてきたのです。日本の村々から、「天主様、ご用達」と書いてやってきたのです。古代のハイウエィから台車に荷物を運んでくると、何十キロ行くと、駅があったのです。
その駅では馬が休めて、荷物を運んでいる人が休憩できたのです。そのような施設があったのです。駅で休み休み行く目的は、奈良の平城京に税金を納めるためです。平城京に到着すると、朱雀門があり、その門をくぐりぬけると、大広場があったのです。
その広場には、全国から来た貢物が降ろされたのです。「わっせ、わっせ、天主様への贈り物だ」と言って門をくぐると、役人がいて、「●●村の甚兵衛か、入れ」と言われて、荷物を降ろしたのです。
筆で「●●村の甚兵衛から、米20キロが届けられた」と書いて、役人に渡したのです。その木簡が平城京跡から、出土したのです。
村人は、荷物を届けると、天平の美女の踊りを見て帰ったのです。「うわー、美しい踊りを見た、天主様はたいしたものだ」と思って帰ったのです。それが、天智天皇、または、天武天皇の時に造られた古代のハイウエィです。
NHKでもかつて放送されていたのです。古代のハイウエィは、天皇へ貢物を届ける道だったのです。朱雀門を通り、平城京には、お米も海産物も届いたのです。それを天皇が一人で食べられるわけがありません。「よし、あの豪族を呼べ、お前にはこれをとらせる」というと、豪族は「はっはー」となり、天皇に忠誠を誓うのです。
天皇は、「お前のところは、海産物がなかったな。これをあげよう」「お前のところは、米がなかったな。これをあげよう」と言って、天皇の周りに集まった豪族に分け与えたのです。
すると、豪族は、天皇に対して忠誠心が芽生えるのです。「ありがたい天皇陛下だ。貢物を分けてくれるのだから有難い」と思うのです。
これが天皇の始まりです。今と違ってお金がないから、現物で集めた物を貴族や、豪族に分け与えたのです。天皇がいないと、地方にいる豪族が税金を取ってしまいます。豪族は、「俺のところに税金を納めろ。天皇にもっていくだと? そんなものは、これだけでいいだろう」と勝手に判断して、自分に納めさせるようにするのです。
古代のハイウエィを造ることによって、日本全国の富、日本全国の力が天皇に集まったのです。これは、経済面から言うと、天皇制の力です。それが今でも続いているのです。(②に続く)
お読みいただきありがとうございます。
よろしかったらクリックしてください。
応援よろしくお願いします!
↓↓↓
※今年から、『中杉 弘の徒然日記』は、月曜日から、金曜日まで掲載します。
土曜日(0:00)は、正理会チャンネルをご覧ください。
■新番組「中杉弘の毒舌!人生相談」、第2回は、2月18日0:00公開!
是非、ご覧ください!
↓

■『正理会ちゃんねる』は、土曜日連載中です。
第14回目のお話は、「仏教とユダヤ教」です。
2月18日(土曜日)0:00公開!
↓

■『中杉弘のブログ』2006年より、好評連載中です!
↓↓↓
http://blog.livedoor.jp/nakasugi_h/?blog_id=2098137
■『中杉弘の人間の探求』にて、「法華経入門講義」を連載しています!
こちらもご覧ください。
↓↓↓
https://ameblo.jp/nakasugi2020