僕が剣道を習ったのは、中学2年、3年、高校1年の時です。当時、学校には剣道部はなくて、僕の親父は講道館の武道家です。剣道を習おうと思っても学校にはないのです。仕方ないので北辰一刀流の金子道場に入門したのです。だから、僕の年齢で剣道を修行した人は本当に少ないと思います。僕は剣道を一生懸命やったのです。それも、「県大会に出て全国制覇する」というものではありません。スポーツ剣道は、私にとって縁がないのです。
全国大会で優勝したり、インターハイで何位になったとか、そんなことをいくらやっても意味がないのです。この間も神奈川県警で全国大会1位になった剣道5段の警察官が、高校生を脅かして「裸の写真を送れ」という事件があり、捕まりました。
現職の警察官で剣道5段までやって何をやっているのでしょうか。剣道などいい加減な気持ちでやっていると棒ふり剣道になってしまいます。竹刀をふりまわしても何も意味がないのです。
剣術は役に立つまでやらないとダメなのです。優勝などできなくてもよいのです。でも、3年修行したら役に立つというものが身に付かないとダメなのです。僕の孫も剣道をやらせていますが、そのようなことを教えています。「優勝などしなくてよいのです」ある程度までいったらやめていいのです。今でいうと3段くらいだろうと思います。後は別にやらなくてもよいのです。
では、何が違うのかというと、それをやることによって全く違う自分が形成されるのです。「男には7人の敵がいる」表に出ると7人の敵がいるのです。それを専門にした暴力団もいます。朝鮮人もいます。恐ろしいものがウロウロいます。そのような世の中で何を武器にして渡っていくのでしょうか。
その時に、僕は「剣術だ」と感じ取ったのです。剣を抱いて、人生を渡るのです。朝堂院大覚先生も『一人一刀』というブログを持っています。「日本人は、日本刀を持たなければいけない」と言われています。それは僕も正しいと思います。
そして、神道の話をしますが、日本神道には、三種の神器があります。鏡・勾玉・草薙の剣です。これが皇室を形成した3つの宝物です。何を物語っているのでしょうか。鏡とは「己を見てかんがみよ」ということなのです。「かんがみる」とは、「反省しろ」ということです。
お前は今、どのような姿をしているのか、「デブになったのか。お前は前からそんなに醜かったのか?」と、鏡を見て醜くなった自分をかんがみて、「これではまずいな」と反省していくのです。顔も太るとブルドックのようになってしまいます。「はずかしい」とかんがみるのが、鏡なのです。
僕の知り合いに、白根というキチガイがいましたが、絶対に鏡を見ないのです。60歳過ぎたオジサンなのですが、「二十歳だ!」と言い張るのです。「鏡を見て来い」と言っても、絶対に鏡を見ないのです。鏡を押し付けても見ないのです。そのようにならないように、鏡を見ることは非常に大事です。
そして、勾玉とは、どのようなものかというと命を現しています。勾玉は命の代表です。この世界にある草木・動物・人間、様々なものが生きていますが、全て「命の根」があるのです。「命は一つ」だと言っているのです。これを現しているのが勾玉です。命という目に見えないけれども存在する、この力の源のことを勾玉と言っているのです。「ああ、そうか。みな命があるのだな」ということを、勾玉が象徴しているのです。
そして、生きていくためには、武器を持たなければいけません。ライオンでも爪や牙があります。それで生きていくのです。人間も生きていくための武器を持たなくてはいけません。「それは、剣だよ」ということを教えているのです。それが草薙の剣です。
この三つが皇室をつくってきたのです。自分が良い政治を行っているか「かんがみる」のです。「命を大切にしているか?」と勾玉を見る。そして、「剣を持って、勇気を持って戦ってきたか?」と草薙の剣を見る。三種の神器はそのような意味があるのです。
外国にも剣や槍もありますが、外国の刀は全て凶器です。動物を殺して、弱い者をしいたげていく凶器が剣なのです。朝鮮半島では、刀などないのです。鉈(なた)と同じです。鉈が即刀なのです。台所に転がしておくのです。戦になると、それをかついでもっていくのです。中国の青竜刀も凶器です。青竜刀は、重さでぶった切るのです。
青竜刀を大事にして床の間に飾るなどという話は、聞いたことがありません。青竜刀のような不格好な物をどうやって飾るのでしょう。西洋の剣も力任せに振り下ろすもので、これらは、全て凶器なのです。
日本だけが、この剣を「聖なるもの」として扱ったのです。聖なるものであるから、命を取ることができるのです。「剣には、神霊が宿るに違いない」と、日本人は考えたのです。だから、一生懸命に剣を磨いて、最高のものをつくってきたのです。出来上がってきたのが、日本刀です。日本刀は神なのです。神に近づくために一生懸命になって頑張ってきて、世界に冠たる日本刀をつくったのです。それは、日本人が剣を神と崇めてきたから、そのようなものができてきたのであって、それが今に伝わっているのです。
この剣というものを、扱う業を教えたのが剣術です。単なる凶器ではないのです。一撃必殺、抜いたら最後です。これは恐ろしいなどというものではないのです。
「益荒男(ますらお)がたばさむ太刀の鞘鳴(さやな)りに幾とせ耐へて今日の初霜」と詠んだ、三島由紀夫の気持ちがよく分かるでしょう。これを抜いたら最後です。刀をぬかない。魂をそこに閉じ込めておく。「魂が出たい」というのですが、「待て!」ということです。腐りきった日本を直したい。今でもすっ飛んで刀は出たいのですが、まだ抜かない。「幾とせ耐へて」とは、「まだまだ耐えて、今日初めて使うぞ!」と思って自衛隊に乱入したのです。
そのような心境なのです。刀というものは、凶器ではなく、神様なのです。剣術も、神の術を習うという気持ちで、必死で修行しなければ役に立ちません。そのように考えて修行すればよいのです。
勝海舟の御父さんの勝小吉は、「お前、本当に修行するならば剣術を修行しろ」ということを言い、勝海舟は剣術の修行を始めたのです。「その代り、本当に修行をしたならば、絶対に人に斬られることはなくなる」これが、勝海舟の極意です。勝海舟は、一生の間に40数回斬りつけられています。しかも、自分は刀を抜けないように紐で結んで刀が抜けないようにして持っていたのです。
岡田以蔵が護衛についている時に、二人の暴漢に襲われるのです。岡田以蔵は天才ですから、斬ってしまうのです。「何故、斬ったのだ!」と、勝海舟が言うと、「私が斬らなかったら、先生斬られていましたよ」と岡田以蔵が言ったのです。それには二の句もなかったという話が残っていますが、本当は大丈夫だったのです。勝海舟は、初太刀をはずすのです。そのくらいの能力はあるのです。それから、「待て!」とやらないと、口先だけで「待て!」と言ってもダメなのです。
勝海舟は、40数回斬りつけられて、体にも傷があったそうです。それと、反対の修行したのが、坂本竜馬です。坂本竜馬は、北辰一刀流です。僕も、北辰一刀流です。竜馬は、北辰一刀流の修行をしたのに、心にスキがあったのです。刀を神としてお祀りしていなかったのです。竜馬は、「邪魔なもんだ」と床の間に刀を放り投げていたのです。拳銃は持っていたのです。
「拳銃も刀も道具で、刀はもう古いんだよ」と考えていたのです。だから、床の間に放り投げていたのです。そこに、刺客に斬り込まれたのです。振り向いた瞬間に斬られたのです。長い刀ではなく脇差です。眉間を一発めでやられてしまったのです。急いで床の間に行って刀をつかんで二撃目を鞘(さや)をつかんだまま受けたので、刀が三日月形に斬れているのです。そのくらい腕がよかったのです。それで、やられてしまったのです。
剣術の奥義からいうと、竜馬は修行が足りなかったということがいえるのです。勝海舟は、ちゃんと修行を積んだから一度も斬られることがなかったのです。これが、剣道と神道の考え方の面白いところだと思います。
『中杉 弘のブログ』2006年より、好評連載中です!
↓↓↓
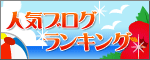
人気ブログランキングへ