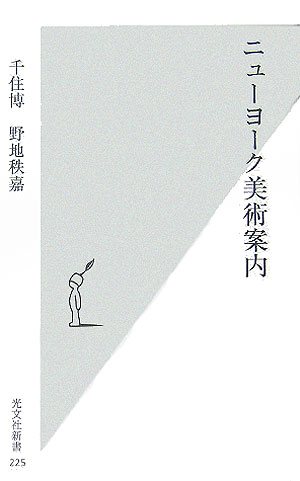良い解説者とともに絵を見るということ ――『ニューヨーク美術案内』とゴッホの絵筆
千住博さんと、作家であり美術プロデューサーでもある野地秩嘉(のじ・つねよし)さんの共著『ニューヨーク美術案内』は、美術館を「名画の倉庫」ではなく、思考と感情を導いてくれる場所として案内してくれる一冊です。
神戸で開催されたゴッホ展を訪れ、私は改めて思いました。
なぜ、あれほど人の心を揺さぶるのか。
なぜ、人は無意識のうちに顔を近づけ、食い入るように画面を覗き込むのか。
山に登るときにガイドがいるように、絵を見るにもよい解説者がいる。
そのことを、この本は静かに教えてくれます。
ゴッホの絵が「古びない」理由
ゴッホは、とても不器用な人だった。
貧しく、つましく暮らしていたけれど、絵の具だけは最高級のものを使っていました。四歳年下の弟テオが、兄に最良の絵の具を使わせるために援助していたのです。
だから、百年以上が経った今でも、ゴッホの絵は剥落も変色もほとんどなく、まるで先ほど描きあげられたばかりのような艶を保っています。
しかも彼は、その高価な絵の具を節約することができなかった。
器用に練り合わせ、薄く伸ばす——そんな要領のよいことができない性格だった。
だからこそ、惜しげもなく、正直に、絵の具を置いた。
「塗った」場所が、どこにもない
ゴッホの絵には、
「ここは適当に塗った」という場所が、一筆たりともありません。
画面の隅から隅まで、すべてが「描かれている」。
細い筆で、藁の束をひと束ずつ積み上げるように、丹念に絵の具を重ねていく。
この執拗とも思える仕事は、
ゴッホにとって神と対話する行為だったのではないでしょうか。
描きながら、自らの仕事を神に問いかけ、確かめていた。
だから人は、思わず顔を近づけてしまうのです。そこに、祈りに近い密度があるから。
ゴッホは狂気ではなく、希望だった
ゴッホを「狂気の画家」と呼ぶ人がいます。
けれど千住博さんは、そうではないと言います。
確かに彼は不器用で、冗談も通じにくい男だった。
しかし、色の選択、絵の具の使い方を見れば、それが正常な判断の産物であることは明らかだ、と。
なによりゴッホは、希望を捨てなかった人でした。
夜の絵でさえ、暗さの中に温かさがある。
悩める老人の姿も、優しい筆致で描かれ、そこには未来への光が差し込んでいる。
もし絶望だけを見ていたなら、
あのパステルトーンは選ばれない。
どの作品にも、良心が満ちている。
邪心も、皮肉も、ブラックユーモアも、画面からは感じられない。
純粋さが、そのまま絵になった人——それがゴッホなのだと、作品そのものが雄弁に語っています。
解説とともに絵を見る喜び
『ニューヨーク美術案内』は、
「知識をひけらかす解説」ではありません。
見る側が、自分の感じた揺れを言葉として受け取るための橋を架けてくれる本です。
絵は、ただ眺めるものではなく、
対話するもの。
良い解説者がそばにいるだけで、
その対話は、驚くほど深く、豊かなものになります。
ゴッホの絵に近づいてしまうあの衝動は、
私たちが無意識のうちに、誠実さに触れようとしている証拠なのかもしれません。