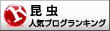前にお邪魔させていただいた舘野スケッチラボ。
下北沢のダーウィンルームで開催されているのですが、
あまりに楽しすぎたので、先日2回目に参加してきました!
スケッチラボには小1~4年まで対象の子供の回と、それ以上向けの大人の回があり、
前回は子供の回に娘と息子が参加しました。
が、今回は私が行きたすぎたため『また子供の回がいい!』と言う娘を半分強制的に大人の回に同行させ、
娘と二人で参加しました。
ごめんよ娘・・・。
で、大人の回なので息子の方は父に任せて置いていきました。
そんなこんなで始まったスケッチラボ。
私は一発目にちょっと可愛い虫を見つけてチャレンジしてみたら、
小さく描き過ぎて撃沈でした。
(写真は3倍ぐらいに拡大しています)

ただ、先生にこの黒い部分の質感の出し方を見本付きで教えてもらい、
次の虫でがんばろうと心に決めたのでした。
ちなみにこの虫、何でこんなにひっかかりが細い後ろ足なんだろうなと思っていたら
糞虫だった。
・・・前足の形とかで何となく予想してたけど(フンコロガシに似てる)、やっぱりか・・・。
糞虫と言われると急に触りたくなくなるんですが、
でも糞虫って触ってもいいと思えるぐらいかわいい虫が多いのはなんでなんだろうか。
「あっこの虫けっこうかわいいかも?!」
『かわいいでしょ?さわってさわってー』
ピタッ
『やーいひっかかったー!オレ糞虫だもんねー。オマエウンコ触ったのと同じだー!やーいやーい』
「げげっ!!」
っていう遊びっていうか小学生的イジメをしたいんだろうか。
うーむ。
先生は他にも凹凸物に対する光の当たり方を解説してくださったり、
絵をちゃんと習ったことのない私には全て目からウロコでとっても勉強になりました。
このスケッチラボ、プロの作家さんに絵を教えてもらえるというのが一つの魅力ですが、
舘野先生の話が超おもしろいというのも大きな魅力。
今回はオサムシ好きな少年のために、オサムシの亜種の分布を解説していた。
亜種の見分け方はオスの○○○の形。
いきなりそこかよ!!
そして喜ぶ子供たち(娘含む)。
東京から西に行くにしたがって、その形が変わるらしい。
「最初はこういう形をしてるんだけど、こっちに来るとこうなって・・・」
「こっちのは形は一緒だけど長くなってー」
「伊豆半島を下るとこういう形になって・・・」
次々と出てくる○○○の図に娘ウケる。
先生は全部を図解していらっしゃるんですが、その知識と記憶量が半端ない。
よく覚えてますねと言ったら、全部自分で採集して確かめたんだそうだ。
「中部まで来ると、今度は山の方(多分木曽山脈)から来る種類と混血して形が変わる」
え、そんなに形違うのに混血できるんだ?というところに驚く。
「この辺はルイスオサムシじゃないんですか?」
ここでオサムシ博士の少年が加わる。
「いやそれはもうちょっとこっちの方かな」
なんかすごい会話・・・。
ルイスってえらい日本らしくない名前だな。
「で、大阪の金剛山にはドウキョウ(道鏡)オサムシというのがいて・・・」
「これだけ○○○のサイズが腹の部分の2/3もある!」
「ぎゃははは!」
この笑ってる声は主に娘。
道鏡って、昔女帝に取り入って出世街道を駆け上がった僧侶のこと。
この命名のセンスは侮れない。
長くなるので続きます。