「情報の歴史」なる本を知った。
情報文化という視点で編集された歴史年表だがあまりにも膨大すぎて
読むという代物ではなかった。
だが、その「情報の歴史」を講義した内容が本になっているということで
読んでみた。
「情報の歴史を読む」がそれである。
ミトコンドリアイブから始まり、現代まで3日間の講義で話してしまうというものなので
全て網羅しているわけではないが、歴史の授業の数百倍面白かった。
特に宗教の歴史や神話の話などは興味深い。
歴史とは神々の歴史でもある。
以下、いくつか読書メモ。
・東海道53次の53は華厳経の善財童子からきている。
・国分寺ネットワークは中央の神、仏というホストマシンを全国に伝える機能
・帝釈天の寅さんもそのひとつ
手塚治虫 火の鳥 太陽編 でも仏教がひろまるなかでの土着の神の戦いが描かれている。
火の鳥 (10) (角川文庫)/手塚 治虫

¥580
Amazon.co.jp
・仏教も聖書も時をへて編集されてきた。
・ルネッサンスの魔術的編集術
ギリシャ・ローマの古典文化を神秘的、ある意味勝手な編集をした
モーセとプラトンを同一とみなすなど。
・ベリニーニは物語の立体化を行った。
教皇の一族の物語をとりだし、それを空間と彫刻におきかえる。
・建築物は宗教の立体化
・「ヒストリー」には「物語る」という意味がある
・アナスタシア伝説
アナ・アンダーソンらが、自分がアナスタシアであると主張したことにより、アナスタシアが生存しているとの噂が広まり、そこから「アナスタシア伝説」が生まれた。またこれをもとにハリウッドで2度の映画化がなされている。この伝説を下敷きにした物語も多く、日本でも夢野久作が『死後の恋』を著している。
DNAは時空をまたいで生きている
この2度の映画化の2つめの作品はディズニーのアニメ。見たことはなかったが、これで興味がわいた。
アナスタシア [DVD]
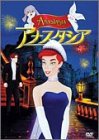
¥1,434
Amazon.co.jp
・情報の性質
・組織化
・複製化
・事故触媒化
・相互作用化
・・・・・・・・・インターネットそのもの!
・完全な平衡状態からは情報は何も生まれてこない
・カーニバルの語源(食人儀礼)
・ネオテニー
・服を着て性器を隠したことから、発情期がなくなり
セックスの意思を伝える必要が出てきた。
それで表情などのコミュニケーションが発達した。
・高橋秀元
・観念技術 思いが実現する
アニマルマスター
・螺旋学
ジョジョのスティールボールランに出てくる螺旋はこの古代の螺旋がヒントでは?
Steel ball run―ジョジョの奇妙な冒険 Part7 (Vol.6) (ジャンプ・コミックス)/荒木 飛呂彦
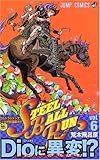
¥410
Amazon.co.jp
・コレクティブブレイン(集合脳)
柿本人麻呂も一人ではなく一族。
今で言うGIGAZINみたなものか。
・空海の夢
空海の夢/松岡 正剛
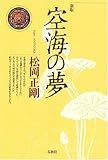
¥2,100
Amazon.co.jp
司馬遼太郎好きとしては
あわせてまだ読んでいない「空海の風景」も読んでみたい。
空海の風景〈上〉 (中公文庫)/司馬 遼太郎
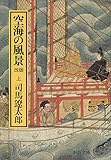
¥720
Amazon.co.jp
・線の発見はリズムの発見
線→文様→輪郭→土器
・ヒエログリフ(神聖文字)
GUIのルールがある。文中の人物や鳥などの動物の顔の向きで意味が決まる。
・山内昌之
歴史学の本
・神との契約は使用言語や文字も決める
・記憶の変換・改ざん・創成
想像の記憶
・世界宗教史
・信仰がエンジンとなるには神殿が必要だった。
・十進法
・分銅の発明
・ポータビリティと度量衡の統一
→各地域の量のルールが統一されることで経済は発展する
・ウルク都市郡の神々
・イアンナ・・・天空神
・エンキ・・・大地神
・エンリル・・・大気神
・一神教と多神教
・オシリスとイシスの物語
・アーリア人の大移動
バルナ・ミスラ
→
イランではアフラ信仰
神々をもっていかれたインドは
アフラをアスラ(阿修羅)といい悪神とし、デーヴァを新たに信仰。
アフラマズダはゾロアスター
ニーチェ ツァラトゥストラはこう言った
・ユダヤ教
・ダビデ→ソロモン 北のイスラエル 南のユダ王国 離散の運命
・バビロンの捕囚 ユダヤ人は地下に
一日目終了。
一日目が一番面白かった。
・イマジナリーメモリー
書き換えの記憶
・アルテミス 月神 百の乳をもつ
・物語の立体化
・アダムスミスも出版業をやっていた。
<出版>L
・雑誌や新聞はコーヒーハウスで配られたチラシが発展してできた
・ダニエルデフォー
・ジャーナル誌 「スペクテイター」
毎日発刊
テーマごとの編集
・モーツァルト ヨーロッパを音楽旅行
・「雨月物語」
・ジョゼフ・プリーストリー
・ルナソサエティ
・蔦屋重三郎
TSUTAYAは創業者が「現代の蔦屋になる」として命名。
・エドモンドバーク
・・・
と、ようやく読了した。
最後にあとがきで書かれていた未来への言葉をメモ。
マルチメディアネットワークの未来は
「これまでのいっさいの情報文化史的な成果の再編集に向かうだろう」
電子情報文化 デジタルとネットワーク化の際に
そのプロセスに独自の情報文化編集が加わらない限り面白くない。
と。
グーグルが電子図書館を構築しようとしていく最中、
赤字になっている新聞社や雑誌社が
これまでにつちかった編集技術をネットでどう活かすのか、
それが問われているのかもしれない。
いずれにせよ、面白い時代である。