ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
*****貸別荘となり ご案内*****
山の中の貸別荘 となり 2018年分ご予約受付中です。
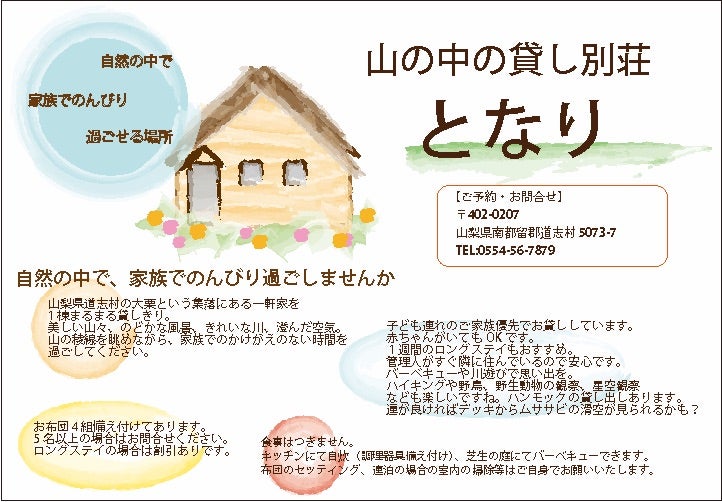
緑と清流の里、キャンパーの聖地ともいわれる道志村で、小さなお子様のキャンプデビューにいかがですか?
一軒家をまるまる一棟貸切、庭にテントを張ったり、バーベキューをしたり、ハンモックに揺られたり。
王道の川遊び、夜は星空観察、ホタル観賞もよいですね。
もともと管理人宅の離れ(別宅)なので、生活に必要なものはそろっています。
思い切って、1~2週間のロングステイなんかもできますよ。
子どもたちに、思いっきり自然の中で深呼吸させてあげてください。
アスファルトじゃない、土の地面を踏みしめ大地を感じ、山や川、目の前に広がる自然の圧倒的な存在感。里山の人々の暮らしの息吹。
大人も子どもも、自分が自然の一部であることを感じに、自然観を耕しにきてください。
そんなはじめの一歩のお手伝いができれば、幸いです。
詳細は以下のHPをご覧ください(道志村観光協会HP内)
http://doshi-kanko.com/minsyuku_01/tonari/index.html
本アメブロ内のカテゴリー「貸別荘となり」にて、各種情報発信しております。
******************
*****貸別荘となり ご案内*****
山の中の貸別荘 となり 2018年分ご予約受付中です。
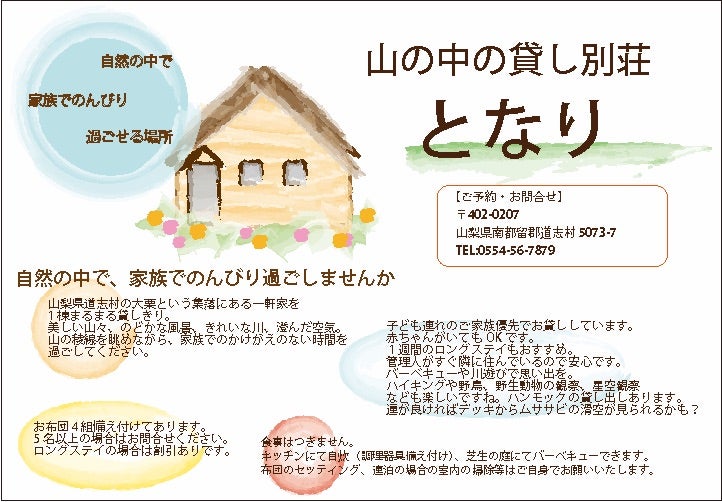
緑と清流の里、キャンパーの聖地ともいわれる道志村で、小さなお子様のキャンプデビューにいかがですか?
一軒家をまるまる一棟貸切、庭にテントを張ったり、バーベキューをしたり、ハンモックに揺られたり。
王道の川遊び、夜は星空観察、ホタル観賞もよいですね。
もともと管理人宅の離れ(別宅)なので、生活に必要なものはそろっています。
思い切って、1~2週間のロングステイなんかもできますよ。
子どもたちに、思いっきり自然の中で深呼吸させてあげてください。
アスファルトじゃない、土の地面を踏みしめ大地を感じ、山や川、目の前に広がる自然の圧倒的な存在感。里山の人々の暮らしの息吹。
大人も子どもも、自分が自然の一部であることを感じに、自然観を耕しにきてください。
そんなはじめの一歩のお手伝いができれば、幸いです。
詳細は以下のHPをご覧ください(道志村観光協会HP内)
http://doshi-kanko.com/minsyuku_01/tonari/index.html
本アメブロ内のカテゴリー「貸別荘となり」にて、各種情報発信しております。
******************
ここから、ブログ本文です。
今年も、6月17日に無事に道志川のあゆ釣りが解禁されました
解禁日は、道志村民にとってはある種のお祭り的な存在です。
解禁日には、毎年のように、いつもお世話になっているMさんのところで鮎パーティ(鮎の炭火焼)にお呼ばれしているのですが、今年の解禁日の釣果は不良だったらしく、パーティはお流れに(ノ_・。)
そうそう、Mさんち(旅館)の川向こうの敷地には、むかーしに建てられた蜂塚というのがあって(蜂を弔うためにMさんの親族の方が建てたとか)、その塚に句碑があるのですが、その句碑はなんと、白蓮(びゃくれん)さんから贈られたものだそうです。(って、Mさんから聞いた)
白蓮さん、ご存知?
朝ドラ花子とアンにも登場した、大正時代を代表する女流歌人です。
大正三美人にも数えられたほどの美貌の持ち主だったとか。
蜂塚の詳細は、道志村地域おこし協力隊の発行している冊子、道志手帖 に、記事があったのですが、
バックナンバーとか、ネットで読めるのかなあ?
(追記:道志手帖インターネットで見られるらしいですよ、リンク貼っときます。https://doshi-te.jimdo.com/)
あ、なんだか話が逸れましたが
あゆ釣りの話ですね。
息子の保育所の送迎時に、いつも釣りをしている方々を見かけます。
解禁日は不良でしたが、それからだいぶ経ちましたがその後は釣果はどうなんでしょうね?
我が家のご近所の太公望、Mさん(旅館のMさんとはまた別の方)に聞けばすぐ様子がわかるんだけど、時間帯が合わなくて最近会えてないからなあ…
Mさんに会えたら、情報を追記しますね。
またまた話が逸れますが、
道志村漁協の設立のいきさつ、とても興味深いのですよ。
私、大学時代に環境社会学という学問を専攻しておりまして、
漁協のその設立経緯が社会学的に非常に興味深い。社会学やってない人には、特にスルーしちゃうネタかもしれませんが。
何十年か前に、道志川の下流(現在の相模原市内)にダムを建てられたわけです。
で、ダム建てると、魚たち、遡上して来られませんよね?
道志川の鮎は、かつて『鼻曲がり鮎』と呼ばれ、小ぶりながらも非常に身がしまって美味しいと評判でした。
道志川の渓流を遡上する間に、鮎の鼻(実際には、鼻ではなくて、口のあたり?)がひん曲がってしまうほどの険しい渓流。
道志川ならではの名物だったわけです。
それで、話はもどりますが、ダムができたら鮎が遡上できない!どうするんだ!!!
鼻曲がり鮎を誇りに思う道志村の方々が話し合いを重ね、漁協を結成したそうです。
ダムを建設する会社(というか、神奈川県営の発電ダムなので神奈川県か)と話し合いの結果、毎年稚魚を神奈川県から道志漁協に贈呈し、漁協が放流、管理することになりました。
ここまでは、よくありそうな話。
何が興味深いかというと、このダムの計画が持ち上がった際(おそらく、1940後半か1950年代?)の、道志漁協の組合員の構成です。
なんと!道志村全戸です!当時、道志村に何世帯が暮らしていたか具体的数字は覚えておりませんが、全戸!
もうね、びっくり。
普通、漁業に従事する、もしくは関連のある仕事をされている方々が構成員となるものと思いますが、
漁業に全く関係の無い世帯までもが、組合員となっていたのです。
これは、環境問題に対する社会運動のひとつと言えそうですね。
そのような運動があったとは、今の平和な道志村からは想像つきません。
当時の村人の結束の硬さや、鼻曲がり鮎への誇り、道志川への愛着、また中心となった方々のなみなみならぬ努力が想像されます。
道志村の人々は、道志川が絡むと本気になるのですね。
(注:現在の漁協の構成員は当時のものとは変わっております)
この話、興味深いと感じた方は、社会学肌ですね!笑(°∀°)b
ちなみに、道志村漁協の設立経緯の話は、学生時代に同輩だったK君の論文の内容から拝借。漁協の人や生き字引のおじーちゃんとかに聞けば、今でも当時の詳細を知ることはできそう。子どもがもう少し大きくなったら、ちょっと調べてみたいなと思っていますが、いつになるやら…?
そんなこんなで、
道志村で今も鮎釣りを楽しむことができるのは、先人のみなさま方の努力の賜物なのですねー。
読者の方に太公望がおられましたら、
鮎釣りの際には、ちょっと先人に想いを馳せながら、釣りを楽しんでみてください。
今までと、ひと味違った釣りタイムになるかもですよー(*^.^*)
