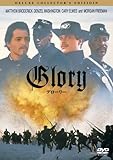- 紫色のクオリア (電撃文庫)/うえお 久光

- ¥641
- Amazon.co.jp
良い評判を耳にしていた『紫色のクオリア』を読了しました。
色んなSFのおいしいとこ取りというか、その上でオリジナリティを確立しています。
人間がロボットに見える不思議な少女、毬井ゆかりと親友波濤マナブの物語。
元ネタっぽいものは
アルフレッド・ベスター『虎よ、虎よ!』
グレッグ・イーガンの『宇宙消失』『万物理論』
小林泰三『玩具修理者』
+
ケン・グリムウッド『リプレイ』もしくは映画の『バタフライ・エフェクト』
ってところか。
イーガンの長編は積読なんでコレは受け売りです、ええ。
そういや『リプレイ』もまだ読んでないな~。
ともあれ、
ちょっと変わった少女の日常コメディを皮切りとして
サスペンス&ちょっと不気味な話へ走り
ガチSFへ跳躍した後に
青春物として着地する
という、贅沢なんだかメチャクチャなんだかよく分からないけれどもとても良い小説でした。
その全てにクオリア(感覚質)という概念が包括されているのがまたステキ。
このネタでここまでやるのか! という驚き。
部分的にはよくある話だけどここまで広げるか! という衝撃。
破天荒ながら分かり易くて説得力がある。
(僕個人が全部キチンと理解出来ているかは不明だけど)
ある意味、僕がライトノベルという分野に関心を寄せる理由が織り込まれた小説だったと思います。
展開早いし、ドラマとしての盛り上げなんかはもうちょっとずっしり書いて良かったんじゃないかという気もしますが、兎に角発想で突っ切った。突飛なキャラが乱造され、キャラ設定だけで胸焼けがしてしまいがちなライトノベルの残った良心と呼べる作品かもしれない。
(もちろん冲方さんや桜坂洋、山形石雄なども良心的)
語り手である波濤マナブの独善性も特筆すべき物がある。
最終的に彼女の行動・努力は必ずしも全肯定される訳ではないが、同時にあの状況に到達するのは彼女が全てを、本当の意味で全てを懸けてゆかりを救おうとしたからだ。
途中で諦めて世界を確定させてしまえば、それきりだったに違いない。
あの足掻きこそが重要だったのだ。
そしてこれは僕の価値観だが、たとえ傲慢だって独善だって越権だって大切な人を救いたかったら救う。
それで良いんだ。『バタフライ・エフェクト』みたいに、途中で投げずよくあそこまでやりきった!(別にバタフライエフェクトの批判ではありません、正直疑問は残ったけど)
波濤マナブは最高に男らしい!
まぁ設定は女なんだけど。
最後はライトノベルらしく青少年のアイデンティティの問題にクオリアを絡めて帰結させるところも良い。
中高生の読み物なんだから、小難しく辛気くさい終わらせ方をする必要なんて無いのです。
バカにしている訳じゃない。複雑にすれば高尚だという発想に拘らなくていいんだって事。
人間の精神に対し誠意を込めて書き、しかもテーマにガッチリ合ってれば問題なし!
そんな訳でとても気持ちよく読める作品でした。
こういうのもっと増えてくれると嬉しいんだけどな~。
追記というかおまけ
ちょっと他の感想見回ってたら、小さいツッコミが気になった。
エピローグに三寒四温という言葉が入っているのが解せないという事らしい。
ここまでの話をしておきながら、寒い温かいの概念とは何か、と。
ううむ……ぶっちゃけ「寒い」「温かい」それ自体がクオリアの筈なんだよな~。
それにこれをツッコむと、三寒四温に限らず名詞・動詞まで含めて全部書けなくなっちゃう……。
批判するつもりは毛頭ないが、思考実験として面白いから考えてみよう。
俺も正確に理解しているとは口が裂けても言えないけれども、概念としてどういう構造になっているか朧気には分かるつもり。
これは言語との対応の問題でもある。本人が「温かい」と実感した、それそのものがクオリアなのだ。
※ 「温かい」を「冷たい」と覚えてしまうなどの言語的ミスは生じていない物と仮定。本当はそれすら不確定な気もするが訳が分からなくなるので単純化。
人物Aの「温かい」というクオリアと人物Bの「温かい」クオリアは厳密には異なると思われる。
それどころか人間には感覚器官の慣れがあるので、例えば1月1日のAによる「温かい」クオリアと1月2日のAによる「温かい」クオリアすら実のところ違うはずだ。
しかしながら、多くの人の中にはそれらを包括して「温かい」という概念が形成されている。
作中解釈によると、全ての自身の可能性の中で共通して「温かい」という概念が一定の像を結ぶ、それをクオリアとしている。主観の中ですらズレはあっても、共有されている概念。
他人もまた同じ……とまでは言えなくても状況は似ている。
人間にある程度高い温度が入力、「温かい実感(クオリア)」が認識され、概念として把握する。
後に学習で、その状態~それに近い状態を「温かい」と言語化する。
で、ぶっちゃけ言語化した場合にも完全に一致する必要はない。
むしろズレているにも関わらず経験上何となく他人とのクオリアが共有出来て居るであろう部分の上澄みを言葉として「温かい」と称しているだけに過ぎない。だから言語に表す場合は自他のクオリア多かれ少なかれずれているが、被っていると思しき部分を言葉として共有していると思われる。
そして人間がロボットに見えるゆかりと他の人間による認識の差異みたいに、被っていない場合にお互いが確認して初めて「違っている」ことがある程度分かるに過ぎない。
まぁ、そこまで極端じゃなくても誤差が認識された時って事ですね。
「美味しい」とか「面白い」みたいな部分で考えた場合が分かり易いだろうか。
同じものを食べて同じ物を観て「美味い・不味い」「面白い・つまらない」というのが差異として生じる。
ただ「寒暖」は物理的に「温度が高い・低い」で表現出来るが、「美味い」とか「面白い」はそうはいかない。
だからたとえ話では分かり易いにしても、クオリアとしては複合的で複雑になってしまうかもしれない。
更に話を発展させてみたい。
『虎よ、虎よ!』を引き合いに出してしまうが、終盤に主人公ガリヴァー・フォイルは共感覚者になる。
その上で、たとえば温度変化は音の高低として示されるとしよう。
そして甘さが温度として感じられるとしよう。
分かり易くする為に感覚器官は我々基準で。
我々が温かいと感じる時、彼は高い音を聞く。
高い音、それが彼にとって他の人間が「温かい」と言語化したクオリアだ。
逆に我々がその感覚の違いを(誤差はあれども)ある程度把握して
「フォイルさんが砂糖を口に含んだ時の感じが、我々にとっての「温かい」なのです」
と間接的に説明することは可能だ(もちろん確認する術が無ければ間違っている可能性もある)
この場合フォイルにとっての三寒四温は、音階が部分的にやや戻りつつも全体としては高くなっていく音調である。そしてフォイルに我々にとっての三寒四温を疑似体験させる為には、部分的にやや戻りつつも苦い物からだんだん甘い物を与えていくような形になるだろう。
我々の「温かい」クオリアはフォイルの「高音」クオリアであるから、フォイルが温度を音に捉えているという意味では違うけれど、我々の認識する「温かい」の時とと同じ刺激が入力されたという意味に於いては同じである。
逆に我々の「温かい」クオリアとフォイルの「甘い」クオリアは入力された刺激としては異なるが、その結果として生じる感覚はある程度共通すると考えられる。
本編に比べて差異の少ないケースではあるものの、つまりはそういう違いであって、言語化してしかもそれがある程度共有出来ればさほど異ならないと言えるし、少しばかり異なっていたとしても誤差の範囲内に過ぎないのだ。
そして本文の記述から波濤マナブの発した三寒四温は波濤マナブのクオリアとしても、我々のクオリアとしてもそう大した違いは無いはずだと推察出来る。あれだけの経験をして居るんだから違いが生じないのがおかしい……と思われたらもうしょうがないが、マナブはエピローグ時点で可能性を拡大させた時の記憶や感覚を喪失しているし、
なにしろあたしは話のオチを、こう締めくくるつもりなのだから。「すべてはあたしの夢でした、ちゃんちゃん」と。
(『紫色のクオリア』 113頁)
と語っている。
だから別にそのクオリアが常人のそれと似通っていても全く不思議ではない。
しかしこう考えるとクオリアって本当に面白いですね。
科学と言うより哲学的な概念にも思えてしまう。