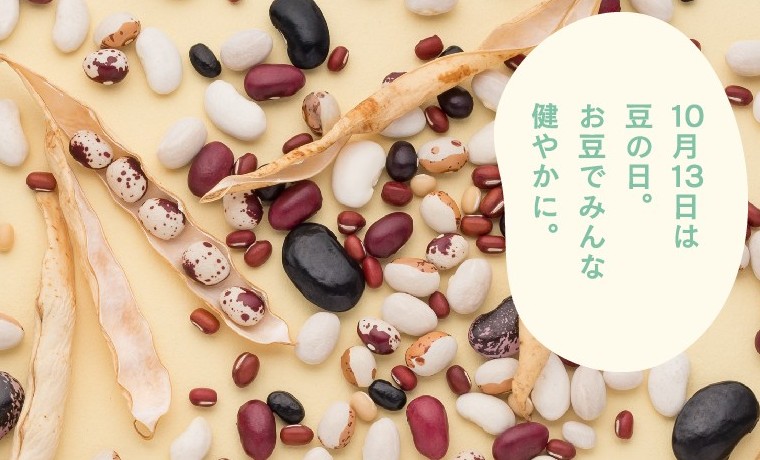おはようございます🍠
美味しいさつまいもの食べ方教えて!
▼本日限定!ブログスタンプ
ブリーフ&トランクス『石焼イモ』
「石焼イモ」歌詞
作詞:マリモラッコ
作曲:伊藤多賀之
星空 木々のざわめき はじめて知った君の香り
制服 姿のふたり 待ちわびたこの時を
「好きだよ」・・・ずっと言えなかった言葉
今なら何度でも言えるさ
目を閉じた君の前髪が風に揺れてる
高鳴るこの胸 唇 潤し 近づいたその時
石焼イモ~おイモおイモおイモおイモ おイモだよ
夜の空を~駆け抜けてく おイモの美味しそうな匂い
クスっと照れ笑い なんだかいびつな 16の夜
はじめて 存在してる 僕の部屋で君が笑っている
今夜は 月の明かりが 消えない魔法みたいだ
震える・・・君の両手をにぎりしめて
キスした精一杯やさしく
今夜終わらない夢をみようあふれる想い
ブラウス 最後のボタンを はずして 近づいたその時
石焼イモ~おイモおイモおイモおイモ おイモだよ
月明かりが雲で隠れてなくなり君を見失った
ため息を殺して 笑ってみせた 18の夜
あれから 10年が過ぎ 幸せの形を築いた
生まれた ばかりの子供 抱いた君を抱きよせて
それでも もろく壊れそうな日々の
何かが 足りないような気分さ
すれ違い始めた僕達のすき間に吹く風
背中を 向けたまま 会話も 笑いも 消えた 僕らの部屋
石焼イモ~おイモおイモおイモおイモ おイモだよ
なじみの声~なつかしいこの響き 涙が止まらない
石焼イモ~おイモおイモおイモおイモ おイモだよ
信じ合って~寄り添い歩いた道をまた歩きだせたら
間違いじゃなかった ふたりの出会いは そう思えるように・・・
2000年1月21日発売
最高位91位
売上げ枚数 0.2万枚
サツマイモの日(10月13日 記念日)
埼玉県川越市のサツマイモ愛好者の集まりである「川越いも友の会」が制定。
日付は10月はサツマイモの旬であり、13日は江戸から川越までの距離が約13里なので、サツマイモが「栗(九里)より(四里)うまい十三里」と言われていたことから。
また、サツマイモは痩せ地で育つ・台風に強いなど長所が「13」もあると言われていることから。
サツマイモについて
サツマイモ(薩摩芋)は、ヒルガオ科サツマイモ属の植物。別名に、甘藷(かんしょ)、唐芋(からいも・とういも)、琉球薯(りゅうきゅういも)、とん、はぬす等がある。英語では「sweet potato」だが、ヤム芋に似ていることから「yam」とも呼ばれる。原産地は南アメリカ大陸、ペルー熱帯地方とされる。
大航海時代にイタリアのクリストファー・コロンブスが1498年にベネズエラを訪れて以降、スペイン人あるいはポルトガル人により東南アジアに導入された。日本へはフィリピンのルソン島から中国を経て1597年に沖縄の宮古島へ伝わった。アジアにおいては外来植物である。中国(唐)から伝来した由来により、特に九州では唐芋とも呼ばれる場合が多い。
サツマイモは繁殖能力が高く窒素固定細菌との共生により窒素固定が行えるため痩せた土地でも育つ。従って、初心者でも比較的育てやすく、江戸時代以降に飢饉対策として広く栽培されてきた。暖地の場合、春に苗を植え付け、晩夏から秋にかけて収穫する。
日本における産地としては、鹿児島県・茨城県・千葉県・宮崎県・徳島県が全国のトップ5県である。この内、上位4県で全国の8割を占め、とりわけ鹿児島県は全国の生産量約81万トンの4割弱を産する。鹿児島は水はけの良い火山灰を含んだ土地が広がっており、栽培に適している。
デンプンが豊富で、エネルギー源として適している。また、ビタミンCや食物繊維を多く含み、加熱してもビタミンCが壊れにくいという特長がある。ブランドには、鹿児島県の知覧紅(ちらんべに)・安納芋(あんのういも)、徳島県の鳴門金時(なるときんとき)、石川県の五郎島金時(ごろうじまきんとき)がある。
関連する記念日として、二十四節気の「霜降(そうこう)」の頃である10月23日は「おいもほりの日」となっている。サツマイモは霜が降り始めるまで太り続けるとされ、この頃に「おいもほり」のピークを迎える。
ピザまんの日(10月13日 記念日)
コンビニなどで販売される加温まんじゅうの衛生管理や品質向上のために活動する日本加温食品協会が制定。
日付は二十四節気「秋分」を過ぎて朝晩の冷え込みが強まり温かいものが食べたくなる10月と、13で「ピ(1)ザ(3)まん」と読む語呂合わせから10月13日としたもの。
肉まん、あんまんに続く中華まんとして、「ピザまん」の美味しさをより多くの人に知ってもらい、味わってもらうことと、片手で食べられる食べやすさを広めるのが目的。記念日は2022年(令和4年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。
日本加温食品協会は、1972年(昭和47年)に井村屋初代社長の井村二郎(いむら じろう、1914~2011年)が中華まん市場拡大に伴う小売店での飲食店営業許可減免、業界の品質向上、蒸し器(スチーマー)等の取扱い衛生管理の徹底などを目的にメーカー、関連業者と共に立ち上げた加温食品協議会を母体とする任意団体である。
井村屋では、冷凍の「肉まん」や「あんまん」「ピザまん」「大豆ミートまん」、具なしの中華まん「すまん」などの商品を製造・販売する。
また、「ピザまん」はセブン-イレブンやファミリーマート、ローソン、ミニストップなどのコンビニで販売されている。生地はモチモチしていて食べ応えがあり、とろけるチーズが入ったものもある。寒い季節になると「ピザまん」などの温かい中華まんが恋しくなる。
「ピザまん」の歴史としては、1979年(昭和54年)に井村屋が「ピザ肉まん」という名前の中華まんを発売したとの情報がある。当時は具をトマトケチャップで味付けしたもので、ピザとは異なる風味であった。
近年では中にチーズを入れ、イタリア風のトマトソースを使用するなど、本来のピザの味に近付けたものも多い。
豆の日(10月13日 記念日)
東京都港区赤坂に事務局を置く一般社団法人・全国豆類振興会が制定。
日本には陰暦の9月13日に「十三夜」として名月に豆をお供えし、ゆでた豆を食べる「豆名月(まめめいげつ)」という風習があった。日付は暦どうりの「十三夜」とすると毎年日付が大きく変動してしまうので、新暦の10月13日とした。豆類に関する普及活動などを行う。記念日は2010年(平成22年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。
いにしえより旧暦の8月15日の「十五夜」と9月13日の「十三夜」に月を愛でる月見の風習がある。今では月見のお供えといえば「月見団子」だが、昔はちょうどその頃収穫される作物として十五夜には「里芋」を、十三夜には「豆」をお供えして食べる習わしがあった。そのため、十五夜は「芋名月」、十三夜は「豆名月」とも呼ばれる。
全国豆類振興会では「豆の日」普及推進協議会を組織し、「豆の日」の料理教室やイベントなどを通じて、健康に良い、栄養豊かな豆類をもっと生活に取り入れてもらうための普及・啓発活動に取り組んでいる。
豆について
豆(bean)とは、マメ科植物の種子のことで、特に食用・加工用に利用される大豆、インゲンマメ、ヒヨコマメ、アズキ、ラッカセイなどの総称である。
豆は人類の農耕文明において、穀物と同じように、長い期間にわたって作物となってきた歴史がある。現在100ヵ国以上で栽培される食用の豆として、インゲンマメが最大の生産量を誇る。そのインゲンマメは、メキシコで紀元前4000年頃のものが見つかっており、メソアメリカが原産と考えられている。