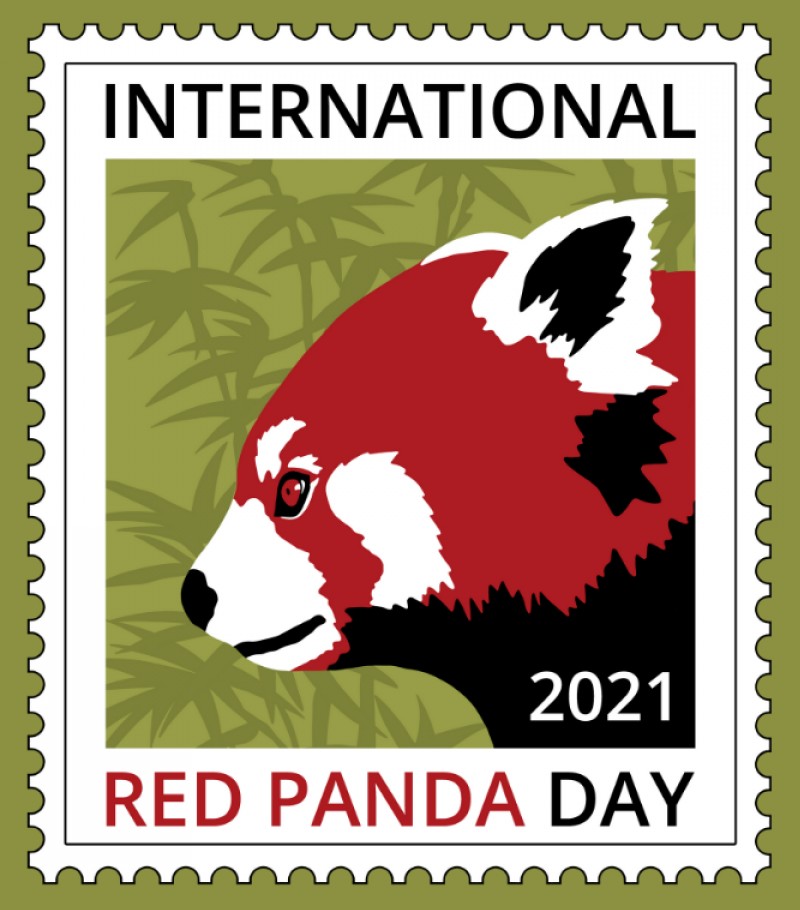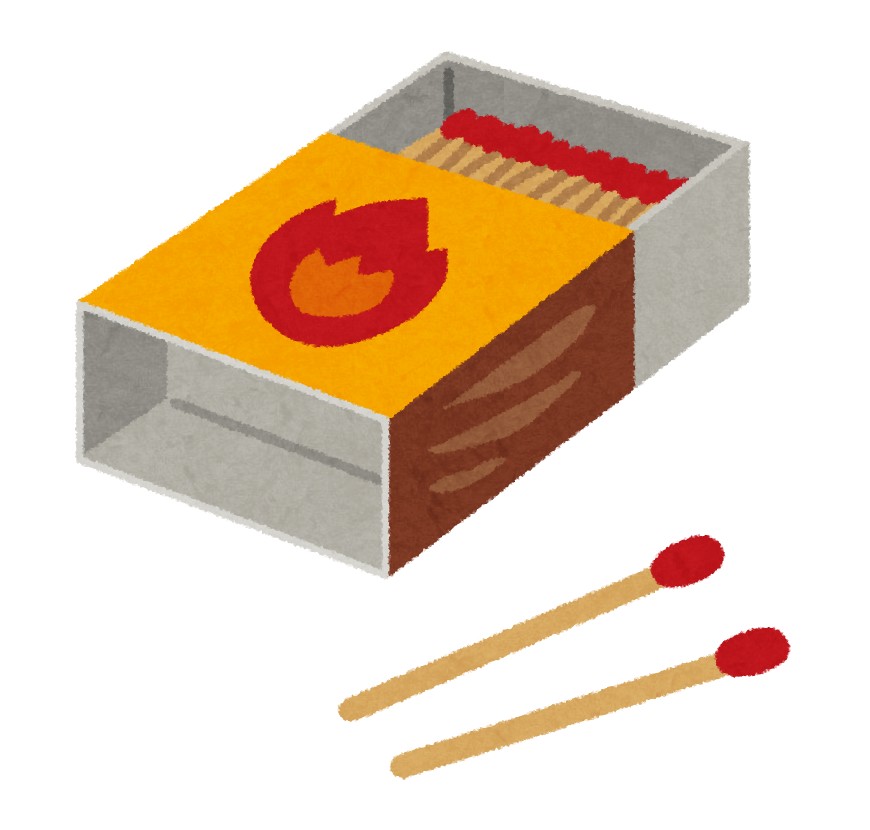こんばんは🌙
無事に更新されましたね🥸
馬券買ったことある?
▼本日限定!ブログスタンプ
競馬の日・日本中央競馬会発足記念日(9月16日 記念日)
1954年(昭和29年)のこの日、日本中央競馬会(Japan Racing Association:JRA)が農林省(現:農林水産省)の監督の下で発足した。
牛とろの日(9月16日 記念日)
北海道川上郡清水町で牛肉製品の製造・販売を行う有限会社十勝スロウフードが制定。
日付は「ぎゅう(9)と(10)ろ(6)」(牛とろ)と読む語呂合わせから。同社の提携牧場であるボーンフリーファームと開発した「牛とろ」を多くの人に食べてもらい、その美味しさを知ってもらうことが目的。記念日は2018年(平成30年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。
牛とろについて
1991年(平成3年)に誕生して以来、根強い人気を誇る「牛とろ」。2011年(平成23年)より、加熱を一切行わない非加熱食肉製品「牛肉の生ハム」として造られている。厳選された部位を、繊細で丁寧な職人の技で仕上げている。舌の上でとろりと蕩けるような食感と、肉本来のうま味を楽しむことができる。
1997年(平成9年)に誕生した「牛とろフレーク」は凍ったまま温かいご飯にふりかけて「牛とろ丼」にすると絶品である。その他、「牛とろ軍艦」「牛とろうどん」などアレンジ一つで色んな料理に活用できる。
国際レッサーパンダデー(9月第3土曜日 記念日)
ネパールとアメリカに事務局を置き、レッサーパンダの保全活動を行う「Red Panda Network」が制定。
「国際レッサーパンダの日」とも呼ばれる。英語表記は「International Red Panda Day」。レッサーパンダの保全活動の必要性や野生での現状を知ってもらうことが目的。
「Red Panda Network」ではこの日を記念して、野生のレッサーパンダを密猟者から守り、レッサーパンダが生息する森を回復させるための募金活動を実施する。
また、この日を中心として、世界各地の動物園でレッサーパンダに関するイベントや啓発活動が行われる。日本でも、この日にレッサーパンダの生態についての特別ガイドなどのイベントを実施する動物園を確認できる。
「国際レッサーパンダデー」の日付は以下の通り。
- 2019年9月21日(土)
- 2020年9月19日(土)
- 2021年9月18日(土)
- 2022年9月17日(土)
- 2023年9月16日(土)
レッサーパンダについて
「レッサーパンダ」は、レッサーパンダ科に分類される哺乳類で、本種のみでレッサーパンダ属を構成する。インド北東部や中国の四川省西部、ネパール、ブータン、ミャンマー北部に生息する。
英語では「Lesser Panda(レッサーパンダ)」や「Red Panda(レッドパンダ)」などと呼ばれ、中国語では「小熊猫」と表記する。なお、中国語でジャイアントパンダのことは「大熊猫」と表記する。また、パンダは「熊猫」と書くが、これはレッサーパンダを指す言葉である。
もともとレッサーパンダは単に「パンダ」と呼ばれていたが、後にジャイアントパンダが発見されて有名になると、単に「パンダ」といった場合はジャイアントパンダの方を指すようになった。そこで英語では「小さい方の」という意味の「lesser(レッサー)」や毛色の「赤色」から「red(レッド)」を付けたという経緯がある。
日本では、2005年(平成17年)に千葉市動物公園で飼育されているオスのレッサーパンダ「風太(ふうた)」が後ろ足二本で立つ姿が話題となり、全国的にレッサーパンダブームを巻き起こした。
うちに来て、もう何年目![]()
![]()
マッチの日(9月16日 記念日)
1948年(昭和23年)のこの日、配給制だったマッチの自由販売が認められた。
1938年(昭和13年)、綿糸配給統制規則によって国内綿糸の消費量が規制されたのに始まり、以後、1939年の電力調整令、1940年の砂糖・マッチの切符制、1941年の米穀配給制、1942年の衣料総合切符制と続いた。戦争の長期化によるもので、日用品から生産資材に至るほとんどの物資が統制配給の対象となっていた。
マッチ(match)は、細長い木片や厚紙などの可燃物質の先端に、摩擦で発火する物質をつけた道具。マッチ棒とも呼ばれ、火を得るために使用される。漢字では「燐寸」と書く。
マッチはリン(燐)の燃えやすい性質を利用している。マッチの種類としては、どこにこすりつけても発火する「摩擦マッチ」と、そうではない「安全マッチ」がある。
摩擦マッチを最初に発明したのは、イギリスの化学者ジョン・ウォーカー(John Walker、1781~1859年)である。薬剤師でもあったウォーカーは、1826年に偶然にも摩擦による発火を発見し、翌1827年に「friction lights」の名称で摩擦マッチの販売を始め、多くを売り上げた。「friction」は「摩擦、擦れ、衝突」という意味。
現在の一般的なマッチは、マッチ箱の側面がヤスリ状の摩擦面になっており、マッチ棒の先端の発火部をこすりつけることで火を発する。これは安全マッチと呼ばれ、19世紀半ばに登場した。マッチ棒の頭薬に塩素酸カリウムを、マッチ箱の側薬に赤燐を使用している。