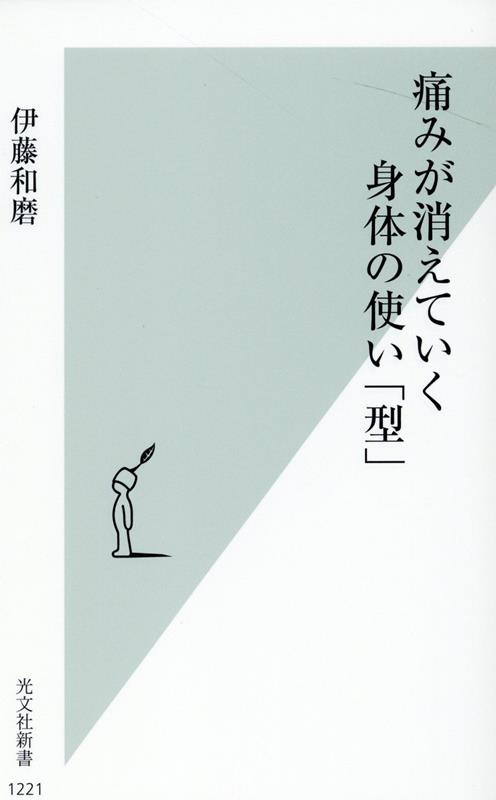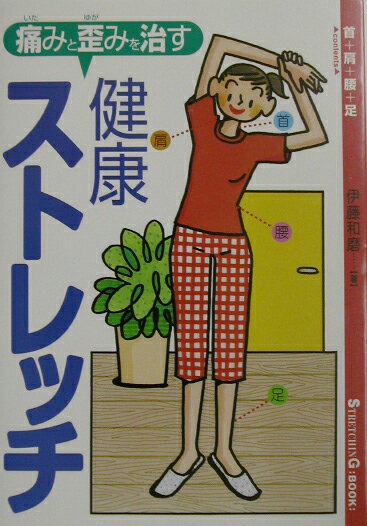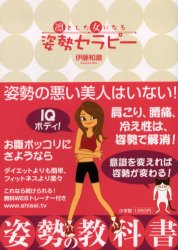薬剤師が弱い健康のジャンルに
身体の使い方があります。
どうして弱いのか?は
まったく勉強しないからです。
勉強しないから
分からないのは当然です。
イメージとしては
身体のことも
解剖学を中心に分かっている
と思われがちですが
全然そんなことは無く
薬剤師が知っているのは
筋肉の分類分け、骨の成り立ちくらいです。
なので
自分らの身体の故障についても
皆目見当がついていません。
自分の腰痛はどうしたら良いんだ?
肩こりは治らないんだな。
とかです。
コリなどは
骨を動かす運動をすれば
血流が良くなり
次第に取れていくんですが
それすら知らないんです。
その為に体の使い方を
プロトレーナーの伊藤氏の著書がとても役に立ちます。
今回は積読本が無くなったので
和磨さんの本を再読です。
出版から12年経っていますが
その内容は色褪せることなく
今も使る内容ばかりです。
買った当初のままなので
ところどころ黄ばみが出ています![]()
お気に入りの本が![]()
虫干ししていないから仕方がないか![]()
勉強になった箇所です。
・人の身体は、壊れてもパーツの交換ができない。壊れてしまったら、完全に昨日が元に戻ることはない。厄介でも自分の身体と一生付き合っていくしかないのである。だから壊れてしまう前に、何とかする必要があるのだ(p4)
・腕のいい歯科医に診てもらっても、歯を磨かなければ虫歯が改善しないように、予防は、病状に関係なく効果があり、自覚症状があってもなくても継続する必要があるのだ(p5)
・呼吸は姿勢の影響を受けるため、姿勢を改善しないことには、呼吸の質を改善することはできない(p40)
・口呼吸は運動器の機能にも影響を悪影響を及ぼす。口から息を吸うと正門が開くため、ふっくうの内圧が低下して腰椎が不安定になる。たとえば、口を開けたままでは肛門を締めるのが難しく、口を閉じることで肛門も締めやすくなるのだ(p41)
・前かがみや猫背だと、脊柱管狭窄症や椎間板ヘルニアを患うリスクが高まる。まさにわるいことづくしなのである(p47)
・お尻の形を腰痛には関連性がある。慢性腰痛を患っている人や、シニアで猫背(前のめり)になっている人を真横から観察すると、大殿筋が委縮し、お尻がペタッとして小さくなっている(p56)
・継続的に有酸素運動をしている人でも、10年年をとるごとに約10%も心肺機能が低下するという指摘がある。本当にそうなら、座りっぱなしの暮らしをしている人は、もっと心肺機能が低下しているハズである~~~~嬉しいことに、運動習慣が無かった人でも、定期的な有酸素運動によって何歳からでも新アピ機能を向上させることが出来るのだ(p87)
・若い頃に運動をしなかった人は、その分足が弱りやすいので、習慣的に早歩きや階段上がりをして、足に負荷を与えることを心がけていただきたい(p134)
・もともとハイヒールは、社交の場でワルツなどを踊る時に、回転しやすくするために考案された靴だった。TPOに合わせて限定的に履いていたようだが、現代の女性は、そrふぇを通勤靴にしてしまったのだから、足のトラブルが絶えないのは不思議なことではない~~~~なぜ、多くの女性は体に悪いと分かっていても、ハイヒールを手放さないのだろう。女性にとっては健康も大事だが、美しくあることはもっと大事であり、それを究めるためなら他所のリスクも厭わないからである。それが女性の「性」というものだろう(p139)
・「健全な身体は、健全な足の上に載る」(p158)
・専門家ですら誤解している場合があるのだが、最終的なゴールは痛みをやっつけることだけではない。結果的に痛みが消失すればよいが、それよりも患部にダメージを与え続けてきた悪しき習慣(姿勢や動作パターン)を改善することが、皆が目指すべきゴールなのである(p197)
・気に血液が供給されないと、酸素欠乏状態と栄養障害が起こり、乳酸と代謝産物が蓄積されていく。次第に患部の血液が酸性になっていき、障害されている細胞で痛みを出す化学物質が産生され筋緊張を増加させる。~~~~痛みがあっても、患部を動かしていれば、筋ポンプ作用によって新たに血液が送り込まれるが、大抵、痛みがあると動かさなくなってしまうので、いつまでの酸欠と栄養不足が続き、痛みも持続するのである。また、筋肉の癒着(拘縮)も進むので、さらに動かすときの痛みが強まってしまうのだ(p208)
・慢性的な疲労は、内分泌系、自律神経系、免疫系の機能を低下させるため、体調不良を招きやすくなる。マッサージ、や鍼、カイロプラクティックなどの徒手治療は、脳幹から抹消へと向かう鎮痛抑制システムを活性化させることが判明している。先述のように、ランニングは内因性オピオイドの分泌を促進させる(p211)
・慢性痛に対しては、薬物療法や安静療法はほとんど意味がないといってよい。ましてや抗うつ剤の服用など、もってのほかである。鎮痛剤で一時的に痛みが抑えられても、根本が解決されていないので、次第に症状がぶり返す。薬物療法は、堂々巡りになるどころか、痛み止めに対する依存度が高まり、自力で改善していこうという気力も萎えさせてしまうのである。鎮痛剤を常用している人が、その事を十分に理解していればよいのだが、大抵は深く考えずに頼っている(p215)
この本が出たのが2013年5月
それから10年以上経っているけど
鎮痛剤を常用している現実が
私が店頭に立っているだけ見受けられます。
鎮痛剤なんて
本当に痛い時だけ服用していて
他の痛くない時には
痛くならないように
自分で自分をケアしないと
基本的には問題ある箇所は問題あるままになっている状態
になっています。
抜き出しはしていませんが
メンタルから来る痛みなども
そのケアのことも書かれています。
和磨さんは「気のせい」と言われる痛みも
バカにせず体を見ているそうです。
今はどうでしょうね??
それからさらにパワーアップしているでしょうからね。
別のアプローチになっているかもしれませんね。
伊藤さん良い本をありがとうございました![]()
内容は深く、ずっと使える内容となっています。
本当に痛いなら
サロンに行けばいいのでしょうが
いけない人のために
このような本を出してくれて
自分でもケアできるような内容になっています。
指導された時の一回の動作より
日常に繰り返す動作を治さない限りは
一生その痛みは無くならないでしょうね。
そんな戒めも書かれていました。
本当に良い本となっています。
整形外科で治っていないようなら
この本の内容を参考にして
まずは自分でやってはどうでしょうか??
いつも身体については
伊藤さんの本を紹介していますが
内容は本当に良いので
他の書籍も読んで実践してみてください