(注意)今日の話はマジメな下ネタを含んでおります。お食事中の「ながら読み」は自己責任で!
モンゴルだるま@ウランバートルです。
ウランバートルといえば、モンゴル国一の大都会です。
私は、都会っぽい仕事(=汗水たらす肉体労働ではない)があるときは、
ウランバートルのA地域と呼ばれる都会のど真ん中のボロアパートに暮らしております。
ボロとはいえ、一応、上下水道(水道にいたっては温水まで!)と電気・集中暖房などの
公共サービスは受けられることになっています。
1年のうち半年以上が氷点下になる国モンゴルでは、この集中暖房という公共サービスはとても助かります。
独り暮らし(といっても愛犬・ジャーマンシェパード(♂)と同居)の私にとって、本格的な寒さとなる12月ー2月くらいは、-20度からー30度が当たり前に冷え込むので
日本での独り暮らしみたいに、帰宅したときの家が冷え切っている、というのは死活問題です。
で、トイレも当然水洗トイレです。
とはいえ、今、ちょっとしたピンチと葛藤を抱えています。
というのは、初雪が朝っぱらから降っていて、
しかも、このブログを新規立ち上げすることとなった9月7日は、
ついつい出不精となってしまい、懸案事項であった
トイレットペーパーの購入をサボってしまったのです。
さらに、なぜだか喉が渇いてプルーン100%ジュースをがぶのみしちゃった。
読者の皆様のなかには、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、
プルーンジュースというのは、便秘がちな女性にとって、
繊維質と鉄分豊富で、お通じをうながす
最強のドリンクです。
そんなHealthyな飲み物をあろうことか、
約1リットルを2時間ほどで飲み干してしまったのです。
当然の結果として、私とトイレの関係はきってもきれないものとなってしまいました。
でも、貴重なトイレットペーパーはそろそろ切れかかってきました。
残り12cmほどが頼りない感じに芯にへばりついているだけ。
私の葛藤は本格的なものになってきました。
トイレには、すぐ手をのばせば、洗面台つきの蛇口があるのです。
おりしも、トイレ書斎で読んでいた本は、「くう・ねる・のぐそ 自然に愛のお返しを」。
くう・ねる・のぐそ―自然に「愛」のお返しを/伊沢 正名

¥1,575
Amazon.co.jp
著者の井沢さんは、地平線会議の仲間であります。
30年以上にわたって野糞を日本国内外で実践している糞土師。
その野糞のエキスパートによると、
大便は日本のようにバクテリアが元気な環境では、土に帰るけれど
トイレットペーパーはいつまでたってもなくならなかった、というのです。
水洗便所によって、排泄物はさーっと家の外に流れていくけれど、
それらの汚物はそのままずーっと下水処理場へと流れていくのみとのこと。
それはそうなのです。
あんまり考えたことなかったけれど、自分の目の前から消えてなくなったといっても、
ブツがこの世から消滅したわけではない。
モンゴル国は水の問題、特に下水処理の問題を常に抱えています。
特に21世紀になって百万人都市となった首都ウランバートルにおいては、
激しい人口流入や工場設立に下水処理能力が全然おいついていないのです。
かといって、肥溜めとかコンポストみたいに堆肥作りができてるわけでもない。
ゲル地区のように下水管がトイレと直結していないところでは、
汲み取りのバキュームカーがきてくれますから、
最初からトイレットペーパーや生理用品その他固形物は
トイレ横に備え付けのゴミ箱に捨てるのが当たり前です。
水洗トイレでもこの習慣が残っており、
また配管の形状や水圧によっては、すぐつまるため、
モンゴル人の多くが、
お尻につかったトイレットペーパーはゴミ箱に、
を常識としています。
井沢さんはさらに、自然に優しくするために
「脱トイレットペーパー」に踏み込んでいきます。
本の中には野糞の仕方が丁寧に図解されています。
そして、井沢さん初めての、
トイレットペーパーなしの「インド式」のときの体験は秀逸。
やっぱ、自分のものであったとしても、
おっきい用を足したあとの孔に
素手で触れるというのはドキドキです。
お風呂に入っているときは、念入りに大切なところを洗うのに・・・
トイレットペーパーのわずか1mm足らずの境に
私達はどんだけ依存していることか・・・
ウォシュレットがかなり普及してきた日本でさえ、
水で洗った後にトイレットペーパーでふき取るために
紙が備え付けられています。
結果的に・・・
昨日は、12cmのギリギリ感に躊躇しつつも
私はトイレットペーパー、使っちゃいました。
インドネシアやマレーシア、タイ、フィリピンの離島などで
仕事(取材だったり調査だったり)したときは、
そもそもトイレットペーパーがついてないし、捨てるところもないから、
「郷に入っては郷に従え」ってことで、
見よう見まね(コーディネーターの女の子に実際、やってみせてもらった)で
びちゃびちゃやってて、これはこれで気持ちよかったのですが、
なんなのかなぁ?この躊躇。
モンゴルでも旧国立デパート(ノミンデパート本店)や
空港近くにあるミシェールエキスポその他で
ウォシュレットっぽい洗浄トイレの販売コーナーが常設されているし、
日本にいったモンゴル人のお土産として
この便座は人気ものです。
でも、わざわざそんなことしなくても、
ちょっとした工夫で自分用の携帯ウォシュレットはできる。
自然に優しいツアーを志すものとしては、
やっぱり、なんとか日常的にトイレットペーパーなどを使わない
排泄行為をマスターすべきだろうか?
草原での暮らしでも、お客様と一緒に草原トイレをすることが多いため
最近は、トイレットペーパー持参でやってしまっています。
ヤギや羊が食べちゃうのか、
うちの周りには、残っていないんだけど。
いろんなことを考えながら、
やっぱり朝、お店でトイレットペーパーを買っちゃいました。
独りで暮らしてる分には、
お尻を水で洗うためには、とっても便利な位置に
洗面台と蛇口がついているのですが、
お客様にまでそれを強要するのはいかがなものか、と。
でも、「くう・ねる・のぐそ」という本は
かなりエポックメーキングな名著であります。
自然と人間の共存共栄をつなぐ鍵が
まさか にあったとは。
読めば読むほどに面白く、
禁断の綴じ込み特集にいたっては圧巻の一言。
そんなわけで、来年までに
なんとか伊沢式をマスターしエコなツアーで普及していこうか・・・
なんて・・・
いや、まだ決めたわけではないんですけどね。
そんなこと断言してお客さんが逃げちゃったら困るから。
でも、自分の排泄物がどこに行くんだろう?
そんな素朴な疑問からもエコライフが広がるっていうこと。
アウトドア派じゃない人にも
ぜひ「のぐそワールド」に触れていただきたいな、と思った次第。
くう・ねる・のぐそ―自然に「愛」のお返しを/伊沢 正名

¥1,575
Amazon.co.jp
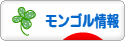
にほんブログ村尾篭な話でごめんなさい。
モンゴルだるま@ウランバートルです。
ウランバートルといえば、モンゴル国一の大都会です。
私は、都会っぽい仕事(=汗水たらす肉体労働ではない)があるときは、
ウランバートルのA地域と呼ばれる都会のど真ん中のボロアパートに暮らしております。
ボロとはいえ、一応、上下水道(水道にいたっては温水まで!)と電気・集中暖房などの
公共サービスは受けられることになっています。
1年のうち半年以上が氷点下になる国モンゴルでは、この集中暖房という公共サービスはとても助かります。
独り暮らし(といっても愛犬・ジャーマンシェパード(♂)と同居)の私にとって、本格的な寒さとなる12月ー2月くらいは、-20度からー30度が当たり前に冷え込むので
日本での独り暮らしみたいに、帰宅したときの家が冷え切っている、というのは死活問題です。
で、トイレも当然水洗トイレです。
とはいえ、今、ちょっとしたピンチと葛藤を抱えています。
というのは、初雪が朝っぱらから降っていて、
しかも、このブログを新規立ち上げすることとなった9月7日は、
ついつい出不精となってしまい、懸案事項であった
トイレットペーパーの購入をサボってしまったのです。
さらに、なぜだか喉が渇いてプルーン100%ジュースをがぶのみしちゃった。
読者の皆様のなかには、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、
プルーンジュースというのは、便秘がちな女性にとって、
繊維質と鉄分豊富で、お通じをうながす
最強のドリンクです。
そんなHealthyな飲み物をあろうことか、
約1リットルを2時間ほどで飲み干してしまったのです。
当然の結果として、私とトイレの関係はきってもきれないものとなってしまいました。
でも、貴重なトイレットペーパーはそろそろ切れかかってきました。
残り12cmほどが頼りない感じに芯にへばりついているだけ。
私の葛藤は本格的なものになってきました。
トイレには、すぐ手をのばせば、洗面台つきの蛇口があるのです。
おりしも、トイレ書斎で読んでいた本は、「くう・ねる・のぐそ 自然に愛のお返しを」。
くう・ねる・のぐそ―自然に「愛」のお返しを/伊沢 正名

¥1,575
Amazon.co.jp
著者の井沢さんは、地平線会議の仲間であります。
30年以上にわたって野糞を日本国内外で実践している糞土師。
その野糞のエキスパートによると、
大便は日本のようにバクテリアが元気な環境では、土に帰るけれど
トイレットペーパーはいつまでたってもなくならなかった、というのです。
水洗便所によって、排泄物はさーっと家の外に流れていくけれど、
それらの汚物はそのままずーっと下水処理場へと流れていくのみとのこと。
それはそうなのです。
あんまり考えたことなかったけれど、自分の目の前から消えてなくなったといっても、
ブツがこの世から消滅したわけではない。
モンゴル国は水の問題、特に下水処理の問題を常に抱えています。
特に21世紀になって百万人都市となった首都ウランバートルにおいては、
激しい人口流入や工場設立に下水処理能力が全然おいついていないのです。
かといって、肥溜めとかコンポストみたいに堆肥作りができてるわけでもない。
ゲル地区のように下水管がトイレと直結していないところでは、
汲み取りのバキュームカーがきてくれますから、
最初からトイレットペーパーや生理用品その他固形物は
トイレ横に備え付けのゴミ箱に捨てるのが当たり前です。
水洗トイレでもこの習慣が残っており、
また配管の形状や水圧によっては、すぐつまるため、
モンゴル人の多くが、
お尻につかったトイレットペーパーはゴミ箱に、
を常識としています。
井沢さんはさらに、自然に優しくするために
「脱トイレットペーパー」に踏み込んでいきます。
本の中には野糞の仕方が丁寧に図解されています。
そして、井沢さん初めての、
トイレットペーパーなしの「インド式」のときの体験は秀逸。
やっぱ、自分のものであったとしても、
おっきい用を足したあとの孔に
素手で触れるというのはドキドキです。
お風呂に入っているときは、念入りに大切なところを洗うのに・・・
トイレットペーパーのわずか1mm足らずの境に
私達はどんだけ依存していることか・・・
ウォシュレットがかなり普及してきた日本でさえ、
水で洗った後にトイレットペーパーでふき取るために
紙が備え付けられています。
結果的に・・・
昨日は、12cmのギリギリ感に躊躇しつつも
私はトイレットペーパー、使っちゃいました。
インドネシアやマレーシア、タイ、フィリピンの離島などで
仕事(取材だったり調査だったり)したときは、
そもそもトイレットペーパーがついてないし、捨てるところもないから、
「郷に入っては郷に従え」ってことで、
見よう見まね(コーディネーターの女の子に実際、やってみせてもらった)で
びちゃびちゃやってて、これはこれで気持ちよかったのですが、
なんなのかなぁ?この躊躇。
モンゴルでも旧国立デパート(ノミンデパート本店)や
空港近くにあるミシェールエキスポその他で
ウォシュレットっぽい洗浄トイレの販売コーナーが常設されているし、
日本にいったモンゴル人のお土産として
この便座は人気ものです。
でも、わざわざそんなことしなくても、
ちょっとした工夫で自分用の携帯ウォシュレットはできる。
自然に優しいツアーを志すものとしては、
やっぱり、なんとか日常的にトイレットペーパーなどを使わない
排泄行為をマスターすべきだろうか?
草原での暮らしでも、お客様と一緒に草原トイレをすることが多いため
最近は、トイレットペーパー持参でやってしまっています。
ヤギや羊が食べちゃうのか、
うちの周りには、残っていないんだけど。
いろんなことを考えながら、
やっぱり朝、お店でトイレットペーパーを買っちゃいました。
独りで暮らしてる分には、
お尻を水で洗うためには、とっても便利な位置に
洗面台と蛇口がついているのですが、
お客様にまでそれを強要するのはいかがなものか、と。
でも、「くう・ねる・のぐそ」という本は
かなりエポックメーキングな名著であります。
自然と人間の共存共栄をつなぐ鍵が
まさか にあったとは。
読めば読むほどに面白く、
禁断の綴じ込み特集にいたっては圧巻の一言。
そんなわけで、来年までに
なんとか伊沢式をマスターしエコなツアーで普及していこうか・・・
なんて・・・
いや、まだ決めたわけではないんですけどね。
そんなこと断言してお客さんが逃げちゃったら困るから。
でも、自分の排泄物がどこに行くんだろう?
そんな素朴な疑問からもエコライフが広がるっていうこと。
アウトドア派じゃない人にも
ぜひ「のぐそワールド」に触れていただきたいな、と思った次第。
くう・ねる・のぐそ―自然に「愛」のお返しを/伊沢 正名

¥1,575
Amazon.co.jp
にほんブログ村尾篭な話でごめんなさい。