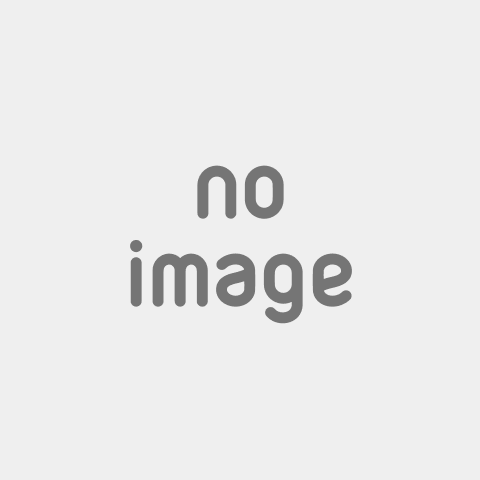The Lobster(2015 ギリシャ、フランス、アイルランド、オランダ、イギリス)
監督:ヨルゴス・ランティモス
脚本;ヨルゴス・ランティモス、エフティミス・フィリップ
製作:ヨルゴス・ランティモス、セシー・デンプシー、エド・ギニー、リー・マギデイ
製作総指揮:サム・ラヴェンダー、アンドリュー・ロウ
撮影:ティミオス・バカタキス
編集:ヨルゴス・モヴロプサリディス
出演者:コリン・ファレル、レイチェル・ワイズ、ジョン・C・ライリー、ベン・ウィショー、ジェシカ・バーデン、オリヴィア・コールマン、レア・セドゥ
①個人的な前置き
この1ヶ月ほどの間に、我々を取り囲む「常識」はずいぶん様変わりしたなあ…と思います。
ほんの1ヶ月前までは、毎朝満員の電車で通勤して、1日中会社にいて仕事して、1日何度も会議して、残業して、終わったら街に出てレイトショーの映画みたりしてたわけです。
満員電車嫌だなあ…時差通勤すればいいのに…とか、この会議意味あんのかな…とか、形式だけの無駄な会合とか手続きとか多いなあ…とか、仲間うちでは文句を言いつつも、どうせ変わらないものと思い込んで、ルーティーンのように毎日を繰り返していたわけです。
時には食事に行ったり飲みに行ったり、休みの日には家族で出かけて遊びに行ったり、していたわけです。
そういうのが、いわゆる「変わらない日常の繰り返し」で。
まあ時々アクシデントとか、思わぬ出来事があったとしても、基本的にはそういう日々が「常識」で、それはずうっと変わらないものと思っていたのですね。根拠もなく。
それが、今は全然違う。
仕事は基本テレワークになりました。毎日ではないですが。満員電車に乗って通勤することは、基本的にはなくなりました。
朝礼とか定例の会議とか、一切なくなりました。なくしてみれば、誰も困らない…というね。なんて無駄な時間を過ごしていたんだ…。
会社にも行かず学校もないので、家族みんなが基本ずーっと顔を突き合わせてます。
映画館に行けないのは寂しいし、休みの日にも遊びに行けないのはストレスたまりますが、一方で家族の時間はいつになく濃厚なものになりました。
なんていうのかな。それが良いとか悪いとかはさておきとして、僕がこれまで当たり前と思っていた「常識」は、別段当たり前で不変のことではなかったんだな…なんてことを思ったりしました。
状況が変われば、僕たちの世界の常識も、あっという間にガラッと変わってしまう。
意外に、簡単に。
そして、これほど簡単に変わってしまうものなのに、それが日常である間は、それを疑うことも、変わり得ると想像することも、まずないのだ…ということ。
実際、1ヶ月前に今の生活なんて到底想像できてなかったですからね。
常識というのはそういうもので、多分今も僕たちの周りには、実は大して根拠もないのに、当たり前で不変だと思っている常識が、無数にあるんだろうと思ったのです。
②常識の滑稽さを外側から見せる
「聖なる鹿殺し」「女王陛下のお気に入り」のヨルゴス・ランティモス監督の2015年の作品。日本公開は2016年です。
「ギリシャ悲劇的な神の視点」「冷笑的で、ブラックな作風」「黒い笑い」が特徴のランティモス作品ですが、これはギリシャ出身のランティモス監督にとって初めての英語作品となります。
2015年のカンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞。
「聖なる鹿殺し」のコリン・ファレル、「女王陛下のお気に入り」のレイチェル・ワイズとオリヴィア・コールマンが出演しています。
「ロブスター」は、非常に奇妙な「常識」の中で生きる人々が描かれています。
その「常識」は我々の生きる世界のそれとはまったく違っていて、どうしてそうなったのかの説明もまったくありません。その世界ではそうである、というだけ。
未来とか過去とかというわけでもなく、もうほとんど別の惑星の出来事のように感じられます。
「ロブスター」の世界は、パートナーを持ち、結婚して子孫を残すことが至上の価値となっています。結婚していない成人は人権を認められません。
離婚や死別などで伴侶を失った人は、町外れのホテルに集められ、そこで生活させられます。
そこでは45日以内に配偶者を見つけなければなりません。配偶者を見つけられたら、さらに24日間の同居生活によってテストされることになります。
期限までに配偶者を見つけることができなかった人は、動物に変えられてしまいます。
そんなメチャクチャな…と思っちゃうような設定ですが、しかしこの世界の中で暮らす人々にとっては、それが常識。まったく疑問に思っていません。
自慰禁止とか、違反した場合は手をトースターで焼かれるとか、嫌だなあ…と思いつつも、みんなはあくまでも「仕方ないこと」として従っています。
「ダメだったら動物にされちゃう」というとんでもないルールにしても、みんな「できれば動物になんかなりたくないなあ…」と思いつつ、これもやっぱり「仕方ないこと」として受け入れています。
確かに理不尽で、「嫌なこと」ではあるけれど、でもそういうものなんだから仕方がない。それが「常識」なんですね。
そんな厳しい罰則があるなら、とりあえずくっついちゃえばいいじゃん…とか思うんですが、この世界では「恋愛のルール」も一風変わっているんですね。
好きという感情はあまり重視されていなくて、二人に「共通点」があることが恋愛関係になっていいかどうかの条件になっています。
「鼻血が出やすい」とか。「性格が冷酷である」とか。「近視である」とか。
共通点があるとわかったら割とスムーズに恋愛関係になれるし、逆に、好きという感情が強くても、共通点がなければ恋愛関係を築くことはできません。
それは社会のルールがそうだから…というだけじゃなくて。共通点がないと、気持ちの上でも恋愛関係を持てないんですね。そういう習慣が、身に染み付いてしまっているから。
映画を観てると、「そんなもん互いに好き合っているんだったらルールなんて無視すればいいやん」とか、「そもそもこんな誰も得しないルール、撤廃すればいいやん」とか思っちゃうんですが、それはこちらが「我々の世界の常識」で見てるから。
常識の中にある人にとっては、「それが変えられる」とか「別の生き方がある」ということ自体、思いつけないものなんですね。
この感じが、我々の生きる世界を実に「いや〜な感じで」写しとってるなあ…と思えて。
実際、我々の世界も同じことで。「毎朝キツキツの満員電車に乗って、ラッシュに揉まれながら出勤するなんて嫌だなあ…」と誰もが思いつつ、「でもそういうもんだから…」と勝手に納得して、仕方がないものとして受け入れている。
「緊急事態」が起こって、本当に必要に迫られたら、時差出勤とかテレワークで結構簡単に回避できることなのに、回避しない。回避できるという発想さえ持たない。
なんとなーく、現状に満足してしまってる。
だから、「ロブスター」のこの極めて特殊な奇妙な社会は、我々の社会の意地悪な戯画化、写し鏡に他ならないんですね。
③特有の意地悪な視点
「聖なる鹿殺し」も「女王陛下のお気に入り」も極めて意地悪な映画で、「意地悪」はランティモス監督の最大の持ち味だと思うんですが。
そういう視点で見ていくと、本作も相当に意地悪な作品であることがわかってきます。
恋愛や結婚がルール化されてて、大の大人が自慰まで管理され、結婚できなかったら動物にされちゃうアホな世界。そこで、何の疑問も持たずに唯々諾々と従うアホな人間たち。
このアホさこそが、お前ら自身の姿に他ならない…というのが、ランティモス監督がこの作品で終始言ってることですね。
彼の映画は、いつもでっかい鏡なんだと思います。映画を観る我々自身が写ってる鏡。
主人公は「どうせ動物にされるなら、ロブスターがいい」とか言うんだけど、ロブスターの生活なんてろくなもんじゃないじゃないですか。
海の底の泥の中を這い回って、魚の死骸とか食って、交尾して、人間に捕まったら鍋で茹でられてお腹の肉を食われて。
でも、当のロブスター本人は、たぶん不満とか思ってない。ロブスターに生まれたからには、嫌だけどまあ仕方がない…と思ってそうじゃないですか。
別の立場に立って見れば、我々も、映画の中の人々も、ロブスターでさえも、そんなに変わらないだろう…ということですね。
そういうシニカルな視点がずっと貫かれているんだけど、その中で生きる人々の懸命さも、また描かれていて。
奇妙でヘンテコで、アホみたいに思える世界だけれど、そこから逸脱しない中で、良かれと思って必死で生きている。それもまた、人間らしい姿なんですよね。
冷笑的な視点の中でも、そんな人間味の部分もしっかり描かれていて。そこがこの監督の惹きつける部分だと思います。