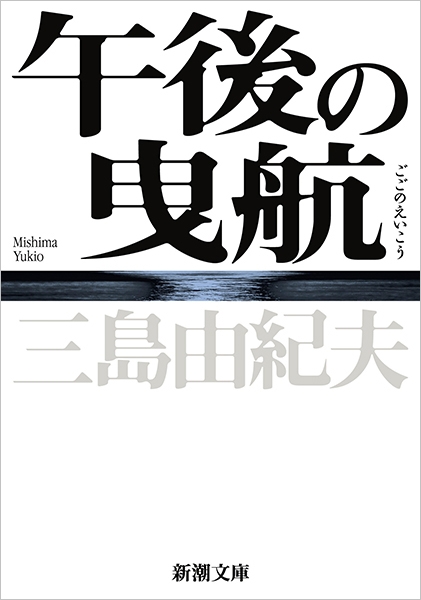二期会がオペラ『午後の曳航』を上演するので、原作の三島由紀夫『午後の曳航』(1963)を読みました。
内容(「BOOK」データベースより)
十三歳の登は自室の抽斗奥に小さな穴を発見した。穴から覗く隣室の母の姿は艶めかしい。晩夏には、母が航海士の竜二とまぐわう姿を目撃する。竜二の、死すら厭わぬ船乗り精神と屈強な肉体に憧れる登にとって、彼が海を捨て母を選び、登の父となる生ぬるい未来は屈辱だった。彼を英雄に戻すため、登は仲間と悪魔的計画を立てる。大人社会の綻びを突く衝撃の長編。横浜港で船員らに取材し一気に書き上げた。38歳の三島が子供世代の目で描く大人の虚妄。
【新装版、新・三島由紀夫】
僕たちが許しているのだ。父親、教師ら塵芥(ごみ)の存在を――。38歳の三島が子供世代の目で描く、大人の虚妄。〔新解説〕久間十義
十三歳の登は自室の抽斗(ひきだし)奥に小さな穴を発見した。穴から覗く隣室の母の姿は艶めかしい。晩夏には、母が航海士の竜二とまぐわう姿を目撃する。竜二の、死すら厭わぬ船乗り精神と屈強な肉体に憧れる登にとって、彼が海を捨て母を選び、登の父となる生ぬるい未来は屈辱だった。彼を英雄に戻すため、登は仲間と悪魔的計画を立てる。大人社会の綻びを突く衝撃の長編。
解説・田中美代子/久間十義。
【本文冒頭より】
おやすみ、を言うと、母は登(のぼる)の部屋のドアに外側から鍵をかけた。火事でも起ったらどうするつもりだろう。もちろんそのときは一等先にこのドアをあけると母は誓っているけれど。もしそのとき木材が火でふやけ、塗料が鍵穴をふさいだら、どうするつもりだろう。窓から逃げるか。しかし窓の下は石のたたきで、この妙にノッポの家の二階は絶望的に高かった。すべては登の自業自得なのだ。彼が一度、「首領」に誘われて夜中に抜け出してからのことだ。……(第一部「夏」第一章)
まずは三島由紀夫の原作を読まなきゃというわけで読んでみた。
最初の方は官能小説で、その後に屈折した少年たちが出てきて猫の惨殺シーンがあったりで、とにかく気が滅入って読み進めるのが苦痛![]() 三島は自分には合わないのかなと諦め、全部で約200ページのうち40ページあたりでストップ
三島は自分には合わないのかなと諦め、全部で約200ページのうち40ページあたりでストップ![]()
私も少年時代は真面目一辺倒できたわけではなく、そこそこな悪いこともいけないこともそれなりにしてきたけれど、この少年たちほど屈折していなかったので、ほぼ共感できない。おそらくだけど、「首領」が突出して悪くて、2号以下は彼に逆らえずに無理やり悪いことに合わせていたような気もする。登も父が死んだとはいえ何不自由なく育っていて、なんなんだろう。大人への反抗心や屈折した気持ちは三島由紀夫の中にもあったのかな。
公演前夜に気を取り直して読み始めると、後半は結構読みやすくて、公演前までにスイスイと最後まで読めた。最後はそこまでやる必要があるのかな〜 「首領」の父親への怒りがそこまでやらせたのか…