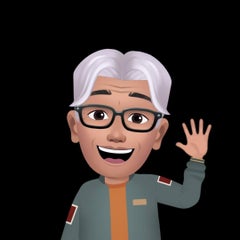ようやく梅が咲き出し、春らしい陽気となってきましたね。蟹江町内にある「源氏塚公園」の紅梅が咲き出してきましたよ。

3月に入り春らしい陽気となってきました。菜園作業が大忙し状態ですが、たまには町内を散策してみたいと思います。この日は快晴状態、まだ町内でゆっくりと散策していない源氏・才勝地区周辺を歩くことにします。スタートは近鉄蟹江駅、蟹江駅前商店街を通り抜け蟹江川堤防に出てきます。そして川に架かる記念橋を渡ると源氏才勝地区に入りました。

蟹江川右岸(西側)堤防沿いに民家が建ち並んでいます。水郷の町らしい風景ですね。

堤防から降りて源氏才勝地区に入りました。元々この地区は、西之森村の枝郷(出郷)として江戸時代になってから形成された地区です。最近まで純農村の風景が残っていました。昭和50年代に蟹江町役場庁舎が移転、名古屋港と一宮市を南北に結ぶ西尾張中央道が開通し、併せて住宅地が建設されるなど都市整備が進むと近鉄蟹江駅周辺を凌ぐ商業地区として発展することとなりました。表通りから一歩街の中に入るとこんな狭い路地や畑が残っているところがあります。これから春の菜園作業を行おうと思っている水郷、ついつい畑で栽培されている野菜が気にかかるところです。
源氏才勝(略して源才)区は、源氏と才勝の両地区から形成されています。写真は才勝地区の鎮守様である神明社です。祭神は天照大神(あまてらすおおみかみ)、創建は解りませんが、江戸時代末期、慶応4年(1868)の西之森古文書に記述され、明治5年7月に村社扱いをされています。なお、才勝の地名は、このあたり一帯に「皀莢(サイカチ)」の木が多く群生していたことに因むようですね。

才勝地区の住宅地から表通りに出てくると佐屋川が見えてきました。写真左は源才地区と新蟹江地区の間に架かる霞切(かすきり)橋です。なかなか風情を感じる橋名ですね。右は同じく近鉄名古屋線の佐屋川橋梁、3両編成の普通電車が通過していきました。

暫く歩くと源氏塚公園が見えてきました。かつてこの一帯は源氏島と言われる小島であったとされています。平成4年に「ふるさと創世資金」を活用し公園が整備されました。
これは源氏塚の碑です。源氏塚や源氏島の由来ですが、平安時代末期頃、この周辺は、一面広々とした海で所々に小島が点在していました。平治元年(1159)、都で起こった平治の乱の際、平氏の棟梁「平清盛」に敗れた源氏の棟梁「源義朝」は東国で再起を図るべく美濃国青墓(現在の岐阜県大垣市)から尾張国内海野間(愛知県知多郡美浜町)へ小舟で下る途中、この小島に暫し舟を止めて休息したと言い伝えられているところから「源氏島」、小島の一番高いところに義朝が休息したことから「源氏塚」と名付けられたと云われています。
江戸時代の文献資料である『張州府志』では、「里老伝えて言う。源義朝京の軍に敗績し、微行して張州に赴くとき、船を此に駐するが故の名なり、開墾して田となる。猶呼びて源氏島なす」と記されています。平治の乱から約1000年が経過、先程述べたとおり、歴史由来もあり公園整備され、今では住民の憩いの場となっています。写真は蟹の噴水です。小島だった頃、ここにも多くの蟹君が生息していたことでしょうね。

この公園内には数多くの梅の木が植えられています。今回の「まち探検」で特に楽しみにしていた梅花観察、もう満開になっていると思っていたのですが。。日当たりの良い部分に植えられている紅梅は、5分咲き程度でした。

それでもやはり開花した紅梅は綺麗ですね。とても上品さを感じさせられます。
白梅の方は日当たりの悪いところにあるのでまだこんな状態です。ちょいと残念な状態でした。

公園内には、紅梅・白梅の他、桃色や紅白が競って咲く源平梅などいろんな種類の梅が植樹されていますが、どれも蕾状態でした。次の週末当たりからが見頃のようですね。写真右は公園内の時計台、先程の噴水と同様、風見鶏ならぬ風見蟹君です。蟹江町は、「蟹」地名の付く唯一の自治体です。町内の施設には多くの蟹君のモニュメントが作られて、とても面白いです。
源氏塚公園の北側にある建物、敷地内には何やら櫓らしいものがあります。これは「尾張温泉郷・湯元館」さんの建物、そして源泉櫓でした。「東海 の潮来」と文豪吉川英治が絶賛した尾張水郷地帯に愛知 県下唯一、摂氏55度の湧き出る温泉 として当時の愛知県知事桑原幹根氏が、「蟹江温泉」というよりも「愛知の尾張を代表する温泉」として「尾張温泉」と命名したとのことです。湯元さんはその中でも歴史と伝統 のある老舗の日本旅館。湧き出る温泉は、含重曹硫化水素泉として、慢性リュウマチ、神経炎、骨や関節の運動障害、糖尿病 、疲労回復 などに効果があるとのことです。門構えなど日本旅館の情調を残し、心が落ち着く雰囲気ですね。


一度源氏塚公園に戻り佐屋川沿いの道を歩くことにします。道路両側にはフランス料理レストラン「くろかわ」さんの建物があります。重厚な日本建築作りの建物ですね。最近はTVなどで「天使のCafe」が紹介され有名です。
そこから暫く歩くと源氏地区の鎮守様八幡社に辿り着きました。祭神は応神天皇、御神体は八幡力大菩薩です。創建は不明ですが、先程源氏塚公園の由来で紹介した江戸時代の『張州府志』記述の伝承をもとに、村人が源氏の氏神である八幡社を鎌倉の鶴岡八幡社から勧請したとされています。なお、これ以外にも地区内には天王社がありましたが、寛延3年(1750)浮場新田(現弥富市)に請われて引社(移築)したことが古文書などに記されています。

地区を南北に縦断する西尾張中央道を渡り、入った公園が源氏緑地です。散歩道沿いには文学碑が設置され「文学遊歩道」と名付けられています。黒川紀章氏の父である黒川巳喜氏の俳句「どか雪に 明けて濁世を 隔てけり」を刻んだ文学碑も設置されています。
公園内から佐屋川沿いに創郷公園を望んでみました。とても水郷地帯らしい景観ですね。

創郷公園を目指して文学遊歩道を進んでいきます。散歩道両側には多くの木が植樹され、海抜0㍍地帯には珍しい緑地帯となっています。

創郷公園に入りました。写真左の建物は蟹江町図書館です。写真右は当町出身の探偵小説家である小酒井不木の生誕地記念碑です。平成16年(2004)4月に建碑されたものです。揮毫は、新蟹江小学校の後輩にあたる世界的建築家黒川紀章によるものです。

佐屋川創郷公園は「水と人とのふれあい広場」「水郷の里再生」を目的に作られた都市公園です。

公園内には噴水や展望台が設置、人工の滝なども作られ、佐屋川沿いに4月は桜、5月から6月には町の花である花菖蒲が開花します。とても親水性のある公園です。
展望台に登ることにします。低地の丘に設置されているので濃尾平野が360度雄大な景観を見渡すことができます。遙か向こうに名古屋駅の高層ビル群が見ることも出来るのも良いですね。正月元旦の「初日の出」を拝むには絶好の場所だと思います。

公園から北へ暫し歩くと尾張温泉郷通りに出てきます。道路沿いには桜並木があります。

あと1ヶ月ほどすると桜並木が満開、さくら祭も開催されますよ。ゆっくりと散歩すると面白いと思います。今年のさくら祭は、確か4月7日(土)に開催されると思いました。
温泉郷通りには、このblogで何度も紹介させていただいている足湯「蟹江の郷」があります。何度お邪魔しても満員ですね。足湯近くの歩道は、大相撲名古屋場所の際、蟹江町に宿舎を置いた二子山部屋、高砂部屋の両力士、貴乃花関や朝青龍関などの足形を刻んだタイルが設置され、別名「大相撲ストリート」と呼ばれています。
足湯に隣接する建物は、尾張温泉観光ホテル(手前)と尾張温泉東海センターです。東海センターは、昭和38年、遊園地や演芸場を配し、入浴を楽しみながら過ごせる「東海ヘルスセンター」として発足、昭和41年、東海ラジオの子会社東放企業が温泉掘削に成功し、高温良質・湯量豊富な温泉が噴出し、現在に至っています。当温泉は「源泉100%かけ流し」で、日本名湯100選にも選ばれています。

建物北側に移動します。写真左は東海センター正面玄関です。そしてその横には「手湯」があります。やはり温泉なので、とても温かいです。足湯には入れませんでしたが、手湯で温泉を実感させていただきました。
尾張温泉東海センター前に架かる水鶏橋から佐屋川北側を望むと川中に桟橋が設けられ、多くの太公望方々がヘラブナやボラ釣りを楽しんでみえました。ここは特にヘラブナ釣りのメッカとして有名なのだそうです。

水鶏橋を渡ると観音寺地区に入りました。かつて、ここには今地区に移転した観音寺というお寺があったことからその地名になったとのことです。写真左は、先月の近鉄ハイキングにも紹介した尾張稲荷大社、温泉の守護神として昭和41年12月に京都伏見稲荷から勧請された神社です。昭和57年3月に新社殿が建設されました。写真右は、観音寺地区の鎮守様である風之宮社です。祭神は、風の神「志那都比古神(しなつひこのかみ)」と「志那都比賣神(しなつひめのかみ)」、風は稲作に欠かせないものとして尊重され、悪風は魔風として恐れられていたため、大風から村人を守るために祀られた神社とされています。創建は不明、慶安4年(1651)に修造するとの記録があり、明治5年に村社に列格されています。


賑やかな温泉郷通りと比較して観音寺地区内はひっそりとしていましたよ。なんとなく純農村という雰囲気です。

再び佐屋川にでてきました。こちらの釣り場も多くの釣り人で賑わっていましたよ。それにしても凄いですね。
釣り人たちを見物していたらJR関西本線佐屋川橋梁を普通電車が亀山方面へ通過して行きました。プチ鉄の血が騒いだ一瞬でした。大都市名古屋と工業都市四日市を結ぶ幹線ながら単線で日中は2両編成が主体、何とも長閑なかぎりです。ここで明治26年(1895)に開通した関西本線の歴史について説明をしてみましょう。関西本線の前身は、私鉄「関西 鉄道 」によって敷設されたものでした。関西鉄道は、草津 ~四日市間を完成した後、名古屋進出を考えて日本有数の水郷地帯を東西に横断する線路の敷設を企てました。その関係で、南北に流れる河川及び水路を跨ぐ橋梁の建設、水害から線路を守るための築堤建設が必要とされました。ところが沿線地域では、排水や農作業が困難になるとのことから反対運動が行われるところが続出したようです。当町でも西之森村から愛知 県知事宛「線路敷設反対請願書」が提出されています。このような困難もありながらも何とか完成。5月24日の開通前の21日に行われた「開通記念式」では沿線各駅で盛大な祝賀行事が行われたようですね。

写真 は佐屋川橋梁を通過する「快速みえ」です。水郷の情緒によく橋がマッチしますね。関西鉄道は、その後路線を途中の柘植から西へ延ばして奈良 へと到達して大阪 鉄道を合併吸収し、名古屋~大阪 湊町(現JR難波 )を本線として、現在の関西本線の路線が完成しました。明治35年と37年には当時の官設鉄道(現東海道本線)との間で名古屋~大阪間の旅客争奪(運賃値下げ・過剰サービス)合戦を華々しく展開したことはあまりにも有名です。片道分のお弁当をお客に振る舞ったりした過剰サービスが有名など今の自由競争原理をいち早く取り入れた鉄道会社でもありました。その後国有化されてまったく近代化されずに、距離的には名古屋~大阪間の最短距離を結んでいながら路線の3分の2以上が単線。そして2分の1が電化 されていないというローカル線となっています。蟹江町内もやはり単線部分が続いています。複線用の用地は確保されているのですが、採算上の問題も有り、未だに単線状態となっております。昭和50年代複線化に理解を示した地権者の皆さんは、土地買収に協力したと伝えられています。その後30年近く放置したままというのは納得いきませんね。もっと貴重な土地を有効利用すべきだと思いますよ。さて、この橋脚は明治26年開通当時のもののようです。橋脚なども機関車 の大型化により大正時代に改修された物がありますが、敷設当時のものも佐屋川橋脚・日光 川橋脚などまだ現存しているものもあるようです。もう110年以上現役で活躍していることになります。そうだとすると凄いです。ちょっとした近代土木遺産ですね。

佐屋川釣り場から蟹江町みどりの家へと向かいます。この施設は、町内の在住の60歳以上で就業を希望する方が、温室やビニールハウスの中でパンジーやポインセチアなどの花を栽培するために昭和62年4月に設置された施設です。季節の分かれ目ですが、いろんな鉢物やポットが売られていましたよ。

みどりの家から歩き、西尾張中央道を横断して再び源才地区へ戻ることにしました。写真左は学戸公園、右は学戸小学校南側水路沿いにある桜並木です。この地区は新しく都市整備により区画された地区なので公園や緑地帯が多いところですね。まだ桜は蕾が固い状態でしたが。。

ここもあと1カ月ほどすれば桜が満開状態となります。町内には多くの桜の名所がありますが、ここの桜もとても見事な桜です。満開の時期が楽しみですね。ここから東に歩いて蟹江町役場に到着し今回のまち探検は無事終了です。梅が咲きだしています。そして桜も間もなく開花、ゆっくりと散歩するには良い時期ですね。MYblogのカテゴリー「蟹江散策」で、町内の一地区を「まち歩き」した特集シリーズを過去に何度も紹介してきましたが、今回のまち探検で、ほぼ蟹江町内全域を歩いたと思います。休日に思い付きで歩いたので完結まで5年間もかかってしまいましたよ。過去の「地区まち探検」を行った特集記録は以下の通りです。関心があれば、URLをクリックしてご覧ください。画像をクリックした場合は新規ウィンドウで開きますよ。今後とも蟹江町の魅力を探って「蟹江散策」シリーズを続けていく予定です。菜園シリーズ同様、よろしくお付き合いくださいね。