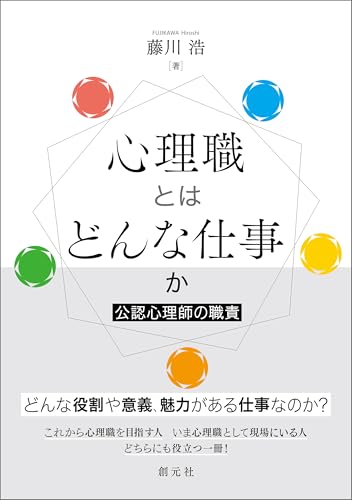現代社会の子育てへの理解について書かれた福祉的視点での本です。
読んでいて、家族って何だろう?ということまで考えてしまいました。
正直多様性がどーのというのはむつかしくてまだ私の中で受け入れられませんでした。
読んでいて共感できたのは、社会福祉士(国家資格)を持つソーシャルワーカーの専門性でしょうか。
最近は公認心理士というのが国家資格でできていますが、ソーシャルワーカーの負担をちょっと減らすためできたのでしょうか?!その辺よくわかりませんが、結局いろんな専門分野ができても上手に連携ができるのか、機能するのかが焦点な気もします。
自分自身福祉を専門性をもって勉学してきたわけですが、進路の時に揺れたのは心理分野でもありました。
自分の興味の分野だからこそいまだにそういう本を読んだりはしますが、自分には向いてなかったんだ職にしなくてよかったんだと思えます。
私は不安を抱える親御さんに上手に社会の手助けができそうにないな・・・と。
(もともとコミュ力ないですし、負担をわかってあげられるように引き出す言葉も持ってないなぁ・・・結局私は心理においても福祉においても分析(?)がしたかったのかも??楽にさせてあげたいとかじゃなく、自分の立場をほかを見て分析したいかんじ?)
子育てって時代でほんとかわります。
布おむつじゃないと濡れた感覚がわからなくてトイレトレーニングが遅れるとか?!(そんなことはない、そして幼稚園はいるまでに外しておかなきゃいけないとかいうプレッシャーも必要ない)
沐浴の後は白湯だろーとか(今はミルク(母乳)でいいといわれている)。
抱き癖ガーとかも今はいわないし、泣かせて肺を強くしろとかも論外な感じだしね。
そして私の時代やってた母乳前の乳首の洗浄?あれ、今はいらないらしいですねー(薬剤成分が新生児に悪影響とまで言われてる!)
ほんと、時代によって変わるし、年寄りが子育て経験者だからと出しゃばって若い家族つぶしにかかるようなことしちゃいけないよな~とおもいます。
子育てバツなんて言われる時代に、誰が子ども持ちたいと思うのか。
正直私の時代だって、私も子ども持ちたいと思ってませんでした・・・女の負担が相当だなと、不安で仕方なかったよ。
で、私の時代に活用したのが、子供育てる不安を言う会に参加すること。
これ、自治体でやってるやつで、子どもの検診時に親の気持ちみたいなのを表情で表現してるのに〇したりしたときに目をつけられてこんなのあるよーと紹介?されるんですが、子供育てる不安、家庭の不満(社会の不満)なんかを子供預けて(隣の部屋で預かってくれる)1時間程度の時間ですが・・・話を聞いてくれるのがありました。
正直それに来てみたら?って言われる時点で「あ、私・・・ブラックリスト乗ったんだ」っておもいましたw
子育て上手にこなせてない人が行く会とおもってましたしね。
ソーシャルワーカーさんが数名、育児に自信がない(?)ママさん10名弱がね、自分の自虐ネタ披露ってかんじで、とりあえずしゃべるだけです。
誰も責めたりしない、助言くれるわけでもない、ただ話してみてすっきりする・・・そんなかんじ。
それ以上にたった1時間でも子供と離れて、ママじゃなく、自分(個人)になった感じがすっきりさせてくれる空間になったんだろうなと今は思います。
みな子供にイライラすることもある、自分虐待してるんじゃない感と不安になる、パートナーは助けてくれないとか親世代からのお小言でしんどいとか・・・自分だけじゃないんだというどこか安心感というかね、類友発見的なのがよかったのかなぁ。
そこでのメンバーと個人的なやり取りも禁止でほんとその場だけ・・・だったけど、結構大事な空間だと思うんだよね。
今の子育て世代にも必要な空間じゃないかなと、思います。
子どもとちょっとだけはなれる、ちょっとだけ不安をしゃべる。
それが無料だったこと、月に1回しかないし別に欠席の時連絡もいらないあの空間、もっとたくさんの人が利用できたら・・・と思ったんですが、なかなかむつかしいのでしょうか。
ワーカーさんの負担や行政の負担ももしかしたらかなりのもんかもしれませんが、結構これ、有効手段だったのではといまではおもいます(ワーカーの仕事を知るいい機会でもある)
私の中で子供を預ける選択じゃなく、我が子を自分で育てる人に専業育児手当をつけるべきという考えがもともとあるんですが、この本読んでたらフィンランドに私が思う制度(在宅保育手当が3歳未満児を家で保育してる親に約6万円月に支給されるというのがあるそうです)があって、ぜひ日本でも母親を産むだけの機械であとは保育所に預けて働いて税金納めよとするのではなく、育てることへの対価を出してあげてほしい、そしてそれを受け取るというのは育児の報告(虐待の確認)もしかりかなと・・・・そして検診と子育て不安などのディスカッションなんかができればいいのでは?とずっとおもってたことなんですが、どうでしょう?!
病児保育とかもできれば子供がそばにいてほしいと願う相手にとおもっているわたしですんで^^;
愛着の章であったように、人と振れることで安心感をもらうという点で病気の時は特に不安もあるでしょうから、どうしても仕事で・・・とかは仕方ないのかもしれませんが、できればそばにいてあげられる環境とかね。
何でもかんでも家で見ろとか、母親の負担を増やしたいわけじゃないんですけどね・・・なんか今の保育園増やせだけの政治家の方法は違うなと私は思ってます
この本の場合、普通に両親がいて健常児で・・・というのは少ないのですが、私のような環境でも子育ては不安で、母親の責任がとっても負担でしんどくてというのがあったんで、もっと家族っていいね見たいなのが子供にも伝わる家庭が増えて、自分も家庭持ちたい!子供がいる家庭作りたい!と思える子を増やさないと少子化はまず食い止められないかなと。
本の感想が少なめですみませんが、本では障害児を育てるという点が多様性の部分として取り上げられてます。
もちろん同性愛で里親制度などで子供を・・・というのもありますが、傷害のない子を望むという点を変えていくのはなかなかむつかしいかなとかんじます。
胎児の段階でその選択をし、陽性なら堕胎率が高いことを責められないとおもうし、傷害があれど生まれてきてよかったと思える社会というのは大事だとおもいます。とはいえ、いろんな負担が多すぎて、そこまでを・・・まず、家庭が望めるかなと。結局社会で子育てを打ち出しても、家庭軸が根本ですし。
なので私は、多様性を認めないわけではないけれど、今はもっと手始めでやりやすいところから…と思いました。
いっぱい気になるところ考えさせられるところが多くて私は読んでよかったと思える本だったんですが、子育てバツなんて言葉が独り歩きして少子化食い止められない社会じゃなくしたいなと、子育てつらいけど子供の成長っていいねと思える何か、バツの面だけが目立つ世の中を変える方向のヒントが、取り入れやすい何かがあれば・・・子供にかかわる専門家(保育士や教師など)にヒントはあるのかなと、読んでもらえたらなと思いました。
これと同時進行で「心理職とはどんな仕事か」という本も読んでたんですが、そちらのほうが言葉かけの具体的なものはあったかな?(心理的分野からの子供とのかかわりなんかの事例もかかれてます)
なんか久々に勉強した感が強くて、まとめられない自分のバカさが露呈しただけになった^^;