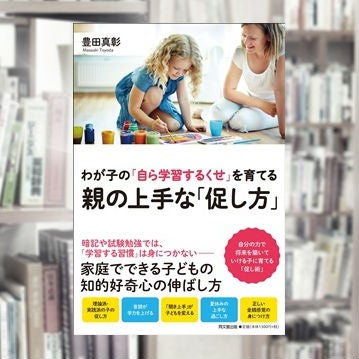発売中!
わが子の「自ら学習するくせ」を育てる 親の上手な「促し方」
定価1300円+税
子どもへの促し術をたっぷり盛り込んだ1冊。
購入はこちら↓ ↓ ↓
■■■■■
本が紹介(書評)されました!↓ ↓ ↓
「教える教育」から「促す教育」へ

http://y-nlife.jp/education/
ブクペ 著者まとめはこちら↓ ↓ ↓
http://bukupe.com/summary/15733
Are You HAPPY? 1月号に掲載されました!↓ ↓ ↓
全国 34都道府県、115の図書館で蔵書されています。※2018年2月18日現在
下記でお住いの地域を検索できます。
日本最大の図書館検索カーリル
https://calil.jp/settings
本が紹介(レビュー)されました!↓ ↓ ↓
◆ダ・ヴィンチニュース 読みたい本がここにある
学校では教えてくれない「わが子」に向いている伸ばし方 2018/2/5

https://ddnavi.com/review/433470/a/
1人でも多くの子供達が、一つでも多くのご家庭が笑顔になれれば嬉しい限りです。
■■■■■
先日、図書館検索カーリルで著書の蔵書状態を調べていて気がつきました。
大学の図書館でも蔵書され始めたみたいです!
★東京農業大学(東京都世田谷・神奈川県厚木)
★日本福祉大学附属図書館美浜本館(愛知県)
大学の図書館ってことは教員を目指している学生さんにも読んでもらえるかなw
2月も中旬になりそろそろお仕事の都合などで新しい引っ越し先を
見つけているご家庭も多いと思います。
今回は東京23区の各自治体の小学校教育特徴をご紹介します。
不動産・住宅サイト SUUMOで行政区別 東京23区 教育環境というページの情報を
引用させていただいています。是非参考になさってください。
●この1・2年で小学校は大きく変わってきた!
・23区では「少人数学級」という低学年時の学力定着を目的とした授業があります。
◎杉並区では、少人数指導を高学年まで実地、今後各区も高学年まで拡大することが予想されます。
・区立小中学校へ非常勤講師の配置が増加
特にこの1・2年目立つのが外国人の外国語講師が増加!
◎北区では区立小中学校へ126人の非常勤講師を配置
◎大田区では地域の人材や教科ごとの校外専門講師を起用。
これら外部の力を使った特別授業や補習教室により、
児童一人ひとりに合わせたきめの細かい教育を行っています。
●小中一貫教育に取り組む区が増加傾向
小中一貫教育というのは小学校6年間、中学校3年間合計9年間を見通した教育です。
形式は大きく3タイプ
・校舎が一体の付属型
・校舎が別の別体型
・校舎が別で連携型
区内小中学校の連携を強化し、小学1年から中学3年までの義務教育9年間を通じた
英語教育などに取り組んでいます。
◎練馬区では平成23年4月に区内初の小中一貫教育校も開校。
◎世田谷区では「世田谷9年教育」を掲げ、区が独自の教育カリキュラムを策定。
◎足立区の「魚沼自然教室」など、体験学習を行うケースが増加しています。
●親世代と違ったパソコンやタブレットパソコンを使った授業が増加!
私を含めた保護者は公開授業などでわが子の授業の様子を見に行くことがありますよね。
昔と大きく違うところはパソコンやタブレットパソコンを使った授業が普通になってきていること。
ただし、各自治体での導入状況に差がある状況なので学校公開日など実際に授業をみて
確かめてみてください。
それでは不動産・住宅サイト SUUMOさん掲載の23区別特徴を引用にてご紹介します。
● 都心部

千代田区
道徳教育や体験学習を通じ「豊かな人間性」を育成。規範意識や人間関係形成能力といった社会性も養う
心の教育コーディネーター派遣による道徳教育の充実や、自然体験、福祉体験を通じた「心の教育」を推進。平成23年度からは小学校に「スクールライフ・サポーター」が入り、子どもたちの学校生活を支援する。
中央区
現場で教員をサポートする人材を一般公募。土曜スクールや特別授業で確かな学力、個性を育む
区立小中学校では「指導サポーター」を募集中。土曜スクールの指導、プール教室の安全指導、学校図書室での読書指導など、さまざまな教育支援を行う人材を活用している。
また、区独自にを配置し、少人数指導の充実にも意欲的。
港区
「教育の港区」を掲げ、教育環境整備に力を入れる。小学校1年生から週2回の国際科授業。
24年度からは国際学級も開設。
教育課程特例校の認可を受け、区立の全小学校で1年生から「国際科」の授業を実施。国際理解を深め、世界の中で活躍できる日本人の育成を目指す。
また、区独自に講師を各校に配置し、少人数指導による授業の充実を図っている。
新宿区
小学校入学前の不安を解消し、スムーズに就学するための「入学前プログラム」を土・日曜に実施
子どもの小学校入学をスムーズに行うための「入学前プログラム」を実施している。同じ小学校に入学する子どもと保護者を対象に、ワークショップなどを開催。親子の連帯感を高め、入学前の不安を解消するのが目的だ。
文京区
低学年からの確かな学力を定着させるとともに、新しい学習指導要領が示す「生きる力」の育成に力を注ぐ
小学校低学年時の複数担任制や少人数指導を推進。基礎学力の定着とともに、子どもの社会性や自立心といった「生きる力」を養うための教育環境を整備する。
「授業改善推進プラン」では、子どもの学力に応じた授業の改善を図る。
渋谷区
ゆとりある学習スケジュールを可能にする「二学期制」を実施。授業力アップに向けた取り組みも積極的
多くの学習活動時間を生み出すため、全ての区立幼稚園、小中学校で「二学期制」を実施。三学期制に比べ学期が長期になり、無理のない教育活動が展開できる、行事や体験学習を増やすことができるなどのメリットがある。
● 東部
他区にさきがけ幼稚園や保育園での「就学前教育」を強化。小学校との円滑な接続にも力を注ぐ
幼稚園と保育園の両機能をもつ認定こども園を、区内2カ所に設置。親の就労の有無に関わらず、就学前の子どもを受け入れる。今後は幼稚園、保育園、こども園と小学校の連携を強化。幼児教育と小学校教育の円滑な接続を図る。
墨田区
区内児童の確かな学力を育む「新すみだプラン」が始動。教員の増強など指導体制を一層強化する予定
平成23年度から、子どもたちに確かな学力を身につけさせる「学力向上『新すみだプラン』」が始動。区独自の指導資料策定や幼小中一貫教育推進のための教員増強、放課後クラブ支援のための外部人材養成などに力を入れる。
江東区
小学校1・2年生クラスに講師を増員。30人以下の少人数学習を実現し、基礎学力の定着を目指す
実質30人以下の少人数学習環境を小学校1・2年生クラスに整備し、基礎学力向上を図る(平成23年度は1年生が対象)。放課後の安全な居場所となる「江東きっずクラブ」を新たに7小学校に開設。
平成31年までに区内の全小学校で実施予定。
荒川区
英語を使ったコミュニケーション能力や、幼児期から芸術的な表現力を磨くための教育に力を注ぐ
小学1年生から年間35時間の英語授業を開始。中学校では外国人講師の常駐化など、英語教育を推進。また、幼児期からの豊かな表現力を磨く芸術教育にも力を入れる。
指定したモデル園で、園児への表現活動を年3回実施する。
足立区
大学・他県と連携した学習や「おいしい給食日本一」を目指す食育への取り組みなど、ユニークな施策も数多い
大学と連携した「大学遠足」、新潟県での「魚沼自然教室」など、小中学校の体験学習が充実。
平成23年からは5歳児を対象にした「幼児教育プログラム」を策定し、就学前教育から小学校教育へのスムーズな移行を目指す。
葛飾区
子どもの発育を長期的に支援する「食育」に積極的。ガイドラインに基づく骨太の教育方針が目を引く
区立保育園を対象に「食育ガイドライン」を作成。ガイドラインに沿ったオリジナル給食の導入や食育への取り組みを行い、子どもの発育を長期的に支援している。また、小中一貫教育の推進にも積極的。「地域に開かれた」学校づくりを目指すという。
江戸川区
待機児童ゼロの学童クラブや学校外の学びの場が充実。図書館の児童図書貸出数190万冊は23区No.1!
希望者全員入室可の学童クラブ「すくすくスクール」を放課後の学校で実施。
平成22年には、ものづくりや天体について学べる「子ども未来館」もオープンした。
また、学ぶ力の基礎となる読書を推進し、23区全校で読書運動を展開。
● 南部
就学前教育&義務教育9年間を通じた教育カリキュラムの整備に力を注ぐ。経済教育など独自の授業もユニーク
全国に先駆け、小中一貫教育を実践。就学前教育プログラムを含め、子どもの成長段階に応じた教育カリキュラムの整備に力を入れている。中学校を対象とした体験型経済学習では生活費の使い方などの経済観念を専用施設「ファイナンス・パーク」で学ぶ。
目黒区
放課後学習を支援する学習指導員を平成22年度から全中学校に配置。学習の機会を拡大
区立小中学校では小学4年から中学1年までの4年間、毎年「自然宿泊体験教室」を実施。
平成23年度からは区立中学校で「土曜日の補習教室」を実施。学習の機会をさらに拡大し、学力の向上を図っている。
大田区
専門講師による補習教室で基礎学力の定着を目指す。子どもの心を守るメンタルヘルスチェックも実施
「総合的な学習の時間」では地域の人材を講師に起用し、地域に根ざした教育を行う。
また、算数、数学、英語の専門講師による補習教室で、基礎学力の定着を図る。
全校にスクールカウンセラーを配置し、子どもの心のケアにも配慮。
世田谷区
区独自の「日本語」授業では、言葉を大切にし、深く考えて自分を表現できる子どもを育成する
「世田谷9年教育」を一部小中学校で実施。学習指導要領をふまえつつ区独自に作成した学習カリキュラムにより、質の高い義務教育を行う。また、世田谷区独自の教科「日本語」を導入。
言葉と日本文化を大切にする子どもを育成する。
● 北西部
就学前の幼児教育に注力。区と現場で働く職員が手を取り合い、幼児教育のレベルアップに努める
特に力を入れるのは幼児教育。区内の子どもの現状を調査し、保育現場で働く職員とともに課題克服に努めている。今後は保育園・幼稚園と小学校の連携、情報共有化を推し進め、スムーズな就学に向けた環境づくりを強化する。
杉並区
区内全小学校、全学年での少人数学級実現を目指す。子どもや保護者の悩み相談、心のケアにも積極的
小学4年生までの少人数学級(30人程度)を実施。平成23年度には5年生で、平成24年度には全学年で実施予定。保護者向け子育て講座を開催する「スクールカウンセラー」や専門家を招いて指導を行う「中学校合同部活動」など多彩な取り組みがある。
練馬区
区内初の「小中一貫教育校」も開校。小・中学校が連携した、魅力ある教育カリキュラムの整備に期待!
平成23年4月に練馬区初の小中一貫教育校が開校。
小中一貫・連携教育グループを指定し、9年間を通じた教育カリキュラムを整備する。
今年からは学校で調理した給食を全校で提供開始。各校の特色を活かした食育も行う。
豊島区
「教育都市としま」の実現を目指し、小学1年生からの英語教育や健康教育など、特色ある教育を推進する
区独自のカリキュラムにより、小学1年生から英語活動を実施。
また、区内6大学と連携し、ほぼ全ての小中学校に学生ボランティアの指導補助者を配置する。
さらに、がんに対する知識など、「健康」についての教育も推進。
北区
中学校への教育アドバイザー派遣や教職員の負担軽減による「授業力向上」を目指す
区内の小中学校が連携し合い、小中一貫教育や幼稚園・保育園での就学前教育を推進。
また、区立小中学校へ非常勤講師126人(平成22年度)を配置し、児童一人ひとりの学力向上を図る。
自然の中での体験教室も積極的に開催。
板橋区
つまずいた箇所に戻って徹底的に復習する「フィードバック学習」により、確かな学力定着を目指す
一人ひとりの理解に応じ、徹底的に復習させる「フィードバック学習方式」を区立全小中学校(小53校、中23校)で実施。放課後の子ども教室と学童クラブを一体化した「あいキッズ」は区立の17校で実施されている。
引用 掲載:不動産・住宅サイト SUUMO(スーモ)
行政区別 子育てサポート&教育環境徹底リサーチ
https://suumo.jp/edit/kyotsu/gyosei_child/tokyo23/e_interview.html
●まとめ
くれぐれも申し上げておきますが、どの区が良くてどの区は悪いということではありません。
お子さんに合った教育方針や特徴のある自治体が行っている授業の様子を
知っていただき、参考にしてください。
現在はお父さんお母さんが経験した小学校授業の内容も活動も大きく違っています。
それぞれの地域の良さや特徴を活かした教育を行っているのが
昔と大きく変わったところです。
お役に立ちましたら、応援(クリック)してくださると、塾長が喜びます♪
次回をお楽しみに♪
■■■■■
検定試験を上手に活用してお子さんの得意を伸ばしたい方、
お電話・メールでお問い合わせください。
小学生のための検定試験専門塾 魅錬義塾ホームページはこちら