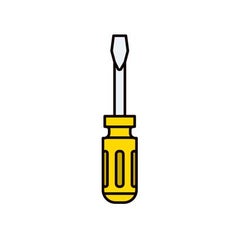代々、家に受け継がれてきた雛壇や兜などがありましたか?
家族の誰かがJWになると大変です。それらは異教にかかわるものとして捨てられるか、焼かれるからです。親や祖父母に対する何という侮辱的な行いなのでしょう。
商業主義に乗せられるのもいけないと思いますが、ここまでギュウギュウに締め付けて、その姿を見てるなんて…どこまでサディスティックなんでしょうね。
日本という国は、様々な文化があります。中には宗教色の強いものもあるかもしれ
ませんが、そここそ、個人の良心、神と自分の関係で決定すべきであり、まして他の人が、長老が、組織が、関与してくる場面ではないのではないでしょうか?
今回は日本文化やその他の習慣についてです。
こんなに毎月毎月証言させられては学校なんて全然楽しいところではありません。
しかし、それが組織の思うつぼなのです。
自称神の組織だけが居心地の良い場所だと思ってしまう
からです。そんな単純なトリックにこれからの子どもたちが引っかかってしまわないことを切に願います。
***********************************************************
(学 20–22ページ 祝祭日と祝い)
エホバの証人は学年度中の他の宗教的ないしは宗教色のある祝祭日の行事や儀式に関しても,全く参加しないという立場を取ります。その理由は,それらの祝祭日もやはり,キリスト教以外の崇拝と結び付いているという点にあります。実際,そのような崇拝のある種の特徴がそれらの祝祭に浸透している場合が少なくありません。次の実例を考慮してみてください。
正月:
一般に正月は民族的な祝いと見られています。しかし,次の引用文が示すようにその由来に神々への信仰と密接な関連があることをお分かりいただけると思います。「正月の行事は,年の初めにあたって家々の祖先にあたる神の来臨を仰ぎ,その年のみのり豊かなことを祈るのが本義であるが,農業国である日本では稲作儀礼としての性格をも多分にふくんでいる。正月にまつる神は年神とか正月様とよばれることが多く,いまでは歳徳神などという名称も行われている……」―世界大百科事典(平凡社,1974年版),第15巻,54ページ。
節分:
「平安時代から節分の日には……宿所を変えて厄を払うことが行なわれた。……ところが宿所を外に求めていたのを,次第に部屋に移るだけに簡略化されるにつれて,その部屋の厄除が必要となった。そのために豆撒きが行なわれるようになったものとみえ(る)。……『福は内,鬼は外』という唱えごとも,……『鬼やらい』の性格を強くもつようになっていった。他方,厄年を忌む思想も平安時代からみられるが,……厄年の人が……年の数だけの豆を食べ,また豆と銭を紙に包んで身体を撫でて厄払いをし,辻に落として乞食に拾わす風習がみえる。疫除の力をもつ豆を厄年に利用したものであるが,次第に厄年の人でなくても,年の数の豆を食べて,その年の災厄から身を守るようになった」―日本風俗史事典(弘文堂,日本風俗史学会編,1979年版),357ページ。
バレンタイン・デー:
これは日本では祝日とはされていませんが,最近,特に若い人々の間で広く知られるようになりました。「バレンタイン・デーはバレンタインという名の二人の別々のクリスチャンの殉教者の祭日に祝われる。しかし,この日と結び付いている習慣は……恐らく毎年2月15日に祝われたルーパーカス祭と呼ばれる古代ローマの祭りに由来するものである。女性と結婚生活の保護神であるローマの女神ジュノーおよび自然の神パンに敬意を表する祭り」―ワールドブック百科事典(1973年版,英文),第20巻,204ページ。
ひな祭り:
「ヒナアソビともいうが,アソブというのは祭ることで,雛マツリと同じ意味。女の子が雛で遊ぶのではない。雛はもともと人形で霊力のある呪具である。鳥取県では三月三日の夕方に,赤い紙衣装をつけた雛を,供物を供えて,棧俵に乗せて川に流す。祓いである。いまの,雛段を作ってならべる内裏びなは,江戸中期ごろに京で起こったもので,起源は新しい」―「日本を知る事典」(社会思想社,1979年版,大島建彦等編),509ページ。
端午の節句: 「節供: 節句とも書く。節は1年のうちの特定の日のことであり,供は供するもの,つまり食物のことで,元来は1年のうちのある特定の日に神と人とに食物を供することを意味した」―世界大百科事典(平凡社,1974年版),第17巻,450ページ。
「端午: 日本では月の最初の5日を〈初五〉または〈端午〉というが,邪気をはらう節日として,5月の5日をとくに〈五午〉〈重五〉などといって重んじたので,端午は5月に限られるにいたった」―同百科事典,第19巻,499ページ。
「鯉幟: 竜門……にのぼることのできたコイ(鯉)は,化して竜となるという伝説から,鯉の滝のぼりは立身出世のたとえにされ……た」―同百科事典,第10巻,12ページ。
母の日:
「古代ギリシャの母親崇拝の習慣に由来する祭り。神々の偉大な母,キュベレあるいはレアのための儀式を伴う正式の母親崇拝が小アジアの至る所で3月15日に行なわれた」―ブリタニカ百科事典(1959年版,英文),第15巻,849ページ。
たなばた:
「七月七日の行事。織女祭・星祭・七夕祭などともいう。……中国では,……この日は牽牛星(わし座の星αアルタイル)と織女星(こと座の星αベガ)が天の川をはさんで年に一度相会する日という伝説があり,この伝説にあやかって女性が裁縫の上達を願う……祭りがおこなわれた。……日本では,中国の風習の伝来により,中古以来……おこなってきた。またこれとはやや異なり,棚を設けて……山の物,海の物を供える織女祭もおこなわれていた。……さらに江戸時代には……イモの葉にたまった露で墨をすって願い事などを書き,五色の短冊や色紙を葉ダケに飾って星祭をする風が盛んになった」―大日本百科事典 ジャポニカ‐11(小学館,1969年版),600ページ。
これらは一般に祝われている祝祭日の幾つかにすぎませんが,それらの祝祭日には学校の生徒たちもある種の活動にあずかって祝いに参加するよう期待される場合があります。学校で行なわれる祝祭日の行事や儀式の形式や目的は国によってそれぞれ異なるでしょう。しかし,エホバの証人は良心上の理由から,それが歌を歌うこと,音楽を演奏すること,演劇を上演すること,パレードで行進すること,絵をかくこと,パーティーに出席すること,飲み食いすること,その他のいずれであっても,こうした祝祭日の活動には一切参加いたしません。しかし同時に,私たちはほかの人々がそのような祝祭日を祝うことに異議を唱えたり,祝うのを妨げようとしたりはいたしません。こうした祝祭日を何らかの形で記念する活動に私どもの子供たちが参加することを先生方のご親切によって免除していただけるなら大変うれしく思います。
***********************************************************
『一切参加いたしません』『免除してください』ですか…。完全に命令じゃないですか!
幼稚園で母の日にママの顔を書きましょう~って時に園児に証言させるわけです。鯉のぼり作ったら鞭されるんです!七夕で短冊作ったら、ビリビリに破れ!という宗教なんです!訳わかりませんよね!でも事実なんです。
これは虐待と言えませんか?
我々2世が大げさに言ってる戯言なんでしょうか?被害者意識が強いだけなんですか?ぜひ一般の方に聞いてみたいです。
2世の方~!
みなさん、
・最初に証言したのって何歳の時ですか?
・どんな気持ちがしましたか?
・異教の習慣に関わるものだから避けるべきである、心の底から本当にそう思いましたか?
・親に吹き込まれただけではありませんでしたか?
・突っ込んだ逆質問されたら答えられないレベルの知識しかなかったのではないですか?
・困ったら泣きながら『エホバの証人だから〇〇はできません』こんな証言ばっかりじゃなかったですか?
所詮、園児や児童に証言させてもこうなるんです。論理的に説明もできないくせに、証言するなんて滅茶苦茶なことさせると思いませんか?
体験されてない方は多分、この問いに対する答えに驚かれると思いますよ。