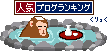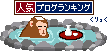
衆議院が解散となり、来月14日に投開票が行われることになりました。今回の選挙ではどの政党に投票すべきかは、非常に難しい選択だと感じています。
安倍自民党が外交・防衛において大きな仕事をしてきたことについては疑う余地はありません。こうした分野においても不十分だと思うことは多々ありますが、安倍総理以外の方が総理になったとして、この状況がより好転したとはとても思えません。こういう点においては、安倍総理を支え、自民党を応援するというのは1つの考えだとは思います。
とはいえ、自民党の中にも未だに親中派・親韓派=反日派が多いことから、自民党よりも次世代の党を推すべきだという考えの方もいらっしゃるでしょう。親中派・親韓派がほとんどいないという点では、次世代の党への期待を持つのは素直な気持ちとしては理解できるところです。
ただ、私のように安倍自民党の経済政策に対して極めて厳しい見方をしている立場からすると、その安倍自民党の経済政策に対する不満から次世代の党を支持する側に回るというのは、ありえない選択肢だというのが私の考えです。
次世代の党のウェブページに飛んで、基本政策を確認してみて下さい。
次世代の党の「基本政策」
基本政策の3番目に「財政制度の発生主義・複式簿記化による「賢く強い国家経営」への転換」という見出しがあり、ここに7つの項目が列挙されています。これを見ていけば、分厚い中間層を日本国内に作り上げていくという発想が全くないことに気がつきます。
まず7つの項目のうち最初の2つを見てみましょう。
① 財政健全化責任法の制定による政府の国家経営に関する責任の明確化
② 中長期財政計画の策定と予測・実績対比による戦略的な財政運営
国家財政はその増減が民間消費や民間投資に与える影響まで含めたマクロの視点でみなければいけないものであるのに、国家財政単体を他から切り離してミクロの視点でのみ捉えようとする狭隘な視線に陥っていることを、はっきりと示しています。
次の2項目を見てみましょう。
③ 次世代への負担の先送りを防ぐため、ムダとバラマキの温床となっている移転支出(H26一般会計・特別会計予算純計31兆9,095億円)を大幅削減した上で、直間比率の見直し等、税制の抜本改革を進める
④ 所得課税の軽減・簡素化(フラットタックス化)
生活保護などの移転支出を「ムダとバラマキの温床」だと断じています。不正受給の対策は考えなければならないにせよ、移転支出を原則「悪」と見る見方には私は賛同できません。「直間比率の見直し」とは、所得税や法人税などの直接税の割合を低下させ、消費税などの間接税の比率を高めるという政策です。お金持ちの人たちの所得税が支払う所得税を小さくして消費税の比率を高めていけば、税の逆進性(所得が小さい人ほど収入の中で支払う税金の割合が高くなること)が強まることは明らかです。このことは④のフラットタックス化と合わせてみると、より明確になります。
次に5番目の項目を見てみましょう。
⑤ 世界中から資本を集めるため、法人実効税率を大幅に引き下げる
世界最大の債権国=世界最大の資本供給能力を持つ金持ち国であるはずの日本が、どうして世界中から資本を集めるために法人実効税率を大幅に引き下げる必要があるのでしょうか。上場企業の半数以上が無借金経営を誇っているように、本来外部からお金を借りてでも投資を行うべき立場の企業に、わざわざ借りるまでもなく儲かると見たら投資に向けたいお金が山のようにあります。国内資本が不足していて外資頼みにしないと国内投資が進まない発展途上国とどうして同じ政策を採用する必要があるのか、さっぱり理解できません。
ここから浮かび上がってくるのは、アベノミクス第三の矢に示される構造改革路線を、次世代の党も明確に賛成しているのではないかという疑念です。実際、基本政策の4番目の「世代間格差を是正する社会保障制度の抜本改革、徹底的な少子化対策」の中にも、例えばTPPで大問題になっている「患者の選択肢を広げるための混合診療の解禁」とか「より付加価値の高い産業に労働力が円滑に移動できる流動性の高い労働市場を形成」といった文言が並んでいます。
しかも基本政策の5番目は、「既得権益の打破(規制改革)による成長戦略と「賢く強い政府」の実現」なのです。この5番目の項目には「経済成長を阻害してきた岩盤規制の打破、「農業」「医療・福祉」「エネルギー」等への新規参入の促進」とか、「自由かつ公正な市場を守るために必要最小限度の規制・ルールへの転換」とか、「徹底した競争政策(②補助金からバウチャーへ、②新規参入規制の撤廃、③敗者復活を可能とする破綻処理制度)による競争力の強化」とか、「国益を踏まえた自由貿易圏の拡大」とか、「徹底的な行財政改革、政策立案体制の向上と国会議員定数の削減 」という項目が並んでいます。ここには、国民生活を守るために国家が経済に介入することをそのまま悪だとみなす新自由主義の主張がそのまま表れています。
基本政策の6番目の「安全かつ安定的なエネルギー政策(新エネルギーの開発・原子力技術の維持)、電源多様化による脱原発依存」にも、「発送電分離を含む市場改革を通じた自然エネルギーの活用の拡大」が盛り込まれ、電源の安定供給よりも市場原理主義を優先する考え方を採用し、自然エネルギーに対する現実離れした高い評価を行っていることが見て取れます。それは同じ6番目の項目の①に、「メガフロート上の洋上風力発電等により水素を生成し、燃料電池のエネルギー供給システムを構築」にも表れています。
基本政策の8番目には「地方の自立、「自治・分権」による日本型州制度の導入」が謳われ、「中央集権型国家から地方分権型国家へ」とか、「内政は地方・都市の自立的経営に任せる」とか、「日本型州制度への移行、国の役割を外交・安全保障・マクロ経済政策等に絞り込み強化」といった項目が並んでいます。日本の各地方がそれぞれの繁栄を求めて競争し、勝ち組と負け組が生まれていくのを、「競争の結果」として容認する考え方がこの底流にはあります。
ここまで過激な改革を指向する政党が果たして「保守」なのでしょうか。反日的ではないという点では評価できるにせよ、新自由主義(資本主義原理主義)の立場から人々の暮らしを支えてきた社会基盤を「岩盤規制」と位置づけてその打破を目指すような考え方が、日本古来の美しい伝統を守り復活させようという立場と両立するとは全く思えません。党首が郵政民営化に反対して自民党の離党を余儀なくされた平沼赳夫氏であることから、その政策をきちんと検討もしないまま、勝手な誤解が生まれているのではないかと思わずにはいられません。
このような点で、次世代の党を応援していこうという考えには私にはなれないということを表明しておこうと思います。