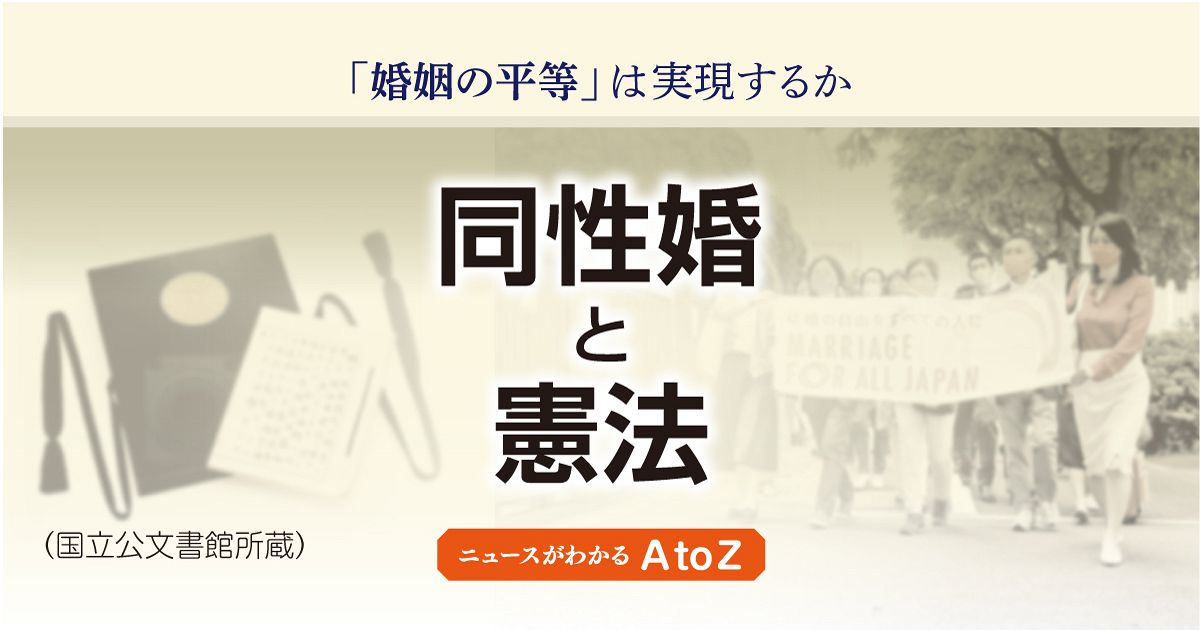岸田首相の補佐官によるLGBTQに対するオフレコ発言の余波は、法的地位に関する法改正論議にまで発展しそうだ。
なお、法改正にはいくつかのハードルがあるのだが、その最大の壁は憲法改正が必要になる可能性があるかもしれない、という点だ。
解釈、議論は色々とあるのだが、私個人の見解としては、現行の日本国憲法が、両性による婚姻について同性婚を想定しているように読めない。
第二十四の規定は以下だ。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
LGBTQの法的保護議論の中には憲法規定の変更は不要という意見や、「両性」を「男男」「女女」もしくは「両当事者」という解釈も可能だから現行憲法で問題ない考え方を主張する意見もある。
しかしそれは少し曲解だと考えている。
何故か?
実は日本国憲法は元々英語が原文だ。
マッカーサー統治下での日本国憲法の策定は、GHQが主導して行った。
これは歴史的な事実だ。
しかし占領国の憲法策定を占領軍が行うのは国際法では違法であるため、GHQの英語版を日本語訳し、それを国会承認させ憲法制定に至っている。
当然だが日本語に方が正文である。
それでも原文である英語版の意図は無視出来ないだろうと考える。
憲法の英語原文では第24条は以下のようになっている。
Article 24.Marriage shall be based only on the mutual consent of both sexes and it shall be maintained through mutual cooperation with the equal rights of husband and wife as a basis.
With regard to choice of spouse, property rights, inheritance, choice of domicile, divorce and other matters pertaining to marriage and the family, laws shall be enacted from the standpoint of individual dignity and the essential equality of the sexes.
もちろん日本国憲法は翻訳された日本語版の方が優越するが、憲法の原文案を書いたGHQ側の意図は英語版を読めば明らかで、both sexesとhusband and wifeの記載を見ても分かるように、男女(Sexesと複数形になっている点がポイント)の夫婦しか想定しておらず、当然これを当時の日本政府関係者が翻訳した際においても、それに準じた翻訳をしているとみるのが普通だろう。
つまり「両性」を「男男」「女女」「両当事者」という解釈にすると、英語版のSexesの記載と対立する。
言葉というものは人によって様々な解釈が可能で一々定義をしておかないと解釈の幅ばかりが拡大するやっかいさがある。
特に日本語は難しい。
少なくとも英語版には両性に内包されている定義は「男女」であるとみるのが普通で、日本語版もそれを意図していると言っていいだろう。
仮に英語版の存在を抜きにして、戦後直後の日本やアメリカの時代背景や一般的な社会常識を考えても分かるが、両性という意味に同性婚を想定していたり「男男」「女女」「両当事者」という解釈を包括していることは考えにくい。
人間は時代背景的に普遍的で常識的な事をわざわざ書いたりしないからだ。
また憲法が同性婚を禁止していないという見解は、想定していないから書いていないだけで、逆にいうと書いてないから想定外もしくは対象外という見方も出来るのだ。
同時に同性婚を禁止していないが同性婚が法的保護対象になるとも書いてない。
つまり当時は一般的な意味で同性婚が普遍性を持った存在ではないというのが常識だから書いてないと考えるのが普通だろう。
存在を認定していないものに対して法的措置を取る事が出来ないのは当然だろう。
現在進行中の同性婚の権利を認めない憲法判断に関する高裁判決は必ずしも一致しないものだ。司法にも色々な考え方が斑に存在しているようだ。
最終的には最高裁の判断待ちになるのだろうが、仮に憲法改正を必要とされるような判断が出た時、日本の世論はどう動くのだろうか?
なお先進国においては同性婚の権利環境は以下のようになっている。
実は結構同性婚を認めている国は多い。
さて、同性婚やLGBTQに関して、実は当事者の方々の間で、メディアが報じるような流れと違う考え方を持っている人たちが少なからず存在する。
つまり同性婚やLGBTQに関する主張が当事者の実態を反映しておらず、左翼の餌場(NPO法人等を使って弱者ビジネスを装い、公金をチューチューしようとしている連中)になっているという感覚を持った当事者がいるということなのだ。
同性婚やLGBTQは正論的な面があるためまともに批判し難いと感じている部分があるが、海外の有り様や日本の伝統文化や歴史の面などを統合した上でどういう在り様が現実的なのかを探る必要があるだろう。
特に善の仮面を被って公金を吸って生きようとする左翼系の集団には要注意。
なお、同性婚をめぐり差別的な発言をした荒井勝喜首相秘書官(経済産業省出身)の更迭はともかく、同性婚やLGBTQの支持者の中には、個人的な心象についてさえも抑え込もうとする勢力がいる。
私はそれは100%反対だ。
同性婚やLGBTQに関して個々人がどのように感じ考えるかは全く自由である。
同性婚やLGBTQに関して否定的な事を考えることさえ禁じるような連中は、ただの全体主義者の一味と言っていい。
但し、個々人の見解を公衆に発信する際、社会的常識を伴った発言態度が必要なだけだ。
荒井勝喜元首相秘書官は、オフレコとは言え、マスコミという左翼の一味に餌を投げ与えただけになった。
キャリア官僚の割に実に脇が甘いと言っていい。
昨今、霞が関の官僚の劣化が激しいと言われているが、この問題はそれを象徴している事例かもしれない。
オフレコ破りによって今後は毎日新聞には生の情報が入らなくなるだろう。
同胞の朝日、東京新聞辺りも困っているはずだ。
ゲーム理論を考えてみれば、オフレコ破りは新聞社にとってマイナスの方が多くなる。
新聞社は自ら情報を産む事が出来ない。
オシント(人的情報)を失ったら新聞なんて無価値なのだから。
オフレコ情報は、各社が記事を書く際の報道指針を見極めるために重要な役割を果たす事があるからだ。
毎日新聞のオフレコ破りは、既にオワコンの新聞の最期の断末魔ということだろう。