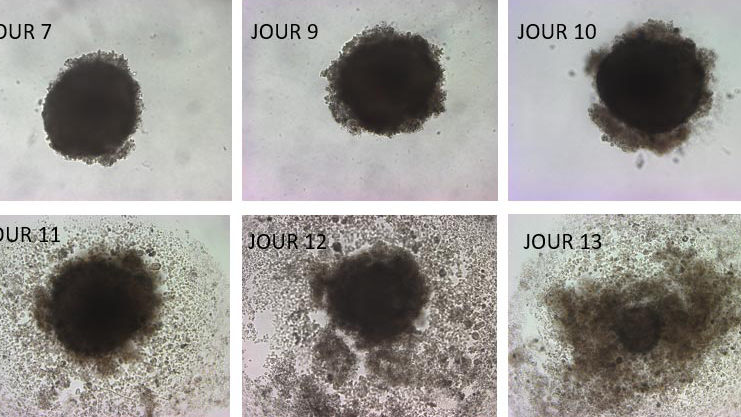9月9日にPSA検査した結果が昨日(9月13日)に来た。PSA2.3と(昨年9月2.3)3月に3.8↑、5月に3.8→、7月に3.0↓と比べ大幅に減少した。ここまで下がることを予想していなかったので、かなりうれしかった。
さて原因は?実施したのは以下の4つである。(ほかにいくつかサプリを摂取)
1.糖質制限
2.高濃度ビタミンC点滴
3.DHA、EPA、パクチーの大量摂取
4.遠赤外線温熱療法
高濃度ビタミンC点滴については前回書いた通りなのだが、7月の検査以降7月20日、8月3日に100gのビタミンCを点滴し、それ以降やっていない。当初50gの点滴をしていたが、PSAが横ばいであったため100gに変更、体の変化としては50gの時は点適時体に変化はないが、100gの時は体が温かくなりのどが渇く。あきらかに体に影響があるのを実感できる。また、点滴のスピードはかなり速く100g1時間強と、看護師さんにたのんで早くしてもらった。血液中のビタミンC濃度は目標の400mg/dlをかなり超えていたと思う。ここで、注意しなければいけないのは、赤血球にあるグルコース6リン酸脱水素酵素(G6PD)という酵素が欠損していると、ビタミンCが作る過酸化水素により赤血球の膜が壊れてしまう「溶血」という減少が起こり、貧血になる。ということである。私の場合事前検査によりその酵素はあるのだが、点滴のスピードを上げたことにより、影響があったのか7月の検査では貧血気味(ヘモグロビンの量が13.0g/dl(13.1以下は貧血気味))の数値となっていた。ただ、9月の検査では通常に戻った。(14g以上)逆に言えばそれだけ癌細胞にも影響を与えたと想定できる。
加えて、糖質制限を実施したことによる効果が大きかったと思う。次にDPA、EPA、パクチーの大量摂取であるが、DHA・EPAは一日2g、パクチー2束を煮込んでカレー味にして食した。DHA、EPAは免疫効果をアップさせ、血流をサラサラにします。ビタミンCがより毛細血管のなかにも行き届くといった効果があったかもしれません。また、以下の論文も興味深いです。2016年、腫瘍学を専門とするOlivier Feron氏が率いるルーヴァン大学の研究チームは、環境が酸性寄りになる腫瘍では、増殖のためのエネルギーがブドウ糖から脂質に置き換わることを発見しました。通常、酸性状態となっている腫瘍において、エネルギー源となる脂肪酸は「脂肪滴」と呼ばれる構造の中に保存されます。脂肪滴は脂肪酸を酸化から守りますが、DHAなどが多すぎると構造内に脂肪酸を収めることが不可能になり、酸化が起こります。そして、この酸化状態が過度に達すると細胞死を意味するフェロトーシスという現象が起こるとのこと。
パクチーには体の有害金属を排出する効果があり、細胞に入った重金属が電磁波などに反応し癌化が促進される可能性を排除できるのではと想定してます。