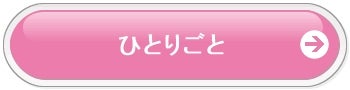東海道の歩きをしていますと、宿場に不自然なZ字の折れ曲がった道があります。これは曲尺手(かねんて)といいます。
なぜ曲尺手が宿場の中にあるのか?その理由が次の3つといわれています。
(1)敵の軍隊が通る時に側面攻撃するため
(2)建物を多く建てるため
(3)大名行列がかち合わなくするため
では詳細を順番にチェックしてみましょう。
(1)敵の軍隊が通る時に側面攻撃するため
東海道が整備された江戸時代初期は大坂に豊臣家がまだ存在していました。
豊臣家が西国大名を率いて江戸に攻めてくることも想定されましたので、東海道の宿場内でもこy激できるよう、側面攻撃のために曲尺手を作ったといわれています。
宿場を利用する客が増えた時、旅籠などの宿泊できる施設や店を増やす必要がありました。
宿場内の道を真っ直ぐ作るより、折り曲げたほうがより多くの店を建てる事ができます。このために道を曲げたとも。
(3)大名行列をかち合わなくするため
参勤交代で江戸に向かう大名行列は、宿場の本陣を利用して泊まっていました。
だから宿場内で大名行列が、かち合うことも考えられてのです。
でも、もし大名行列が鉢合わせした場合、格下の大名が格上の大名に挨拶するというマナーがありました。
これは現在では当たり前と思うかも知れませんが、大名も武士なので、相手が格上とはいえ、大衆の面前で駕籠から降りて挨拶に出向くとなると恥なのです。
だからどの大名行列も偵察隊みたいなのがいて、前から大名行列が来ないか確認していました。
そのための曲がり角でもあったのです。
もし前から格上の大名行列が来ていたら、休憩という理由で近くの寺に行列ごと入ってやり過ごしたとか。
そう考えるとこの曲尺手も江戸時代通して必要なものだったのですね。
画像は愛知県知立市に残る東海道・池鯉鮒(ちりふ:ちりゅう)宿の曲尺手。この曲尺手は東海道の宿場には、ほぼあるものなので、街道ウォーキンクに行くことがあったら探してみてください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【一緒に東海道の宿場巡りや街道歩きをしませんか?】
愛知県の東海道五十三次の宿場や美濃路、佐屋街道などの街道歩きを現地集合解散で巡る街道ウォークの会・【愛知ウォーキング街道巡りクラブ(AWK)】。活動は夏季を除く毎月第一土曜、もしくは日曜日。江戸好き、街道歩き好きの集まりですが知識の多い少ないは関係なし!好きならそれでOKです。入会費や年会費などもないので、あなたも気軽に遊びに来てみませんか?