Just Me
海外の絵本で「Just Me」という作品を読みました。
「もりのなか」(In the Forest)で有名なMarie Hall Etsさんの作品です。
(↓は「もりのなか」)
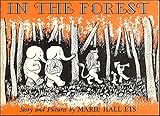 |
In the Forest
Amazon |
男の子がいろんな動物のまねをします。
ネコがいたら、ネコの歩き方をまねしてみる。
ニワトリがいたらニワトリの歩き方をまねしてみる。
ブタがいたらブタの、ウサギがいたらウサギの、ヘビがいたらヘビのマネ・・・。
次から次に見つけた動物の動作を真似していきます。
男の子は農場かなにかに住んでいるようで、いろんな動物を飼っているし、森のなかでもたくさんの生き物が見つかります。
・・・で、ここまで読んで、子どもが感じている世界観に寄って、子どもたちがよくやるような動作に焦点をあてて、優しい眼差しでとらえた、繰り返し系の絵本。いわゆる、ままよくあるパターンの作品かと思ったのですが、この作品は想像以上に深かったです。
作中の男の子は、たくさんの動物の真似をしていきます。ウシ、ガチョウ、ウマ、リス、ヤギ、カエル、カメ・・・そして最後にトウモロコシ畑の先でお父さんを見つけます。お父さんが男の子に気づかず、そのまま行ってしまいそうになると「待って!」といって走っていきます。
で、そのときとっさに駆け寄ったときの走り方は、いままでいろんな動物たちをマネしてきたような、他の誰をマネしたものでもなく、「JUST ME」、ただただ自分自身の走り方だった。そういうオチがついて、最後はお父さんとボートで遊びに行っておしまいの話です。ここで、このお話の題名にもなっているJUST MEの意味がようやくわかりました。しかも文中で、ここだけ全部大文字で「JUST ME」と強調しています。
おそらくこの作品が言わんとしていることは、いろんな人達のやり方を学び、真似して、あーでもないこーでもないと試行錯誤し、そういったことをやり尽くしたあとで、なにかの拍子に、他の誰でもない、自分自身のオリジナルのやり方・あり方がポンっと出てくる。そういったことがテーマになっているように感じました。いわゆる守・破・離的な意味合いです。作者のMarie Hall Etsさんが絵やお話をかかれる方なら、きっとご自身でもそういった体験をされているのでしょう。いろんな作家さんの作風を学び、試行錯誤を尽くして自分の作家性を模索したことだと思います。勉強、訓練、練習、修行・・・いろいろあるでしょう。それが何かの拍子にふと他の誰でもないオリジナリティを自覚した体験を通して、超ロングセラーの名作絵本をたくさんかかれるようになったのではないかと思いました。
しかもこのお話、最初に出てくる動物はトリなんです。トリはネコに驚いて、すぐにぱーっと飛んでいってしまいます。で、作中に何度も男の子に、動物に会う度に「僕はトリのように飛ぶことはできないけれど、きみのように〇〇することだったできるよ」と言わせています。おそらく、最初に出てくるトリが、とても手が届かない憧れの象徴。それで、トリのようには飛べないと言っています。ですが、以降登場する動物たちのマネは「きみのように〇〇できる」と言わせて、私たちがするいろんな手習いや試行錯誤を象徴しているようです。そして最後に、他の誰でもない「JUST ME」になるわけです。
原文で読まなかったら、ここまで深読みすることはなかったと思います。ただ、わりと名作・定番絵本というのはかなり確信犯的に非常に深い設定が背後に組み込まれているので、読み解くのは楽しいです。以前、絵本の編集者の方に同じ作者の「もりのなか」の読み聞かせを聞かせていただいたことがあるのですが、そのときもすごい深読みで、いろんな背景の考え方を教えてもらって、とても勉強になったことがあります。
こういう大人になってからより深く知ることができる「深読み」も絵本の楽しみ方の一つだと思います。しかも原文で読めるので、2重に楽しむことができました。これからも定期的に原文で絵本を読んだりしたいと思っています。