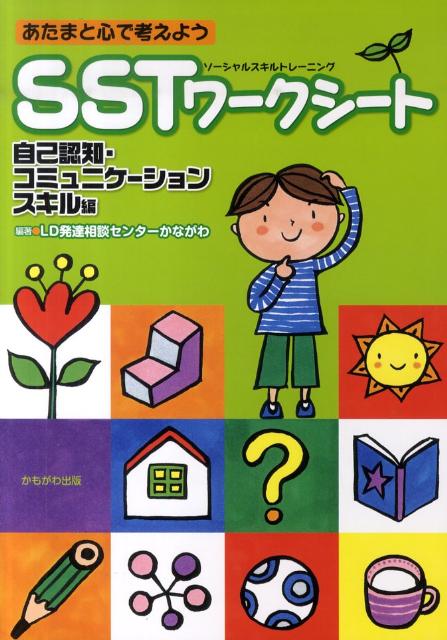入学準備もラストスパートといった頃合いかと思います。
学校生活に必要な道具、提出書類、手続き、たくさん保護者の方の支援があってお子さんの楽しい学校生活が成り立っています。
今時だと、氏名や住所をハンコを作ってぽんぽんと押せるようにしたり、記名済みのオリジナルえんぴつなどの購入で、少しは負担を減らせるように工夫されているご家庭も。
↑えんぴつってどこかにいってしまいがちですが、これならぱっと見て全部入っているか分かりやすい。それに、削れているかも確認しやすい。
↑リビング学習オススメです。こういうのがあると、消しかすも子どもがぶいーんと片付けられる。そういう家庭学習グッズを入れた箱なんかを、リビングの一角に置いておくと便利ですね。
それでも、学校指定のもので、算数セットなんかはちまちまと大変な作業があったり。
手提げバッグの長さの指定に悩んだりもしたことでしょう(机の横などにかけた時、床につかないように指定されています)。
ほんとにお疲れ様です。
たくさんがんばったことだし、楽しく学校生活が送れるといいなという願いが高まっている頃合いかと思います。
そんな期待と興奮入り混じった感情であるところに水を差すような話になってしまわないか心配ですが、もし役に立つならという思いで、私の持っておくと良いという情報や心構えを書き連ねようと思います。
1、マクマーティン保育園裁判から学ぶ「記憶の不確かさ」
有名な事件です。趣旨に合うところだけ抜粋すると、「保育士に性被害や虐待に遭ったと証言した子ども達は、カウンセラー(資格ナシ)の誘導尋問じみた聴き取りによって、保育士達の不祥事を捏造したことでモラル・パニックを起こした(※正義があるならどれだけ責めても良いと思い込む)近隣住民の行動で大量の保育士が仕事を失ったり、借金を負って破産状態になったり、子どもを預ける施設が軒並み閉鎖してしまった。」
ポイントなのは、「子どもはそうだと思い込むとなかった出来事をあったかのように語る」というところです。これは、子どもが悪いという話ではないです。まだ未成熟だから、そうなります。
保護者の方にお願いしたいのは、帰宅したお子さんに対して学校であったことを聞くときには「今日はどんな楽しい(嬉しい)ことがあった?」とポジティブに聞いて、良い雰囲気(子どもの脳がポジティブな状態ともいう)になってから「他にも何かあった?」と聞いて話を広げてください。局所的→全体的な話題の転換です。ポジティブ脳を作る会話術でもあります。お子さんは基本、話したがりです。大人しい子も(※私自身の体験)お家の方に話を聞いてもらえるのは嬉しいことです。
ここで注意なのは、「イヤなことはなかった?」とネガティブな聞き方は控えることです。上記と逆で、ネガティブ脳になります。そして、お子さんは何とか話を続けたい、興味をもってほしい、という願いで、話を捻り出そうとしてしまいます。
そして、自分にとって都合が悪い出来事を、他者(学校の先生、友達など)が一方的に悪い話として記憶を捻じ曲げて話してしまうことがあります。これは、低学年がよく起こします。
教員の不祥事はセンセーショナルに報道されやすい。長年教員していれば、実際、体罰を行うような教員を目の当たりにしたこともあります。でも、どの職種でもそういう倫理観のない人は一定数います。教員という立場だからこそ、その一定数の人たちが叩かれて、その他大勢の普通に仕事をしている教員までも同じ不信感の目で見られてしまいがち。
でも、子どもは悪意のある無し関係なく「嘘をつく」ものなのです。それが普段お利口さんなお子さんでも同じことです。むしろ、高学年になっていくにつれて、家で優等生な振る舞いをしている子の方が、ご家庭でストレス発散できない分、学校で問題行動に出やすいです。私も「まさかこの子がそんなことを!?」という事例に出会したことがあります。
何かトラブルがあれば、まず冷静に落ち着くことをおすすめします。心配が勝って、「どうしたの!? 大丈夫だった!?」と保護者の方が慌ててしまうと、お子さんは思いがけないことを言い出すことがあります。大事に手塩にかけて育ててきたお子さんが、目の離れたところで不可思議な出来事に遭遇してしまうと不安になってしまうかもしれませんが、頭の中で一歩引いた自分に問いかけながら、まずは「様子を見る」という選択をしてほしい。と思います。
ただ、繰り返し妙な言動をする教員がいたら、それは糾弾してください。私も同僚にそういう人がいて、何度も管理職に訴えたものの、「あの人は話が通じないから」で流されてしまったことがあります。そういう時、保護者の方による意見があると、管理職も重い腰(💢)を上げて動かざるを得なくなります。教育委員会にメールフォームがありますから、そこから連絡することもできます。学校の管理職、市町村の委員会が動かなければ都道府県の方に働きかける手もあります。
2、発達障害は誰にでもある
これは私が読んだ著書に書いてあったことです。算数が苦手、絵がちょっと変わったデザインだな。文房具の扱いが不器用。運動神経が悪いかも。友達となかなか仲良くできないな。学校に行き渋るのに困っている。などなど。小学生になるとウィスクという心理検査でどういったことが苦手なのかというのを検査することができます。大人バージョンはウェイス。私はこれを受けて、自分が自閉症スペクトラムだということを初めて知りました。
結果は、折れ線グラフで出てきます。これの折れ具合が大きいと、発達障害と認定されます。ですが、これが平らになる人なんて、いるのだろうか。殆どの方が、多少の偏りが出るはず。発達障害と認定されるレベルではなくとも、どこか苦手分野があれば、それは脳の構造の問題でなっている可能性があります。
結果をもとに自分でも推測したことがあります。それが、算数の苦手さ。どの分野もそこそこできる、というか、自閉症スペクトラムの特性である「努力家」なところが発揮されて推薦制度を活用し、自分の得意分野で挑戦できるようにしてきたから、私は大学も行けて、ストレートで合格できました。しかし、算数だけは、苦手。その苦手な理由は、「限局性学習症」(※大卒だからと心理士からはそう診断されませんでしたが、自覚症状として)があるから、算数が苦手だったのではと思っています。
発達障害があっても、異様に算数苦手であっても、教員という仕事に就けている私ですが、「療育」を受けていたら、算数が苦手であることも払拭されていたのかもしれません。
そんなお子さんには、学校で全体と同じことをしていてもしんどくなって勉強嫌いになってしまったり、お友達とうまくいかなくて辛かったりする人生になるかもしれません。そんなお子さんに対して、学校では診断が降りているお子さんを支援級配置にすることくらいしかできないことも。
でも、ご家庭でできることもあります。ウィスクを受けることも一つの手ですが、支援に足る道具や著書はたくさん世に出ています。
↑ワーク系は、書店だと大型で、かつ教員用の専門書の棚にあります。友達関係や言動にお悩みでしたら「SST」や「アサーション」「認知行動療法」系のワークシートがおすすめ。最近、書店巡りしていないので、子ども向け「アサーション」と「認知行動療法」の本でいいものが浮かびませんが、SSTに関してはこのシリーズが、研修でもオススメされていたものです。
学習系は、何年生でもつまずきが見られたら、こちらのシリーズがお勧め。下にもあります。勧めた保護者の方からも「子どもが楽しいって言いながらやっていました!」と評判良し。漢字を中心に壊滅的だったお子さんが宿題を出し渋っていたので、宿題はご家庭でできる範囲に決めてもらい、ワークを毎日一枚やるというルールにしてもらったら、ビックリなことに漢字50問テストで100点連発。達成感を味わうことが勉強好きになる一歩だと思います。やる気を出したからこその100点連発。
「くるんぱす」や「三角定規」などは3年生くらいからですが、コレがあるなしで出来が異なります。器用な子でも、定規やコンパス系の問題はズレてしまってバツになることがあります。
このように、お子さんの不器用さの支援や言動や考え方の改善、学習支援となるワークが世の中にはたくさんあります。
他にも多いのは、「忘れっぽい」「うっかり」という困り感。ランドセルの内蓋に蛍光色のメモ付箋を忍ばせたり、手に直接書いたり、玄関扉に持って歩く絵の具セットや工作道具などを紙に書いて貼っておく。といったかんたんにできる対処もありますが、これらも対応策は売っています。
↑毎日のルーティーンを忘れてしまう子は、掲示型のものなんかもあります。「忘れ物」で検索するだけでたくさん出てきます。ADHD傾向にあってもなくても、どんな子でも大人も同じく人間は「忘れる」生き物。心配性なお子さんなんかにも、こういうものがあったら安心感に繋がるかもですね。
3、沢山の書類と効率よく戦いましょう
新年度は特に大量の書類を書いては提出、ということが多いです。
しかし、そんな山場を超えても、定期的にくるのが何かしらの承諾書。今はメール配信などでスマホから確認できるようになっている学校も多いとは思いますが、まだまだ紙文化な学校生活。『校外学習に参加しますか。アレルギーはありますか。』「いやいや、年度初めの提出物に書いたじゃない!」と思うかもしれませんが、アレルギーは追加されていく事情(※実際、アレルギー持ちではなかったお子さんが給食を食べて発症した事例があります。)もあり。考慮事項は、その都度確認させてほしいのが現場のお願いです。
そんなプリント地獄に対応すべく、提出忘れや確認漏れがないようにするために、収納の仕方を工夫することが大事。
↑「プリント 収納」で調べるとたくさん出てきますから、ご家庭にあった収納の方法で忘れ物防止を。たまったプリントは、ファイリングもよいでしょう。学級通信をよく出す学級なら、別のファイルを用意して別にまとめておくと、連絡事項以外にも思い出(私は写真や作品掲載で週一出していたタイプだったので)としてとっておくことも。
お子さんが忘れずに、ぐしゃぐしゃにせず持って帰ることも大事です。ランドセル内蓋に「プリントをわけてもってかえろう!」と書いておくと、習慣つきやすい。ソニックから出ている連絡袋は、袋内で分別できるようになっています。また、百均などで色別にファイルを買い、上の方に「おうちの人に見せるもの」「じゅぎょう」「しゅくだい」「わからない」と書いて持たせておくのも良いと思います。
また、蛇足かもしれせんが、お子さんがたびたびさまざまな図工の絵の作品などを持ち帰るかと思います。
そういったものを1年間ずつ、「作品収納」で検索してでてきた箱の中に収納し、年度終わりには思い出に残しておきたいもの(学級通信や賞状など)と一緒にまとめて入れておくと、すっきり収納できてオススメです。
なお、整理整頓が苦手なお子さんも多くいます。そういうお子さんに効果的なのは、学校の机の中に入れておく引き出しの中は、最低限のものにさせておくこと。
例えば、折り紙。よく百均で売られている箱型のプラスチックの入れ物のまま持たせて、引き出しにしまっているお子さんが見られます。これが圧迫してしまい、他のものが収納しづらくなって、結果的にぐしゃっと他のプリントをつっこむことに。なんなら、教科書やノートまでもそう。
そういうのを避けるには、「ジップロック」が活用できます。百均などで何十枚入りの折り紙を購入したら、袋に入れておく。スッキリしますし、取り出しやすいです。
他にも、昔遊びで駒を持参している場合、小さい給食で使う250ミリの牛乳パックが入れ物にちょうど良く、仕分けやすい。
「ジップロック」は、細々としたものの収納に便利です。歯がふと抜けた時用に、小さいものを持たせたり。折り紙の作品を持ち帰る用に持たせたり。ぐしゃっとランドセルの底で埋もれることを防ぎます。
なわとびも、手提げ袋セットのものにしておくと、ロッカーや机横に下げておくときに、うまく結べないお子さんでも「入れるだけ」になるから楽になります。そのうち結べるようになりますから、気長に。
さて、色々と伝えさせていただきましたが、同じ一年生でも、それぞれ考え方も違い、得意不得意も違います。「うちの子は〜がダメだ」というのではなくて、ならば「うちの子は〜が苦手だから・・・しよう」と考えてあげてほしいです。
そして、たとえ他の子より上手ではなかろうと、上手いと思ったものは得意なこととして存分に認めて「あなた〜が得意だから・・・しよう!」と、伸ばしてあげてほしいです。人格も、学力も、体力も、全てパーフェクトなお子さんなんていません。大人だって同じです。
最後に、もっとも大切なのは「家は安らげる場所」「学校は頑張る場所」と、保護者の方とお子さんが同じ考えであることです。ちょっと家でだらだらしたり、ワガママ言ったりは、健全な成長です。学校は小さな社会であり、「外で倫理的な言動を取る場所」たるべき。これが逆転していると、不健全な成長をしたまま、誰からも認められない子になってしまいます。お家の方は、そういったバランスが取れているかを見守ってあげてほしいと思います。