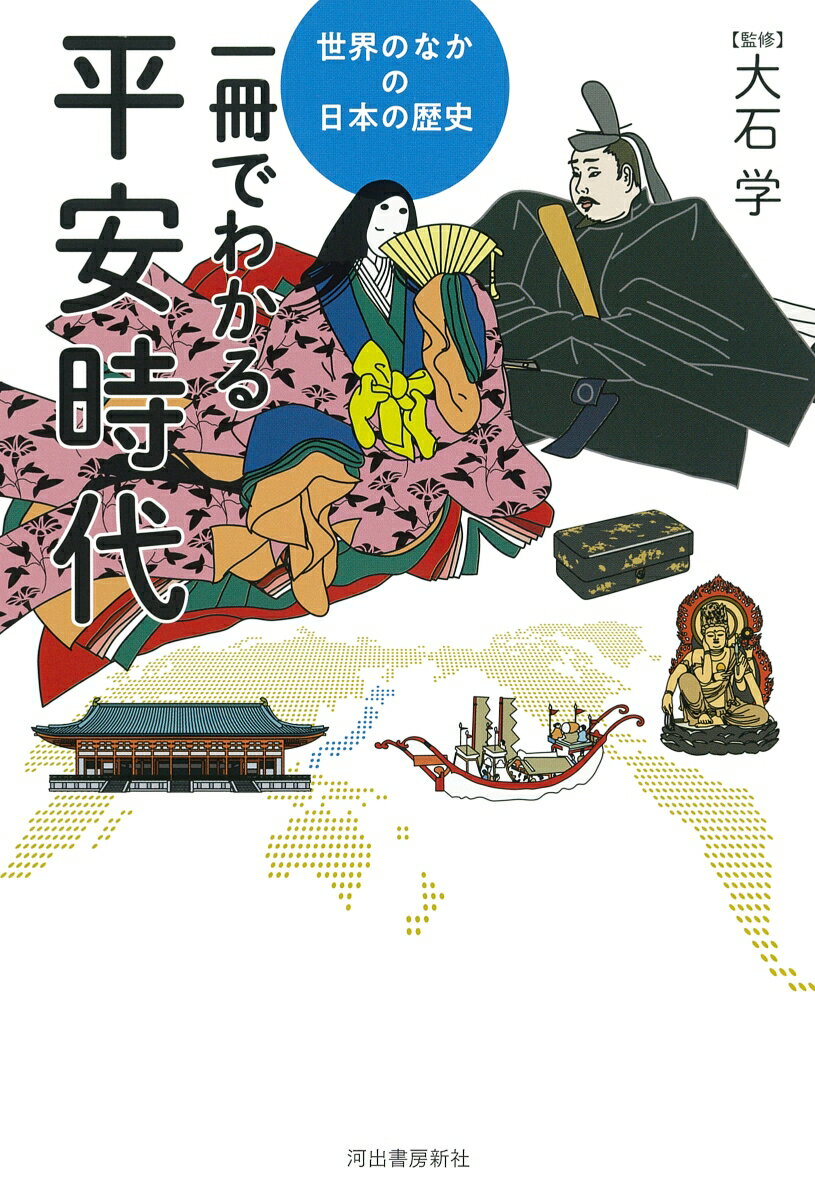【カバー袖部の内容紹介を引用】
平安時代は日本史における時代区分でいうと、日本史上最長の時代です。「平安」という名称や、長期にわたって続いたことなどにより、「平和な時代」とイメージされがちです。しかし、その実態は大きく違います。古代から中世への400年にもわたる、静と動をあわせ持ち、数々の歴史的な転換が生じた時代を追体験していただければ幸いです。
【引用終わり】
●平安京に遷都し、蝦夷・隼人の征討を行った桓武天皇。母親は光仁天皇の正妻ではなく渡来人の子孫であり、出自に負い目があったことから、自身の権威を広く知らしめようとした(のでは)。
●大宝律令に基づく政治制度。官人は8000人〜9000人、位階は30階あり、五位以上の貴族は150人未満。
●平城天皇のころから、藤原四家(南家、北家、式家、京家)の同族での勢力争いが始まるが、「薬子の変」で北家が台頭。
●唐との交流と、最澄・空海の台頭。神仏習合の始まり。
●武士の台頭と平将門/藤原純友の乱。
●藤原良房から藤原氏(北家・摂関家)が摂政・関白を独占し、摂関家内で権力争い。藤原道長の栄華の時代。
●後三条天皇のころより、藤原氏による摂関政治が終わり、院政による権力争いの時代に。
●各地を支配する国司とは別に、有力な貴族や寺社が所有する領地(知行国)が増え、地方領主が各地に分立する時代となる《中世の始まり》。
●平家の政権。源氏による平家滅亡となり、平安時代は終わる。
400年続いた平安時代をざっくり学ぶ本です(僕はパラパラ読みですが)。
長く続いた時代なのに、空海・最澄、菅原道真、藤原道長の時代(安倍晴明、紫式部など)、源平合戦以外は小説にも映画にもならないので、馴染みが無い方が多いのでしょうね。
古代の稲作による中央集権、中世の地方分権、近代の帝国主義による軍事力支配、現代の民主主義と独裁主義の対立と、世界はほぼ同時進行で支配体制が変わっています。それは、「稲作」「武器」「輸送手段」などの科学技術との関連か深いと思うのですが、その視点で平安時代を語る本があれば面白いと思いました。
「一冊でわかる平安時代」大石学(河出書房新社)
【5月8日読了】
【オススメ度★★★】