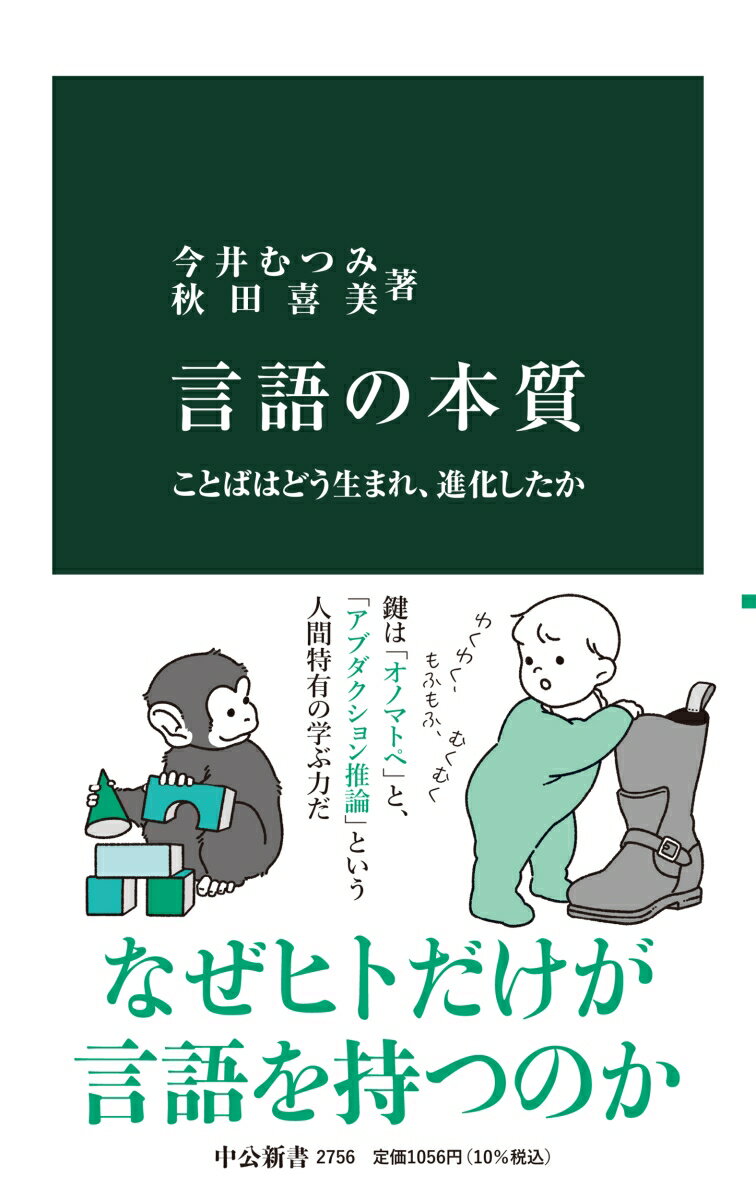言葉を使うためには身体的経験が必要なのか?
言葉とは身体感覚とは直接つながりのない抽象的な記号なのか?
言語はどのように発生し、どのように進化したのだろうか?
言語は発生当初から抽象的で複雑で巨大なシステムだったのか?
「記号接地問題」を提唱した認知学者のスティーブン・ハルナッド氏は、「少なくとも最初の言葉の一群は、身体に接地していなければならない」と主張した。
本書は、その「記号接地問題」を基点に「言葉の本質」を考える。
オノマトペとアイコン、子どもの言語習得、言語の進化、ヒトと動物を分つもの、言葉の本質などなど。。。
本書によると日本語はオノマトペが発達した言語だという。
言語が一つのシステム(OSのようなもの)だとすると、言語によってOSが違うとも言える。民族や国家を分ける一番の特徴は言語なので、民族や国家によってOSが違うと考えることもできる。
日本語の一番の特徴は、言葉を決定づける動詞が一番最後にくることである。
動詞が二番目にくる英語などとは違って、日本語は相手の顔色やその場の空気を探りつつ、自分が発する言葉の結論(動詞)を最後に選択することが出来る。
相手の顔色やその場の空気は、身体のセンサーをフル回転させて感じなければならず、また自分の言葉に身体性を持たせて相手に伝えるためにためオノマトペを多用しているのかもしれない。
日本語というのは、極めて身体性が高く、より高度な言葉と言えるのでは無いか。
さまざまな文化・文明が流れ込み、天災が多く、季節の変化が激しい日本の風土で養われてきた身体性言語が日本語なのだろう。
しかし、その日本語の特徴がゆえに、一つ前に読んだ本に書かれていた「訂正する力」が働きにくいのだろう。
国際社会では、国際語である英語を思考のOSに置いてコミュニケーションしないと、今後も日本は負け続けるのではないだろうか。。。
「言語の本質」今井むつみ・秋田喜美(中公新書)
【4月4日読了】
【オススメ度★★★★】