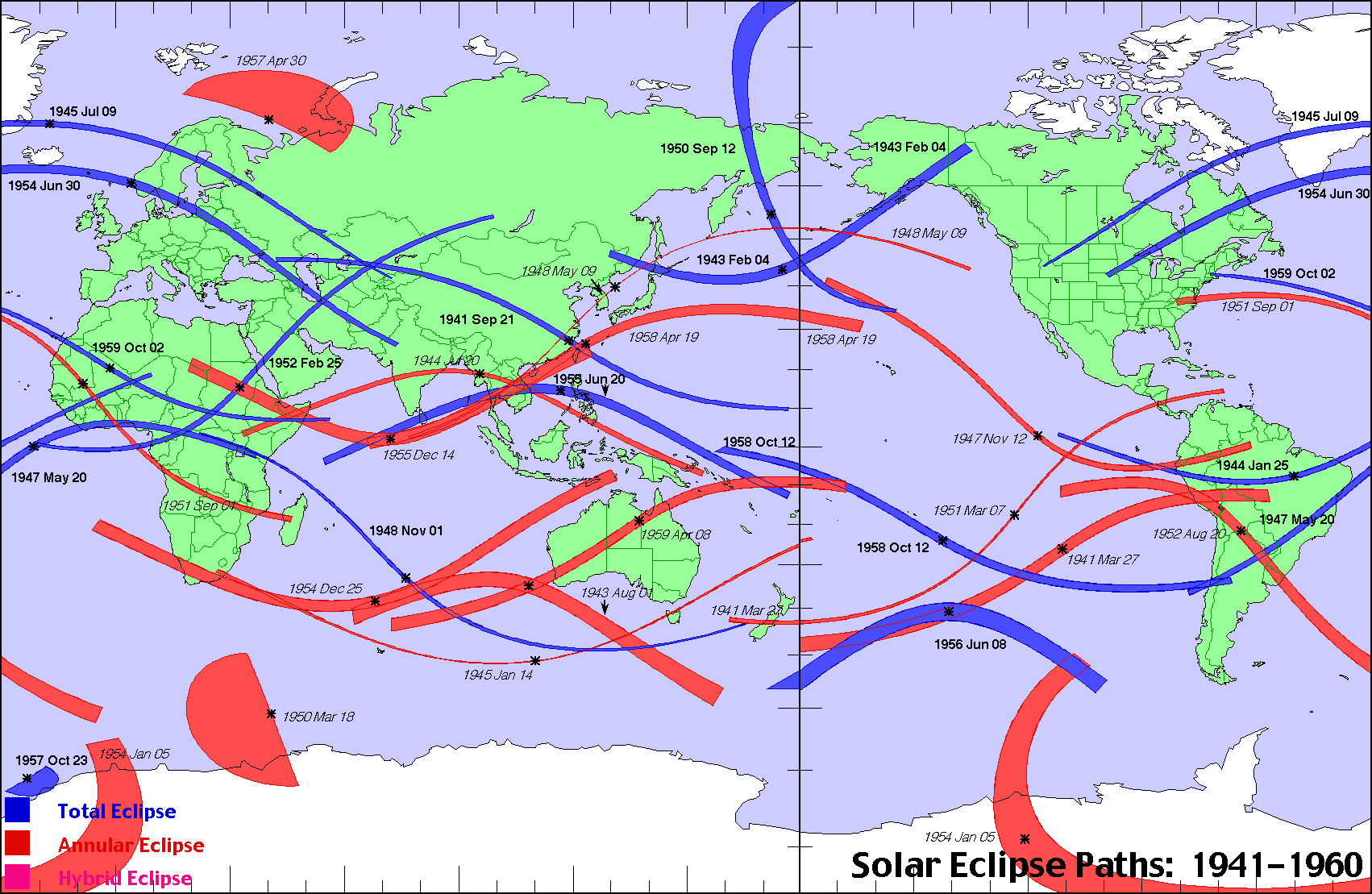
 一見、何だかワケの分からないような帯が出ています。これは地球上で過去20年間に渡って見られた皆既日食と金環日食が見られた帯を示す地図です。この帯の下だけ見られました。
一見、何だかワケの分からないような帯が出ています。これは地球上で過去20年間に渡って見られた皆既日食と金環日食が見られた帯を示す地図です。この帯の下だけ見られました。聞くところによると、1941.9.21の皆既日食はちょうど戦時中のものでした。そこで海軍同士が戦闘中、皆既日食が見られることを事前に知っていたため戦闘を一時中断してコロナを鑑賞後、再び戦闘を再開したと言ういわれがあります。1943.2.5に北海道で見られた皆既日食は、名寄で雲間から見られたものの釧路では快晴の下で観測されたそうです。
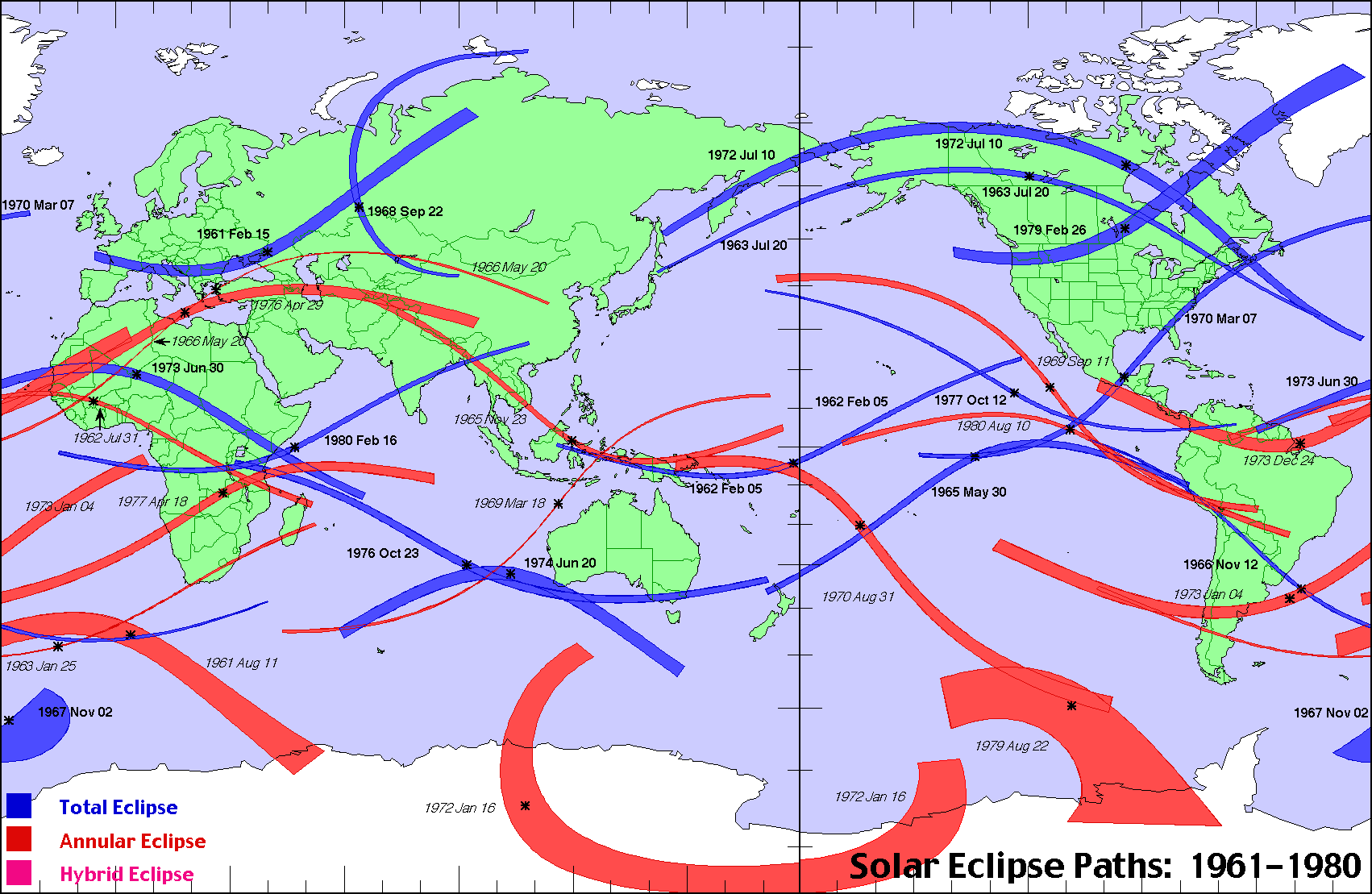
 1968.9.26の皆既日食は、日本のアマチュア天文家16名が初めて海外遠征を試みたものです。1968年はチェコスロバキアでプラハの春と呼ばれる変革運動にソ連が軍事介入した影響で、日本の観測隊は皆既帯の南100kmのアルマ・アタに留まらざるを得なかったそうです。そのため、99%の部分日食を観測せざるを得ませんでした。当時は東西冷戦の真っ只中なので、ソ連での観測はかなり困難を極めました。もし当時の遠征隊がこの皆既日食を写真に収めていたら、かなり貴重な記録になったでしょう。
1968.9.26の皆既日食は、日本のアマチュア天文家16名が初めて海外遠征を試みたものです。1968年はチェコスロバキアでプラハの春と呼ばれる変革運動にソ連が軍事介入した影響で、日本の観測隊は皆既帯の南100kmのアルマ・アタに留まらざるを得なかったそうです。そのため、99%の部分日食を観測せざるを得ませんでした。当時は東西冷戦の真っ只中なので、ソ連での観測はかなり困難を極めました。もし当時の遠征隊がこの皆既日食を写真に収めていたら、かなり貴重な記録になったでしょう。右の写真は、ロシアのサイトに掲載されていた1968.9.22のコロナの写真です。やや極大期型のコロナでしたね…
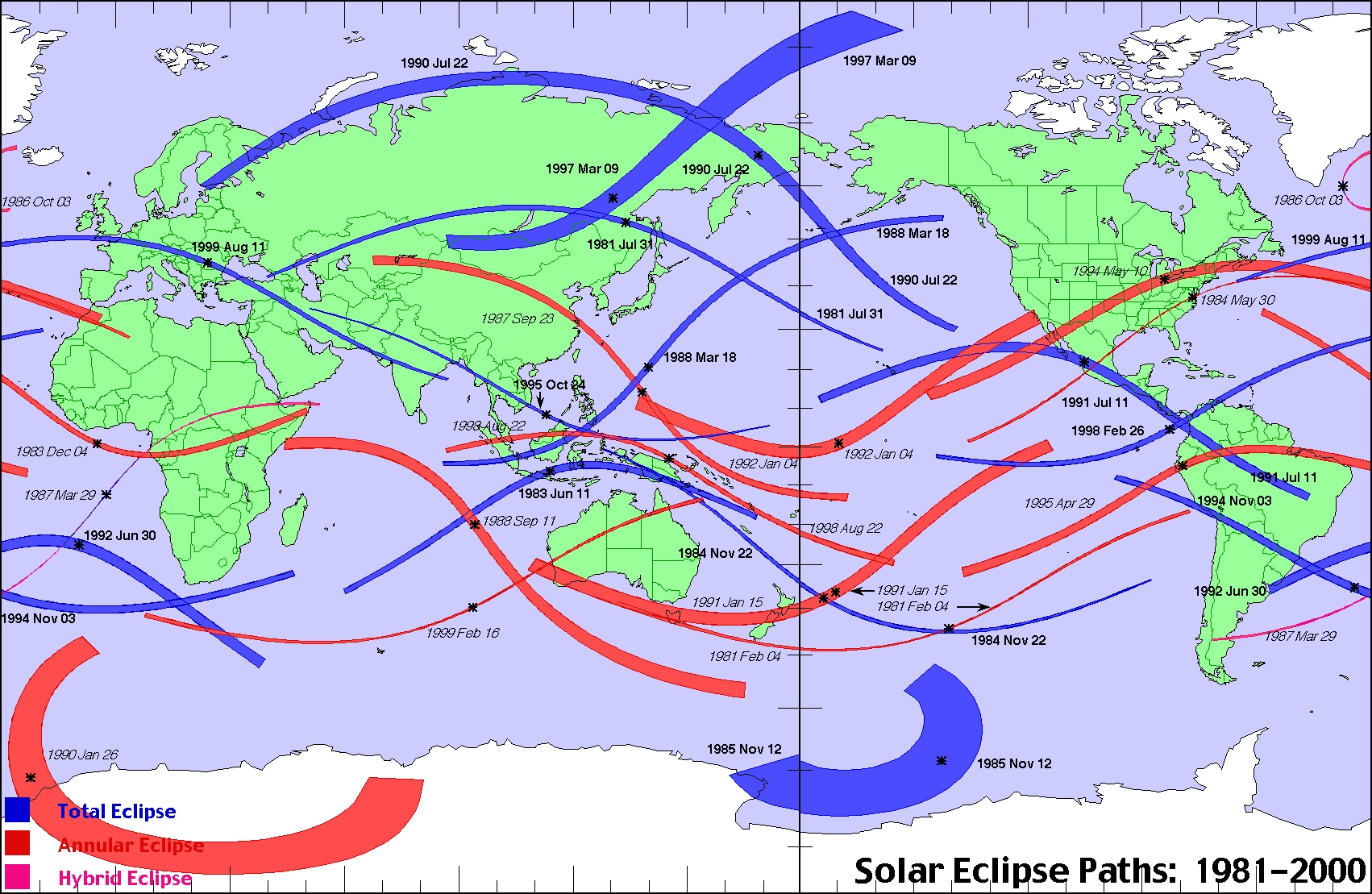
 1988.3.18の小笠原沖皆既日食から皆既日食旅行をしています。右写真は1991.7.11にメキシコのバハカリフォルニア(カリフォルニア半島先端)のロスカボスのサンホセ・デルカボで見られたモヒカン刈り型コロナです。南北の正しい位置にコロナを合わせました。Photoshopで直したので、写真の黒カバーが間に合わず変に黒くなっています。何卒、御容赦下さい。
1988.3.18の小笠原沖皆既日食から皆既日食旅行をしています。右写真は1991.7.11にメキシコのバハカリフォルニア(カリフォルニア半島先端)のロスカボスのサンホセ・デルカボで見られたモヒカン刈り型コロナです。南北の正しい位置にコロナを合わせました。Photoshopで直したので、写真の黒カバーが間に合わず変に黒くなっています。何卒、御容赦下さい。肉眼では横に長く見えたのですが、観測地点に引かれている南北線で見たコロナはこのような形をしていました。太陽の南北は磁力線に伴うストリーマーが流れているのですが、その位置に巨大なコロナの流れが来ています。地球は太陽と遠近感がかなりあります。普通極大期には同心円状で見えるコロナが、1/20の確率でこのようなモヒカン刈り型コロナに見えるそうです。このような形のコロナが見られたのは、1970.3.7にメキシコ湾からアメリカ東海岸沿いに見られた皆既日食以来だそうです。
管理者に無断での使用・複製・転載・流用禁止