「東洋経済オンライン」から
「職場で愛される人」は
会話にコツがある!

今の時代、まじめにコツコツやる人が必ずしも評価されるとはかぎりません。単純作業はコンピュータがやってくれる今、どんな仕事にもクリエーティビティが求められています。そしてその能力が高い人のことは、「おもしろい人」と呼ばれます。
この「おもしろい人」には、笑わせる、楽しませるといった要素以外にも、仕事ができる、ユニークな視点を持っている、個性的な生き方をしているなど、多くのいいイメージを内包しています。みんながおもしろい人になりたい、そう思われたいと感じる時代だと思います。
ではどうやったらおもしろい人になれるのか。その第一歩はコミュニケーションから始まります。私は、能力もセンスもないから……なんて言わないでください。コミュニケーションの仕方を変えれば、眠っている才能が花開くかもしれません。
僕は「サラリーマンNEO」や「あまちゃん」、最近では志村けんさんの新番組「となりのシムラ」といった番組に監督として関わってきました。その僕が、2月に『「おもしろい人」の会話の公式』(SBクリエイティブ)という本を出しました。なぜテレビの監督がコミュニケーションについて書くの?と疑問を持たれる方も多いことでしょう。僕はこれまで、ずっと笑いを中心にした番組を作ってきました。ずっと「おもしろい」ことを追求してきました。
監督というとなんだか偉い人のようですが、実は何か技術を持っているわけではなくて、言ってしまえば、ただしゃべっているだけの人なのです。
自分がおもしろいと思っていることを、役者、カメラ、衣装やメイク、編集マン、など多くのスタッフに言葉で伝えるわけです。そういった現場の経験が、今は、組織でも(ぼくも普通の会社員ですので)プライベートでも役立っています。
そうした経験から、話がおもしろくなり、仕事もうまくいくコツについて、僕が考えたことをお伝えしたいと思います。
上司の「もう、しんどい…」の愚痴にどう返すか
「おもしろい人」は、愛される人です。嫌いな人をおもしろいと思う人はいません。だから嫌われないように振る舞う人は多いでしょう。でも、自分が気を遣ったほど、相手は自分の気遣いを評価してはくれませんよね。
おもしろいとは、人とは違うことをしながら、人に理解されなければなりません。そのためには、自分の立場やエゴを守るのではなく、相手の立場で考えることが重要です。
ここでは会社の上司と部下のコミュニケーションを例に取りましょう。うまくいく秘訣はずばりこれです!
「上にはツッコミ、下にはボケる」
これで僕は、組織の中で楽しく仕事をできています。
「上司にツッコむなんて、とんでもない」と思うかもしれませんが、では、自分が上司の立場だったらどうでしょう。ツッコんでもらえると、けっこううれしいのではないでしょうか? そのツッコミが的を射ていると、物事の本質が見えているなどと評価されることもあります。特に優秀な上司ほど、「思ったことを素直に言ってくれる部下」を重んじるものだったりもします。
いつも「はいはい」と言って従っている人は、その場は無難に済みますが、いざ仕事上、大きなプロジェクトのメンバーを選ぶとなったときに、上司の頭に浮かぶ可能性は低いでしょう。投資でも人生でもそうですが、リスクを取らないとリターンは得られません。まずは小さなリスクを取ってみましょう。
たとえば、上司が、
「オレももう年だから、仕事しんどいよ」
と言ってきたとします。よくある、ぼやきですね。そんなとき、あなたならどう返しますか?
「そんなことないですよ」
……普通です……。しかも逆の立場に立ってください。その後、会話は続きますか? 代わりに、こう返したらどうでしょう。
「でも、その割に徹夜したりしていますよね」
具体性があるので、上司もオレのこと見てくれてるんだなという気持ちにさせられます。
では、次はどうでしょうか?
「でも、夜は元気ですよね」
「夜」っていう言葉の中に、仕事からエロまで、さまざまな意味を含んでますから、笑いが起きます。
上司を元気づけようと思ったら、上司が元気である具体例を探す。で、それだけではもったいないので、ちょっとずらしてツッコむ。
このずらすができないんだよ、という人。友達同士との会話でもできませんか?もし友達にはできているのに上司にできないなら、それは嫌われてはいけないと警戒しているからです。警戒している人に、相手は心を開きません。
会話は習慣です。確かに習慣は無意識なので、変えるのは簡単ではありません。でもそれを意識して、上司にツッコむぞ!と頑張っていると、いずれ必ず変わってきます。そうしたちょっとした意識が結果的に、人と違った視点で考えるクセを自然と身に付けさせ、おもしろい会話ができる土壌を作っていきます。
ちなみに、「でも、●●じゃないですか」という受け答えは、こちらが疲れているときでも、自動的に上司と会話ができるいいフレーズです。
「何かと電話をかけてくるお客さんがひとりいて、大変だ」
「でも、それだけ頼りにされているってことじゃないですか」
「昨日なんて2回も電話がかかってきて、ほかの仕事ができないよ」
「でも、課長は仕事が早いから大丈夫ですよ」
「それに、急に部長から呼び出されてさ」
「でも、それも部長からの信頼があってのことですよね」……
何も考えていなくても、どんどん続きます。
こういうのは本当にコツだけですが、やってみると、周囲からの見方は変わってくると思います。「おとなしい人」から、「話しやすい人」「声をかけやすい人」になると、その分、機会も広がるし、味方になってくれる人も増えてくると思います。
あと、「部下にはボケる」ということですが、これは比較的簡単。自慢や説教や愚痴を控え、失敗談や悩みを中心に話すと自然とできると思います。
「おもしろい人」は、盛り上がりの輪に入らない
おもしろい人の特徴として、物事を客観的に俯瞰して見る傾向があると思います。空気を読んだり、適確なボケやツッコミを入れられたりすることも、そのためです。そして俯瞰してみる能力は、実はコミュニケーションでいちばん難しい「だまる」ということも可能にします。
たとえば、合コンでも宴会でも、みんながうわーーーっと盛り上がっているとき、あなたはどうしていますか? そんな様子を見てほほ笑んでいませんか?
これは、会議や打ち合わせでもそうなのですが、盛り上がっているときは、全員が同じ思いを共有しています。しかしこれが危険で、歯止めが利かずやりすぎてしまい、内輪ウケになってしまいがちです。
テレビを見ていてもよくあるでしょう。調子に乗って突っ走って、やっているほうはおもしろいんだろうけど、イタイわ~ってこと。そういうときに黙っている人は、空気を正確に察知して、やりすぎだということに気づくことができます。
また、ひとしきりの後にくるなんとも言えない沈黙に備え、次の話題を提供できたりします。会話のテンポもよくなります。
上手なアナウンサーの方も、そうです。たとえば、ミヤネ屋の宮根誠司さんなどは、コメンテーターの話が盛り上がったら、それを繰り返さず、次の話にいきます。テンポが悪い司会者は、盛り上がるとそこで終わればいいのに、その盛り上がりを振り返ってしまうのです。
これは普段の会議の進行でも参考になります。いちいち「○○さんは、☓☓の意見ということですが……」と繰り返す必要はありません。俯瞰して、もしくは聞いている立場になって考えてみればわかるのですが、今、聞いていたことを繰り返されるのはうっとおしいですよね。
おもしろいコミュニケーションには、俯瞰する視点が必要なのです。
自分のコンプレックスは、売りに転換する
それは今ご説明した「場」だけではありません。最も必要なのは「自分自身」を俯瞰する能力です。
たとえばですが、髪が薄い方でも、言える人と言いづらい人がいます。これを……
「愛されるハゲと愛されないハゲ」の法則と呼びます。
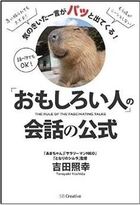
たとえば、飲み会などにいって、若いのにかなり髪の毛がいってしまっている人がいるとします。周囲は、一瞬、ひるみますよね。
先日、僕も飲み会で途中までかぶっていた帽子を脱ごうとした瞬間、女の子たちが一瞬黙り、僕の頭部に視線を送りました。そこに毛があることを確認すると、ホッとした顔をし、その後、なんとか戸惑いをごまかそうと半笑いする姿がありました。
実際のところ、当人が抱えているコンプレックスのほとんどは、他人とってはどうってことのないことです。そう思えれば、実はハゲは強力なおもしろさの武器です。
「いやー、まぶしくてすいません!」
と明るく言ってくれたらどうでしょう。
周囲は明るくなりますね。と、同時にこの人、人の器がでかい!と思われたりします。なんならイケメンよりモテたりします。ただハゲをハゲと言っただけなのに、です。
でもこれは実は深い話です。自分のコンプレックスを明かせる人は、自分を客観的にとらえられる人であり、それは相手の気持ちも考えられる人ということです。だから評価されるわけです。
これについては僕は、あまり偉そうなことは言えません。昔、体重が98キロありまして(現在は68キロ)そのときにはデブを売りにできませんでした。だからもしコンプレックスを克服できず、コミュニケーションにも悪い影響を及ぼしているなら、そのコンプレックスを克服(減量や増毛など)するか、開き直るかどちらかです。いちばんよくないのは、どちらもせずに見ないフリをすることです。