(※九州大学の2008年後期文系コア科目「異文化理解の心理学」を聴講した際に提出したレポートです。)
①「自分と違った人(考え、文化、習慣、性、等々)を理解することは可能か?――私の経験から」
あれは私が中学生のときだっただろうか。田舎道を自転車で走っていると、向こうから「外人」の家族が歩いてくる。福岡の田舎。白人。アメリカ人なのか、イギリス人なのか、軽い緊張を感じながら、横を通り過ぎる。「異質なもの」との出会いの経験とは、たとえばこういうことなのだろうか。
大学に進学し、神奈川県の横浜市で独り暮らしをした。横浜駅から程近い居酒屋でアルバイトを始めた。働き始めて気づいたのは、中国人の従業員の多さである。日本人の先輩から聞いた話では、経営者が「在日」で、中国人を積極的に雇っているということだった。日本人と上手くやれるひとも多い。アルバイトはだいたいみな若いので、「若さ」という共通前提があり、また、彼らの多くはかなり流暢に日本語を話した。しかし、中には、日本人と反りが合わないひともいる。そういう場合、突如として、彼らが中国人であることが強調され、異質さが鋭く意識化されることになる。自分たちとの行動の違いなどを取り上げ、皮肉ったり、嘲笑気味に語ったりする。私の印象では、その個人の特性がまず注目され、日本人との異質さが際立っていると判断されると、そこで彼らの出自が問題にされるようだ。逆に言えば、日本人とそれほど違わないと判断された中国人は、「仲間」として迎え入れられ、出自を問われることは少ない。そこには大いに主観が関係しているようだ。
また、レゲエが流れるカフェ・レストランで働いたときは、黒人と一緒だった。ある日、こんなことがあった。何の連絡もせず、彼が大遅刻をして出勤してきた。事情を説明しようとしても、激怒した日本人の店長は聞こうとせず、私に彼の仕事をするように命じた。そのときは、とんだとばっちりだと思ったが、よく考えてみれば、釈明をさせる余地ぐらい与えてもいいのでは、と思う。これが、日本人だったら、同じ対応をしただろうか。疑問である。
心理学では、「対応バイアス」という認知の歪みの存在が知られている。人間の行動の原因は「帰属処理」によって説明されるが、それには大きく分けて「外的状況帰属(外部帰属)」と「内的特性帰属(内部帰属)」がある。たとえば、あるひとが石につまずいて転んだとする。その原因を、そのひとが「おっちょこちょい」だったという性格、つまり内的特性のせいにすることもできるし、「つまずきやすいところに石があった」という外的状況のせいにもできる。しかし、人間は、外的状況を軽視して、内的特性(性格、能力、信念など)を原因だと考えたがる非常に強い傾向があることがわかっている。これが対応バイアスである。だが、実際には、人間の行動は私たちが思っている以上に強く状況に影響を受けている。これは、人間の環境適応力の高さだとも言える。しかし、適応不全状態、たとえば「カルチャー・ショック」などの場合、そのひとの振る舞いは、受け入れ先の社会・文化集団からは、まさに異質に見えるかもしれない。
J・W・ベリー(1997)は、移民の異文化への態度の側面に関して、自文化の維持の程度と移住先社会への接触の程度でふたつの焦点を設けて、その状態を4つに分類している。ひとつの焦点が「自文化のアイデンティティや特色を維持することが重要だと考えるか?」で、もうひとつが「移住先の社会との関係を維持することが重要だと考えるか?」である。前者焦点1と後者焦点2ともにイエスなら、その状態は「統合」、焦点2がノーなら「分離」。また、焦点1と焦点2ともにノーなら「周辺化」、焦点2がイエスなら「同化」である。
外国からの労働者や留学生は移民ではないかもしれないが、ある程度この研究が適用できると思う。彼ら外国人は、受け入れ先国の社会・文化に対して、自らのアイデンティティや価値観を調整しようと苦闘する。いずれ母国に帰るという前提なら、自文化を捨て去るという選択は考えられないだろうから、おそらく彼らは統合と分離の間で揺れることになるのだろう。そのとき、彼らが見せる言動が、対応バイアスにより内部帰属で判断されてしまうと、思わぬ誤解や偏見を生むかもしれない。だが、考えてみれば、彼らの視点に立てば、日本こそが「異文化」なのだ。そういった外的状況に左右、または翻弄されているのではという可能性を頭の隅に置いて、彼らとつき合うべきかもしれない。
これまでの「外人」たちとのつき合いを思い出してみると、私の好奇心のせいか、私が「変人」だからか、嫌な思い出や不快な思い出は少ない。それは、私がなるべく彼らを理解しようとしていたからかもしれない。理解とは、自分の認知的枠組み(スキーマ)に対象を置き、論理的に解釈することである。その意味で、理解できないことなどないとも言える。理解に苦しむ、とか、理解し難いというのは、そこに感情的判断が強く働いているということなのだ。別の言い方をすれば、理解できないのではなく、理解したくないということだろう。そこに自民族中心主義(エスノセントリズム)やショーヴィニズム(優位思想)の臭いを嗅ぎ取ることができるかもしれない。ますます「国際化」する社会で、なるべく軋轢を生まないために、やはり彼ら「外人」の置かれた状況を理解する努力が必要だろう。彼らから見れば、私たち日本人が「外人」なのだ。
(引用・参考文献)
丸山圭三郎(1990)『言葉・狂気・エロス』講談社現代新書。
大橋英寿編著(2004)『フィールド社会心理学』放送大学教育振興会。
高野陽太郎、波多野誼余夫編著(2006)『認知心理学概論』放送大学教育振興会。
②「ゲイ・レズビアンのカミングアウトとアイデンティティ」
「あなたは異性愛者ですか?」という質問ほど、ひとをたじろがせるものはない。あまりに当然すぎて、考えたこともない問題だからだ。ひとは、自分とは違った性のあり様に、どうしてたじろいだり戸惑ったりするのだろうか。伏見(1991、1997)は、それはセクシュアリティがパーソナリティの基層に位置するからだ、と言う。異質なセクシュアリティとの出会いは、ゆえに人格を揺さぶる。異性愛者のアイデンティティは、自立的に強固なものとして存立していない。それは「~でないこと」によって自己規定される「本質」である。多様な「性」という現象の中で、「男」と「女」の間に営まれる「正常な」性愛以外を認めないという態度の中で守られるものだ。異性愛者とは「『性』という領域の持つ可塑性ゆえ現実に存在するさまざまな性的偏差と、自己との間に線引きし続けることによって維持される、不安定で、排他的なアイデンティティなのである」(伏見、1997)。
同性愛者(ホモセクシュアル)に対する異性愛者(ヘテロセクシュアル)のタブー視は、たとえばこんなかたちの「神話」を作り出す。
「テレビ番組や小学校の教科書、映画、雑誌、民話に、そして運動場やスーパーマーケットでの日常生活の至るところにその神話は登場する。それは幸せなヘテロセクシュアル像であり、私たちが社会でどのように成長発達していくべきかを示す指針となっている」(ハート、2002)。
この神話が語る文化的な生活様式の中の重要な要素は、次のようなことだ。(1)異性のみに魅力を感じること(同性に惹かれることはあり得ない)、(2)異性との愛情や恋愛、性的関係を正当なものとして認める結婚式を教会で挙げること、(3)パートナーとの間に実子をもうけること、(4)その家族と生涯ともに暮らし、(5)老後は孫を持ち、その面倒を見ることを生き甲斐にすること。将来の孫を想像してみると、そこには幸福かつ健康で「ノーマル」な彼、または彼女のイメージが思い浮かぶはずだ。
社会の中で異性愛者として生活していく上では、この神話は子育ての手引きや精神的な拠り所ともなり、社会的なサポートにもなる。しかし、セイム・セックス(同性)に惹かれるひとにとっては、幸福なヘテロセクシュアル像という神話は、葛藤の原因であり、重荷にもなっている。
同性愛(ホモセクシュアリティ)は、犯罪や道徳的退廃、精神疾患、現代においてはエイズなどと結びつけられてイメージされてきた。社会の中の負の要素が、無根拠にスティグマ(烙印)としてラベルされてきた。
「青年たちが同性への欲望を口にすると、家族は激しい拒否反応を見せることが多い。社会全体はゆっくりと変化し、社会に根付いた神話の変化のスピードはそれよりも遅いことが多い。多くの人々にとって、同性愛は出来の悪いハリウッド映画に登場するモンスターと同じく、想像するだに恐ろしい邪悪な存在なのだ。大勢の人々が同性愛の扱いに戸惑い、息子や娘の感情を隠し、押さえつけようと強い圧力をかけることもある。その結果、若者たちは同性に対する欲望を公言すれば、家族を裏切り、結婚や姓の継承に重きを置く性文化や性の生活様式の伝統に背くことになると考えるようになる」(ハート、同書)。
こうした社会の側のホモフォビア(同性愛恐怖)は、彼らゲイ・レズビアンに内面化されて、自己嫌悪につながることもある。この自己嫌悪には、4つの強力な呪術的とも言える信念が存在するという。1つ目は、ホモセクシュアルは狂気で、ヘテロセクシュアルは健康だという認識。2つ目は、同性に向かう欲望に関する問題は自己の中にあり、社会にはないという認識。3つ目は、同性に向かう欲望を持つことは、それまでのジェンダーを反映した役割を捨て、ジェンダー転換した人間として行動することを意味するという意識。4つ目は、ゲイ・レズビアンになるには、目標や規律、役割、そして実践され、表現されなければならない政治的、社会的信条が必要であるという思い込みである。
このような、異性愛を正常で健康な規範的存在様式として強制し、同性愛を抑圧するメカニズムの総体を「ヘテロ・システム」と呼んでもよいだろう。このヘテロ・システムにおいて、「新たな自己規定、すなわち自分自身やゲイ・コミュニティとの新たな社会的契約への道を切り開いてくれる儀礼」が「カミングアウト」である(ハート、同書)。
人類学者ファン・ヘネップは、20世紀初頭、「通過儀礼」という概念を提唱した。人間の一生の中で、それぞれの節目に行われる儀礼のことだ。ある集団から次へと移るときに、前段階からの分離、移行、後段階への合体の儀礼が行われた。
「異性愛者であると思われながら一方で、同性愛者であることを完全に隠して、秘密を抱えたまま暮らすという『どっちつかず』な状態に置かれ、アイデンティティの危機に直面している人々にとって、カミング・アウトは事実上の通過儀礼となる。ゲイやレズビアンの生活様式、あるいはゲイやレズビアンの性文化に足を踏み入れて初めて、人々は新しい文化の規律や知識、社会的役割と関係へと社会化されていく。多くの人々にとって、この経験は解放を意味する。それは大いに物議を醸すと同時に、感情の変化を伴う劇的過程であり、人生のあらゆる領域に及ぶ 血縁家族を持ち、仕事仲間や友人、学友に囲まれ、生涯にわたる性的な恋愛関係を同性のパートナーとの間に築きながら 大人のゲイやレズビアンへと変容するためのプロセスなのである」(ハート、同書)。
カミングアウトは、同性愛者のアイデンティティ形成過程の画期であり、また既存のヘテロ・システムに対する異議申し立てでもある。私たちの社会のステレオタイプや反同性愛的な法律の中に否定的イメージやスティグマ、社会の著しい悪影響が存在し続けていることから、同性愛者はカミングアウトを課されるとも言える。だから、カミングアウトは非常にリスキーである。たとえば、アメリカの富豪や著名人には、カミングアウトする者が少ないという。
「市場競争を基本原理とする資本主義社会では、カミング・アウトはそのまま社会的資本の喪失につながりかねない。雇用主や顧客といった立場を問わず、彼らは常に、ホモフォビアによって市場からはじきだされるのではないかという恐怖を感じている。ゲイのカミング・アウトとは、職や収入を失うリスクに身をさらすことである。雇用主や家族の社会的地位の低下を招き、地域社会で得ていた特権や名声を失う可能性もある。ホモフォビアの根強い社会では、同性愛者は不本意にであるが、いわゆる重要な他者にさえ、そのような損害をもたらしかねない。社会・経済的ステータスと社会階層上の地位を喪失する可能性は、強固な壁となってカミング・アウトを阻んでいる」(ハート、同書)。
しかし、自分らしく生きたいという願望と、社会の偏見や抑圧との間のアイデンティティをめぐる葛藤は、異性愛者として「パス」するという秘密主義の段階を経て、カミングアウトへといたる場合もある。
「ゲイやレズビアンはそもそも、異性愛者であるという仮定のもとに成長する。同性への欲望を隠し、それとは逆に振る舞わねばならないという意識や、ストレートとして行動しようという意識から、そうした欲望を自覚した人々は様々な秘密を抱えることになる。しかし、のちに性的にも社会的にも経験を重ねると、それまでとは異なる意識が芽生え始め、真実を公表したいという感情が生まれる可能性がある。その次に続くのがカミング・アウトのプロセスであり(中略)それはゲイやレズビアンとしての自己アイデンティティの確立へとつながっている。この秘密を明らかにする儀礼的段階を通して、ゲイ及びレズビアン・コミュニティへの加入を含めた、あらゆる種類の新たな社会化や機会がもたらされるのだ」(ハート、同書)。
特に、ゲイ・レズビアンの権利主張や差別反対運動といった「アイデンティティの政治学」の領域では、「隠さないこと」を選択するよう求められている。また、ホモフォビアにまつわる非合理で呪術的な社会通念の影響圏から遠ざかり、精神的健康への肯定的な第一歩を踏み出すためにも、カミングアウトは重要である。実際、アメリカのゲイ・レズビアンの若者の間では、心理的、文化的に「カム・アウトしていること」が、自己を守り情報を得て、仲間同士のネットワークを獲得する能力において決定的な前提となっているという(ハート、同書)。カミングアウトは、そうした有形無形のソーシャル・サポートにアクセスするうえで、自己呈示となる。
ゲイ・レズビアンの、既存の社会体制・秩序と相容れない側面を突き詰めた地点に「クイア」という概念が浮かび上がる。
「『クイア(Queer)』は名詞、形容詞、動詞として機能するが、いずれの場合も『正常(ノーマル)であること』、正常化の逆を意味する。クイア理論は単独の、あるいはシステム化した概念的、方法論的な枠組みを持たず、むしろ性、ジェンダー、性的欲望の関係についての知的な取り組みの集合したものである」(スパーゴ、2004)。
ゲイ・バッシングに対抗するために町のパトロールを組織し、街頭の落書きキャンペーンで同性愛嫌悪の暴力の犠牲者を追悼し、ストレートの連中のたむろするバーで反同性愛嫌悪の学習会を開いたりしていたラディカルな共闘グループ、クイア・ネーションやピンク・パンサーズが、レトリックと表象の戦略のキーワードとして用いたのが「クイア」というスラングだった。これは、同性愛嫌悪の言説内だけでなく、「ゲイ」や「レズビアン」より以前に、あるいはその代わりに、一部の同性愛者たちが好んで使っていた言葉だった(スパーゴ、同書)。
19世紀から20世紀にいたる非異性愛者のアイデンティティの軸の変遷を、「同性愛」から「ゲイ」「レズビアン」、そして「クイア」へというように分析し、支配的な言説や知との関係から生まれた個人や政治行動の可能性や問題を、それぞれがいかに提供したかを見るのはそれほど困難ではない。だが、アイデンティティの政治学の新たな基礎として、クイアがひとつのカテゴリーとなれば、それもまた、必ず排除と制限を行うことになる。そもそも「理論上クイアは、支配的な異性愛であれ、ゲイ/レズビアンのアイデンティティであれ、正常なものや規範とは永久に両立しない。それは決定的に中心から離れ、正常からは程遠いものなのである」(スパーゴ、同書)。
マイノリティが政治的運動に乗り出すにも、やはり既存の古い統一的な社会体を前提として、行動しなければならない。そこでの対立は、しかし、別の視点から見れば依存とも言える。
「いかなる対立も完全に孤立した状態では存在しない。すべては他との関係のなかで作動する。たとえば、互いに依存しながらも反目している伝統的な男性/女性の対立は、理性的/感情的、強/弱、能動的/受動的などの他との関連を通して階層的な構造を作りあげている。同様に、異性愛/同性愛も互いを支えあうネットワークに巻き込まれているのである」。社会の主流の内側にある異性愛と外側にある同性愛とを分断し、解放を企てる戦略には限界がある。「隠蔽されたセクシュアリティというクローゼットの『外側』に出ることを宣言するのは、個人的には解放であるかもしれないが、今なおクローゼットの『内側』にいる者の周縁性を強化し、異性愛の中心性を認めることになる。要するに、完全に異性愛の外側に出ることは不可能なのだ。(中略)同性愛の明確なアイデンティティの認知を要求することは、必然的に同性愛と異性愛の不平等な二項対立を再確認することになる」(スパーゴ、同書)。
また、そのアイデンティティなるものは、社会構築主義的観点から再検討されている。
「個人は、言語から独立して存在する内在的、本質的なアイデンティティを持つ自立したデカルト的な主体(『我思うゆえに我あり』)とは見られないということである。かわりに、われわれが普通に何げなく『自己』と考えているものは、社会的に構築されたフィクションであり(真摯なものであっても)、言語の産物であり、知の領域に結びついた言説の産物であると考えられる。むしろ、私はなぜかしら本質的に、私流に私自身であり、挫折することもあるが、言語を通じて私自身と私の考えを他人に伝えようとしていると考えてよいであろう。しかしこの考え、この個体感覚、自立感覚は、自然の事実であるというよりもむしろ、それ自体が社会的に構築されたものなのである」(スパーゴ、同書)。
また、言語学の言語行為論の「行為遂行」論的観点からの説明もある。
「われわれは自分のジェンダー・アイデンティティがあるから決まった方法で行動するのではなく、ジェンダーの規範を支えているその行動パターンを通してアイデンティティを獲得するのである」(スパーゴ、同書)。
双方に共通するのは、社会内の主体・事象は、「本質」が内在していたり、「客観的事実」であったりするのではなく、社会的に作られるものだという認識である。確かにこの思想はマイノリティにとって、「抑圧されたり圧迫された自然な本性の解放を目的とする政治的な運動を文字どおり根底から破壊するが、その一方で、アイデンティティの政治学によって動きのとれなくなっていた抵抗と攪乱の可能性を開くものでもある」(スパーゴ、同書)。
精神分析家E・H・エリクソンの心理社会的発達論におけるアイデンティティ概念には、主体の生物学的基盤を前提にしている側面がある(エヴァンズ、1981)。社会構築主義や行為遂行論は、そうした「基盤」「核」「本質」といったものを、とりあえず括弧に入れる。これは、従来の民族・人種・性的マイノリティの政治的実践活動に変更を迫る考え方かもしれないが、新たな可能性でもあり得る。
ゲイ・レズビアンを社会の「異物」として扱うヘテロ・システムは、一方、その異物と相補的に成立してもいる。異性愛も同性愛も社会システムの相関物だとも言える。そして相互補完関係にある。その意味で、ヘテロ・システムは消滅しない。クイアは、差異化の機能を果たす概念ではあるが、安定したアイデンティティを形成することはないのだろう。それはヘテロ・システムの効果だとも言える。にもかかわらず、彼らのカミングアウトは終わらない。「そのプロセスには多くのイベントが含まれ、それらは成人期初期、特にゲイ・及びレズビアンの自己や役割、社会的関係などの発達段階で頂点に到達する。カミング・アウトは生涯にわたって展開されるものであり、その過程に真の終わりはない。その背景には、ゲイ・レズビアンの加齢や社会状況の変化に従い、ゲイやレズビアンであることの意味を新しい適切な方法で彼らは表明し続けていくから、という簡潔な理由がある」(ハート、前掲書)。
(引用・参考文献)
R・I・エヴァンズ/岡堂哲雄、中園正身訳(1981)『エリクソンは語る アイデンティティの心理学』新曜社。
伏見憲明(1991)『プライベート・ゲイ・ライフ ポスト恋愛論』学陽書房。(1997)『<性>のミステリー――越境する心とからだ』講談社現代新書。
ギルバート・ハート/黒柳俊恭、塩野美奈訳(2002)『同性愛のカルチャー研究』現代書館。
タムシン・スパーゴ/吉村育子訳(2004)『フーコーとクイア理論』岩波書店。
(参照)
○異文化理解の心理学:http://togetter.com/li/599987
言葉・狂気・エロス 無意識の深みにうごめくもの (講談社学術文庫)/丸山 圭三郎

¥840
Amazon.co.jp
アイデンティティとライフサイクル/E.H.エリクソン
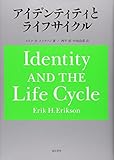
¥3,780
Amazon.co.jp
プライベート・ゲイ・ライフ―ポスト恋愛論/伏見 憲明

¥1,572
Amazon.co.jp
同性愛のカルチャー研究/ギルバート ハート

¥3,024
Amazon.co.jp
フーコーとクイア理論 (ポストモダン・ブックス)/タムシン・スパーゴ

¥1,620
Amazon.co.jp
①「自分と違った人(考え、文化、習慣、性、等々)を理解することは可能か?――私の経験から」
あれは私が中学生のときだっただろうか。田舎道を自転車で走っていると、向こうから「外人」の家族が歩いてくる。福岡の田舎。白人。アメリカ人なのか、イギリス人なのか、軽い緊張を感じながら、横を通り過ぎる。「異質なもの」との出会いの経験とは、たとえばこういうことなのだろうか。
大学に進学し、神奈川県の横浜市で独り暮らしをした。横浜駅から程近い居酒屋でアルバイトを始めた。働き始めて気づいたのは、中国人の従業員の多さである。日本人の先輩から聞いた話では、経営者が「在日」で、中国人を積極的に雇っているということだった。日本人と上手くやれるひとも多い。アルバイトはだいたいみな若いので、「若さ」という共通前提があり、また、彼らの多くはかなり流暢に日本語を話した。しかし、中には、日本人と反りが合わないひともいる。そういう場合、突如として、彼らが中国人であることが強調され、異質さが鋭く意識化されることになる。自分たちとの行動の違いなどを取り上げ、皮肉ったり、嘲笑気味に語ったりする。私の印象では、その個人の特性がまず注目され、日本人との異質さが際立っていると判断されると、そこで彼らの出自が問題にされるようだ。逆に言えば、日本人とそれほど違わないと判断された中国人は、「仲間」として迎え入れられ、出自を問われることは少ない。そこには大いに主観が関係しているようだ。
また、レゲエが流れるカフェ・レストランで働いたときは、黒人と一緒だった。ある日、こんなことがあった。何の連絡もせず、彼が大遅刻をして出勤してきた。事情を説明しようとしても、激怒した日本人の店長は聞こうとせず、私に彼の仕事をするように命じた。そのときは、とんだとばっちりだと思ったが、よく考えてみれば、釈明をさせる余地ぐらい与えてもいいのでは、と思う。これが、日本人だったら、同じ対応をしただろうか。疑問である。
心理学では、「対応バイアス」という認知の歪みの存在が知られている。人間の行動の原因は「帰属処理」によって説明されるが、それには大きく分けて「外的状況帰属(外部帰属)」と「内的特性帰属(内部帰属)」がある。たとえば、あるひとが石につまずいて転んだとする。その原因を、そのひとが「おっちょこちょい」だったという性格、つまり内的特性のせいにすることもできるし、「つまずきやすいところに石があった」という外的状況のせいにもできる。しかし、人間は、外的状況を軽視して、内的特性(性格、能力、信念など)を原因だと考えたがる非常に強い傾向があることがわかっている。これが対応バイアスである。だが、実際には、人間の行動は私たちが思っている以上に強く状況に影響を受けている。これは、人間の環境適応力の高さだとも言える。しかし、適応不全状態、たとえば「カルチャー・ショック」などの場合、そのひとの振る舞いは、受け入れ先の社会・文化集団からは、まさに異質に見えるかもしれない。
J・W・ベリー(1997)は、移民の異文化への態度の側面に関して、自文化の維持の程度と移住先社会への接触の程度でふたつの焦点を設けて、その状態を4つに分類している。ひとつの焦点が「自文化のアイデンティティや特色を維持することが重要だと考えるか?」で、もうひとつが「移住先の社会との関係を維持することが重要だと考えるか?」である。前者焦点1と後者焦点2ともにイエスなら、その状態は「統合」、焦点2がノーなら「分離」。また、焦点1と焦点2ともにノーなら「周辺化」、焦点2がイエスなら「同化」である。
外国からの労働者や留学生は移民ではないかもしれないが、ある程度この研究が適用できると思う。彼ら外国人は、受け入れ先国の社会・文化に対して、自らのアイデンティティや価値観を調整しようと苦闘する。いずれ母国に帰るという前提なら、自文化を捨て去るという選択は考えられないだろうから、おそらく彼らは統合と分離の間で揺れることになるのだろう。そのとき、彼らが見せる言動が、対応バイアスにより内部帰属で判断されてしまうと、思わぬ誤解や偏見を生むかもしれない。だが、考えてみれば、彼らの視点に立てば、日本こそが「異文化」なのだ。そういった外的状況に左右、または翻弄されているのではという可能性を頭の隅に置いて、彼らとつき合うべきかもしれない。
これまでの「外人」たちとのつき合いを思い出してみると、私の好奇心のせいか、私が「変人」だからか、嫌な思い出や不快な思い出は少ない。それは、私がなるべく彼らを理解しようとしていたからかもしれない。理解とは、自分の認知的枠組み(スキーマ)に対象を置き、論理的に解釈することである。その意味で、理解できないことなどないとも言える。理解に苦しむ、とか、理解し難いというのは、そこに感情的判断が強く働いているということなのだ。別の言い方をすれば、理解できないのではなく、理解したくないということだろう。そこに自民族中心主義(エスノセントリズム)やショーヴィニズム(優位思想)の臭いを嗅ぎ取ることができるかもしれない。ますます「国際化」する社会で、なるべく軋轢を生まないために、やはり彼ら「外人」の置かれた状況を理解する努力が必要だろう。彼らから見れば、私たち日本人が「外人」なのだ。
(引用・参考文献)
丸山圭三郎(1990)『言葉・狂気・エロス』講談社現代新書。
大橋英寿編著(2004)『フィールド社会心理学』放送大学教育振興会。
高野陽太郎、波多野誼余夫編著(2006)『認知心理学概論』放送大学教育振興会。
②「ゲイ・レズビアンのカミングアウトとアイデンティティ」
「あなたは異性愛者ですか?」という質問ほど、ひとをたじろがせるものはない。あまりに当然すぎて、考えたこともない問題だからだ。ひとは、自分とは違った性のあり様に、どうしてたじろいだり戸惑ったりするのだろうか。伏見(1991、1997)は、それはセクシュアリティがパーソナリティの基層に位置するからだ、と言う。異質なセクシュアリティとの出会いは、ゆえに人格を揺さぶる。異性愛者のアイデンティティは、自立的に強固なものとして存立していない。それは「~でないこと」によって自己規定される「本質」である。多様な「性」という現象の中で、「男」と「女」の間に営まれる「正常な」性愛以外を認めないという態度の中で守られるものだ。異性愛者とは「『性』という領域の持つ可塑性ゆえ現実に存在するさまざまな性的偏差と、自己との間に線引きし続けることによって維持される、不安定で、排他的なアイデンティティなのである」(伏見、1997)。
同性愛者(ホモセクシュアル)に対する異性愛者(ヘテロセクシュアル)のタブー視は、たとえばこんなかたちの「神話」を作り出す。
「テレビ番組や小学校の教科書、映画、雑誌、民話に、そして運動場やスーパーマーケットでの日常生活の至るところにその神話は登場する。それは幸せなヘテロセクシュアル像であり、私たちが社会でどのように成長発達していくべきかを示す指針となっている」(ハート、2002)。
この神話が語る文化的な生活様式の中の重要な要素は、次のようなことだ。(1)異性のみに魅力を感じること(同性に惹かれることはあり得ない)、(2)異性との愛情や恋愛、性的関係を正当なものとして認める結婚式を教会で挙げること、(3)パートナーとの間に実子をもうけること、(4)その家族と生涯ともに暮らし、(5)老後は孫を持ち、その面倒を見ることを生き甲斐にすること。将来の孫を想像してみると、そこには幸福かつ健康で「ノーマル」な彼、または彼女のイメージが思い浮かぶはずだ。
社会の中で異性愛者として生活していく上では、この神話は子育ての手引きや精神的な拠り所ともなり、社会的なサポートにもなる。しかし、セイム・セックス(同性)に惹かれるひとにとっては、幸福なヘテロセクシュアル像という神話は、葛藤の原因であり、重荷にもなっている。
同性愛(ホモセクシュアリティ)は、犯罪や道徳的退廃、精神疾患、現代においてはエイズなどと結びつけられてイメージされてきた。社会の中の負の要素が、無根拠にスティグマ(烙印)としてラベルされてきた。
「青年たちが同性への欲望を口にすると、家族は激しい拒否反応を見せることが多い。社会全体はゆっくりと変化し、社会に根付いた神話の変化のスピードはそれよりも遅いことが多い。多くの人々にとって、同性愛は出来の悪いハリウッド映画に登場するモンスターと同じく、想像するだに恐ろしい邪悪な存在なのだ。大勢の人々が同性愛の扱いに戸惑い、息子や娘の感情を隠し、押さえつけようと強い圧力をかけることもある。その結果、若者たちは同性に対する欲望を公言すれば、家族を裏切り、結婚や姓の継承に重きを置く性文化や性の生活様式の伝統に背くことになると考えるようになる」(ハート、同書)。
こうした社会の側のホモフォビア(同性愛恐怖)は、彼らゲイ・レズビアンに内面化されて、自己嫌悪につながることもある。この自己嫌悪には、4つの強力な呪術的とも言える信念が存在するという。1つ目は、ホモセクシュアルは狂気で、ヘテロセクシュアルは健康だという認識。2つ目は、同性に向かう欲望に関する問題は自己の中にあり、社会にはないという認識。3つ目は、同性に向かう欲望を持つことは、それまでのジェンダーを反映した役割を捨て、ジェンダー転換した人間として行動することを意味するという意識。4つ目は、ゲイ・レズビアンになるには、目標や規律、役割、そして実践され、表現されなければならない政治的、社会的信条が必要であるという思い込みである。
このような、異性愛を正常で健康な規範的存在様式として強制し、同性愛を抑圧するメカニズムの総体を「ヘテロ・システム」と呼んでもよいだろう。このヘテロ・システムにおいて、「新たな自己規定、すなわち自分自身やゲイ・コミュニティとの新たな社会的契約への道を切り開いてくれる儀礼」が「カミングアウト」である(ハート、同書)。
人類学者ファン・ヘネップは、20世紀初頭、「通過儀礼」という概念を提唱した。人間の一生の中で、それぞれの節目に行われる儀礼のことだ。ある集団から次へと移るときに、前段階からの分離、移行、後段階への合体の儀礼が行われた。
「異性愛者であると思われながら一方で、同性愛者であることを完全に隠して、秘密を抱えたまま暮らすという『どっちつかず』な状態に置かれ、アイデンティティの危機に直面している人々にとって、カミング・アウトは事実上の通過儀礼となる。ゲイやレズビアンの生活様式、あるいはゲイやレズビアンの性文化に足を踏み入れて初めて、人々は新しい文化の規律や知識、社会的役割と関係へと社会化されていく。多くの人々にとって、この経験は解放を意味する。それは大いに物議を醸すと同時に、感情の変化を伴う劇的過程であり、人生のあらゆる領域に及ぶ 血縁家族を持ち、仕事仲間や友人、学友に囲まれ、生涯にわたる性的な恋愛関係を同性のパートナーとの間に築きながら 大人のゲイやレズビアンへと変容するためのプロセスなのである」(ハート、同書)。
カミングアウトは、同性愛者のアイデンティティ形成過程の画期であり、また既存のヘテロ・システムに対する異議申し立てでもある。私たちの社会のステレオタイプや反同性愛的な法律の中に否定的イメージやスティグマ、社会の著しい悪影響が存在し続けていることから、同性愛者はカミングアウトを課されるとも言える。だから、カミングアウトは非常にリスキーである。たとえば、アメリカの富豪や著名人には、カミングアウトする者が少ないという。
「市場競争を基本原理とする資本主義社会では、カミング・アウトはそのまま社会的資本の喪失につながりかねない。雇用主や顧客といった立場を問わず、彼らは常に、ホモフォビアによって市場からはじきだされるのではないかという恐怖を感じている。ゲイのカミング・アウトとは、職や収入を失うリスクに身をさらすことである。雇用主や家族の社会的地位の低下を招き、地域社会で得ていた特権や名声を失う可能性もある。ホモフォビアの根強い社会では、同性愛者は不本意にであるが、いわゆる重要な他者にさえ、そのような損害をもたらしかねない。社会・経済的ステータスと社会階層上の地位を喪失する可能性は、強固な壁となってカミング・アウトを阻んでいる」(ハート、同書)。
しかし、自分らしく生きたいという願望と、社会の偏見や抑圧との間のアイデンティティをめぐる葛藤は、異性愛者として「パス」するという秘密主義の段階を経て、カミングアウトへといたる場合もある。
「ゲイやレズビアンはそもそも、異性愛者であるという仮定のもとに成長する。同性への欲望を隠し、それとは逆に振る舞わねばならないという意識や、ストレートとして行動しようという意識から、そうした欲望を自覚した人々は様々な秘密を抱えることになる。しかし、のちに性的にも社会的にも経験を重ねると、それまでとは異なる意識が芽生え始め、真実を公表したいという感情が生まれる可能性がある。その次に続くのがカミング・アウトのプロセスであり(中略)それはゲイやレズビアンとしての自己アイデンティティの確立へとつながっている。この秘密を明らかにする儀礼的段階を通して、ゲイ及びレズビアン・コミュニティへの加入を含めた、あらゆる種類の新たな社会化や機会がもたらされるのだ」(ハート、同書)。
特に、ゲイ・レズビアンの権利主張や差別反対運動といった「アイデンティティの政治学」の領域では、「隠さないこと」を選択するよう求められている。また、ホモフォビアにまつわる非合理で呪術的な社会通念の影響圏から遠ざかり、精神的健康への肯定的な第一歩を踏み出すためにも、カミングアウトは重要である。実際、アメリカのゲイ・レズビアンの若者の間では、心理的、文化的に「カム・アウトしていること」が、自己を守り情報を得て、仲間同士のネットワークを獲得する能力において決定的な前提となっているという(ハート、同書)。カミングアウトは、そうした有形無形のソーシャル・サポートにアクセスするうえで、自己呈示となる。
ゲイ・レズビアンの、既存の社会体制・秩序と相容れない側面を突き詰めた地点に「クイア」という概念が浮かび上がる。
「『クイア(Queer)』は名詞、形容詞、動詞として機能するが、いずれの場合も『正常(ノーマル)であること』、正常化の逆を意味する。クイア理論は単独の、あるいはシステム化した概念的、方法論的な枠組みを持たず、むしろ性、ジェンダー、性的欲望の関係についての知的な取り組みの集合したものである」(スパーゴ、2004)。
ゲイ・バッシングに対抗するために町のパトロールを組織し、街頭の落書きキャンペーンで同性愛嫌悪の暴力の犠牲者を追悼し、ストレートの連中のたむろするバーで反同性愛嫌悪の学習会を開いたりしていたラディカルな共闘グループ、クイア・ネーションやピンク・パンサーズが、レトリックと表象の戦略のキーワードとして用いたのが「クイア」というスラングだった。これは、同性愛嫌悪の言説内だけでなく、「ゲイ」や「レズビアン」より以前に、あるいはその代わりに、一部の同性愛者たちが好んで使っていた言葉だった(スパーゴ、同書)。
19世紀から20世紀にいたる非異性愛者のアイデンティティの軸の変遷を、「同性愛」から「ゲイ」「レズビアン」、そして「クイア」へというように分析し、支配的な言説や知との関係から生まれた個人や政治行動の可能性や問題を、それぞれがいかに提供したかを見るのはそれほど困難ではない。だが、アイデンティティの政治学の新たな基礎として、クイアがひとつのカテゴリーとなれば、それもまた、必ず排除と制限を行うことになる。そもそも「理論上クイアは、支配的な異性愛であれ、ゲイ/レズビアンのアイデンティティであれ、正常なものや規範とは永久に両立しない。それは決定的に中心から離れ、正常からは程遠いものなのである」(スパーゴ、同書)。
マイノリティが政治的運動に乗り出すにも、やはり既存の古い統一的な社会体を前提として、行動しなければならない。そこでの対立は、しかし、別の視点から見れば依存とも言える。
「いかなる対立も完全に孤立した状態では存在しない。すべては他との関係のなかで作動する。たとえば、互いに依存しながらも反目している伝統的な男性/女性の対立は、理性的/感情的、強/弱、能動的/受動的などの他との関連を通して階層的な構造を作りあげている。同様に、異性愛/同性愛も互いを支えあうネットワークに巻き込まれているのである」。社会の主流の内側にある異性愛と外側にある同性愛とを分断し、解放を企てる戦略には限界がある。「隠蔽されたセクシュアリティというクローゼットの『外側』に出ることを宣言するのは、個人的には解放であるかもしれないが、今なおクローゼットの『内側』にいる者の周縁性を強化し、異性愛の中心性を認めることになる。要するに、完全に異性愛の外側に出ることは不可能なのだ。(中略)同性愛の明確なアイデンティティの認知を要求することは、必然的に同性愛と異性愛の不平等な二項対立を再確認することになる」(スパーゴ、同書)。
また、そのアイデンティティなるものは、社会構築主義的観点から再検討されている。
「個人は、言語から独立して存在する内在的、本質的なアイデンティティを持つ自立したデカルト的な主体(『我思うゆえに我あり』)とは見られないということである。かわりに、われわれが普通に何げなく『自己』と考えているものは、社会的に構築されたフィクションであり(真摯なものであっても)、言語の産物であり、知の領域に結びついた言説の産物であると考えられる。むしろ、私はなぜかしら本質的に、私流に私自身であり、挫折することもあるが、言語を通じて私自身と私の考えを他人に伝えようとしていると考えてよいであろう。しかしこの考え、この個体感覚、自立感覚は、自然の事実であるというよりもむしろ、それ自体が社会的に構築されたものなのである」(スパーゴ、同書)。
また、言語学の言語行為論の「行為遂行」論的観点からの説明もある。
「われわれは自分のジェンダー・アイデンティティがあるから決まった方法で行動するのではなく、ジェンダーの規範を支えているその行動パターンを通してアイデンティティを獲得するのである」(スパーゴ、同書)。
双方に共通するのは、社会内の主体・事象は、「本質」が内在していたり、「客観的事実」であったりするのではなく、社会的に作られるものだという認識である。確かにこの思想はマイノリティにとって、「抑圧されたり圧迫された自然な本性の解放を目的とする政治的な運動を文字どおり根底から破壊するが、その一方で、アイデンティティの政治学によって動きのとれなくなっていた抵抗と攪乱の可能性を開くものでもある」(スパーゴ、同書)。
精神分析家E・H・エリクソンの心理社会的発達論におけるアイデンティティ概念には、主体の生物学的基盤を前提にしている側面がある(エヴァンズ、1981)。社会構築主義や行為遂行論は、そうした「基盤」「核」「本質」といったものを、とりあえず括弧に入れる。これは、従来の民族・人種・性的マイノリティの政治的実践活動に変更を迫る考え方かもしれないが、新たな可能性でもあり得る。
ゲイ・レズビアンを社会の「異物」として扱うヘテロ・システムは、一方、その異物と相補的に成立してもいる。異性愛も同性愛も社会システムの相関物だとも言える。そして相互補完関係にある。その意味で、ヘテロ・システムは消滅しない。クイアは、差異化の機能を果たす概念ではあるが、安定したアイデンティティを形成することはないのだろう。それはヘテロ・システムの効果だとも言える。にもかかわらず、彼らのカミングアウトは終わらない。「そのプロセスには多くのイベントが含まれ、それらは成人期初期、特にゲイ・及びレズビアンの自己や役割、社会的関係などの発達段階で頂点に到達する。カミング・アウトは生涯にわたって展開されるものであり、その過程に真の終わりはない。その背景には、ゲイ・レズビアンの加齢や社会状況の変化に従い、ゲイやレズビアンであることの意味を新しい適切な方法で彼らは表明し続けていくから、という簡潔な理由がある」(ハート、前掲書)。
(引用・参考文献)
R・I・エヴァンズ/岡堂哲雄、中園正身訳(1981)『エリクソンは語る アイデンティティの心理学』新曜社。
伏見憲明(1991)『プライベート・ゲイ・ライフ ポスト恋愛論』学陽書房。(1997)『<性>のミステリー――越境する心とからだ』講談社現代新書。
ギルバート・ハート/黒柳俊恭、塩野美奈訳(2002)『同性愛のカルチャー研究』現代書館。
タムシン・スパーゴ/吉村育子訳(2004)『フーコーとクイア理論』岩波書店。
(参照)
○異文化理解の心理学:http://togetter.com/li/599987
言葉・狂気・エロス 無意識の深みにうごめくもの (講談社学術文庫)/丸山 圭三郎

¥840
Amazon.co.jp
アイデンティティとライフサイクル/E.H.エリクソン
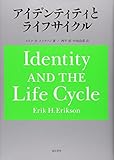
¥3,780
Amazon.co.jp
プライベート・ゲイ・ライフ―ポスト恋愛論/伏見 憲明

¥1,572
Amazon.co.jp
同性愛のカルチャー研究/ギルバート ハート

¥3,024
Amazon.co.jp
フーコーとクイア理論 (ポストモダン・ブックス)/タムシン・スパーゴ

¥1,620
Amazon.co.jp