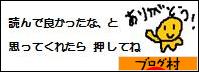天皇誕生日(12月23日)如何なる困難に遭遇しても日本国民が勇気と再生の力を得られる不思議
天皇誕生日(12月23日)を迎えさせて頂くにあたり、国際派日本人養成講座より、日本には天皇がおられるという国がらについて身近な事由から理解させて頂ける記事が出されていましたので転載させて頂きます。
先進国という言葉がありますがこれは西洋思考から出て来たものです、その先進国の中に日本はいるわけですが欧米先進国と基本的に違う国である点を私ども日本人はもっと理解し知っておくべきではないでしょうか
魚の形態をしていても海にすむ魚と淡水湖に住む魚は同じでしょうか、四足の動物もライオンや牛を肉食と草食の違いを考えず同じ動物として取り扱って良いのでしょうか
自ずと生き方や生活様式は違っているわけです、それを世界はひとつ(ワンワールド)という人間が考えた都合に当てはまる事が進んでいるかのような考えが世界には存在します。
そこにはそれぞれが違うから調和ができる、という考えがありません、藻類を食べて生きている琵琶湖の魚の形態に、ブラックバスの様な肉食の魚を一緒に住まわせるという人為的な行いが如何に生態系を破壊する行為であるかを考えれば、それと同じ様な間違いを犯し続けているとも言えるわけです
国民を如何に支配するか、というのが世界の支配層の常識です、同じ先進国と言われる日本では国民は神からの賜り物でありお預かりしているのだという価値観の天皇がおられる国を欧米先進国と同じ先進国と分類する事は上記の様な間違いを犯していると言える事になって来るわけです
西洋は論理的な国と言う事から言えば、日本は論理を越えたモノが存在する国と言えるわけで、その一端がこの記事には語られていると存じます
|
両陛下のお言葉に勇気づけられた人々が、被災地の復興を成し遂げた。
|
国見(くにみ)とは、天皇が国土を巡幸することで、その繁栄を祈ることだ。万葉集冒頭の第2首目に次の舒明天皇の御製がある。
__________
大和には 群山(むらやま)あれど
とりよろふ天の香具山 登り立ち 國見をすれば
國原(くにはら)は 煙(けぶり)立ち立つ
海原(うなはら)は 鴎(かまめ)立ち立つ
うまし國ぞ 蜻蛉島(あきづしま) 大和の國は
(大和には多くの山があるが、とりわけて立派に装っている天の香具山、その頂きに立って国見をすると、国土には炊煙がしきりに立ち、海上には鴎が翔り続けている。美しい国よ、蜻蛉洲大和の国は)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
単に国土を見て賛美した、というだけではない。
__________
見ることは、視察に留まらず、良き状態への転換を生む力の付与なのである。見て誉めることは対象を誉めた状態に転化させることなのだ。天子様が見て誉めると状況はその通りになる。それは古代人にとって観念上のことではなく現実のことであった。[1,p6]
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
これは古代人の迷信ではない。平成の現在においても、現実に起こっている事実であることを、以下に紹介したい。
■2.「二度とこの場所に住むわけにはいかないかもわからない」
「きれいな村だったんでしょうね」という陛下のお言葉が、新潟県の山古志村の長島忠美村長は、ずしんと胸に刺さったという。
平成16(2004)年10月23日午後5時56分、マグニチュード6.8の中越地震が山古志村を襲った。地滑りによって東京ドーム63個分の斜面が崩れ、住宅の40%が全壊し、1029ヵ所の農業道路、460ヵ所の水路、194ヵ所の棚池が被害を受けた。
長島村長は、日本初となる全村避難勧告を決断した。村民2千2百余名の避難を見届けて、最後に村を離れた。その時の心境を、こう語る。
__________
あの時は、自分が情けないのと、何をしたらいいのかわからないい絶望感で一杯で、涙が止まりませんでした。村民を避難させた後、自衛隊の方と村の中を最終点検をすることになりました。その時、口が裂けても村民には言わないでおこうと思ったことがありました。
二度とこの場所に住むわけにはいかないかもわからない、実はそんな気持ちを抱いてしまったんです。絶望という言葉は知っていましたが、何をしたらいいかわからない、何ができるのかわからない、というそれが絶望だと感じました。[1,P48]
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
■3.「きれいな村だったんでしょうね」
震災からわずか2週間後に、両陛下がヘリで山古志村の状況をご視察になることになった。
__________
新潟空港からすぐヘリに乗って山古志に向かうことになりました。そして山古志に入り、私が説明する番になりました。ヘリっで騒音が大きくて、通路を挟んでお話ししたらあまり聞こえないんですよね。すると隣に座るように言われまして、陛下のお耳元でご説明することになったんです。
そのとき私は、両陛下のいらっしゃる日本国民でよかったと思いました。陛下は「牛はどうしていますか」、「錦鯉はどうしたんですか」ってご質問になるんです。もちろん我々のことも心配してくださいました。
そのあとで言われた「きれいな村だったんでしょうね」というお言葉がずしんと胸に刺さりました。両陛下がきれいな村だったと言ってくださっている村を取り戻さないわけにはいかないと思って、私の勇気を奮い起こしてくれました。[1,p52]
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
陛下が牛や錦鯉のことも訊ねられたのは、山古志村の闘牛「角突き」は戦国時代以前に遡る神事であり、また錦鯉の養殖が山間部の生活の糧であったからだ。角突きは昭和53(1978)年には国の重要無形民俗文化財に指定されている。ご視察の前に、そこまで調べられていたのだろう。
長島村長は最終的に1200頭の牛をヘリに乗せて救出する、という決断をする。生活の復旧が最優先で、角突きなどという文化的なものは後でいい、という議論もあった。
__________
でも、牛の命を救うことと文化を守るということは私たちにとっては一つでした。仮設の闘牛場でもいいから闘牛という文化を再生しようと考えていました。牛が元気になれば私たちも元気を出せるという思いがそこにあったからです。[1,p51]
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
山古志村の「角突き」は、二頭の牛が角を突き合わせて戦うが、これ以上戦わせるとどちらかが倒れるという寸前に、行司役が「引き分け」を下し、勢子(せこ)が二頭を引き離す。勝敗はつけずに、いつも「引き分け」で終わる。これは山間の物資の運搬に牛が欠かせず、家族のように扱ってきたからだ、とある村民は言う。
■4.「角突きの技見るはうれしき」
4年後の平成20(2008)年9月8日、再び、両陛下は山古志村を視察された。今度はヘリコプターではなく、村内を歩かれて、錦鯉の養殖や牛の角突きをごらんになられた。
長島村長の話によれば、皇族が山古志村に来られるのは有史以来のことであり、村民の気持ちも高まって、誰が言ったわけでもないのに全ての家が国旗を掲揚していた。
両陛下は次のような御歌を詠まれた。
天皇陛下 中越地震被災地を訪れて(平成20年)
なゐ(地震)により避難せし牛もどり来て角突きの技見るはうれしき
皇后陛下 旧山古志村を訪ねて(平成20年)
かの禍(まが)ゆ四年(よとせ)を経たる山古志に牛らは直(なお)く角を合はせる
角突きは山古志村の人びとの心を結ぶものであった。それが復活したということは、もとの「美しい村」に戻ったということであろう。
翌平成21(2009)年10月11日、闘牛場が改修され、その場内に両陛下の御歌を刻んだ碑が建立された。両陛下に見守っていただいて、復興を成し遂げ得た村民の感謝の現れである。
■5.「おばさん、今度家に来てね」
三宅島は東京から60キロほど南下した海上にある、伊豆諸島の一つだ。島の中心にある雄山(おやま)が平成12(2000)年に大噴火し、全島民が本土に避難した。
平成17(2005)年、村長の決断により、帰島が開始され、噴火前の約75%にあたる2800人が我が家に戻った。これまでの間、両陛下は毎年、村民の避難先を訪問されて、激励を続けられた。
平成12年12月20日 あきる野市「都立秋川高等学校」に避難児童をご訪問
平成13年8月27日 下田市「下田臨海学園」に避難漁業者をご訪問
平成14年3月18日 八王子市「三宅島げんき農場」に村民をご訪問
平成15年4月30日 江東区「三宅村ゆめ農園」に村民をご訪問
平成16年5月20日 北区「三宅村桐ヶ丘支援センター」に村民をご訪問
被災当初だけでなく、その後も被災者がもとの生活に戻れるまでお見舞いを続けるというのは、両陛下の御思いである。
下田市では並んで待っていた被災者の中で、小学校低学年の女の子が皇后陛下に「おばさん、今度家に来てね」と言った。まだ小さくて皇后陛下のことを分からなかったのだろう。その女の子の家族は、下田に家を借りて住んでたのだが、次の日に皇后陛下が本当に玄関に立っていて、びっくりしたという。
■6.「良い日が来る事を祈っています」
平成16年の北区「三宅村桐ヶ丘支援センター」では、避難中の高齢者たちに、両陛下は一人ひとり「こちらの生活にはなれましたか?」「三宅島の家は大丈夫ですか?」「良い日が早く来る事を祈っています」と声をかけられた。
三宅島で特別養護老人ホーム「あじさいの里」施設長をしていた水原光男さんは、「両陛下にお言葉をかけていただいて、皆とても喜んでいました」と語る。水原さん自身も、陛下から「お疲れ様、ごくろうさま」と声をかけていただいた、という。
翌平成17年2月に避難指示が解除されて、島民の帰島が始まったが、「あじさいの里」再開の目処は立っていなかった。介護をする職員が退職を余儀なくされ、しかも避難先ですでに職についていたからだ。介護職員がいなくては介護認定を受けている人びとは島に帰れない。
しかし、両陛下のお見舞いが、水原さんの使命感に火をつけた。
__________
陛下にご心配いただき、「良い日が来る事を祈っています」とのお言葉を賜った高齢者たちは、早く島に戻りたい、元いたところに戻りたいとの気持ちを強く持っていました。
そのような人々にとって島に戻る事は喫緊の課題であり、そのためにも「あじさいの里」はなくてはならない施設でした。だからこそ、早急に何とかしなければならなかった。[1,p19]
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
高齢者受け入れの第一歩として、平成17年4月にデイサービスを行うセンターが開設された。しかし職員2人で150人もの在宅介護を行わなければならなかった。
その後、水原さんは職員確保に奔走して、平成19年4月、17名の職員を得て「あじさいの里」が再開され、介護認定された高齢者もようやく帰島が叶った。
■7.「この島に戻りこし人ら喜び語る」
平成18年3月7日、両陛下は三宅島をご訪問され、デイサービスセンターにも立ち寄られた。そこでお待ちしていた20名ほどのお年寄りに、両陛下は親しく声をかけられた。その時の様子を水原さんはこう語る。
__________
両陛下は、利用者に対して、島に帰ってからの生活や精神的な状況、帰ってきた感想を聞かれたり、また励ましのお言葉をかけられたりしていました。特に精神面に対してかけられるお言葉が多かったです。これまでの噴火で島外へ避難することはなかったので、噴火が高齢者に与えた精神的影響はとても大きいものでした。[1,p21]
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
両陛下は農業関係者と懇談する場では、集まった人々に「あなたはあのときいらっしゃいましたね」などと話しかけて、皆を驚かせた。その時のことを平野村長はこう語る。
__________
とにかく普通の人とは気遣いが違います。両陛下は島に3時間くらい滞在されましたが、島民全部が感動していたんじゃないでしょうか。この島まで足を運んでいただいたこと自体嬉しい事なのに、様々なお気遣いをいただいたことは、ちょうどこれから復興していこうとしていた私たちにとって、とても大きな励みになりました。[1,p22]
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
噴火以来、6年もの間、両陛下に見守っていただいた事を後世に残したいと、村役場に平野村長自らが揮毫して次の御製の碑が建てられた。
三宅島(平成18年)
ガス噴出未だ続くもこの島に戻りこし人ら喜び語る
■8.「天子様が見て誉めると状況はその通りになる」
前号でも紹介したが、現代リーダーシップ論の旗手サイモン・シネックは「人を動かすのは、利益ではなく、大義だ」と言っている。
その言葉通り、山古志村の長島村長や、「あじさいの里」の水原施設長を動かしたのは、村民のため、高齢者のため、という「大義」であった。この二人を中心に、周囲の多くの人々がこの大義に共感して、力を合わせたので、復興が成し遂げられたのだろう。
そして、これらの人々に大義を改めて強く心に刻ませたのが、陛下のお言葉だった。長島村長は「両陛下がきれいな村だったと言ってくださっている村を取り戻さないわけにはいかない」と決意し、水原施設長を動かしたのは「良い日が来る事を祈っています」という御言葉に高齢者たちが島に帰りたいという気持ちを強くしたことだった。
両陛下のお言葉によって「世のため人のため」の志に火をつけられた人々が国家、国民のために尽くす。皇室は国民統合の象徴であるが、統合力の源泉でもあるのだ。
「天子様が見て誉めると状況はその通りになる」という古代人の国見の信仰を、21世紀の我々日本国民は目の当たりにしているのである。「両陛下のいらっしゃる日本国民でよかった」とは、長島村長だけの思いではあるまい。
この12月23日、天皇陛下は満81歳の誕生日を迎えられる。
(文責:伊勢雅臣)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
確かに「現代リーダーシップ論の旗手サイモン・シネックは「人を動かすのは、利益ではなく、大義だ」と言っている。」と書かれています
その点もありますが私は天皇が行幸された時に、例えば会場内に来られた時にその瞬間場内の空気が変わり、陛下が来られただけで、感動し今まであった不安や失望が払われて、蘇りの力を頂かれている様をまざまざと拝見させて頂きます
陛下は大義を論理的にとうとうとお話しになられませんが、そのお姿だけで、圧倒的な言葉を超越した威徳を自然的にお持ちになっておられるわけです。
大義という言葉を越えたあるがままの威徳によって、天皇の本分を貫かれていますしその謙虚で敬虔なお姿に姿勢を正される思いを感じたりするわけです。
この様なご存在がある日本を単なる先進国の一つとして欧米の国々と同じという分類では他の先進国との本質的な違いが明確にならないわけで、どうして大災害にあった時に暴動や略奪が起きない、皆の為という無償の行使を言われずして発揮する国民性が存在しているのか、その意味や理由を世界が気づき理解する事が難しくなってくるわけです。(これは日本人にも当てはまる事ですが)
ですから奴隷を作った差別感を持つ西洋思想で日本文化を考えたりしてしまいますと、陛下の御心とはかけ離れた、日本がどこよりも一番で最高であるという様な上から目線の差別的見方を持ってしまったりしてしまうわけです。
大戦時もユダヤの人々を助けたり、戦後はサマワでも現地労働者が日本の自衛隊員と一緒になって遅くまでせっせと働く事に欧米の部隊がどうしてだと見に来る事が起こっています
やはり日本人にとっては上官も現地の人と同じ様に汗を流して作業するのが当たり前という考えですが、そこには人種を越えた公平という姿勢が差別意識を持った他の欧米部隊との違いとなって表れているわけです。
人間は物質面の肉体と精神(生命)面の魂が一つになって存在していますから、肉体面だけでなく、見えないけれど存在している精神(生命)の存在を無視してはいけないわけで、己を知る上においても目に見えない価値を大事にしているという日本文化の持つ欧米にはない特性にもっと注目すべきではないか、また明治以後の西洋化で西洋の持つ特権意識や差別意識を先進的な考えと受け入れた為に日本文化が間違って怖いモノの様に取られてしまっているところの排除が必要であると申し上げたいわけなのです。
http://ameblo.jp/matsui0816/entry-11964655148.html
ランキングに参加しております。是非1クリックご協力お願いします!
 1クリックお願いします!
1クリックお願いします!
 1クリックお願いします!
1クリックお願いします!
![]() 記事一覧http://ameblo.jp/matsui0816/entrylist.html
記事一覧http://ameblo.jp/matsui0816/entrylist.html
まずは応援クリックをお願い致します。
↓↓↓