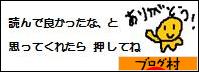織田信長型と豊臣秀吉型の「金箔瓦(復元)」を
近江八幡市立図書館で展示
これは滋賀県近江八幡市の八幡山の麓にあります近江八幡市立図書館のエントランス(入口)風景です
この玄関を入って中の扉を開けますと、目の前にケースに陳列されました信長型・秀吉型の金箔瓦(復元)の展示が目に入ってきます

織豊時代の「金箔瓦」を漆で瓦に金箔を貼りつける当時の方法で復元させて頂いた事は以前に以下のブログでお知らせさせて頂いております。
まだ、お読みで無い方は是非さきに、これをご覧ください
京都・滋賀報知新聞にて「信長・秀吉」の金箔瓦再現で織豊時代の町近江八幡をアピール2013.6.22
http://ameblo.jp/matsui0816/entry-11558075022.html
この時は講演の会場の一角で展示させて頂いただけだったのですが、新聞にも出して頂き好評でしたので市の図書館での展示になったわけでございます
玄関を入ったすぐ目の前ですので大変分かり易いところに置かれていますから、是非お立ち寄りになって見て下さい
そこに簡単な解説を作って置かせて頂いています、ここに来られない方も多いと存じますので、その内容を以下に載せさせて頂きます。
信長・秀吉が戦国の世を終わらせて太平の世に持って行く背景に「金箔瓦を使った城の築城」があります。展示されている本物の金箔が貼られた瓦を目の前にされて、どの様な感想をお持ちになるでしょうか・・・
下剋上が続く戦乱の中で瓦に金箔を貼って城を飾り、信長・秀吉は自らの威勢を示したわけです、つまり戦いの城が金箔瓦を使った安土城からは権力の象徴としての城として近江八幡の地に出現したわけです。
これまでの城の常識を破って、本来なら攻撃される本丸に莫大な金をかけ豪華にするという考えられない発想で信長は城を戦いだけに使う城から、居住と防御が一体化した城に進化させ他の大名を圧倒する策に出たわけで、特に安土城の場合は天守閣の横に本丸御殿が建てられ、天皇の間が作られて、天皇をお呼びして天下布武を完成させようと考えていたのではないかと思われています。
残念ながら、その信長の夢は本能寺に果てたわけでございますが、その考え(政治戦略)と発想を実に良く理解して実現したのが当時信長の家臣であった秀吉であり、秀吉は京都の御所から丁度西にあたる内野(平安京の大内裏跡)に聚楽第という政庁兼邸宅を作り、そこに天皇の行幸を仰ぎ、諸大名には関白豊臣秀吉に違背のないことを誓約した起請文に署名させて天下人秀吉の誕生を進めて行ったわけです
その聚楽第跡や御所と聚楽第の大名屋敷跡からも多数の金箔瓦が出土されていますから、展示の金箔瓦を見られて当時を思い浮かべて頂きますと、実に豪華な町並みが戦国の終焉を迎えるにあたって都に作られた事が想像されて来るわけです
この様に、大きな時代の転換に際し不可欠の道具として金箔瓦が作られているのですが時代は金箔瓦の作り方に信長と秀吉の性格(キャラクター)の違いを出させているとも言える様な違いを創り出しています
それは、展示の金箔瓦を見て頂きますと瓦の文様の引っ込んだ凹面に金箔が貼られているモノと出っ張っている凸面に貼られているモノがある分けで、信長は金箔を瓦の凹面に貼り、秀吉は瓦の凸面に金箔を貼って作るという様に、正に真逆と言うか陰陽とも言うべき2種類(様式)の貼り方で作られているのです。
そこで凹面に金箔が貼られているモノを信長型、出っ張っている凸面に貼られているモノを秀吉型と便宜上分けて表現させて頂いているわけです。
特に信長のモノは信長が本能寺で早くに亡くなっている事から使用された城も少なく、その意味で貴重なのですが、その信長型と秀吉型という2種類の金箔瓦が2種類とも出土しているのが近江八幡市なのでありまして、この事実は国内唯一であるという事を強調させて頂きたいわけなのです
近江八幡市の安土城などから出土された信長型の金箔瓦や再現瓦は安土城考古博物館や信長の館で見る事ができます、また近江八幡の八幡城や秀次館から出土している秀吉型金箔瓦はかわらミュージアムなどで見る事ができます、しかし秀吉型での再現された金箔瓦は今までありませんでした。
そこで、当時の方法として漆を使って金箔を瓦文様の凸部に貼った秀吉型の金箔瓦を同じ瓦によって両者の比較ができるようにして再現させて頂き、それをさる6/23に同近江八幡市立図書館にて開催の歴史講演会「秀次公と聚楽第」(近江八幡市郷土史会主催)にて初公開させて頂いたわけなのです。
好評でありました事から、今回近江八幡市立図書館1階の展示スペースにての展示公開に至っております。
特に実際に漆を使って金箔を瓦に貼って製作させて頂きますと漆は縄文時代から使われている事や展示の瓦を見て頂きますと特に凸部に貼られている場合はこんもりとした丸みのある丘の様なところに金箔を貼る必要があるので、その時には蒔絵の技術が必要である事、また当時は漆が西洋に知られていなかった事から、この金箔瓦は日本でしか作れなかった事なども分かってきました
私の家は元々八幡瓦の窯元でした、ですから瓦を製造していましたので金箔瓦に関しては、瓦に金箔を貼ったくらいの感覚でいたのですが、この金箔瓦が当時のハイテクの集積で作られている事が製作過程から気付かされ驚かされています
金箔瓦を通じて戦国の終焉をはじめた信長・秀吉の時代が近江八幡の歴史にもあった事の展示を多くの皆様にお楽しみ頂ければと思う次第でございます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以上です
展示期間 平成25年7月13日(土)~8月18日(日)まで
展示は終了されています
近江八幡市立図書館 TEL.0748-32-4090
開館時間 午前10時~午後7時まで(ただし土・日・祝は午後6時まで)
休館日 月曜日、毎月最終水曜日
祝日の翌日(ただし、土・日・祝は除く)など
是非、織豊(しょくほう:信長秀吉)の歴史溢れる
近江八幡に「いらっしゃ~い!」
はげみになりますので宜しくお願いいたします