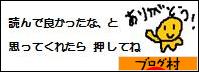米中首脳会談 太平洋は2大国の空間か
http://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/ddb5e4ce4e43c11b9efe82764efb6d9a (まずは記事↑をご覧ください)
オバマ米大統領と中国の習近平国家主席との首脳会談で「太平洋には両国を受け入れる十分な空間がある」との習氏の発言しており、「新たな形」の協力関係を築くことで一致した、という動きは注目に値する事ではないでしょうか
ハワイから西を中国、東をアメリカと中国がアメリカに言っている事は明確に太平洋の西半分を中国が支配しますよ、イイですよね、と意志表示しているわけで、アメリカに対し抜け抜けと言ってのけているという事は、そのバックにこう言ってもアメリカが明確に拒否する事がないという条件作りがされていると考えられるわけです
米中首脳会談 太平洋は2大国の空間か
http://sankei.jp.msn.com/world/news/130609/amr13060903360002-n1.htm
2013.6.9 03:36 [主張]
オバマ米大統領と中国の習近平国家主席が初の首脳会談に臨み、「新たな形」の協力関係を築くことで一致した。
冷戦後、唯一の超大国となった米国と急速に台頭した中国は良好な関係を維持することが望ましいが、それが2国の世界支配に向かうことがあってはならない。
特に気になったのは、「太平洋には両国を受け入れる十分な空間がある」との習氏の発言だ。中国の海洋進出の野心が露骨に表れており、日本を含む太平洋の国々にとっては警戒すべきことだ。
中国は外需依存の経済成長で大国にのぼりつめた。軍事力を背景とした海洋権益の拡大やサイバー攻撃、貿易不均衡など、世界でさまざまな軋轢(あつれき)を生じさせている。米国との新たな冷戦との見方もある。「新たな形」の関係は、こうした対立や不安を解消させるものであるべきだ。
習氏は就任後わずか3カ月での訪米となった。会談はカリフォルニア州の保養地で行われ、2日間に及ぶ。異例の舞台設定は、首脳同士の信頼関係の醸成が不可欠だとの双方の認識を示している。
両首脳がサイバー空間の安全に向け、共通のルールづくりを目指すことで一致したのは、協力関係の第一歩として評価したい。
企業の知的財産に関する情報が盗まれ、膨大な損失が出ているとして米国では大きな問題になっている。中国政府・軍の関与が指摘されるが、中国側は自らも被害者だと主張している。
ただ、サイバー空間に国境はない。日本を含めた多国間の協力が必要だろう。
会談の冒頭、オバマ氏は北朝鮮の核・ミサイル開発への対応で協力の必要性も強調した。北は対話の姿勢に転じている。米中に日本、韓国、ロシアを加えた従来の枠組みに引き戻すべきときだ。
オバマ氏は中国の人権問題の重要性を強調し、さらには、気候変動や経済摩擦など幅広い問題を列挙した。
これに対し、習氏の発言は「中米関係の将来の青写真」「新たな大国関係」など具体性に欠け、大国意識ばかりが鼻についた。
「太平洋には」の発言が、尖閣諸島(沖縄県石垣市)を含む東シナ海が中国の空間だという意味なら、日本として看過できない。
オバマ氏はそのことをしっかり認識し、中国にモノを言ってもらいたい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
転載は以上(強調部は松井による)
米中の会談でも孫子の兵法を旨とする中国からの政治戦・世論戦は実に活発と言わざるをえません、アメリカがサイバーテロに対し中国の仕業と言う事に対して中国は「自らも被害者だ」と言ってのけています
つまりアメリカに中国が悪モノであると思わせる様な事を中国は(何者かに)されられている、だから中国こそ被害だ。
というわけでして、サイバーテロが犯人の特定が難しいという特性を捕まえて、ハッキリ言えん事をエラそうに言うな、と釘をさしているわけです。
戦前からアメリカの中国市場へのあこがれ、アメリカ国民を戦争に駆り立てる為の日本への憎悪書きたてマスコミ報道や蒋介石夫妻による日本悪モノ中国可哀そうな国発言などウソを真実と思わされて来ているアメリカの中国重視の見方があった事などです。
アメリカの中国に対するフトコロの甘さが出てきている原因には、アメリカも歴史的には中国に騙されている国である事は知っておく必要はあるのではないでしょうか(日本はもっとひどいわけです)
アメリカがサイバーテロに関して、想像以上の対策の遅れを出している事が今回の会談の中から感じられてきます、この事はイギリスの記事からも分かる事で
「中国・華為に注意せよ!」 英議会がずさんな政府セキュリティーに警鐘http://sankei.jp.msn.com/world/news/130608/chn13060822440006-n1.htm
【ロンドン=内藤泰朗】英国政府が中国の通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)へのセキュリティーチェックを怠ったことで、英国が中国からのサイバー攻撃や国家によるスパイ行為にさらされる危険が増大している-。英議会の情報安全保障委員会(ISC)は8日までに、英通信業界で主要プレーヤーにのし上がった同社を名指しし、その伸長に警鐘を鳴らす異例の報告書をまとめた。
■米は調達排除
中国広東省深●(=土へんに川)に本社を置く華為は昨年10月、米下院情報特別委に同業の中国国有企業、中興通訊(ZTE)とともに「米国に安保上の脅威を与える可能性がある」として、米政府調達からの排除を勧告されたハイテク民間企業。業界世界第2位という売上高を誇る華為への風当たりは欧州でも厳しくなりつつある。
ISCの報告書は、政府が華為の数々の活動を監督できていない事実に「衝撃を受けた」として、サイバー攻撃を監視・対抗するその戦略は「お粗末で虚弱なものだ」とこき下ろした。
華為の活動を監視する英政府のシステムは、実際には同社の資金と人材を使って同社自身が行っていると指摘。「自分自身で自分の安全の度合いをチェックするというようなことはあり得ない。監視するのか、されるのか、どちらかだ」と述べ、英政府のずさんなセキュリティー管理態勢を非難した。
英国政府が8年前、100億ポンド(約1兆5千億円)をかけて通信インフラの近代化を行った際、すでに華為製の機器が使われ、英国の基幹通信事業の主要受注企業に同社が入っていたことを政府の閣僚たちも知らされていなかったという。
■中国関与を指摘
さらに、報告書は、具体的事例は挙げなかったものの、英国に対するサイバー攻撃の多くに中国政府が関与している疑いがあると言明。「華為と中国政府との関係には懸念がある」とくぎを刺した。同社最高経営責任者(CEO)の任正非氏(68)は中国人民解放軍出身で、中国政府や軍との関係については不透明な部分があるとされる。
オーストラリア政府も昨年、高速通信網事業から華為を排除。先月には、欧州連合(EU)が同社をダンピング(不当廉売)の疑いで調査すると発表し欧州でも風向きが変わり始めた。
ただ、英産業界で中国からの投資や中国市場への期待は高い。ISCの報告書が発表された6日、オズボーン財務相は「英国は中国からの投資に門戸を開いている」と述べ、英政府が中国との良好な経済関係の継続を望んでいると強調した。
一方、華為側は7日付の英紙フィナンシャル・タイムズに、「英政府の要求に従い、すべてのことをやってきた」などとする声明を出し、報告書に反論した。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
転載は以上(強調部は松井による)
イギリスでも言われている様に、中国製品の使用によるサイバー被害の延焼です、もし軍事行動をする事が起こっても、その軍隊の精密な部分に中国製品が多く使われている事のよる不安、言いかえれば、つい安い?からと思わされて中国戦略にまんまと乗らされて重要なところに余りにも多く採用してきた事のツケの大きさが、米英の動きに感じられるわけです。
孫子の兵法、戦いとは欺く事である、という伝統を貫く国の戦略に今アメリカも深くやられている、というわけなのでしょう。
アメリカも中国にしてやられている体の中に中国のバイ菌を埋め込んできた付けの清算をする為の時間稼ぎが必要である様子が感じられるわけで、その弱みの分、中国から言いたい事を言わせる事になっている原因になっていると思われる分けなのです。
アメリカも弱みを見せられないところから、中国の思惑を明らかな否定をしないという事で対応しているわけで、日本としても、サイバーテロを中国がやっていると分かっていても、中国は「自らも被害者だ」とアメリカに応戦しますし
イギリスの中国の電子部品排除に関しては「英政府の要請に従ってやって来た」つまり、「あんたの言う様にやってきたのに犯人扱いはないやろ」と反発(いなおり)しています。
悪くてもそれを言葉巧みに認めず、逆に世論戦を展開する中国のしたたかさを考えます時に、アメリカやイギリスに対しても、尖閣の様に自分が悪くても相手が悪いと言うわけですから、日本だけと思っていたら大間違いであるわけで
アメリカからもカチンと言われない様に世界戦略を進める中国が隣国である事に気を引き締めて、アメリカに全面的に頼らなくても日本は大丈夫という外交戦略の構築を安部政権には進めて頂きたいわけなのです。
しかし、本当は日本を軍国主義とか侵略国というレッテルを張って植民地化でアジアを苦しめてきた張本人(欧米)をすり替えられ、冤罪が続けられ今も慰安婦などで利用されている現状に対して日本こそ「アメリカの鏡」を書かれたアメリカのヘレンミュワーズ氏ではありませんが、日本こそ「欧米政府の要求に従い、明治以後すべてのことをやってきた国」と、欧米に利用されてきた歴史を世界に問う事が必要であると申しあげたいわけなのです
。
はげみになりますので宜しくお願いいたします
![]() 記事一覧http://ameblo.jp/matsui0816/entrylist.html
記事一覧http://ameblo.jp/matsui0816/entrylist.html