【三人閑談】ベトナムに誘われて
三田評論ONLINEより
-

長島 清香(ながしま さやか)
ライター、編集者。
2004年慶應義塾大学文学部卒業。日本、シンガポール、ニュージーランドにて活動後、2018年よりハノイを拠点に旅行記や食文化を発信。現在はセブ島で現地メディアの統括も担当。 -

グェン・バオ・トゥアン
株式会社アジラ プロジェクトマネージャー。
ハノイ貿易大学卒業。スタートアップ企業勤務を経て2021年慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科修士課程修了。世界で活躍する起業家を目指しビジネスに従事。 -
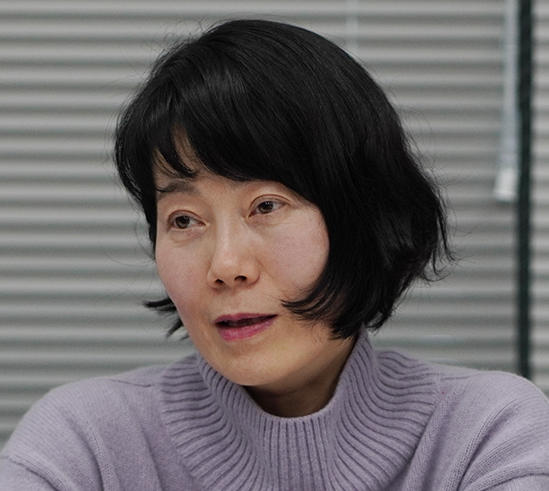
難波 ちづる(なんば ちづる)
慶應義塾大学経済学部教授。2000年慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。2006年リュミエール・リヨン第2大学博士号(歴史学)取得。専門はフランス植民地史、インドシナ史。
ハノイへ、そしてハノイから
難波 私は慶應の経済学部でフランスの植民地統治を研究しています。ベトナム、ラオス、カンボジアからなるインドシナ連邦の中でもフランスにとって一番重要なのはベトナムでした。私の研究はおもにフランス側の視点ですが、ベトナム側の視点を知るためにも資料調査や現地視察をしによく行きます。
初めてベトナムに行ったのは1995年です。ドイモイによって国が市場経済導入路線に転換し、観光客を受け入れ始めた頃でした。私は修士課程への進学を決め、研究テーマを模索している最中だったのですが、フランス人観光客がとても多かった記憶があります。まだ渡航自体がそれほど多くない時代で、フランス人が観光客の7割を占めていました。ベトナム戦争の傷跡が生々しく、国もまだ貧しい時代でしたが、リタイアしたフランス人たちがかつての植民地で楽しそうにしているのを見て、どういう心理なんだろうと不思議に思ったものでした。
フランスや米国、中国との戦争を経験し、植民地支配が長かったこの国で、フランスがどういう植民地支配をしていたのかを研究してみようと思ったのが始まりです。最近は2017、8年に1年半ほどハノイに滞在しました。
長島 私は大学を卒業後、日本で雑誌の編集に携わっていました。2015年からシンガポールで働くことになりますが、その前の2012年に初めてベトナムに行きました。その時にホーチミン市でひどいぼったくりに遭ったのですが(笑)、それも含めて体験したことがない文化に触れ、とても新鮮に感じました。
シンガポールからニュージーランドに移動する際にフリーライターに転身し、その後は東南アジアや日本など場所を決めずに活動していました。しかし、パソコンと通信環境があればどこでも働けることから、どうせなら自分の好きな国で仕事をしようと思い立ち、ハノイに住むことにしました。2018年~20年はハノイでライターをしながら、現地の人材会社で日本語を教えたりもしていました。
グェン 私はハノイ貿易大学を卒業後、2カ月ほど現地の日本の企業でインターンシップをしていました。その後、先輩とともに起業したのですが上手くいかず、次のステップとして日本留学を決めました。当時はハノイに日本のIT企業が増え始め、日本に留学することで貢献できることがあると思ったのです。
2018年に日本政府から奨学金をもらうことができ、2019年に慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科(KMD)の修士課程に入りました。2021年に修了し、今は日本の企業で働いています。
ハノイとホーチミン市の違い
難波 ベトナムが好きな人の中には、ハノイが好きという人もいれば、ホーチミン市が好きという人もいますね。グェンさんはハノイのご出身だそうですが、ホーチミン市とは随分異なるのでしょうか。
グェン まず天候が違います。ホーチミン市は一年中暖かいのに比べ、ハノイは日本のように四季があります。
難波 ハノイの冬は寒いですよね。
長島 そうですね。冬はダウンジャケットが必要な時期もあるほどです。
難波 体感的には気温よりも寒く感じます。湿気のせいでしょうか。
グェン ハノイは湿気があり風が強い地域ですが、建物の風通しが良いのも寒い原因かもしれません。
難波 最低気温が10℃を下回ると小学校が休みになるそうですね。
グェン いや、8℃です(笑)。
長島 寒いと学校に行かなくていいというのもめずらしいですね(笑)。
難波 暖房設備がないからでしょうか。
グェン そうですね。ですが、今年はエルニーニョ現象の影響で暖かいようです。最近帰った時には25℃もありました。
ハノイとホーチミン市はライフスタイルに対する考え方も違います。ハノイの人たちは子どもの教育や家を買うためなどにお金を貯めますが、ホーチミン市の人たちはサラリーが低くても外食や買い物が好き。新しいものにお金を使います。
難波 両方の都市に行くと確かにそれが実感できますね。資本主義の発達度合いも違う。東京で暮らしていて言うのもなんですが、ホーチミン市は大都会で少し疲れます。
長島 そうですね。他方のハノイは政府機関や学術的な拠点が多く、京都や奈良に近いイメージです。
ハノイのコミュニティ
難波 ホーチミン市に比べるとハノイは規模が小さいですよね。こぢんまりとしていて移動しやすい。植民地時代の古い建物が残っていて街の雰囲気も良いですね。
グェン ハノイ中心部にはホアンキエム湖があり、このエリアが旧市街です。36本の通りがあり、それぞれの通りでさまざまな特産品が売られています。ハノイに観光で訪れる人たちの多くはこのエリアに滞在し、昔の街の雰囲気を味わえます。
難波 ベトナム戦争が終結してしばらくの間は国がまだ貧しく、建物を積極的に残すというよりもあるものを使う感じだったと思いますが、今は残すことで観光資源になるのをベトナムの人たちはよく理解しています。フランス人が建てたものだけでなく、ベトナム人建築家による建物もあって街を歩くのがとても楽しい。
グェン 私の家はハノイ旧市街から少し離れたエリアにあります。日本で言う社員寮のような団地に、祖父母やその会社の人たちと一緒に暮らしていました。ですので周りに住んでいる人のこともよく知っていましたし、人間関係も良かった。東京とは対照的な環境です。
長島 私も日本語の授業後には生徒たちとともにお茶会をしたりしていました。日本人コミュニティがホアンキエム湖周辺で清掃のボランティア活動をする時には、地元の若者たちも積極的に参加していました。
日本語を習いに来る人たちはとても気さくで、授業が終わった後にはごはんを食べにいろいろな店に連れて行ってもらいました。私1人で注文するのはためらわれるような、チュンビロンというアヒルの卵を出してくれる屋台に行ったり。近所にあるアパートの管理人のおじさんとも毎日顔を合わせるうちに仲良くなり、「お茶飲んで行きなよ」と招き入れられることもありました。ベトナムの人たちは人情に厚いイメージがありますね。
ベトナム語も日本語も難しい
難波 ベトナムで日本語を学ぶ層はまだ一定数いるのですか。
長島 私が教えていたクラスには、日本でITエンジニアとして働きたい人たちが集まっていました。年齢層はさまざまでしたが、かなり多かったです。
難波 留学をする人たちの間では今、米国やヨーロッパが人気で、日本に来てくれる学生が少し減っているように思います。
グェン ベトナムでは最近、中学校や高校にも日本語のクラスがあり、日本語を勉強する人は増えています。でも日本語は難しい。少し勉強しただけでは留学できるほどにはなりません。
難波 グェンさんは最初から日本に留学するつもりだったのですか?
グェン そうですね。日本に来た時は全然日本語が話せませんでしたが、最初に2カ月ほど勤めた日本企業の経営者が慶應の博士課程を出ていました。彼と話すうちに尊敬するようになり、私もそういう人になりたいと思い、慶應を選びました。
もう一つは、ベトナムに日本企業が増えており、日本の文化やユーザーセントリック(ユーザー中心志向)を学びたいと思ったことも大きいです。日本のユーザーセントリックはよく知られており、私も起業した時にいろいろな本を読んで学びました。日本でそういうサービスやプロダクトを学びたかったのです。
長島 日本語は難しいですよね。私の生徒たちも苦戦していました。
グェン 私は日本に来てから1年間勉強しましたが、大学院の入学資格がJLPT(日本語能力試験)のN1レベルで、1年勉強するだけでは足りません。そこでKMDの、英語で提供される授業のみで学位が取得できるプログラムに進むことにしました。今仕事で使うのはほぼ英語ですが、日本語の勉強も続けています。
長島 一方でベトナム語を習得するのも大変です。とくに発音がとても難しい。私は今も全然話せません。
難波 私もです。学生時代から勉強していますが、全然話せるようにならない。やっぱり発音ですね。
長島 カフェで「スアチュアカフェ(ヨーグルトコーヒー)」を注文したいのに、何度言い直しても聞き取ってもらえませんでした。
難波 日本語の「ん」も、ベトナムにはいろいろな「ん」があります。「NH」と「MH」と「NG」があり、どの「ん」かと訊かれ、1つじゃないの? と驚きました(笑)。
グェン ベトナム語には声調が6種類もあるんです。ですが、日本語の「はし」も「橋」や「端」、「箸」があるように、ひらがなでは発音の区別ができません。その点、ベトナム語は書かれている文字をそのまま読むことができます。
難波 今はもう使わなくなりましたが、ベトナムでも昔、漢字が使われていましたよね。グェンさんも漢字を学んでいると思いますが、かつてベトナムで使われていた漢字がわかるといったことはありますか?
グェン 日本語の漢字の中にもベトナム語と似た発音のものがあります。漢字によってはそれを読むとベトナム語でその言葉が出てくることもあります。
ベトナムのソウルフード
グェン ベトナムの食文化は北と南で99パーセント違います。ハノイとホーチミン市だけでなく、中部のダナンも材料は似ていますが、料理としては他のものになります。同じ名前の料理もありません。もちろん、フォーやバインミー(ベトナム風サンドウィッチ)のように有名なものはどこでもありますが。
長島 南部のほうが甘い味付けだと聞いたことがありますが、いかがですか?
グェン そうですね。ホーチミン市のほうでは調味料として砂糖をよく使います。
難波 フォーの味も南と北で全然違いますよね。
グェン はい。フォーはたぶん南部のほうが甘いです。ホーチミン市のフォーは野菜と一緒に食べたりもします。ハノイは野菜を入れると言ってもネギくらい。
難波 お肉は入りますよね。
グェン はい、牛肉がメインです。鶏肉の店もありますが、牛肉で出すお店のほうが多いです。店ごとに作り方が決まっているのがベトナム料理の特徴かもしれません。牛肉のお店が鶏肉のフォーを出すことは滅多にありません。
難波 フォーと言えば、ハノイの名店フォーティンが池袋にオープンしました。おそらくハノイで一番有名な牛肉のフォーのお店ですよね。
グェン そうですね。フォーティンの特徴は牛肉を炒めるところです。フォーの肉は茹でるのが普通で、炒めるのは珍しいです。
長島 グェンさんはバインミーもよく食べていたのですか?
グェン よく食べていました。バインミーはベトナム人のファストフードですから。皆、朝の出勤途中にバイクで屋台に乗りつけてささっと買って行きます。100円とか150円くらい。私は家のそばに店を出しているおばさんからよく買っていました。私の母が売っていたこともあります。
長島 そうなんですね。
グェン でも、朝3時に起きて支度をしないといけないのが大変だと言っていました。今は別の仕事をしています。
長島 バインミーはいろいろな種類がありますよね。卵とかパテとか、好きな具材をコレとコレと言ってその場で挟んでもらうのが楽しいです。お願いすればアレンジもしてくれるし、どれも美味しい。
難波 そうですね。私はフランスに留学中、フランスパンを食べ飽きて見たくもないほどだったので、最初はどうしてベトナムに来てまでフランスパンを食べなきゃいけないのかと思っていましたが、ベトナムのパンは美味しいです。
長島 バインミーのパンはフランスパンのようで、嚙んでみるとサクサクして柔らかい。バインミーのパンは、このためにつくられるものなのでしょうか。
グェン そうです。フランスパンに似ていますが、具材を挟みやすいように中が空洞になっています。
長島 なるほど!
難波 バインミーは今、日本人にも人気ですね。フランスパンでは硬すぎて、バインミー用のパンをつくるのがやっぱり大変なのだそうです。
ベトナムグルメ自慢
難波 お米はどうですか? 第2次世界大戦の時に、フランスではベトナムから動員された人たちにカマルグという地帯でお米をつくらせていました。稲作大国のベトナムにとってお米づくりはお手のものだったと思いますが、彼らの多くは戦争が終わってベトナムに帰り、フランスに残った一部の人たちも今はお米をつくっていません。
長島 フランスでもお米のニーズがあったのでしょうか。
難波 19世紀末からつくっていたようですが、良いお米ができず、すっかり廃れていたようです。そこにベトナム人を連れてきてつくらせたところ、ちゃんとしたお米ができ、それをきっかけに稲作地帯は復活したと言います。今では美味しいカマルグ米という高級米がつくられています。
グェン 日本のお米がもちもちして食べやすいのとは対照的に、ベトナムのお米は細長くてドライなのでチャーハンに適しています。ベトナムではお茶漬けのように、スープをかけて食べるのがポピュラーです。でも日本ではふつうごはんとスープは別々に食べますよね。
難波 ベトナムは麺類も美味しいですね。私はハノイでチャーカーにハマり、しょっちゅう食べていました。あれは日本では食べられません。
長島 たしかに見かけないですね。
難波 ハノイの名物ですよね。ターメリック和えにした魚のぶつ切りをディルなどの香草やネギとともに多めの油で炒める。それをニョクマム(魚醤)と麺で食べるのがものすごく美味しくて、私も日本に帰ってから自分で試したりもしました。チャーカーに使う魚は川魚ですか?
長島 雷魚だと思います。チャーカーは私も大好きです。
私はハノイの東にあるハイフォンという港町の名物バインダークアにハマりました。フォーに似ているのですが、サトウキビを混ぜてある茶色い平打ち麺を、カニの出汁が効いたスープでいただくのです。日本風に言うとカニのラーメンみたいな。さつま揚げみたいな具がのっていて、脂っこくなくさっぱりしている。それがすごく美味しかった。
難波 バインダークアも日本には入ってきていないですよね。
長島 そうですね。
グェン ベトナムの麺料理は本当にいろいろな種類があります。
長島 ご当地ビールもたくさんありますよね。私はいろいろな土地で飲みましたが、それぞれ特色があっておもしろいです。ハノイのほうは寒い季節があるせいか、やはり味が濃く、それに比べてホーチミン市の333(バーバーバー)などは薄味です。
難波 中南部のダラットでつくられるダラットワインも、とても美味しくなりました。
長島 そうそう。私も最近初めて飲んで美味しいと感じました。昔はそうではなかったのですか?
難波 全然美味しくなかった(笑)。ですが、この20年でベトナムのワインの質は飛躍的に上がりました。
ベトナムの家庭の味
長島 グェンさんにとって故郷の味というのは何ですか?
グェン ハノイにいた頃は、スペアリブの甘酸っぱい煮物をよく食べていました。ベトナムにも日本の豚の角煮と似た料理がありますが、味付けにニョクマムを使います。醤油とニョクマムのように、日本とベトナムは調味料も似ていますね。
長島 ニョクマムは北でも南でも料理に使うのですか?
グェン そうですね。醤油のように、いろいろなものにつけて食べます。
ベトナムの食文化と言うと、野菜をたくさん食べます。種類が豊富でどれも安く、茹でた野菜を大きな皿に盛って皆で食べます。
魚もベトナムは川魚。日本は海のものが多いと思いますが、とくにハノイは海が遠いこともあって川魚のほうが安く手に入ります。
難波 中華料理の影響はあるのでしょうか? 中国の影響下にあった時代も長かったと思うのですが。
グェン 中華料理の影響は少ないように思います。それよりもフランスやタイのほうが近いはず。中国の料理は調味料を多く使いますが、ベトナムはそこまでじゃない。日本と同じように材料の新鮮さを生かして食べます。シンプルですが、ハーブなどの香菜をたくさん使います。
難波 確かにベトナム料理はハーブの使い方が巧みですね。
グェン ハーブは味も色も種類が豊富です。市場に行けば、たくさん売っていてスーパーよりも安くて美味しい。鶏肉も市場で売られているニワトリは所謂フリーレンジ(放し飼い)なので歯ごたえが良いです。
市場の良いところは安心して買えることです。私の母は市場で働いている知り合いが多く、食材のクオリティも信頼できるものばかりです。
長島 グェンさんのお宅では、大体家でごはんを食べていたのですか? それとも屋台?
グェン 普段は家で食べていました。もちろん屋台で食べることもあります。屋台は安いので1人暮らしの人に人気です。
難波 屋台は本当に安くて美味しいですよね。私はいろいろなお総菜が並んでいる屋台が好きです。
グェン コムビンザンですね。
難波 そう。ハノイにいた時には自炊をほとんどせず、コムビンザンでいろいろなものを食べていました。ビンザンは「平民」といった意味なので、日本で言う「大衆食堂」といった意味ですね。
長島 私もコムビンザンはよく利用しました。バインミーのように、コレとコレと指さしてご飯と一緒に盛ってもらうのが楽しかったです。
交通事情とライドシェアの普及
難波 ところで最近、行くたびに物価高を感じませんか。この20年の間に物価がとても上がっているのに驚きました。私が初めてベトナムに行った時の一番大きなお金の単位は5万ドンでしたが、今は50万ドン(約3,000円)になっている。給与水準も上がっているのだと思いますが、10倍は驚きです。
長島 最近ハノイもクルマが増えました。かと言ってバイクも減ってはいないので、街の中はすごい渋滞です。ベトナムの財閥企業のビングループが自動車の生産・販売を始めたので、ベトナムの人たちも乗りやすくなったとは聞いていたのですが、これにともない信号も整備され始め、バイクもクルマもちゃんと止まるようになった。そういう変化が良くもあるようで、寂しくもあります。
難波 そうすると、最近は横断歩道を渡るのが命がけではなくなってきたんですね(笑)。
長島 そうです。でも中心から少し離れたエリアでは昔ながらの感じが残っています。やはり左右を見ながらバイクの間を縫うように渡るのがハノイで生きていくための第1関門ですよね(笑)。
私は街中の移動に路線バスやバイクタクシーを利用していました。とくにバイクタクシーは普通のタクシーよりも開放感があるのでよく使っていました。
難波 ハノイで印象的だったのは、路線バスで席を譲られたこと。私、まだそんな歳じゃないのにと戸惑いました。乗客には若い学生さんが多いので、相対的な問題だよねと思い直し、今ではありがたく譲ってもらっています(笑)。
長島 私も譲られたことがあります。若い人たちは皆、とてもスマートに譲ってくれますよね。
難波 私はコロナ前から普及していたGrabタクシー(ライドシェアタクシー)を使うことも多かったのですが、長島さんは使ったことがありますか?
長島 ライドシェアアプリのGrabは便利ですよね。私もよくGrabでバイクタクシーを利用しました。
グェン 日本のタクシーはあまり変わっていませんが、ベトナムのモビリティはどんどん変わっています。Grabが普及するまでは、近所のおじさんなどに頼んで行きたい場所まで連れて行ってもらっていました。最近はGrabのようなアプリだけでなく、ビングループからエンジン音の小さな電動バイクが発売されたりもしています。
難波 Grabのドライバーの人たちもすごくいい車に乗っていたり、何だかもう日本と逆転しつつある感じです。私の学生時代はまだ経済水準の差が大きく、ベトナムの人とごはんを食べても日本人がごちそうする感覚でしたが、今は逆。現地でたくさんごちそうしてもらいました。ベトナムって同年代の人と食事する時でも、皆、おごる文化がありますよね。
グェン そうですね。
難波 割り勘みたいにけちけちしない。そういう時に沈みゆく日本と発展するベトナムの対比を感じます(笑)。
長島 ベトナムは活気があって、私も行くたびに日本との違いを感じつつ、いつも元気をもらいます。
難波 グェンさんは日本にいて悲しくなりませんか?(笑)
グェン そんなことはありません(笑)。ですが、ベトナム人と比べて日本の人とは仲良くなりにくいと感じます。日本の人はあまりプライベートな話をしないので。
難波 その点は違いますね。ベトナムの人たちは個人的なことをすぐに訊いてきます。結婚しているのか、子どもはいるのか、何歳なのか、収入はいくらかと。
長島 踏み込んできますね(笑)。
難波 そう、いきなりそれ訊きますかという感じ(笑)。
グェン もちろん、プライベートなことを訊きすぎるのはよくありませんが、それによって仲良くなりやすいところもあります。
難波 なるほど。こういう話題をきっかけにいろいろと話が広がっていくのですね。
ベトナム名所案内
長島 どうしてもハノイとホーチミン市の話が中心になりますが、北部にはサパという山岳地帯があり、この地域の棚田はとてもきれいです。サパには山岳民族の人たちが多く暮らしていて、少し違う文化圏という感じがしました。ベトナムにはいろいろな民族の方がいますよね。人口の1割ぐらいをとても多様な人たちが占めています。その人たちは民族によって衣装が違えば、織物も違う。サパはとてもいいところでした。
グェン ホーチミン市とハノイ以外で最も都会なのは中部のダナンです。東ベトナム海(南シナ海)に面して人口はあまり多くなく、バイクが少ないので安全です。最近は日本のIT企業や工場が増えていて直行便も出ています。ダナンに旅行する日本人も多いと思いますが、ベトナム人にとっても人気の都市です。
ベトナム人の観光客が多いのはニャチャンや世界遺産があるホイアン。日本ではフエの遺跡も人気ですが、暑くて雨が多いので旅行で出かけても大体1、2日です。
難波 私は最近、コンダオに行きました。ここはもともと流刑地だった島で植民地時代はフランス語でプロコンドールと呼ばれていました。そこにかつてのコンダオ刑務所跡が残っています。
グェン ダオは「島」を意味します。日本ではコンダオ島とも呼ばれます。
難波 最近観光地化されていると聞いたので、それは行かねばと。島には素敵なホテルができていましたが、多くの人たちが殺された歴史があります。島は風が強く、波も荒い。とてもじゃないけど逃げられません。ここを囚人島にしたのはそれなりの理由があったんだと思いました。
この島はインドシナ戦争でフランスに抵抗して19歳で殺されたヴォー・ティ・サウのお墓があるんです。ヴォー・ティ・サウはベトナムのジャンヌ・ダルクとも呼ばれる女性で、ベトナムの人たちが今もお参りに行きます。お墓にはいつも花が供えられており、ベトナムの歴史にとってとても重要なところだと思います。
国外で学ぶ人たち
難波 今はグェンさんのように、日本に来てビジネスを経験した後、帰って起業するような人が年々増えていると思うのですが、グェンさんもいずれはそういう事業を考えておられるのでしょうか。
グェン そういう人もいますけど、私の周りには留学先の国で働きたいと思っている人がたくさんいます。私もまだ帰りたくないです。
難波 それはなぜですか?
グェン 日本語を勉強しながら旅行するといろいろな新しい発見があって楽しい。日本は交通機関も発達していてとても便利に生活できます。ベトナムではいろいろなところに出かけたくとも移動が不便です。
難波 そうかもしれませんね。フランス統治時代につくられた鉄道を使えば南北を行き来できますが、ハノイ~ホーチミン市間の移動にはとても時間がかかります。必要に迫られて移動する場合は大抵飛行機でしょう。そういう事情もあって皆すぐには帰らないのですね。
グェン 帰る人たちの中には2つのタイプがあると思います。1つは家族と暮らしたい人。ベトナム人に何が一番大事かと尋ねると、ほとんどの人は家族と答えます。皆家族と一緒に暮らしたいと思っています。
もう1つはビジネスをやりたい人。たしかに現在、ベトナムではビジネスチャンスがたくさんあります。若い人も多く、スタートアップは日本よりもベトナムのほうがしやすいでしょうね。
難波 でもベトナムもこれから少子高齢化がものすごい勢いで進むことでしょうね。ベトナム政府は二人っ子政策を打ち出していましたが、これも緩和されました。
グェン そうですね。でも今も多くの家庭で子どもは2人です。ベトナムでは子どもをつくりたくないと言うと家族から強く反対されます。日本でもそういうことはありますか?
難波 家族によると思いますが、日本もそういうことは多かれ少なかれあると思います。でもベトナムほどではありません。ベトナムはやはり家族をとても大切にしますね。
グェン ベトナムでは家族との時間やワークライフバランスをよく考えます。夕方6時になれば皆仕事を終えて帰ります。日本では6時を過ぎても上司が残っていたら帰りにくいでしょう? ベトナム人はそういうことをあまり気にしません。
難波 良いことだと思いますよ。日本も次第にそういう考え方に変わりつつあります。
ベトナムの歴史とこれから
長島 ベトナムは東南アジアの国ではありますが、私が感じるのはタイのような底抜けの明るさがないことです。むしろ少し落ち着きがあり、日本の“わびさび”に近い。どこか深みがあるところに魅力を感じます。
難波 歴史的な背景があるからかもしれませんが、私は、ベトナムの人たちは逞しいと感じます。彼らがかつての植民地時代をどう認識しているのかがすごく気になるのでいろいろな人に尋ねるのですが、まったく頓着する様子がありません。フランス人のことも大好きで、私が滞在した2018年にはちょうどサッカーのワールドカップでフランスが優勝したのですが、皆たいへんな喜びようでした。あれほど大変なことを経験しながらも前を向いているのはすごいと感じます。
ところで、これからのベトナムはどのように変わっていくと思いますか? 2023年は日本とベトナムの国交樹立から50年という節目の年でしたが、今やものすごい勢いで経済成長が進んでいます。それが次第に落ち着くと、物質的な豊かさ以外のことにも目が向けられるようになると思うのです。そうした時に、フランスや米国、中国といった大国と戦争し、ことごとく勝ってきた人たちがどのように成熟していくのか、私はとても興味があります。
今は、かつての戦争のことは置いておいて経済発展にまい進していますが、いずれやはり過去に目を向けることになると思うのです。ベトナムの人たちがそれにどう向き合うかというのが、10年後、20年後に向けた私の関心です。
グェン 2、3年前は、カフェを始めるうえで一番重要なことと言えば立地だったのですが、今はサービスやコーヒーの質が重視されるようになりました。移動手段もアプリが便利になり、電動バイクの品質も上がっています。私はこうしたサービスや技術がこれからどのように発展していくか楽しみです。
難波 今はとにかくエネルギッシュに前を向く時代を突き進んでいるわけですね。過去のことはどうでしょう? 例えば、グェンさんは戦争の話をおじいさんやおばあさんに聞くことはありますか?
グェン 戦争で犠牲になった方々に関する番組は、お正月によく放送される内容の1つになっていますが、戦争のことを祖父母と話す機会はあまりありません。
難波 それはなぜですか。戦争を経験された世代ですよね。
グェン 戦時中は食べ物がなくて苦しんだから食べ物を大事にしなさいといったことは言われます。ですが、それ以上のことは話しません。
難波 それはあまりにも重い経験だからなのでしょうか。
グェン そうだと思います。
難波 あまりお話になりたくないのでしょうね。でも、その時代を生きた経験をグェンさんたちには聞いておいてほしいと思います。ベトナムの人たちはあまり政治の話をしませんが、グェンさんのように海外で教育を受けた人たちが10年後や20年後に戻った時、ご自身の国のことを考える時がくるのではないかなと思うのです。
長島 私も同感です。ベトナムは平均年齢が若く、さらに若い世代を中心にスマートフォンなどのツールが普及しており、さまざまな情報に自らアクセスできる状況になっています。「経済成長」「国の発展」と聞くと、日本の高度経済成長期が思い浮かびますが、手元に情報ツールがあるという意味では、それとは違った発展のかたちを遂げるのではないでしょうか。
若さに加えて、情報ツールを兼ね備えた世代が、今後どのような方向に国を発展させていくのか。その時に、グェンさんのようなエネルギッシュな若い世代がこれまでのベトナムをどのように考えるのか。国の発展とともにとても興味深く思います。
(2024年1月18日、三田キャンパスにて収録)
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。