【特集:新春対談】新春対談:「慶應義塾の目的」へと向かうために
三田評論ONLINEより
-
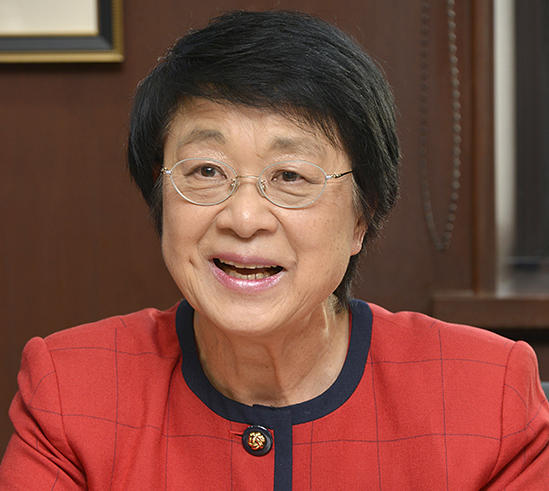
向井 千秋(むかい ちあき)
1952年生まれ。東京理科大学特任副学長、慶應義塾理事・評議員。JAXA特別参与。77年、慶應義塾大学医学部卒業。心臓血管外科医として慶應義塾大学医学部外科学教室に勤務。85年、宇宙飛行士に選定される。94年、スペースシャトル「コロンビア号」にアジア人初の女性宇宙飛行士として搭乗。98年、スペースシャトル「ディスカバリー号」に搭乗し、2度目の宇宙飛行を経験。
-

伊藤 公平(いとう こうへい)
1965年生まれ。1989年慶應義塾大学理工学部計測工学科卒業。94年カリフォルニア大学バークレー校工学部Ph.D取得。助手、専任講師、助教授を経て2007年慶應義塾大学理工学部教授。17年~19年同理工学部長・理工学研究科委員長。日本学術会議会員。2021年5月慶應義塾長に就任。専門は固体物理、量子コンピュータ等。
女子高から慶應で学んで
伊藤 明けましておめでとうございます。本年の新春対談は宇宙飛行士の向井千秋さんをお迎えしています。
向井 明けましておめでとうございます。今日は有り難うございます。大変光栄です。
伊藤 向井さんに昨年行っていただいた2022年度学部卒業式の来賓祝辞が実に素晴らしく感動的でした。今日は、そのスピーチの内容を起点として、さらに挑戦することの大切さや地球環境問題、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(DE&I)に関することなどを議論していきたいと思います。
向井さんの祝辞は人間味と温かみに溢れながらも、持続可能で建設的な地球環境と人間社会をつくっていくために、前向きな挑戦の大切さを卒業生の胸に刻んでくださいました。まず、向井さんの塾生時代について伺いたいと思います。どのような女子高生、医学部生でいらっしゃいましたか。
向井 私は群馬県の館林出身なのですが、当時、私が通った中学校も小学校も田舎の学校でしたので、慶應女子高に来て最初に思ったのは、同級生の人たちはすごく洗練されている、やはり都会の人たちなんだなということでした。ちょっと後ずさりするくらい色彩が違うという感じがしました。
伊藤 数ある東京の高校の中で、慶應女子高を選ばれた理由は何かあったのですか。
向井 当時、私は慶應義塾の精神とかを深く知っていたわけではないのですが、慶應を卒業したいとこがいまして、慶應義塾というのは自由で素晴らしい、というようなことを言っていたんですね。ただ、当初は、都立高校から国立の医学部に行こうと思っていました。決して裕福な家ではなかったので、私立の医学部はお金がかかると思っていたからです。しかし、当時、慶應の医学部は文学部や工学部(現理工学部)の費用とほぼ同じで、実習費等が足されているだけで、決して今の私大医学部のようにお金がかかるものではなかったのです。
中学3年生、14歳で故郷を離れて出てきたわけです。国立は東大を狙っていたのですが、東大はストになったり、当時、入りたかった日比谷高校もストをしていました。それで、慶應は医学部もあるし、一貫教育だし、ストで不安定なこともないので、慶應のほうがよいと思ったのですね。
伊藤 向井さんが慶應に来てくださったのはストのおかげだったのですね(笑)。女子高で出会った友人たちの印象はいかがでしたか?
向井 洗練されていましたね。私が慶應女子高で一番気に入っていたのは、女子高なのにいわゆる子女教育というものをまったくしなかったところです。女子高だから女子らしくという教育ではなく、本当に皆が伸び伸びしている。中等部から来た人、幼稚舎から上がってきた人たちも、とてもクリエイティビティが高い。いわゆる受験勉強で疲れてしまっているところがまったくないんです。
さらに、私がすごくいいなと思っているのは、受験校ではないので、例えば日本史の授業にしても、先生方がいい意味で自由なカリキュラムで、自由な時間の使い方をされていて、ご自分が面白いと思ったところに時間をかけられているのですね。そういうところが表面的にカリキュラムをすべて終える教育より、よかったと思いました。
伊藤 女子高では、クラブ活動はされていたのですか。
向井 スキー同好会みたいなものをやっていました。それと家庭科同好会だったのですが、食べ歩き同好会のような自由な雰囲気がありました。あとは生物学研究会を日吉の高校と一緒にやっていました。
伊藤 館林でスキーをされていたので、スキーは相当得意でいらっしゃったのですね。
向井 はい、5歳くらいからスキーをやっていました。後に、医学部の大会で、それほどのレベルではありませんが、東日本の個人戦で優勝もしました。
伊藤 女子高時代の勉強はいかがでしたか。
向井 理系科目は大好きだったのですが、やはり国語や歴史が苦手でした。また、今でも思い出すのは、女子高にはリトミックという、すごく特殊なものがありまして(笑)。私は体育が大好きで成績もよかったのですが、あれはメチャメチャ苦手でした。
伊藤 なるほど。でも、その中で食べ歩きとかも楽しまれながら過ごされたと。
向井 そうですね。友達も非常に先進的で、自分のことは自分で決めるようなところがありました。ファッションも、自分がどう見られているというより、「どう見せたいか」という意識が強い。だから、人のこともリスペクトするけど自分が流されない、いい意味の独立自尊の精神が女子高にはすごくありました。
自由に伸び伸びと出てきた枝葉を、盆栽のように切り取ったりしないで、伸びたい枝は伸ばしなさい、という教育だったと思います。
自由の重みを感じた医学部時代
伊藤 医学部の学生時代はいかがでしたか。
向井 スキー部でスキーしかやっていないという感じでしたね(笑)。当時の医学部は出欠もとらないし、実習は別として、基本的なことができていればあとは自由という感じでした。だから、いつも前の席にいる成績優秀な人からノートを借りて、それを夜行列車の中で必死に書き写して試験を受けていました(笑)。
伊藤 でもそういう医学部時代だったから、逆に伸びることができて、宇宙飛行士としてヒューストンに行けたようなところもあるのではないですか。
向井 そうですね。そこも慶應の独立自尊で、自分のリスクのもとに自分を磨きなさいというところがありました。だから、上から「これをやったら受かりますよ」と言われなくても、慶應は国家試験の合格率が高いんですよね。
伊藤 体育会では仲間と力を合わせて問題を乗り越える力が養われることもありますよね。
向井 そうですね。だから、チームワークがいい。大体年50日くらい山にいたので、他の大学の人との連携も強くなり、知識だけではなく人間力のようなものがつきます。医学部にしても女子高にしても、慶應の教育方針はいろいろな意味で自由でしたが、自由って逆に厳しいじゃないですか。「自由にしなさい」というのは自分を自制しなければいけないわけですから。
伊藤 そうですね。自由に伴う責任がありますね。
向井 慶應はそれがすごくあったような気がします。
伊藤 スキー以外で医学部時代で特に思い出に残ることはありますか。
向井 もう1つは解剖の実習でしょうか。3年で信濃町に来て初めに出合うのが解剖学です。そこでご遺体を解剖させていただき、様々な勉強をしていくのですが、ショックを受けて泣き出したり、数年に1人くらいは、「自分には向かない」と辞めたりします。
私はご遺体を解剖させていただいて思ったことは、草花でも何でも、生きているもの、命があるものは美しいんだな、ということです。そこで美しさに関する自分の感覚、考えが変わってきたのです。特に顔の解剖で顔の皮を剝いでしまったご遺体が並んでいるのを見ると、生きている時は美男子や美女であっても、皆同じに見えたのです。それを見た時に、「美しさというのは何なのだろう」とすごく悩みました。結局は、誰であっても、生きて、目を輝かせて、何かをしていれば、それで美しいのではないかと。
伊藤 内面から出てくるものということでしょうか。
向井 ええ。何かの物語で読んだのですが、昔のエジプトとかで、王様も王女様も皆同じような洋服を着せられ、奴隷となってしまった。しかし、プリンセスだった人は、どんな洋服を着ていても内面から出る美しさがあって、それは敵国の人にもわかるという話でした。付けていた宝石を奪われても、学問や、自分の内面の中で築いてきたその人らしさは、絶対に人が取ることはできない。解剖実習以降、人から取られない、自分のものが大事なんだと思えるようになりました。逆に表面的な美しさにあまり価値を感じなくなってしまったところがあります。
医師になるという選択
伊藤 向井さんは、祝辞の中で、病気で苦しんでいる人の役に立ちたいという思いで医師になられながらも、病院で人生の最期を迎える方、病院で生まれて外の世界を知らずに命を終える子どもたち、そして、ご自分と同世代の方々が夢を果たす途中で亡くなられることに触れられて、運命の理不尽さに心の底から悩まれた、とおっしゃいました。
さらに、「つらく、苦しく、どちらに進めばいいか選択すらできず悩むこともあります。そんなとき進路の選択に悩むことすら許されず、この世を去っていった人たちがいることを思い出します。もし自分が夢の実現に邁進することを選択できるのなら、その選択を許されなかった人たちのためにも、失敗を恐れずに、夢に向かって新たな世界に挑戦し続けるべきです。自分の選択で人生を歩んでいけることの有難さを多くの患者さんから学びました」と続けられましたが、私はこの向井さんのフレーズを伺い、感動で身震いが止まりませんでした。
向井 有り難うございます。
伊藤 「人生は一度きり」と誰もが知りながらも、夢の実現に向けた進路の選択になると二の足を踏む時があります。私もそうですが、ほとんどの人が向井さんを初めて知ったのは宇宙飛行士として成功されてからです。そして、「あれほどのことができる向井さんはもともと自分たちとは違う人間なのではないか」と思ったのではないでしょうか。
向井さんは「自分の選択で人生を歩んでいける」ともおっしゃっていました。「希望に胸を膨らませて苦難を乗り越えて歩んでいくと、その先に続く新たな道のりが見えてくるものです」と。つまり、1つ1つを着実に、諦めずに進んでいくと希望に続く新たな道が見えてくるとおっしゃっています。ここで私が感じたのは、向井さんという方は、希望をもって、小さな努力を1つ1つ積み重ねながら一歩一歩進んで来られた方で、何か近道をして、誰もが尊敬するような存在になられたのではないのだということです。
向井 私は決して自分ができる人間ではなく、常に悩みがありました。小学4年生で医者を目指した時も、「自分よりも勉強ができる人はたくさんいるけど、たぶん医者になって患者さんを助けたいという、その1つの思いだけは絶対負けない」という思いがありました。勉強も、普通の人がすぐできることだったら、私は3倍時間をかければ必ずできるだろう、という思いでいつもやっていました。
よく「私、能力がないから」と諦めてしまう人たちがいますが、それはやってみなければわからないと思うのです。確かに私はモーツァルトのような天才ではない。でもモーツァルトだってずいぶん苦労をしていると思うんです。エジソンだって「天才とは1パーセントのひらめきと99パーセントの努力」という言葉を残しています。だから、どんなに能力のある人でも、ものすごい努力をしているはずなんですよね。
そう考えると、初めから諦めずに、自分がそこに行ける可能性があるのならば「行こう」と思うことが大事です。ただ、そこに行けなかった人もたくさんいます。本当に行きたかったのに、亡くなってしまったりした人を私はたまたま見ていたので、行けると思うなら10年やればできると思ってやってきました。
いつも思うのですが、知識や技術であれば、高校を卒業して6年間勉強したら医者になれるんですよね。だから、やりたいことがあれば、できないと思わずにやったらいいのではないか、と思うのです。
伊藤 小学4年生から、常にお医者さまになりたいという気持ちは変わらずにいたのですか。
向井 そうですね。私はすごく夢が多くて、映画を見て「こういう生き方がしたいな」と思うと、1週間くらいはその人生を夢見ていました(笑)。よく友達には「最近、どういう人生をやってるの?」と言われていました。パティシエにもなりたかったし、オリンピックでスキーの大会にも出たかったんですが、それらの思いは1週間くらいで消えてしまう。でも、弟が足が悪くて、病気で苦しんでいる人が横にいたということもあり、医者になりたいという思いだけは、1週間たっても消えなかったのです。だから、夢がいろいろあった中で、かなえられたのは医者と宇宙飛行士だけ、と言っています(笑)。
また、私はすごく運が良かったとも思います。自分が水たまりでもがいていても、真剣にもがいていると、人間は1人で生きているわけではないので、周りにその真剣さを見てくれている人たちもいるのです。そうすると、「こっちから出たほうがいいんじゃない?」と手を差し延べてくれたり、後ろから押してくれたりする。いい加減にやっていると人は助けてくれませんが、必死でやっていれば周りから見るとわかるし、やはり助けたくなるんですよね。そういう人たちにすごく助けられてきたと思います。
地球の健康を守る立場へ
伊藤 病気で苦しんでいる人の役に立ちたい、だから医者になりたいという夢から、今度は「宇宙から故郷の地球を見たい」という夢になったとおっしゃっていましたね。この夢の転換は斬新で、私はこの話を伺いながら、大きなジャンプのように感じたのです。
向井さんはこのようにもおっしゃいました。「飛行士の仲間たち誰もが宇宙からいとおしく見つめているのは故郷です。私も宇宙から地球、日本、群馬県の館林を見つめ、そこに住む父や母、きょうだい、友人、そして、郷土の美しさを思い出したものです」。「私たちの故郷地球は、われわれが考えているほど大きくはありません。そして多くの宇宙飛行士たちが『宇宙から見ると国境が見えない』と語るように、われわれの生息する地球環境は『One Earth One Health』として捉えられています。地球生命圈は強靱ではなく、地球資源も有限です」。
私はその時、向井さんは人間の健康を守る立場から、地球の健康を守る立場にご自分を発展させたのではないかと感じたのです。結果的に地球環境の健康を守る立場に移っていかれたのかなと。
向井 そうですね。私が初めて地球のことが人間のように見えたのはカリフォルニアを飛行機で飛んでいる時でした。砂漠の光景を上から見た時、砂漠の中に青いものが生えている部分が人間の皮膚病みたいに見えたんですね。そのとき初めて、「地球というのはやはり人間と一緒に生きているんだな」と思いました。そして、実際に宇宙から地球を見ると、本当に地球が息づいているような感じがありました。
2回の宇宙飛行をベースにして、その後、人工衛星を使って宇宙医学関係の研究を始めました。WHOなどでも人工衛星を使って地球自身を見ると、例えばPM2・5のような大気汚染や、あるいは雨季などでベジテーション(植生)が多い時、そこはマラリアの発生率が高くなるのがわかるのです。また、汚れている水を飲んでしまうとポリオなどになってしまいますが、どこの水が汚れているのか、人工衛星を使うと、雨が山のどちら側に流れるかでわかるんですよね。
地球の健康管理という意味では、宇宙の非常に広く高い視野と、センサーを上手く使うことで人間の目では見えないものが見えてくるのです。
伊藤 なるほど、そうなのですね。宇宙でのミッションは何年と何年に行かれたのでしたか。
向井 1994年と1998年の2回です。ただ、短期ミッションですから2週間と10日です。今の宇宙ステーションのような6カ月とはちょっと違います。
伊藤 1回目と2回目では違いましたか。
向井 やはり2回目のほうが要領は良くなりました。私は絶対2回目も行きたかったんです。その最大の理由は、宇宙飛行士というものを職業として確立させたいと思ったからです。通常、開発途上国の飛行士だと、1回飛んで、その後は広報活動をして終わってしまう。宇宙開発も続かない。でも日本は、1期生からずっと続いているので、職業としてのカテゴリーをつくりたかった。
また、重力のない宇宙に長くいて、地球に帰って来てすぐプレスカンファレンスをやった時、記者から渡された名刺に「重さ」をとても感じたのです。今まで自分の能力の中に隠されていたものが出たみたいな思いがしました。宇宙を飛んだら、こんな紙1枚がズシッとなるような感覚が自分の中にあったことが面白かったのです。人間というのは、地球環境に戻ってくると、重さをだんだん感じなくなり、3日くらいで元に戻るんです。するともう2日目の夜には人魚姫みたいな感じで、「明日の朝になったら、この感覚を失ってしまうかもしれない」とすごく寂しくて(笑)。
だから、2回目の飛行の時に一番期待していたのは、自分の体をまたそういう重力のない環境に慣らして、地球に来た時にズシリと重い、あの感覚をもう1回体験したいと思いました。
NASAでDE&Iを実践する
伊藤 それはもう体験してみないとわかりませんね。
そして、宇宙飛行士の訓練も含め、DE&Iについてもずいぶん祝辞の中で言及してくださいました。宇宙飛行士として訓練を始められた1958年に男女雇用機会均等法が制定され、翌年に施行された。すなわち、日本で女性の社会進出が始動した時期と重なったとおっしゃいました。その時はまだDE&Iというコンセプトはなかったですね。
でも向井さんは、女性として日本人宇宙飛行士の第1期生になることに戸惑いはなかった。なぜかというと、医師として働き始めた時から、女性だから、男性だからという考え方はもうすでになくなっていた。その考え方が、グローバルで多様化している集団の中で非常に役に立った、とおっしゃいました。年齢、性別、教育、民族、国籍、宗教などのサブグループで自分の可能性を限定すべきではない。しかし、その一方で、DE&Iは、その概念は理解できても実行が難しいとも語られました。
そこで卒業生たちに対して、「あまり難しく考えずに、人はそれぞれの顔が違うように考え方も違うのは当たり前だというところから始めてみよう。そうすれば、違う意見を聞いてもストレスを感じることはなく、建設的な議論をすることができるのではないか」と呼び掛けられました。このようなお考えに至ったNASAでのご経験と、また今の日本の状況をご覧になって、思われることはいかがですか。
向井 DE&Iというのは今、企業や大学など様々なところで言われています。これは私の印象では言うは易しく、実行するのは難しいことです。また、女性にガラスの天井があると言われますが、もともと多様化した世界の中に入っていく側、自らが繭、垣根をつくっていることもあるわけです。「私は日本人だから」とか、「私は女性だから」とか、「何々だから」と自分を閉じ込めてしまっていることがある。
男女だとか、宗教などを含めて、垣根というのは意外と自分でつくってしまっている場合があります。そのことがわからないと、もうそこから出られず、いつまでたっても井の中の蛙になってしまいます。
私はヒューストンに行った時、「日本人だからできない」とは決して言わせないと思いました。私はこのポジションで飛行するとNASAから任命されているのだから、私が女性であれ男性であれ、地上では背が小さく届かないことがあっても、宇宙では届く。フィジカルなことも含めて、このポジションを務められると思われてやっている。だから、もしそれができないのであれば、それは自分が訓練をしていないからで、日本人だからできないわけではない、と常に言っていました。だから、「自分で垣根をつくらないほうがいいですよ」と言いたかったのです。
人それぞれ顔が違うのだから、皆が同じ考え方だと思わないで、もともとバラバラなのだというところから始めればいいと思うのです。皆考えが同じだと思うから、少しの違いにストレスを感じてしまう。でも「全部違う」と思って始めたら、同じであることを見つけるとそれを慈しむことができる。その上で違うところを見つけたら、「ラッキー。そこから自分は学べる」と思ったほうがいい。同質のものからは学べないですから。そうやって自分を広げて違うものを見つけて「そういう考え方もあるんだ」と思えれば、それは結局、自分の肥やしになるわけです。NASAではそのようにやっていました。
欧米の人は自分の価値観で動きますよね。マジョリティーがこう思っているから仲間外れになってしまうという心配などせず、「誰が何を思おうとも私はこう思う」という人が割と多い。だから、いい意味で個人主義的で、そして相手を個人としてリスペクトしますね。
伊藤 そうですね。マサチューセッツ工科大学(MIT)を卒業したある女子学生を研究室に迎えたことがあるのですが、その人は剣道が好きで、剣道を究めたいと体育会に入ったのです。
彼女はその後、筑波大学で剣道の専門分野で修士号を取り、しばらく屋久島でネイチャーガイドをしながら、剣道も楽しんでいたのですが、やはり物理の研究に戻りたいといって、30代後半くらいで、物理に戻りました。なかなか日本人では考えられない経歴ですよね。MITを出たら、日本だとそのままエリートコースだろうと思ってしまいますが、好きなことを1つ1つやっていって、やはり物理に戻っていく。その自由さですね。
向井 そうですね。自由さと、やはり自分はまた戻れるという自信もあるのでしょうね。
チームの中に共通項を探す
伊藤 DE&Iについて、向井さんは、マイノリティーとマジョリティーがいるとすれば、まずはマイノリティーの立場でお話をされたと思うのですが、マジョリティー側にもやはり同じようなことが言えるわけですよね。
向井 はい。マイノリティーのほうが、マジョリティーの集団に入っていく際に自分の存在価値とユニークネスを探していく面があります。一方、逆にマジョリティー側が、自分はマジョリティーではなかったと気付く時があるんです。
NASAの例で言うと、1990年代の後半、ロシアが宇宙ステーションに入ってきて一緒に活動することになり、アメリカの飛行士がロシアの「ソユーズ」で飛ぶことになった。彼らNASA精鋭と言われる人たちがロシアのシステムで、ロシア語を使わなければならなくなったんです。彼らは帰って来て、「チアキたちは日本語が母国語なのに英語でこれだけやっていることのすごさがわかった」と言いました。
それで私も、「今ごろやっとわかった?」と言ったんです(笑)。マジョリティーと同じようにやっていくマイノリティーの人たちの努力が、そのようにして認められることもあります。
伊藤 ある意味、マジョリティーの人たちこそ、マイノリティーの立場を経験する機会をつくることがよいということでしょうか。
向井 そうですね。また、マイノリティーが常にマイノリティーのままとも限らない。例えばヒスパニックの人を何人採るとか、マイノリティーのほうのポジションを上げようという時代もありました。
伊藤 アファーマティブ・アクションですね。
向井 マジョリティーの天下は必ずしも続くわけではなくて、しっぺ返しがくることもあるわけです。だから、世の中の流れで自分がマジョリティー側にいることに気が付くと、アンコンシャス・バイアスがあることに気が付くし、マイノリティーはマイノリティーの中で自分がユニークネスを出さなければいけないとわかるのではないでしょうか。
伊藤 そういったことは、今後日本社会で、小学校から、どうやって教育に反映していくのがよいでしょうね。「女の子だから」とか、「男の子だから」とか、そもそも性自認がどうなのか、人によって違うような世の中にだんだんとなってきていますね。
向井 そうですね。ここはなかなか難しいと思うのですが、私は要するに公約数でいいのだと思います。公約数というのは、数値がバラバラな中で、一番の共通の数値を見つけるわけじゃないですか。その数値さえ見つかればバラバラの顔がまとまると教えていく。それが基本合意だと思うんですよね。
だから、チームの中で多様な人がいた時に、その中の公約数は何か。最大公約数もあれば、何か小さいものでも共通項を探していくのがよいのかと思います。
共通の目的を達成するためのDE&I
伊藤 そういう意味では、「共通の目的を達成するためのDE&I」ということが、キーワードになると思いました。向井さんが祝辞の中で、「様々な意見を持つ人たちが団結できるのは共通の目的を達成させたいという思いを持つからです」と言及されました。そして、次のように続けられています。
「個々の利益ではなく、チームやグループの目的遂行のために多様化した人たちがまとまると、多様化している困難に立ち向かえる強靱なチームになります。そして、お互いの違いから学び、お互いが共有することを慈しむことで、地球のどこに住んでいようと人は皆同じであることが共感できる。また、議論に行き詰まった時に、自分が帰属するグループを1つの大きなものに置き換え、ズームアウトして、いつもの立ち位置より大所高所の観点から問題を捉えると、より客観的な解決を探していくことができます」。
実は今の塾生たちも、多くが向井さんと同じ考えを持っているのだと思っています。何か1つの共通の目的を持ち、そこで皆と一緒に取り組みたい。その中に多様性が必要だということです。DE&Iと聞くと年配の世代は、「義務で、やらなければいけないこと」と捉える人もいますが、塾生たちにとってDE&Iというのはもう切実な希望だと思うんですね。
向井 Z世代では当たり前になっていますよね。
伊藤 そうなんです。そういう意味では比較的世代による分断もあるような気がします。今の塾生たちにとってはDE&Iというのは当たり前で、他人からやらなければいけないと言われるものではないわけです。
向井 今のZ世代というのは、自分らしく生きていくという意味で、肩の力が抜けているのではないかと思います。だから、もしかすると年配の方は、「力、抜きすぎじゃない?」と思うのかもしれません。でも今、ウクライナもガザの問題も、世界がすごく分断されていて、国連などが機能していない状況になっている。結局、国のエゴでやっているからです。もう1つ大きなスーパー国連みたいなものをつくり、職員も無国籍の人で、地球のことを考えるような組織をつくらない限り、機能しないのではないかとさえ思います。
今の若い人も、自分の所属というものを、もっと広い意味で考えないと、この多様化する世界の中、やっていけないと思っているのではないでしょうか。われわれの年代よりも若い年代のほうが、いわゆるボーダーだとか、年齢、国籍といったものを外して考えられる人たちが多いのではないかと思っているんです。
伊藤 特に少し上の世代で「オールジャパンで」という言葉を使われる方がいますが、そういった考え方はだんだんなくなっていきますよね。
地球を守るために何をしていくか
伊藤 その中で、現在、慶應義塾の大学や一貫教育校、病院で、DE&Iとして取り組むべきことは何だとお考えでしょうか。
向井 慶應は、そういう点は塾長はじめ皆さんとても先進的だから、DE&Iというのは言うは易しくやるのは難しいということさえわかっていれば、あとはやり方なのだと思います。
「人類共通の目的」ということで私が考えていたのは、個人の1つの顔、個々の1つのデータポイントというのは全部、光らせて最大効果を出す、つまり少ないリソースで最大成果を出していくということです。1+1は数学的にはやはり2になってしまう。でも、2と3を足した時には5だけど、掛けたら6になるわけです。そういう形で個々を光らせたら、力は3倍にも4倍にもなる。そういうやり方がわかれば、チームで目的を持ってやることの意義がわかり、結局、手を組んだほうが自分の得になるんですよね。
伊藤 どうしても人間社会は好き嫌いで事が進んでいったり、ちょっとした目先の利益や既得権を守りたくて進まない時もありますが、結局は皆で力を合わせることが皆のためになるということですね。
向井 そうだと思います。ウクライナの戦争にしても、これが長い目で見た時に、得になるのかどうなのか私にはよくわからないのです。ああいった破壊的な行為よりも、皆で何か共有する、分かち合う、自分で独占しないということが大切なのではないか。共有するということについては、シェアハウスとか、カーシェアリングなど、若い人のほうが普段の生活に取り入れているのではないかと期待しているんです。
伊藤 明らかにそうだと思いますね。
向井 だから、若い人たちがスーパー国連をつくってくれると、国籍もパスポートも要らない世界に近づいてくる。そうしないと地球って思っているほど大きくないし、温暖化もものすごい速度で進んできている。危機的な状況になってしまうことを心配しています。
伊藤 結果的におそらく国境とか国家安全保障という考え方が邪魔になっているのですよね。安全ということはそれぞれの国で大切ですが、つまるところ地球が大切です。そこに国境があると、様々な利権が絡み、周りの国に対して強権的になる。その単位が国や民族で、それが極端な方向まで行くと、地球の資源が限られている中で厳しくなるのは明らかですよね。
向井 ロングタームで見れば、結局、自分がだめになりますからね。なかなか難しいと思うのですが、ヒューマニタリアン的な話を含めて、やはり人の尊厳はリスペクトすることが大切です。
また、これからの時代はテクノロジーを使えるようになることが大事ですが、今の生成AIなどは、その情報が正しいとは限らないわけです。すると、本人が正しく判断できるような能力、何でも狂信的に信じないという判断能力が大事になりますね。
伊藤 そうですね。鵜呑みにせずに、人間がAIの上に行く学びを続けなければいけないということですね。
「慶應義塾の目的」と独立自尊
伊藤 今のような話は、向井さんは祝辞の後半でされていました。
「気候変動に誘発される自然災害の増加や新型コロナウイルスのパンデミック感染、そして分断・孤立、格差社会における都市構造や人間社会の脆弱化など、現代の社会課題は単一ではなく複合的です。人類全体で協力して解決すべき課題が多々あります。環境を探査し、問題点に気づき、その解決策を他分野の人たちと協力して社会実装をさせていくために、総合的な人間力やリーダーシップが必要な時代に私たちは生きているのです。そして、それぞれの人の命が輝き、尊厳ある社会を構築していくうえで一番大切なことは、人類愛、ヒューマニティと思います。自分を大切に思うなら隣人を大切にする。幸せな人たちに囲まれた自分も幸せな立場にあるのですから。明日を思い今を生きることで、建設的で活力ある持続可能な社会を構築していこうではありませんか」。
このように卒業生に語られる向井さんを、私は本当に尊敬の眼差しで拝見していました。同時に、「慶應義塾の目的」の末尾の、「居家、処世、立国の本旨を明にして、之を口に言うのみにあらず、躬行実践、以て全社会の先導者たらんことを欲するものなり」をそこに重ねて話を伺っていました。
今日、私たちは具体的に何に取り組むべきなのか。「慶應義塾の目的」を上手に現代版に言い換えていただいたような言葉だと思いました。「慶應義塾の目的」に私が重ねたことをどうお感じになりますか。
向井 非常に深く洞察されたと思います。私は簡単に言ってしまっただけですが、やはりそういう思いはありました。慶應の卒業生たちはそういうところは脈々と受け継いで来ているのではないでしょうか。
伊藤 そうですね。ただ、先ほど私が引用した向井さんの言葉の最後の部分と、「慶應義塾の目的」にもある、人類を愛する、隣人を大切にするという考えは結構キリスト教的なことでもあるのです。今度、私は上智大学の聖イグナチオ教会から講演を頼まれているのですが、上智には「他者のために、他者とともに」という標語があり、われわれには「独立自尊」がある。
独立自尊は、自分の夢を追って、皆で力を合わせて前向きに進んでいこうというところがある。でもキリスト教は「無償の愛」とか「無償の奉仕」とか、隣人を助けましょうと言っている。このバランスが非常に求められるということですね。
向井 そうですね。だけど、自分が強くなければ人を助けられないじゃないですか。水の中から人を引き上げようと思っても、筋力がなかったら沈んでしまう。そういう意味では、慶應の「独立自尊」で、やはり個々の人を光らせ、個々を鍛える。そういう人が自分のことだけではなく、その周りを助けるという順番ではないでしょうか。
伊藤 それが「独立自尊」なんですよね。自分を大切にして、他人を大切にする。
向井 上から目線で助けるというのではなく、そうすることによって、自分の生きている範囲が広がっていく。別に見返りを考えているわけではなく、そのことがひいては、自分の生きている場所が幸せな人に囲まれ、自分の幸せにつながる。自分だけが幸せで隣の人が嘆いたりしていたら、やはり一緒に騒げないですよね。
おいしいものを1人で全部食べるよりも、隣の人とそれを食べたほうがおいしいねって言える。物理的なものだけではなく、一緒に語り合えるほうがいい。それこそ「人はパンのみにあらず」です。私はあまり考えずに地で行ってしまっているというだけですが。
伊藤 でも、とてもいろいろな考えを引き出してくださるスピーチでした。
向井 こんなに細かく分析していただき、本当に感謝感激です。
宇宙で聴いた「若き血」
伊藤 向井さんもお気付きになったと思いますが、卒業式の記念館の檀上からは、1人1人の顔がよく見え、皆が本当に輝いているなと思ったのですが、向井さんの祝辞の時の表情は別格で、皆さんの全てのエネルギーが向井さんに吸い込まれているようでした。でも、その中で、祝辞の最後のところで向井さんがおっしゃったことで、急に会場中が爆発したようになった言葉がありました。
「宇宙で仕事場に向かう時、いつも慶應義塾の応援歌である『若き血』を聴き、仕事へのエネルギーを充電したものです。故郷は物理的にも精神的にも心のよりどころです。夢に向かって邁進する時、そして、人生の困難に遭遇にして途方に暮れた時、母校慶應義塾に入学した時の気持ちを、そして本日の卒業式の晴れやかな気持ちと自信を思い出してください。母校は私たちの心の原点、故郷の1つなのです」。
宇宙でお聴きになった「若き血」と、地上でお聴きになる「若き血」に何か違いはありましたでしょうか。
向井 地上だと、皆と一緒に「若き血」を歌っているという連帯感があるわけですが、宇宙だとやはり1人で「頑張るぞ」と自分を鼓舞するものです。
ものすごくすてきな応援歌です。宇宙では当時はカセットで毎日それを聴いて「行くぞ!」ってやっていました(笑)。
伊藤 「若き血」の「行くぞ!」というところ、特にお好きな歌詞はどの部分でしょうか。
向井 やはり「若き血に燃ゆる者」という、あの出だしのところ。もうそれを聴いただけで「よしッ、今日は燃えちゃうぞ」って(笑)。単純ですから。
伊藤 「見よ精鋭の集う処」で、宇宙船の中の「精鋭」を意識したわけではなくて、もう「若き血」のところで、「慶應スピリットで行くぞ」と。
向井 そうです。やはり慶應をバックにしている「私の精鋭」みたいな感じでした。タイトルの「若き血」も、いくら歳を取っても、「あのころ、血が熱くなるようなことがあったよな」と思い出すじゃないですか。だから、「若き血に燃ゆる者、はい、私です!」みたいな(笑)。もう初めのところで高揚していきました。
やはり戦いに出るには「若き血」の赤がいい(笑)。戦いに出て行くとか、新しい時代をつくっていくとか、何か困難に立ち向かう時はこの「若き血」がぴったりですね。
伊藤 「若き血」はすごい歌ですよね。慶應では塾長賞というのがあるのですが、それは光輝に満ちた人たちに渡されます。それが塾長賞の1つの要件で、その考え方が「光輝みてる我等」という、「若き血」の2行目の歌詞に出てくるわけですね。
驚くべき人間のクリエイティビティ
向井 宇宙で私が気に入って聴いたもう1つの曲が「ふるさと」なんです。
伊藤 「兎追いしかの山」ですね。
向井 あの歌詞の1番はふるさとのことで、2番は父母の話でしょう。自分が宇宙飛行に行く前に聴いてちょっと涙が出たのは、「こころざしをはたして いつの日にか帰らん」という3番です。
ふるさとというのはやはり遠くにあって思うものです。もしかしたら宇宙船が爆発して帰れないかもしれないなとも思う。遠くなればなるほど、「なんていいところから私は来たのだろう」と慈しみの心が出るじゃないですか。あの「ふるさと」は、宇宙時代になっても通用する歌だと思うんですよね。「山はあおき故郷 水は清き故郷」。本当にその通りで、あのブループラネットの山がいつまでも青く、水が清くいてほしいなと思いながら聴いていました。
また、私が驚いたのは人間のクリエイティビティのすごさです。宇宙飛行から学んだ最大のものは「ニュートンはすごいな」ということでした。地球から出たことがないのに「万有引力」を考え出した。ニュートンは目に見えるりんごを見ていたわけではなく、地球と小さなりんごが同等に引き合っているという、インビジブルなものを捉えてその定理を考えました。
天才と言われるニュートンは宇宙に行かなくても万有引力がわかってしまう。それはやはり人間のクリエイティビティのすごさだと思うのです。
そういうことが肌身で感じ取れた。私は宇宙に行って視野を広げなかったら、きっと教科書で読んだ「万有引力」の本当のすごさはわからなかったと思っています。
伊藤 私も物理学者ですが、質量がエネルギーであり、「万有引力」があることを先代が見出してきたのですから、これはすごいことですね。
最終的に「重力」はまだ理解できていません。「万有引力」という法則はありますが、いわゆる「大統一理論」という、重力をどうやって電磁力と合わせこむかということがまだできていない。だから、物理学者はその「大統一理論」を目指して、統一的な世界の物理学の体系をつくりたいのですが、重力というのはどういう力が働いているのか人間の直感ではすごく理解しにくいのですね。
皆で達成する自己実現の場をつくる
伊藤 2024年を迎えてということで私から申し上げると、今日のお話を伺い、向井さんは「慶應義塾の目的」を本当に体現されている方なのだと確信しました。
向井さんのような方が1人でも多く出て、自由に、でも皆のために一緒になってこの社会、そして地球の今後を担っていくような塾生が学んでいく場をつくっていこうと、今日の対談を通じてより責任を感じたところです。慶應義塾には、それに取り組む優秀で、信頼できる仲間がたくさん揃っています。
皆と1つの目的を持つことが慶應義塾の目的なのですが、皆が多様にバラバラの方向に進みながらも、お互いに助け合いながら、結果的にその目的を達するような方向に向かうようにしたい。
例えば、全く違う方向に行く2人がいるかもしれない。その2人だけだと引っ張り合ってしまい、どちらにも進まないのですが、そういう人たちがたくさんいるのであれば、集団として結果的に皆で正しい方向に進んでいくようにしたい。それが慶應義塾のやり方ですので、そのような慶應義塾をつくっていきたいと思っています。
向井さんには評議員のみならず、理事としても慶應義塾の様々な経営運営に参画していただいています。塾生のためにも、研究のためにも、今後とも引き続きいろいろとお知恵をいただきたいと思います。
向井 私は慶應義塾を卒業させていただいて、本当に有り難いと思っています。女子高の頃から独立自尊や福澤先生の「天は人の上に人を造らず」のお話などを聞いてきましたが、このこと自体がダイバーシティだと思うのですよね。
そして、上から目線でものを見ない。かといって下から「自分はできないから」と卑下しない。やはり自分自身が輝いていける環境があれば、それを有り難いと思って、その中で自己実現をしていく気風があります。慶應義塾の教育を受け、それを実践していける場をいただいたという気がしています。慶應義塾のそういった精神はこれからもずっと続いていくのでしょう。
今の塾生が他人事ではなく、歴史の1つのデータポイントを自分がつくっていると思えば、100年後の人が見た時、もしかしたら自分がキャンパスで何かやっている1カットが慶應義塾の歴史になるかもしれない。そんなふうに「母校の中で歴史をつくっているのは自分なのだ」というくらいのつもりでやっていくと、毎日楽しくポジティブに生きていけるのではないかなと思います。そういう塾生の皆さまが育っていくことを期待しております。
伊藤 有り難うございました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。2023年1月号