【話題の人】山田悟:緩やかな糖質制限「ロカボ」で世の中を変える
三田評論ONLINEより

-
山田 悟(やまだ さとる)
北里大学北里研究所病院糖尿病センター長
塾員(1994医)。医学博士。「一般社団法人食・楽・健康協会」代表理事。2007年より現職。糖質制限の第一人者として活躍中。 -
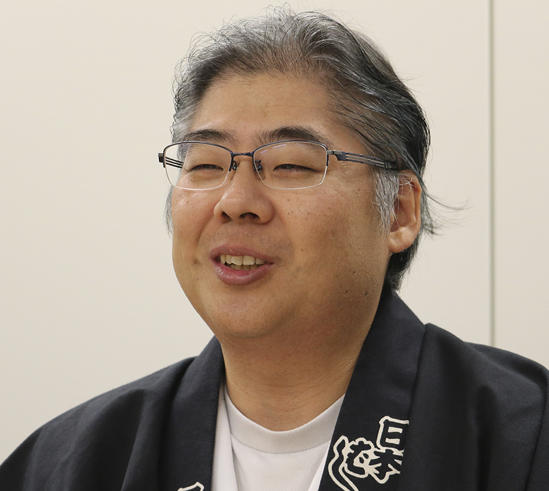
インタビュアー湧井 浩之(わくい ひろゆき)
うなぎ割烹「大江戸」取締役・塾員
「ロカボ」という食事療法
──糖尿病の専門医である山田君が「ロカボ」という糖質制限食を提唱されて話題になっています。このロカボとはどういうものですか。
山田 「ロカボ」というのはローカーボハイドレート(Low carbohydrate)を縮めたものです。カーボハイドレートとは炭水化物のことですが、炭水化物は糖質と食物繊維に分けられます。ただ、この「ローカーボハイドレート」という言葉は、アメリカなどでは極端な糖質制限も含む概念・呼称で、きつい食事制限を求めると、つらくて続けることができなくなってしまう。そこで、僕らは「緩やかな糖質制限」を「ロカボ」として広めているのです。
ロカボが効果を発揮する「メタボ」(メタボリックシンドローム)とか、筋肉や骨が衰えていく「ロコモ」(ロコモティブシンドローム)と同じように3文字で略すと馴染みやすいとも思いました。とにかく、糖質を緩やかに制限して、食生活を楽しむということを条件にしているのです。
──そうやって、糖尿病の方、もしくはその予備軍の方の食生活を改善していくということですね。
山田 はい。そもそも糖質制限は、糖質を控えるだけで、体重、血糖、血圧、高脂血症、といった、いわゆるメタボリックシンドロームの構成要素がすべてよくなるという食事療法なのです。
昔は食べ過ぎるから肥満になる、と思われていましたが、実はそうではなく、今ではエネルギーの取り過ぎは結果として起こるのであり、原因は糖質の取り過ぎだと分かっています。
糖質を過剰に取ると食後の高血糖が起こる。すると、それを抑えるために、遅れて大量のインスリンというホルモンが出てくる。そして脂肪細胞にエネルギーを放り込んで肥満をつくると同時に、急激な血糖の降下を生みます。
この急激な血糖の降下がすさまじい空腹感をつくるんです。そして、あらがいようのない食欲が出て食べ進んでしまう。だから食べ過ぎが起こって肥満が助長されるのです。肥満が起こると、内臓脂肪から血圧を上げやすくする物質も出て、そこから出てきた脂が高脂血症をつくることにもなる。
──そういう意味で糖質制限が重要なのですね。
山田 そうです。食後の高血糖を抑制すれば、メタボの構成要素をすべて抑制できる。食後の高血糖をつくる要素は糖質だけなので、それを控えることでメタボをやっつけられることが分かってきました。
なぜ「緩やか」でなければいけないかというと、極端にやったほうが治療効果が大きいように思えても、現実には、続けられなくなり、リバウンドしてしまうからです。
僕たちは、1食につき糖質を20グラム以上、40グラム以下にしてそれを3食、それとは別に1日に10グラムの嗜好品までをOKとし、食事を楽しみましょうという、緩やかな糖質制限「ロカボ」を提唱しているのです。
──ロカボというのは、ダイエットなんでしょうか。
山田 太っている人にとってはダイエットです。しかし、日本人には痩せていて糖尿病の人もいるので、その人にとっては体重を落とすことが目的ではなく、あくまでも血糖値の是正が目的になります。こういう人は筋肉を付けながら血糖を管理することが必要で、ロカボはそれが可能なのです。
──健康になるための食生活が、ロカボの目的なのですね。糖尿病の方は日本でどのくらいの数がいるのでしょう。
山田 糖尿病患者の方が1千万人、その予備軍が1千万人と言われていますが、実はこれは空腹時採血でしか見ていない。本来、日本人など黄色人種は食後の血糖値が上がりやすいのでそれを調べるべきなんですね。そうすると私は4千万人程度の血糖値異常の方がいるのではないかと思っています。
ですからロカボという食生活は、30代になったら全員が行ったほうがいいと僕は思っています。
カロリー制限神話を打破する
──こういった食生活の改善を普及させているのですね。
山田 2013年に「一般社団法人食・楽・健康協会」という団体をつくり、ファミレス、コンビニをはじめ、いろいろな企業に、楽しくて続けたくなる健康な食生活のあり方を、地道にお伝えする活動を続けて6年たったところです。
──以前は「カロリー制限」という方法が主流だったと思います。これを糖質制限へ変えていかれた。これは大変ではありませんでしたか。
山田 実は、僕らもずっとカロリー制限食は正しいものだと信じて、患者さんにずっと指導してきたけれど、実は本当に意味がないんですね。
今のカロリー制限食は、現在ガイドラインに載っている内容でも、もっと厳しい場合でも、体重を増やしてしまったという研究が報告されています。
だから、カロリー制限神話をなんとか打破したかったのです。結局、1日おなかを空かせて我慢して、自分はやれている気になっても、ある日に、今日くらいは、とおなかいっぱい食べてしまうので、最終的には同じエネルギー摂取量になりかねないのです。
──カロリー制限は、食べる量を抑える、量の規制ですが、糖質制限は、糖質さえ取らなければ量は食べていいのですね。私も実際にやってみましたが、明らかに糖質制限のほうがストレスフリーで長く続けられますね。
山田 僕も昔、今より体重が10キロぐらい重いときがあり、カロリー制限をやって、ものの見事にリバウンドしました。糖質制限に出会ってからは、日々満腹になるまで食べても、ちゃんと学生時代の体重にとどまっています。
──でも、糖質制限がまったくストレスフリーかというと、日本人はご飯が大好きなので、それを我慢するのが一番ハードルが高いですね。
山田 おっしゃる通りです。だからこそ食・楽・健康協会の企業さまに、低糖質のパン、麺、スイーツなどの開発をしていただいています。低糖質でふっくら、もっちりしたお米ができれば一気に解決するのです。
そういう意味では、今回湧井君が、「日本橋ロカボ祭」のために開発してくださった、「サーモンとアボカドのオリーブオイル丼」は素晴らしいですね。少し糖質を抑えたお米を使い、サーモンとアボカドの脂やタンパクで糖質を抑えながら、上手くマスキングしていただいた。
日本の米の文化を享受しながら糖質制限できると、これは絶対輸出産業になるはずなのです。
日本橋からの発信
──昨日、今日(10月28、9日)とやっている「日本橋ロカボ祭」は今年が2年目ですね。
山田 湧井君をはじめ日本橋の飲食店の皆さま方のお力添えをいただいています。1つのお店だけではなく、日本橋という日本の文化の源のような地域全体でやっていただけているのは本当にうれしいことです。
──糖質を下げることと、おいしいものをどうやって両立させるのかは結構悩んだところです。最初に話を聞いたときは、「そんなのできないよ」と思いました。
山田 先ほどの「サーモンとアボカドのオリーブオイル丼」をはじめ、皆さまに素晴らしい食事を作っていただいています。私が日本橋の料理人の方たちにお願いしたのは、ひたすらおいしいロカボ食を出していただきたいということです。お客さまだって、おいしくて不健康なものと、おいしくて健康なものだったら、やはり健康なものを選ぶはずですから。
日本橋料理飲食業組合の組合長の「舟寿し」の二永さん、「繁乃鮨」さん、和食の「ゆかり」さんなど日本橋を代表する有名な老舗の方に入っていただきました。さらに「にんべん」さんと、「榮太樓總本舗」さんにもご協力いただき、去年から日本橋からロカボを発信しよう、と「日本橋ロカボ祭」を始めたんですね。
──実はこのきっかけは、3年前の「中等部同窓会の日」の幹事年だったことなんですよね。そこで同期の山田君にロカボの講演をしてもらい、その考え方に則した料理を僕が作ることになったんです。やはり日本橋で健康になれると思ってほしい。日本人がマインドチェンジをするきっかけになればと思います。
山田 有り難い限りです。福澤先生は実学を重視されましたが、論文や研究は理論でしかないので、それが初めて日本橋の料理人の方たちの力や企業さんのお力を借りて、形になることは実学そのものだと思うんですよね。
実は北里柴三郎先生も「叡智と実践」ということを言われている。叡智に支えられてない実践はいずれ廃れてしまう。だけど、実践できないような叡智は価値がない。理論と、現実世界の食がお互いを高め合う関係になれば、ロカボは世の中に広められると確信しています。
やはりまだまだ「健康によい食事=おいしくない食事」「伝統に反するような考え方」という見方がある。その中で、日本橋で和の伝統をしっかり守りながら、おいしいロカボがあれば、世界に広がっていくと思っています。
──サッカーの長友佑都さんの食事のアドバイザーをされていると聞いています。スポーツとロカボも、やはり密接な関係にあるということですか。
山田 昔は、糖質を食べていないと筋肉内のグリコーゲンという栄養源が足りなくなってしまうと考えられ、僕らも学生時代はそう教わっていました。しかし、実はエネルギーさえしっかり取っていれば、糖質を制限していてもグリコーゲンの貯蓄はちゃんとできることが分かってきています。
3年ほど前、長友さんが、どうも自分は血糖値が乱高下すると運動パフォーマンスが落ちていると感じる、と雑誌に書いていました。それで、これは糖質制限が効くなと思って、出版社さんを通じてご連絡したら、関心を示してくださってお会いしました。
そして、実際にロカボを取り入れたら、足がつる頻度が減ったり、ケガからの回復が早くなった。体感としては、本当に調子がよくなり、また圧倒的に筋肉の質がよくなったということで、ロカボに傾倒してくださったんです。
──有名な方が支持してくれると、認知が広がりますよね。
山田 そうですね。病気の人が健康になるための食事というだけではなく、アスリートがパフォーマンスを向上させるためにロカボを取り入れているのが知られると、本当に広がっていくかなと思っています。
糖尿病に向きあう情熱
──山田君が糖尿病専門医を目指したきっかけはどういうものですか。
山田 医者になって3年目に、現在埼玉医科大学教授の島田朗先生から、「糖尿病の医者にとって最大の資質は情熱だよ」と言われました。
例えば循環器などの内科では、血管が全部詰まっていたら、どんなに医者が情熱を持っていても救えない。だけど糖尿病の人は、すさまじい高血糖であっても、こちらの情熱で、健康に関して正しい知識を持っていただいたら、患者さんの生活が変わり劇的によくなることがある。この話をされたときに、すごく感激し、糖尿病専門医を目指してみたいと思ったんです。
──糖尿病は人間の体にいろいろな影響を与えますね。
山田 循環器や腎臓の疾患は根っこは糖尿病や高脂血症、あるいは高血圧から来ることが多くて、これらは生活習慣をしっかりとコントロールできれば抑制できるはずなんです。一次予防と言いますが、そこで多くの人を助けられるんですね。
日本人の死因のうち、がんや心臓病、脳卒中、また肺炎も脳卒中の後遺症からきていることが多いので、3分の2はいわゆる生活習慣病が原因となっている。それらはロカボで救えるものだし、寝たきりだって、実は骨粗しょう症や骨折にも糖尿病は関係していますし、認知症にも大きく影響します。
──患者さんの生活習慣をどう変えるかは、大変な努力が必要なのではないですか。
山田 昔は、患者さんの行動変容をどうやって起こすかを考えていたのですが、最近考え方を変え、その人の食習慣を記録したものを見せていただき、どれだけ生活習慣をそのままにしながら糖質を抑えるかを提案しています。
ライフスタイルというのは、その人に一番都合がいいように出来上がっているので、それを変えられる人のほうが少ない。できる限り患者さんのライフスタイルそのままで、糖質を落とす提案をしていきたいと思っています。
そして、これまでだと「どう食事を我慢するか」だったのが、「じゃあ大江戸さんに行って食べてくださいよ」という一言。この生活習慣指導が一番楽なんですよ。塾員の患者さんは、「大江戸さんに行っていいんですか」とすごくお喜びになる(笑)。
──「そこに行って食べてもいいですよ」という店がたくさんあれば、選択肢が広がりますね。
北里研究所から世界へ
──北里研究所病院というのはどういうところなのですか。
山田 北里先生は1892年にベルリンのコッホ研究所から日本に戻ってきました。でも、東大出身でありながら、東大の先生方の脚気菌発見の論文を否定していたので職がなかった。
そのときに、長与専斎先生の依頼を受けた福澤先生が設立を助けたのが伝染病研究所で、北里先生はここの所長になるのです。翌1893年には、結核療養所の土筆ヶ岡養生園をつくるにあたり、北里先生のために福澤先生が自身の土地を提供しています。そして、私立伝染病研究所が国立になり、その後、北里先生がそこを辞めて土筆ヶ岡養生園のところにつくったのが北里研究所で、土筆ヶ岡養生園の後身にあたるのが北里研究所病院なんです。
そのように福澤先生と北里先生の絆は深く、1917年に慶應の医学部ができたときには、北里先生が医学部長になっています。北里研究所病院の医師は、今でも北里大学よりも慶應医学部出身者のほうが多いので、小さな慶應のような感覚で、しかも慶應よりも自由度が高いんです。
──なるほど。そうなんですね。
山田 先ほど「叡智と実践」についてお話ししましたが、北里先生が我々に遺した言葉は他に「開拓」「報恩」「不撓不屈」と3つあります。
私が科学的根拠に基づかないけれども常識になっている、カロリー制限食に反旗を掲げ、学会の重鎮が盲目的に批判してきた糖質制限食を当院に取り入れようとしたとき、北里研究所からは、それを「開拓」であるとして認めてもらえました。そして、私はカロリー制限食に反旗を掲げることこそが、学会の重鎮の方たちに対する「報恩」であると思っています。
剣道には「守」「破」「離」という考えがあると言います。師の教えを盲目的に「守」ることは初期に求められる姿勢で、一定のレベルに達したら、師の教えを「破」ることが必要で、最終的には師の教えから完全に「離」れて新たな型を自ら作り出します。
今、私は「破」の段階にあると考えていて、いずれ湧井君を中心とする日本橋の方たちとともに日本全体、そして世界に向かってこの緩やかな糖質制限を発信、啓蒙するときが「離」の段階だと思っています。私が糖質制限に正面から取り組めたのは、本当に北里研究所であったからこそだと思っています。
──ぜひとも日本を代表するロカボの提唱者として、今後の活躍を期待しています。
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。2019年