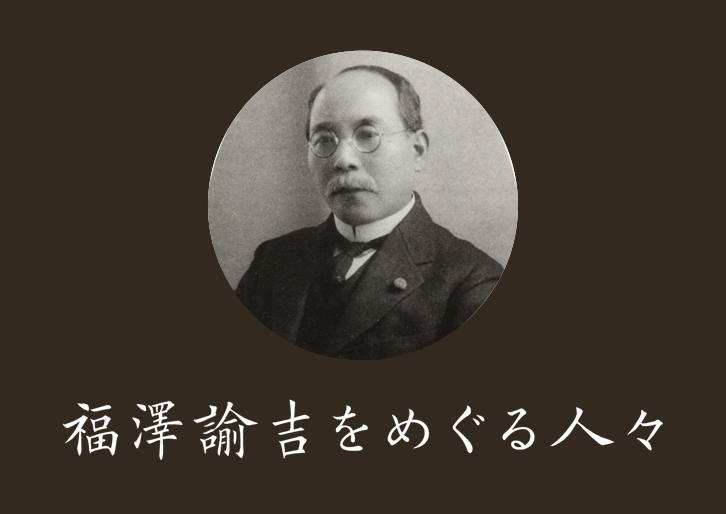福澤諭吉をめぐる人々;林 毅陸
-
小山 太輝(こやま たいき)
慶應義塾幼稚舎教諭
福澤の死後、義塾史上で最も長い25年の間、塾長を務めた、鎌田栄吉。戦前戦中の義塾を支えた塾長、小泉信三。そして、その間に挟まれ、大正から昭和にかけて10年間の義塾を塾長として支えたのが林毅陸(はやしきろく)である。関東大震災からの復興、日吉キャンパスへの学園拡張計画の発起など、その後の礎を着実に築き上げた。
学者としては、欧州外交史の嚆矢とも称される『欧州近世外交史』等の著者であり、高橋誠一郎が「慶應義塾の先生の中であれほどの雄弁家はおそらくあるまい」と語るほどの雄弁家であり、政界でもその力を発揮した「自由主義」者である。
少年・青年時代
林毅陸は、明治5(1872)年、長崎県東松浦郡田野村(現佐賀県唐津市)に中村清四郎の四男として生まれた。10歳の頃、フランス学の塾を開いていた兄に連れられ東京に出るが、その近くで漢学塾を開いていた林瀧三郎(竹堂)に見初められ、11歳の春、香川県高松へ同行し、7年間の訓育を受けることになった。竹堂の寵愛を受け、他の生徒と違い「学び且つ教える」という塾頭のような立場で学んだ。高松は自由民権論が活発だったこともあり、16、7歳の頃から、政治論に興味を覚え、時々それらの会合に出席、時には「生意気にも」演説会に登場していた。政治への興味はこの少年時代に大いに養われたという。
明治22(1889)年、福澤を崇拝する兄義三郎の助言、そして竹堂の賛同により、慶應義塾に入学した。当時、大学部開設計画が発表されていたことは「私学としては破天荒」であり大いに刺激になったと後に回顧している。なお、この時期に毅陸は、竹堂の養子になり、林姓となった。
『生い立ちの記』の中で林は、当時の義塾では、月2回課せられた日本作文が特徴的であったと挙げている。この出題は最高幹部が行っており、実社会の問題を取り上げることで、学生たちは、日々、「時事新報」をあたかも教科書の如く読み、生きた常識を養う習慣を身につけた。また、毎月2回開かれる三田演説会は、先輩や学生が入り混じり「実に塾の教育上の重要な機関となっていた」という。そこでの福澤の講話が「何よりも大切であった」 とも回顧している。
林は、25年に正科を卒業すると、23年に開設されていた大学部の文学科に進学した。当時の塾生は旧来の課程で十分と考える者が多かったので、同期の27人中、大学部に進んだのは林1人であったという。
教員時代
林は、明治28年に大学部文学科を首席で卒業すると義塾の教員となった。その頃、義塾では、大学部が不振な上に、旧来の課程と大学部の関係が複雑なままだったこともあり、林によれば、「学制改革と教務刷新とが若い教師連の間に盛んに論議せられ、私もその仲間の1人であった」という。1人で福澤を訪ね「大に種々の意見を開陳」することもあった。
結局、学制改革により、31年、幼稚舎6年、普通学科5年、大学科5年という、今日に至る計16年の一貫教育の体系が確立した (翌年には、普通学科は普通部に、大学科は大学部に名を改められた)。その改革の流れの中で草創期を支えた小幡篤次郎などの世代が 一線を離れ、鎌田栄吉を塾長とし、大学部出身の新しい世代が中心となる形で人事が刷新されることになった。各科の責任者として教務主任が置かれ、普通部主任に林毅陸が、大学部の法律学科、文学科、理財学科の主任には神戸寅次郎(かんべとらじろう)、川合貞一、気賀勘重(かんじゅう)が就任することになった。
林は後に、「僅かに27歳に達したばかりの私は主任である責任上、先達となって一切の進行を図るに努めた。如何にも生意気に見えたであろう」、「福澤先生が斯(か)かる若輩に主任の地位を与えられたのは、(略)年老いて後に回顧すれば、よくも先生が之を断行せられたものと深い感激を覚ゆる」と振り返っている。
この普通部主任時代の有名なエピソードに、1900年12月31日夜に三田山上で開かれた世紀送迎会における、「世紀送迎の辞」の朗読がある。この辞は、富田正文によれば「19世紀の政治、軍事、社会、文化の転変と輩出した人物を走馬灯の如く語り、青春の発情があふれ、新文明の選士たる義塾の意気を高唱した」非常な名文で、万場を酔わせたのであった。
また、福澤の思想を「独立自尊」に集約した「修身要領」が発表されたのも、この主任時代であった。復古調で儒教主義の「教育勅語」とは異なるものであったので、世間からは多くの批判を受けた。これに対し、林は「『修身要領』に対する井上哲次郎氏の批評を読む」を『慶應義塾学報』に発表した。「独立自尊」は人に従うという美徳を失わせるのではないかという井上の批判に対し、何よりも「先づ自己の独立自尊を認め」た上で、「自由意思の判断を持」って行動することこそが重要であり、「卑屈なる妄信と自由なる選択とを混同」してはいけないと説いている。
明治34年には普通部主任を離れ、慶應義塾の留学生として、ヨーロッパ外交史を学ぶためにパリの「エコール・リーブル・デ・シアンス・ポリチック」(今日のパリ政治学院)に派遣された。それまで大学部が外来講師に依存していたことから、義塾出身の大学部教員を育成しようとの趣旨ではじまったばかりの制度である。欧州留学は初め3年の予定であったが、後に慶應義塾から比較憲法をも研究科目に加えられた関係もあり、1年延長され、38年に帰国した。帰国後は、大学部政治学科教授となった。
代議士・塾長時代
林は、明治45年、衆議院議員になった。以降、塾長に就任する大正9(1920)年まで連続4回当選している。8年には、パリ講和会議参加、9年原内閣の外務省参事官、10〜11年全権に随行してワシントン会議に出席するなど政治にも深く関わった。
中でも山本権兵衛首相に対する質問演説は、藩閥政治から政党内閣時代への転換点にあるものとして日本の政治史上も意義が大きい。林は、山本に対し、陸海軍大臣の任用が現役将官に限られていることについて「憲政の運用に支障あり」と指摘するなど政党内閣としての限界を追及した。結果として軍部大臣の任用資格が拡げられる等、政界の空気は転換した。
林の議会初演説でもあったが、後に法学部教授の中村菊男は「大正政変と林毅陸」と題する論文で「明治憲法の枠内において政党内閣制を確立せんとするのがその意図である。(略)慶應義塾において自由主義的知性と教養を身につけた彼によって始めて可能なことであった。林をしてこのような決意をなさしめたものは彼の自由主義的教養であり、知性であったが、彼をして敢然立ってこの要求をなさしめたものは桂内閣弾劾のために立上った大衆の力であった」と評価している。
なお、この自由主義者的な思想は第2次世界大戦の時期も変わらなかった。林を慕う有志で行われていた「林会」では、いつもヒトラーを罵倒し、「ヒトラーの末路を見届けるまで死ねない」とまで言い放ち、「自由主義者としての節を曲げなかった」と星野靖之助は、追悼している。
大正12年11月、前年に文部大臣就任のため塾長を辞した鎌田栄吉に代わり、林が塾長となった。しかし、高橋誠一郎によれば、これには内部の不満もあったようで、一度門野幾之進、福澤一太郎を挟み意図的に冷却期間をおいてからの就任という形がとられるなどあまり気持ちの良くない就任劇であった。
林は就任演説で、福澤諭吉以来の義塾の教育方針である「学問の独立」「学問の実践」および「自由着実な学風」の3点を掲げた。さらに実務上では、三田山上の整理、商工学校の移転、研究室の整備、大学新学部増設、医学部の拡充、震災被害の復旧などの問題の解決に当たりたいと具体的に語った。事実、関東大震災で被った義塾内部の損害の復興のために義塾初の塾債の発行に踏み切り、慶應義塾といえば三田という固定観念の中で、日吉に新たなキャンパスを開設するなど大いに尽力した。
しかし、当時の評議員は活溌に意見したので気苦労は多く、また「両老(鎌田、門野)の間に挟まって、実に苦しい思いをした」と高橋に語ったという。昭和8(1933)年に塾長の任を退いたが、この時も「余りに生一本なのに嫌気がさした」「老先輩たち」からの圧力もあったことを高橋は記している。
毅陸の人物
最後に毅陸の人物について触れたい。まず、教師としては、講義のたびに、夜遅くまで研究し準備をするほど非常に熱心であった。講義はとても早口ながら「名調子」で「実に面白」かったと高橋は記している。一方で、学生の研究報告や試験答案に対してもあまりに几帳面で、細かく読みすぎるため、「学生の方が降参して怖れをなしていたくらい」(及川恒忠)であった。
このきめ細かな気質は、塾長になっても変わらなかったようで、例えば、義塾から差し出す大抵の書面は自分自身で書いていたばかりでなく、事務の係りが書いたものでも、必ず筆を加えたので、担当の職員はとても恐縮をしていたという。
また、後に幼稚舎長を務める吉田小五郎は、塾長が林に代わってから「春秋の遠足ごとにその予定表を塾長に出し、これは遠すぎる、もっと近い所にしろなんて、小うるさい干渉が出るようになりました」(『幼稚舎の歴史』)と記している。これは極端な記述ながら、小さなことに気が回る性格だったことがうかがえる。
塾長を辞任した後も林は、外交史の講義を続ける一方で、交詢社理事長、東亜同文会理事等を歴任した。また戦後は、枢密顧問官、そして初代愛知大学学長を務めた。この間、戦争末期には四国に疎開したが、そこで書き上げたのが、『欧州最近外交史』であり、小泉信三は「学者の老健」と讃えた。その出版から3年後の昭和25年、78歳で歿した。
毅陸は明治40年、『慶應義塾学報』の中で、「福澤先生の人となりを見るに、リベラルの一語は最も適当の評語である」とし、塾の「学風の形容はリベラルの一語最も適当である」と記した。そして、「固陋偏狭なる双思想の猶覚め終わらざる我国の社会に向て、新鮮爽颯なるリベラリズムの新空気を送るは、正に我党の天職である」と語った。その使命を生涯大切にした林は、今の社会を見て何を思うだろうか。
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。