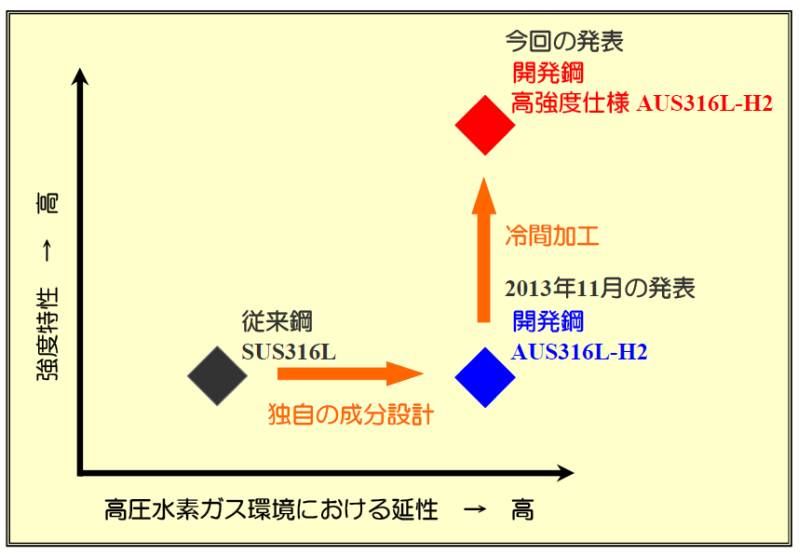Jetro 世界は今
↓
今回は日本の得意とする水素ビジネスについての特集です。思っていたよりビジネスが進行しているようにも見えます。
だた、お隣の中国が国を挙げて水素戦略を展開しています。
↓
○水素エネルギー中長期発展規画(2021~2035年)
----------------------- 抜粋します。
<現状と情勢>
中国は世界最大規模の水素製造国であり、水素製造量は年間約3,300万トン、工業用水素ガスの品質基準を満たす製造装置は約1,200万基に達している。再生可能エネルギーユニット容量は世界首位であり、グリーン水素(注1)の供給において潜在力を有している。
ただし、現段階は発展の初期段階であり、国際的な先進レベルと比較すると産業創造力は不十分で、基礎的制度も遅れている。一部地方政府の無秩序な追随により、レベルの低い建設動向が目立っており、トップレベルの設計と統一的な計画の強化が急がれる。
---------------------------
中国にしては謙遜しています。世界一であるにもかかわらず、まだまだという認識はなかなか言えないものです。(珍しく正直)今でも十分だと思います。
------------------------------ 抜粋します。
<発展目標>
2025年
水素エネルギー産業の発展のため制度と政策環境を整え、産業のイノベーション能力を向上させ、中核技術と製造能力を掌握して比較的整ったサプライチェーンと産業システムを構築。
燃料電池車両の保有台数を約5万台、水素充填(じゅうてん)ステーションを多数配置する。再生可能エネルギーによる水素製造量は年間10万~20万トンに達し、二酸化炭素排出を年間で100万~200万トン削減。
--------------------------------
「第14次5カ年計画」期間における産業イノベーション応用モデルプロジェクト
--------------------- 抜粋します。
交通:特定エリアにおける水素燃料電池トラックによる輸送、都市路線バスなど公共サービス分野における燃料電池車両の利用や、70メガパスカル(MPa)水素貯蔵ボンベ車両の応用検証の実施。
貯蔵:再生可能エネルギーの需要を考慮して貯蔵・水素充填一体化ステーションを配置し、水素エネルギーの分散型生産と現地利用を促進。
発電:水素と電力を融合させたマイクログリッドモデルを実施し、燃料電池のコージェネレーション供給の応用と実践を推進。
工業:化石燃料に代替した再生可能エネルギーによる水素製造モデルの構築を実施。
-----------------------
トヨタも中国には「水素自動車ミライ」を提供しています。
↓
70MPaという数値が出てくるのは当然でしょう。(日本のモデルをそのままパクってます。
------------------------- 抜粋します。
◎2020年7月 リンデ(Linde、ドイツ)
リンデは、国有企業の中国海洋石油集団(CNOOC)の子会社である中海油能源発展と覚書(MoU)を締結し、中国で水素エネルギー産業の共同開発を実施。
水素製造と充填施設へ投資し、産業およびモビリティー分野での水素使用を促進。
中海油能源発展
◎2021年9月 カミンズ(Cummins、米国)
カミンズと上海市臨港新区自由貿易試験区との間で投資協定を締結。
臨港新区に中国本社とR&Dセンターを配置。プロトン交換膜 (PEM) 燃料電池、電解水による水素製造装置スタック、燃料電池スタックの製造拠点を建設。
上海市臨港新区
◎2022年10月 バラードパワーシステムズ(Ballard power systems、カナダ)
上海市嘉定区人民政府と投資協定を締結。
今後3年間で約1億3,000 万ドルを投資し、新しい膜電極接合体(MEA)の生産設備とR&Dセンターを建設。建設した生産施設でMEAを約1,300万枚/年を生産能力、水素燃料エンジン600台の組み立て能力を確保。
上海市嘉定区
◎2023年1月 プラスチックオムニウム(PLASTIC OMNIUM、フランス)
商用自動車向けの高圧水素貯蔵システムの製造と販売を行う合弁会社を上海市嘉定区に設立。
2026年以降、年間で最大6万基の高圧水素容器が生産可能なプラントを稼働予定。
-------------------------------
既に各国と連携を取っています。
中国は日本の何倍もの規模で着々と水素戦略を実施してきます。明確な国家戦略と目標が定められています。お隣に日本という有能はイノベーターがいるので、日本の戦略をそまま規模を大きくして実施すれば世界を制する事ができます。
水素戦略については、過去にもブログで何度も触れています。日本国が主体となって進めて来たビジネスモデルですが、、既に中国に抜かれています。風力発電を見るまでもなく、中国がやり出したらとまりません。
基本、エネルギーは外交戦略です。技術だけで決まるものではありません。国による包括的な外交的政策実施を望みます。(国家間の枠組み作り。)国家がすることは外交努力であり外交交渉です。企業は技術開発で勝負します。国は、企業の努力を無駄にしないでください。(MRJの二の舞は御免被ります。)国家が主導で動かないと戦略はうまく機能しません。この辺りは、本来は官僚の仕事だと思います。企業に出来る事には限界があります。
↓
パイプラインの方が輸送コストが抜群に安くなります。
↓
<追記>
経済産業省の資料。(NEDO)
↓ 2023年4月
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/suiso_nenryo/pdf/031_06_00.pdf
---------------- 抜粋します。
--------------------------------
日本は国を挙げて、中国を終始一貫支援していきました。これからも、その姿勢に変わりはないでしょう。企業はその狭間で。。大変だと思います。