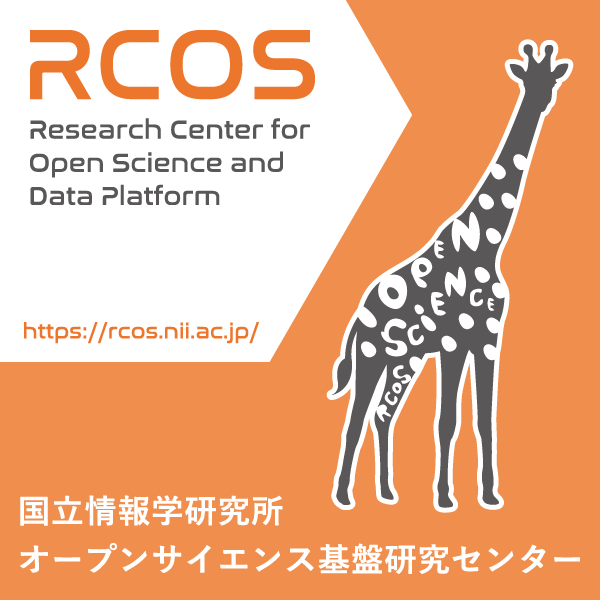Gigazine
↓
高額すぎる掲載料に対する抗議から学術委員会の全科学者が辞任したようです。
元ネタ。
The Guardian
↓
--------------------- 抜粋します。
辞任した科学者の1人でカーディフ大学のクリス・チェンバーズ教授は「エルゼビアは学術界を食いものにして、科学にほとんど価値を与えることなく、莫大な利益を要求しています」と述べ、他の科学者たちに、エルゼビアの学術誌を捨てて、チームが代わりに立ち上げた非営利でオープンアクセスの学術誌に論文を投稿するように呼びかけました。
エルゼビアは世界の科学論文のうち18%を発行し、2022年の収益は前年比10%増の29億ポンド(約4940億円)。利益率は40%に上り、この部分が科学者の反発を呼んでいます。
-----------------------------
とあります。
嫌われて当然でしょう。ネイチャーといい、エルゼビアといい昨今の論文誌の掲載料や雑誌の金額は異常です。
過去にも色々あるようです。欧米の学者は戦っています。論文誌の好きにはさせません。
↓
↓
2014年 「なぜエルゼビアはボイコットを受けるのか 」
↓
http://user.keio.ac.jp/~ueda/papers/sc2014.pdf
このあたりの事情は、以下の本に詳しいです。(学会誌の問題点が詳しく解説されています。)
↓
「学術出版の来た道」 有田正規
例えば、ネイチャー。(正確にはシュープリンガー・ネイチャー)日本の大学の図書館で購入すると、148万6000円(1年購読 2021年の値段)にもなります。(理工系の学部を持つ大学の運営に取っては厳しいものがあります。)個人で購入すると、5万6000円(1年購読 2021年)日本の科学者は昔から、この2大学会誌に弱い。欧米に比べてぼったくられています。(同じ学術誌でもサイエンスは良心的と言われています。)
最近の論文誌の流れはとても複雑です。(オープンデータベースの時代です。)エルゼビアは医学系の内容が多いので、医学界にも影響力がとても強いと思います。(新型コロナの時の論文が多数掲載されています。しかも参考になります。)
現状、論文誌は制御不能な状態に陥っているように見えます。商用化した科学と数値目標が一人歩きしています。(インパクトファクター信仰。もはや宗教です。)
↓
---------------- 抜粋します。
ただし近年は一部に、学術雑誌の購読料が高すぎる(年間5千ドルのものもある)という批判があり、2012年にはエルゼビア社の論文誌への投稿をボイコットする運動(学界の春)やSci-Hubなどのダウンロードサイトによる活動が起こっている。
----------------
有益な論文が多いだけにとても残念な事です。ネイチャー/エルゼビアという2大論文誌に抵抗するのは至難の業でしょう。それでも、科学者の不満は限界に来ているようです。歴史のある学会誌だけに今後の動向が気になります。一方日本では、日本発の世界的学会誌が育たない事が問題となっていると思われます。
いつまでも欧米の高額な学会誌を購入し続けることは日本の科学の発展には繋がらないと考えます。学科誌の歴史を調べると多くの矛盾点が見えてきます。(論文の数≠論文の質)論文は数が多ければいいわけではありません。日本の学識者の頑張りに期待するしかありません。