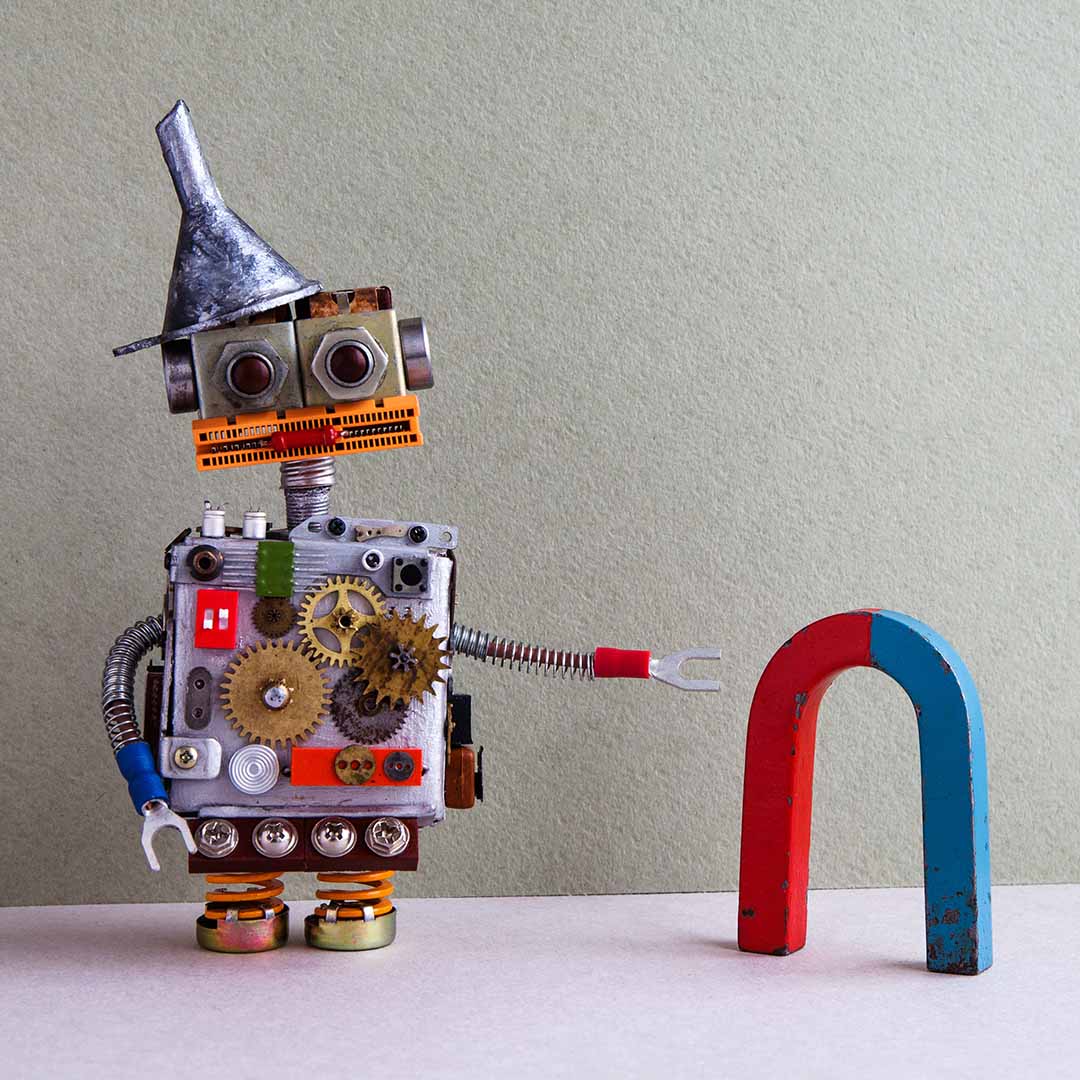なかなか厳しい状況のようです。原料の高騰に対しての価格転嫁が出来ない構造的欠陥を持った日本の制度下では、どの化学メーカも苦労しています。
ザクっとっぐってみました。(化学の会社は日本に多数あるので、ほんの触りだけ見てみました。深堀しません。)
①デンカ
↓
セメントと言えばデンカでしたが、昨年事業ごと譲渡しました。日本の建築産業さん。大丈夫でしょうか。。セメントは悪者ではありません。化学製品を生成するのに膨大なエネルギーは必要です。CO2排出は避けられません。
➁三菱ケミカル
↓
ギブソン社長。次々と不採算部門を売却しています。石油化学からの脱却を目指しています。
--------------------- 抜粋します。
ギルソン 機能商品です。ビジネス分野としては、エレクトロニクス(電機)、半導体、ライフサイエンス、自動車を対象にした戦略を策定中で、世界中のあらゆる成長機会を取り込むつもりです。
また、石化事業の中でも、アクリル樹脂の原料でリサイクル性が高い素材のMMA(メチルメタクリレート)と、MMAから作られるMAA(メタクリル酸)などには引き続き注力します。世界シェア4割と高い競合優位性を持つ強みがあるからです。
---------------------
↓
再統合が着々と進められています。(道半ばです。指標値として、事業部ごとにROICを目標設定しています。=会社の目標です。)
↓
ROICの向上は、今後の一番の課題でしょう。
③旭化成
なんと言っても、リチウムイオンの吉野彰氏の存在が光ります。
プロフィール
↓
元々、磁気センサーでも世界No1のシェアです。
↓
↓ 正確にはホール素子
この会社、次々と新しい製品を開発しています。
ホームページ
↓
ここのサイトは、とても分かりやすく見やすい工夫なされています。昔から感心していました。
様々な工業基礎の元なる素材を輩出しています。
↓
④信越化学
↓
利益率において、同業他社を圧倒しています。原料が高騰している中で、高収益を上げています。
↓
↓
この会社は、全体におていのバランスの良さが光ります。塩ビ、合成石英、半導体シリコン事業においては世界シェア1位は伊達ではありません。
日本の強みは化学に強い事です。様々な素材を要求に応じて提供する事ができます。素材産業の原点と言っても良い。
どの企業も、M&A、事業譲渡を積極的に行っています。同業のグループの再編成を実施しています。それでも、原料を輸入に頼っているので、利益を上げるのは至難の業です。昨今のカーボンフリー化は、化学工業を悪者扱いし過ぎです。石油合成製品が無くては、スマホも車も飛行機も宇宙船も、家庭にある家電も作れません。薬も石油合成製品です。産業の基盤となるのが化学です。どこかの省庁が、半導体の2㎚プロセスルールと作ると言ってますが、、これも化学の分野です。化学無くして日本国無しです。(ただし、ステッパーに至っては日本は壊滅的ですが。。)下地産業はお金がかかります。直ぐには成果もでません。基礎研究は大切です。(長年日本は放置しました。=個人の努力でなんとかしてきた。優秀な研究者が海外に逃げ出すわけです。近年日本人ノーベル賞の受賞者が少なくなってきています。)
昨今の行き過ぎたカーボンフリーの動きは、化学工業のさらなる再統合を要求しているように見えます。ただし、行き過ぎた(そもそも無理な)目標設定はいかがなものかと考えます。化学産業に限らず、全ての業種で再統合が加速されると予測される2023年ですが、一度火を消すと、元には戻らないテクノロジーもあります。
世界が平和で、仲良く貿易、文化の交流を進めていた時代が終わった気がします。世界の情勢が変わりました。(自国でできる事は自国でやった方が良いという状況はしばらく続くでしょう。)日本国政府も、政策の修正は必須でしょう。過去に作った根拠のないドクトリンに縛られる必要もないと考えます。為替の安定位はやって頂きたい。多くの企業が振り回されています。(現在でも130円辺りをふらふらしています。いくら企業が為替予約しても利益が吹っ飛びます。=決算の修正の多い事。)
ちょっとググっただけでも、、日本の企業の舵取りの難しさが理解できます。政府の理解と支援は必要不可欠だと考えます。