![]() ご訪問ありがとうございます
ご訪問ありがとうございます![]()
地元の石井啓一衆議、藤原みどり市議、隣町の後藤るみ市議、大阪の山本かなえ参議
他の党は誰も来ませんでしたねー。ただ後日、日本維新の会の候補の(本人乗ってない)選挙カー![]() が回ってました
が回ってました![]()
![]()
「政治を変える!」と訴え続けていましたが、"言うは易く、行うは難し"。変わるべきは、庶民の声すら聴かない、維新のような選挙目的の政治屋でしょう![]() (旧体制の自民党は当然として
(旧体制の自民党は当然として![]() )
)
過干渉でも放置でもなく、子どもに「心からの信頼」を―東京医科歯科大学教授 藤原武男さんに聞く

変化の激しい“不確実な時代”において、子どもたちには、どんな力が必要なのでしょうか。東京医科歯科大学の藤原武男教授は、「学力も重要ですが、それだけでなく、より“根本的な人間力”が求められる」と言います。これからの時代を生き抜くための子育てについて聞きました。(聞き手=掛川俊明、村上進)
東京医科歯科大学教授
藤原武男さん
【プロフィル】ふじわら・たけお 1974年生まれ。東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授(公衆衛生学分野)。医学博士。2006年、ハーバード大学公衆衛生大学院で公衆衛生学修士号(MPH)取得。その後、国立成育医療研究センター研究所社会医学研究部部長などを経て、16年より現職。専門は母子保健、虐待予防、ライフコース疫学、社会疫学など。
■育児の情報が氾濫する中で、「何のため」という問いが大切
―実は、記者も乳児の子育て真っ最中なのですが、いろいろな子育て情報があふれていて“何が正解なのか”と戸惑うこともあります。
育児の手法について、さまざまな情報が氾濫しています。しかし、「何のための子育てか」という根本的な問いに、もっと向き合うべきだと思います。
私は、子育ての目的を「子どもが自分自身で成長できるようになること」だと考えています。子どもが自分を奮い立たせ、困難にぶつかっても乗り越え、自分で自分を成長させられること。それが、その子の幸福につながります。
ただし、何に幸福を感じるかは、子ども自身にしか分かりません。親が子どもに、幸福それ自体を与えることはできないのです。けれど、幸福を得るためのスキルを育てることはできます。何かをやりたいと思う心、そして困難に立ち向かう心を育てることはできるのです。

子どもが、自分でやりたいことを見つけて、その道で試行錯誤を繰り返し、人間的に成長していく―そうした本当の意味での自己実現が、最終的には重要なのではないかと思います。
やりたいことを成し遂げるためには、さまざまな能力が必要です。読み書きや知能などの「認知能力」と、人間力や生きる力にもつながる「非認知能力」、それらの前提になる「健康・体力」が相互に関連しています。
今、世界は激変し、将来の予測がつかない“不確実な時代”になっています。こうした時代において、子どもの幸福のために必要な力を考えることが、本当の意味で“子どものためになる”子育てにつながるはずです。
―著書『子育てのエビデンス』(大修館書店)では、全ての土台になるものとして「アタッチメント」という概念を紹介されています。
子ども自身が安全を感じられる、自分にとっての「安全基地」を持っている感覚が、アタッチメントです。主に「愛着」と訳される、子どもの心の状態を指す言葉です。
それは、自分の全存在を肯定してくれる、帰るべき「母港」があり、よって立つ「大地」があるということです。例えば、赤ちゃんが泣いたら、親がそれに応えてミルクをあげます。こうしたやりとりを重ねて、アタッチメントが形成されます。
アタッチメントができると、探索行動つまり「遊び」が始まり、子どもは自分でやりたいことに向けて動き出せるようになります。アタッチメントは、ストレスに強い性質や、多少のリスクを取って行動できる能力につながるのです。
さらにアタッチメント形成によって、子どもは人を信頼できるようになります。ケアを求めたら、相手が応答してくれたという経験を重ねると、他者の行動が予測できるようになるからです。さらに養育者から肯定されることで、自分で自分を信じることもできるようになります。
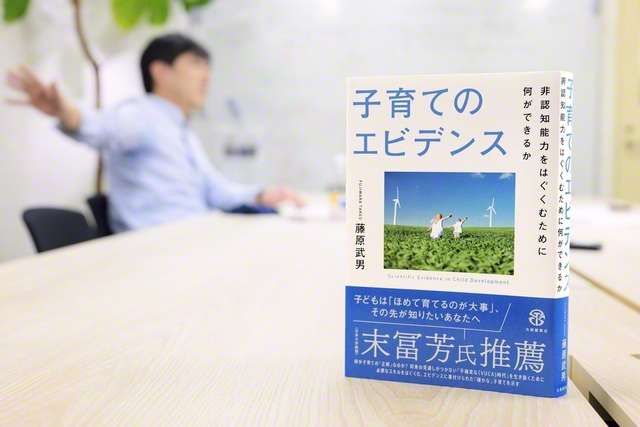
甘えるなどの子どもの求めに対し、親などが必要なケアを行う、こうしたやりとりをテニスに例えて、「サーブ・アンド・リターン」とも呼びます。
けれど、全ての要求に気付き、完璧にリターンすることは不可能です。実際には、親として正解が分からないながらも、泣いている子どもの様子を観察して、いろいろ試してみるしかありません。
十分に甘えてアタッチメントが形成できると、探索行動によって自分の世界が広がり、社会性も育まれるので、その後はいわゆる「甘える」子どもではなくなります。逆説的ですが、甘えさせることによって、甘えなくなって自立できるのです。
ただし、適切な甘えと「過保護」は違います。「ケアされたい」という求めがある時は、甘えさせることが必要です。一方で、全てを先回りして与えてしまうのは、過保護です。
アタッチメント形成は2~3歳頃までが重要といわれますが、それ以降でも十分に取り戻せます。思春期においても、子どもからの“気にかけてほしい”という求めには、適切に応じる必要があります。

―子どもをあやす時、スマートフォンは使ってもよいでしょうか。
最近は、子育てにおけるデジタル機器の存在も大きくなっています。子どもが幼い頃は、どうしても泣きやんでもらいたい時など、スマホを使ってあやすことが避けられない場面もあります。一切使わないというのは、現実的ではありません。けれど、スマホの使用が常態化しないように、気を付けたいものです。
それに、スマホも使い方次第です。親子で一緒に動画を見ながら話すなど、コミュニケーションが発生すれば効果的でしょう。
デジタル機器それ自体が、良い悪いということではありません。例えば小学生以上であれば、大切なのは、子どもが「自分でスイッチを切れるかどうか」だと思います。
―アタッチメントという土台の上に、どのような力を育むことが求められるでしょうか。
一つは、衝動性を抑える「セルフコントロール」です。これは単に“我慢する力”ではなく、“自らを使いこなす力”のことで、特に他者との関係において必要になります。例えばグループで行動する際に、衝動的に自分がやりたいことだけを押し通すと、衝突や摩擦が生じます。自分の思いや行動を調整し、コントロールすることが求められるのです。
ただし、セルフコントロールが利き過ぎると、言われたことしかできなくなったり、自分を押し込め過ぎて息苦しくなったりもするでしょう。あくまで、子どもの幸福のためのセルフコントロールであることが重要です。

二つ目は「モチベーション」です。自分を内側から駆動させ、引っ張っていく動機付けは、生きていく上でのエンジンのようなものです。
さらに、多様性が増すこれからの時代において、自分とは異なる人を理解して思いやる「共感力(エンパシー)」も求められます。“自分の目線”で感情を抱いて行動する「シンパシー(同情)」に対して、“相手の目線”で状況を理解し、同じように感じようとするのが「エンパシー」です。
ただし、他者に共感するのは、しんどいことでもあります。あらゆる人に共感しようとしたら、疲れ果ててしまうでしょう。大切なのは、自分が関わる“具体的な人”を思いやることだと思います。

最後に、困難や逆境を乗り越える「レジリエンス」です。これは外からの圧力であるストレスに対し、元に戻ろうとする回復力、復元力のことです。ストレスを石のようにはね返す「頑健性(ロバストネス)」とは異なり、ゴムのようにストレスを受け止めて変形しつつ元に戻る、“しなやか”な対処がレジリエンスです。
このレジリエンスを育むには、①思いやりを持つ、②あいさつをする、③野菜から食べる、④歯磨きをする、⑤ロールモデル(模範となる人)を持つ、⑥サードプレイス(家庭と学校以外の“第三の居場所”)があることなどが効果的です。
特に、あいさつは「他者をきちんと認識する」ことであり、「ちょっとした勇気を要する」ことでもあるため、レジリエンスにつながります。
―創価学会では、座談会や家庭教育懇談会など、地域の大人が、未来部員をはじめとした子どもたちに接する機会があります。
会合だけでなく、「訪問・激励」を通して、親ではない大人、またはお兄さん、お姉さんなどの先輩が、未来部員と触れ合っているのが素晴らしいと思います。実は、アメリカでは「家庭訪問」が、重要な子ども向け政策の一つになっています。訪問して子どもと会うアプローチには、親子の健康を守るといった効果があることも分かっています。

日本でも、産後に保健師や助産師が訪問しますが、思春期の子どもを対象にした施策は少なく、未来部の訪問・激励は、社会的にも大きな意義があると思います。
日常生活において、気にかけてくれる親以外の大人の存在がある―そうした“斜めの関係”が、子どもにとって非常に重要なのです。
―子どもは親の背中を見て育つといわれる一方で、親の考えや価値観が伝わらない場面もあります。
変化の時代ですから、親子で価値観が合わなくなることもあります。親のやり方や手法を継承させるというよりは、親の信念など“根本”の部分を伝えることの方が大切だと思います。子どもの価値観を尊重することも大事ですが、親の価値観も大事です。ポイントは、いかにお互いを理解するか、ということでしょう。
実は昨年、アメリカに1年間滞在することになり、2人の息子と一緒に渡米しました。そこで気付いたのは、それまで、いかに子どもと話していなかったかということでした。改めて、息子と意識的にコミュニケーションを取る機会になりました。

子育ては“バランス”が大切です。全てに口を出す「過干渉」は良くないですが、反対に何も関わろうとしない「放置」も問題です。偏りのないバランスを支えるのは、子どもに対する「心からの信頼」ではないでしょうか。
親の価値観を伝えるといっても、初めの一歩は、子どもとよく話し合うことです。私自身が昨年、痛感したように、意識的に子どもとコミュニケーションを取ることから、全ては始まります。それが、子どもを一人の人格として尊重すること、心から信じること、肯定することにつながると感じます。





