政治学者 姜尚中
【カン・サンジュン】1950年、熊本県生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了。国際基督教大学准教授、東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授、聖学院大学学長などを経て、現在は、東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長・鎮西学院学院長・鎮西学院大学学長。専攻は政治学、政治思想史。ミリオンセラーになった『悩む力』をはじめ、『心の力』『マックス・ウェーバーと近代』『在日』『オリエンタリズムの彼方へ』『朝鮮半島と日本の未来』など著書多数。小説作品に『母 - オモニ - 』『心』がある。近著は『それでも生きていく - 不安社会を読み解く知のことば』(集英社)。
●気候変動やコロナ禍、ウクライナ危機など、さまざまな課題が山積するこの時代を、どのように見つめてこられましたか。
歴史を俯瞰して見てみると、現代の危機の端緒は、半世紀以上前にあったことに気付きます。
ローマクラブが地球の有限性に警鐘を鳴らしたリポート「成長の限界」を発表したのは、1972年。その前年には、金と米ドルの兌換停止が宣言された「ニクソン・ショック」が世界経済に影響を与え、後に大半の国が通貨の変動相場制へと移行していきます。米ドルという一国の通貨が、金に代わって、世界の通貨の安定を託されるようになった。さらに、73年には第1次石油ショックが発生しました。
世界経済が、アメリカ次第で右にも左にも揺れ動く時代が、70年代初頭に始まったということです。その経済活動のありようは、ものを生産・販売し、それに対価を支払うといった「実体経済」から、金融取引や為替相場の変動で富を増やすといった「金融経済」に変わっていきました。私はそれを“虚の経済”と呼んでいます。
地球環境がグローバル経済の成長に耐えられないという状況が、すでに始まっていたにもかかわらず、資本は無制約で世界中に広がっていった。今日の気候危機は、不可避の事態として起こったといえるのです。
一方で、ウクライナ危機をどう見るべきか。第1次世界大戦(1914~18)と第2次世界大戦(1939~45)の“終戦”のあり方を比較すると、浮かび上がることがあります。
第1次世界大戦に終結を与えた「ベルサイユ条約」は、戦勝国である連合国と、敗戦国であるドイツとの間に調印されたものでした。新たな国際秩序が形成されるはずでしたが、この条約によってドイツは植民地や領土を失い、賠償支払いを課せられるなど、徹底的に圧迫されました。すると、条約を恨む気分がドイツ国内に強まっていった。それがナチスドイツによって利用されるようになり、政権掌握の一因となったと見ることができるのです。
その歴史の教訓から、第2次世界大戦後、アメリカが推進した「マーシャルプラン」と呼ばれるヨーロッパの復興計画は、敗戦国であるドイツやイタリアを含む広域に適用されました。それによって、極右勢力が出てくる可能性が摘み取られたわけです。
そうした経緯もあり、戦後の東西冷戦の時代は、国際社会で紛争や戦闘が繰り返される中でも、ある種の均衡を保っていました。高度経済成長に入った日本にとっても、ある意味で“幸せな”時代だったともいえます。
しかし、1989年の「ベルリンの壁」の崩壊に象徴されるように、その冷戦が終結すると、唯一の超大国として世界に君臨したのがアメリカです。そのアメリカと西欧諸国が構築していった安全保障の枠組みは、ロシアの地位を十分に考慮したものではなかった。いわば、ロシアが冷戦の“敗戦国”であると位置付けられたとも捉えられるのです。
一方ではアメリカが、世界を“一極支配”したかのように振る舞い、他方ではロシアが、“国土は大きくても軍事的には二流、三流の国家だ”と、西側諸国から下に見られるようになった。その屈辱を晴らし、国際社会での立ち位置を挽回したいと考えたのが、プーチン大統領だといえます。そうした背景が、現下のウクライナ危機につながっていると見ることができる。まさしく、第1次世界大戦のベルサイユ体制の時と同じ過ちを犯してしまったといえるのです。
冷戦後、ロシアが安全保障上で危機感を持たないような国際秩序を構築できていれば、今日のような戦禍は免れることができたのではないか - 。そう考えざるを得ません。
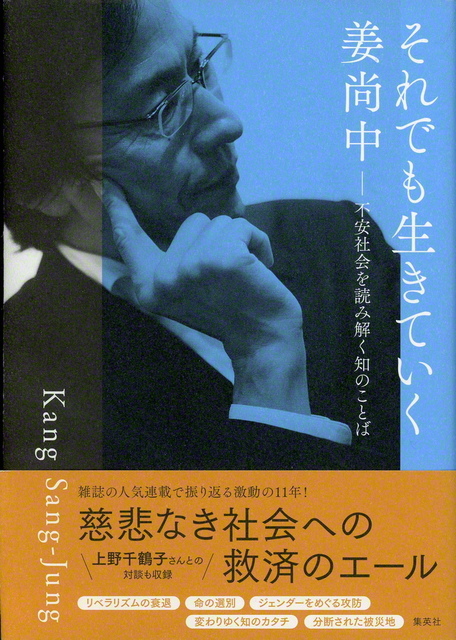
●20世紀に芽生えた危機が、さまざまな形で噴出する現代の世界のありようを、歴史の上からどう捉えるべきでしょうか。
歴史というのは、繰り返すのではなく、「韻を踏む」。アメリカの作家マーク・トウェインが言ったとされる言葉ですが、これにならえば、現代は1930年代と似た様相を呈していると思います。
1930年代は、ウォール街の大暴落(29年)などを背景に、自由主義と資本主義に対する不信感が高まった時代でした。政府が経済活動に介入しないといった、イデオロギーとしてのリベラリズムは神通力を失い、むしろ、国家が介入することが、社会の秩序を保つ“切り札”であるとされていった。「小さな政府」から「大きな政府」への移行です。国民の、国家に対する期待値、国家との一体感を求める思いが、強まる時代だったということもできます。
日本では、この数十年間、没政治化とさえ言える状況がかなり進んでしまったのが現実です。官僚主導で物事を進め、政治家は口を挟むなという空気があった。その中で、選挙での投票率も下がり続けた。今、日本の最大の問題は、経済の問題ではなく、国家の問題、政治の問題であると私は思います。
政治がうまく機能するためには、やはり社会が強くなければいけない。そして社会が強いというのは、国家と国民を結ぶ中間集団が機能しているということなのです。
●個人でもない、国家でもない、その間に位置する中間集団が、社会で果たす役割とは何でしょうか。
中間集団に自分の居場所を持つ人は、自分の考えを伝えるとともに、他にもさまざまな意見があることを知り、議論し合うことができます。一方、そうした場を持たない人は、自分と社会との間に介在する多様な価値観に触れることなく、むき出しの形でメディアの洗礼を受けます。
すると、自分の身の回りで起こっている現象について、流れてきた情報を鵜吞みにしたり、フェイクニュース(虚偽報道)に侵されたりしてしまう。SNSが普及する現代においては、なおさらです。
現代は、中間集団が痩せ細り、若者を中心に、社会関係の網の目から離脱する人が増えてきています。そうしていわば“砂粒化”した個人が、極端な情報や言説に触れることで、バラバラだった状態から、一定の方向にマスとなって動き出してしまうことがあります。それはナショナリズムや全体主義の温床となる危険をはらんでいます。
偏った情報や妄想を信じている個人が、マスとなって固まれば、極端な方向に向かうのは十分にあり得ることです。
一方で、普段からいろいろな人と自由に、対等に交流し合える中間集団に足場を持っている人は、デマや妄想とは対極の、リアリティーと常に接点を持つ人たちです。その結果として、仮に極端な考えを持っていたとしても、リアリティーを伴う人間関係の中で、やがて均衡のある考えへと是正されていくのです。こうした身体的なつながりの価値は、ますます高まっています。
現代は、さまざまな苦悩を抱えて暮らす人がいながらも、彼らを取り巻く社会の課題が、見えづらくなっています。苦悩を誰にも相談できないがゆえに、反社会的な行動を起こす人もいる。個人が、遠心分離機にかけられたように砂粒化し、極端な方向へと動いてしまう。それは、彼らをすくい上げる中間集団がなくなってきているからだと思うのです。

人は誰でも、社会の中に生まれ、社会の中で育ちます。でも、ここで私が言う「社会」とは、大文字で語られるような観念的なものではなく、地域やボランティア団体といった、人の顔が浮かぶ具体的な社会のことです。そうした中間集団を持たない人にとって、個人主義が至上の価値になっている現代社会は、非常に生きづらいと思うのです。
現代の人たちは、「自由」という言葉を毎日、シャワーのように浴びて生きてきました。自由が与えられるということは、それだけ多くが自己責任化されているということでもあります。ただ、人は自己責任だけでは生きていけない。病気や災害があれば、誰かの力が必要であり、ネットワークの力ですくい上げられて、初めてまっとうに生きていける人が多くいます。
中間集団が至る所に存在して、人々をすくい上げられるようにしていくことが、社会の足腰を強くすることだと私は思います。しかし実際、長年、勤め上げた企業を定年退職した男性の高齢者などは、自分の居場所がないと感じている人が多いのではないでしょうか。一般に「アソシエーション」と呼ばれるような、共通の目的や関心を持つ人々同士が関わり合える空間が、もっと自発的に出てくれば良いと思います。
中間集団が痩せ細ってしまうと、自分の悩みを誰にも言えない人たちが増えていきます。最近では、衝撃的な元首相の銃撃事件(7月8日)もありました。容疑者である青年が犯したことは決して許されることではありませんが、彼も孤独だったのではないか。社会の中に、彼のような人をすくい上げる余地がなくなってきていることの危険性を感じています。
その上で心配なのは、今回の事件に関連して、あくまで「反社会的な団体」と一部の政治家のつながりが問題となっているわけですが、これを機に、「政治と宗教」の関わりを全般的に問題視するような見方があるとしたら、これは全くの筋違いということです。今、見つめなければならないのは、「政治と宗教」というより、「政治と反社会的な団体」の関係性を巡る問題であるからです。
●近著『それでも生きていく - 不安社会を読み解く知のことば』(集英社)をはじめ、危機の時代を乗り越えるための指針を多く発信してこられました。今、私たちは何を心掛けて生きるべきでしょうか。
これは今、私自身がさまざまな人生経験を積んで、70代に入ったから感じることかもしれませんが、「時間軸を長く取ること」が必要だと、最近改めて思います。というのも、私たちは普段、小さな時間の単位でしか、人生を考えていないのですね。特に若者には、そうした傾向が強いのを、大学等の現場で感じています。
その場その場で、受験に合格したら喜ぶし、どの大学に行くかで人生が決まるといった感覚に、吸い込まれてしまった人たちが多くいる。そんなことで人生は決まらないよと言っても、若い人にはなかなか理解されません。「人生100年」といわれる時代にあって、日本は世界に誇る長寿社会であるにもかかわらず、驚くほど短い時間軸で物事を考えていることを、私は憂慮しています。
人生には、良い時も悪い時もあるわけですね。でも、そのたびに一喜一憂する必要はない。『ゾウの時間ネズミの時間』(本川達雄著)ではないが、大きなサイズで時間を考えると、人生の出来事を違った視点から見ることができるように思います。
そのように長い時間軸で人生を捉えられるようになるには、“敗者復活戦”が許される社会にならなければならないと思います。たとえ一度は失敗しても、やり直しができる社会です。例えば、新卒で一斉に採用するような仕組みではなく、いつどんな時でも、中途採用ができるような雇用形態に変えることなどです。アメリカでは、50歳で大学に入って学び直したり、弁護士事務所を開いたりしても、何も珍しいことではなく、当然のように受け止められます。
そうした社会の変革は、制度・慣行・生き方の三位一体で進んでいくのが望ましいです。しかし実際には、制度や慣行はすぐには変わらなかったりします。だからまずは、自分の生き方、考え方を「ゾウの時間」に変えてみることです。
今だけを考えてしまえば、つらいことは、つらいままでしかないかもしれない。しかし、人生あと数十年あると捉えて、今はダメでも敗者復活戦で逆転できると考えられれば、つらいことにも「意味」が伴っていくと思うのです。
人生は選択の連続といえます。“あれもこれも”と何でも選べた高度経済成長期とは異なり、現代は、何かを選ぶことは、何かを失うことでもある。仕事を切り上げて家族と時間を過ごすのも、地域貢献の活動に精を出すのも、選択ですね。“あれもこれも”は選べないかもしれないけれど、“あれがダメならこれがある”というふうに、選択肢を増やしていくという考え方が大切ではないでしょうか。人生を「複線化」していくということかもしれません。
●長い時間軸で人生を見つめるからこそ、“幸もあれば不幸もある”現実を受け止めることができるようになる - 近著では、ご自身の経験からそうつづられています。
2010年に息子を亡くしたことは、私が、「幸せ」について深く考えるようになるきっかけでした。
何の不自由もないことが幸せであり、それが人生の目的であると考えてしまえば、不幸に見舞われたときに、それを恨んだり、否定したりしてしまいます。そしてそれは、私たちが無意識に抱いている幸福観かもしれません。
でも、今は悩み一つない人生であっても、誰もが家族や親しい人を失うなどの場面に直面するでしょうし、いつかは自分にも病や死が訪れる。もしも、幸福と不幸が分断されたものであると捉えれば、“いつか自分は不幸になるのではないか”という不安は尽きません。しかし、長い時間軸で人生を見つめて、幸福と不幸は地続きであり、“どちらもあるのが人生だ”と考えると、私自身も完全に不安から解放されたわけではありませんが、だいぶ気持ちが楽になりました。
アメリカの哲学者ウィリアム・ジェームズは、「二度生まれ」という概念を提唱しています。人は苦痛や苦悩を引き受けることで、自分の中の価値観を変え、「二度目の誕生」を経験する、と。
William James(1842 -1910)
私は、ジェームズがそう書いた背景には、宗教的な経験があったのではないかと思っています。人生には、知識や経験を増やすといった次元を超越して、人間が“丸ごと”変わる瞬間がある。それは信仰に基づく経験である、と。
そのときに、人は今まで知らなかった、自分の未知の領域を発見します。場合によっては、今まで自分が幸せだと考えていた価値観が、崩れていくかもしれません。
しかし人間は、現状に満足しているときよりも、幸せではないとき、幸せを求めるその過程にいるときのほうが、思索を重ね、自分を深めていけるという側面があるのではないかと、私は思うのです。
誰の人生にも、1回や2回は訪れるであろう「二度生まれ」の経験は、生き方の転換を促すきっかけになります。この価値の転換は、知識の伝授では起こりえないものです。

●「不安社会」を生き抜く若者に、メッセージをお願いします。
最近、若者の口から「希望」という言葉を聞かなくなったと感じています。
「幸せ」は、何かうれしいことがあったなど、自分一人で感じられる喜びや満足を指すのだと思います。でも「うれしいことがあったから希望を感じた」とは言わない。希望とは、「共に喜ぶ」ことであり、他者がいてこそ感じられるものだと思うのです。
自由と自己責任をうたった新自由主義的な価値観のもとで、「幸せ」を実現する人はいるかもしれないけれど、「希望がある」とはなかなか言えないのが現代です。誰かが幸福であれば誰かが不幸であるといった、“ゼロサムゲーム”のような社会であると考えられることが多い。幸せそうな人に嫉妬したり、攻撃したりする人もいる。
格差や不平等がまん延する社会にあって、ドイツの哲学者ニーチェが「ルサンチマン」と表現した、弱者が強者に対して抱く嫉妬・怨恨といった感情が、全世界的な傾向になってしまっているのではないでしょうか。
Friedrich Nietzsche(1844-1900)
だからこそ、希望を生み出すことが必要です。自分の未来に希望を抱いている人は、たとえ今不幸であっても、耐えられる。他者の不幸の上に自分の幸福を築くようなことは、しないはずです。
現代は、人を幸福にするはずだった自由が、かえって人を孤独にする時代であるともいえます。しかしかといって、人は自由を求めずには生きられません。難しい時代ですが、同時に「生みの苦しみ」の時代でもあるのです。
ここをくぐり抜けることができれば、必ず明るい未来が開けてくる - 。一人一人が、その希望を社会に灯し続ける存在になっていただきたいと思います。







