カポーティ長編2作目となる作品。
先日の「遠い声 遠い部屋」と同じく自伝的作品と言われているそうですが
こちらはずいぶん読みやすく、また大変わたし好みの作品でした。
両親が亡くなり、親戚の初老の姉妹の家に引き取られたコリンが
彼女たちと共に過ごした11歳から16歳までの日々の回想です。
特にコリンのよき理解者でよき友人でもある、内気で温和な姉・ドリーと、
経済活動に頭角を現している、やり手の妹・ヴェリーナが仲たがいしたことで
コリン、ドリー、そして家事手伝いのキャサリンの3人が家出をした
その前後譚がメインとなっています。
ドリーが薬草から作る水腫薬、ムクロジの樹の上の古い小屋、
打ち捨てられたボートハウス、ピンクに塗られたドリーの部屋、
屋根裏部屋・・・こういう環境とか小道具がたまりませんね。
さらに美しい自然を描写する、情感あふれる文章がすばらしい。
この時代について、カポーティはいくつかの短編を残しており
相当に印象的で幸せな時代だったのだろうと想像できます。
まったく同じ過去を共有していなくとも、自分の持っている思い出の
なにかしらと重なるものが多々あって、それゆえにこのシリーズは
人の心を打つのだと思います。
最終的には樹の上の家での生活はわずか数日にして、街の人々の知るところとなり、
彼らから精神的にも肉体的にも迫害に近いものを受け、コリンたちは
この小屋を後にすること、つまり日常の生活に戻ることを決意します。
決して迫害そのものに屈したわけではなくて、しがらみなどを考慮して
自ら選択してはいます。
でも手に入れたばかりのこの新生活や新たな間関係を捨てなくてはならない
このシーンはとても哀しい。
ヴェリーナや町の人から見たら、かなりの異端者・変人であるコリンたち。
その彼らが多勢の側に戻るというか、彼らに紛れ込まねばならないのですから。
カポーティについてよく使用される「無垢」という言葉よりも
モラトリアムな時代との訣別という印象が残りました。
(日本語の「無垢」は、イノセントの訳として十分ではないと
思っています・・・が、このことについてはいずれまた。)
意にそぐわないものをあえて受け入れていく決意の瞬間ですね。
まさに歌でいう「大人の階段上る~♪」、そんな感じでしょうか。
束縛するものからの逃避、つまり自由になるということは誰とも関係を持たず
孤独であることがまず第一に必要なのかも、などと思いました。
なかなか難しいことですね。
草の竪琴 (新潮文庫)/新潮社
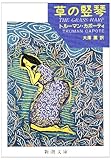
¥473
Amazon.co.jp
映画化もされているようですよ。
グラスハープ-草の竪琴- デジタルニューマスター版 [DVD]/東北新社

¥4,104
Amazon.co.jp