レイモン・ラディゲの突然の死を受け止められず、重度の阿片中毒となったコクトーが
解毒治療に専念するために入院した時に書いたものだそうです。
前半はひたすら「阿片」の魅力について語っており、まるで阿片賛歌のよう。
阿片がいかに素晴らしく、魅力的なものであるかを語ります。
このひとつのものへの執拗な固執の仕方はやはり中毒ゆえなのだろうと思いますが、
でも文章や視点には乱れがないように見えます。
それはコクトーが中毒となってもなお、芸術家としての矜持を持っていたからなのか
それともどうやっても何を取り去っても、正真正銘、生まれつきの芸術家だからなのかは
わかりませんが、もし自身の意志をコントロールしてこれを書いていたとしたら
やはり尋常な人間ではないだろうと思いました。あたりまえか・・・。
この阿片賛歌は、忘れがたい想い人の素晴らしさを語っているようにも見えます。
決して阿片を悪く言うことはありません。
これはまるで恋じゃないか、と思いながら読みました。
そんな合間合間に、たくさんの芸術家たちの名前が出てくるのはなかなか楽しいもの。
時に辛辣な言葉もあったけれど、ピカソだの、マティスだの、プルーストだの・・・。
打って変わって後半では、阿片の毒気が抜けてきたようで阿片よりも圧倒的に
芸術の話題が多くなります。
ただその話題はフランスの芸術に造詣が深くない私にはついていけない。
○○夫人などの固有名詞や、おそらく当時話題になった演劇や事件の話などは
ついつい流し読みになってしまいました。
「阿片」などというものについてということもあると思いますが、
読んでいて正直決して楽しくはなかった。
マルグリット・デュラスを読んでいる時と同じ感じ・・・でもあちらは
大好きな最後の数ページという目的があるからあの苦行にも耐えられるのですが。
翻訳はあの堀口大学先生…この時以来どなたも新訳を試みていないということ?
どんな事情があるのかわかりませんが・・・。
フランス語もスペイン語と同じように関係詞を使った長文が多いのかもしれないけれど、
それをそのまま日本語に翻訳されているとしたら、正直読みづらいです。
適度に文章は分けてあったら良いかも、と思いました。
コクトーと阿片の関係ががこのあとどうなったのか私は存じませんが、
本書の最後のほうで阿片に誘われたらまた嗜むようなことを書いていました
…懲りていない!?ですね。
コクトーが治療院で解毒中に書いた、ペンによるちょっと気持ちの悪い
ドローイングもページの合間合間に数点、収められています。
フランス的な哲学というか思想とか、あの持って回った独特の言い回しが
お好きな方にはたまらない本かもしれません。
私はADIOS!って感じかな。
私のは表紙が池田満寿夫さんによるものでした。
阿片―或る解毒治療の日記 (角川文庫)/角川書店
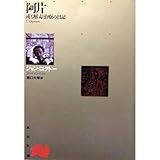
¥410
Amazon.co.jp