自らは多くを語らないマーロウの、テリー・レノックスへの関わり方、行動が
マーロウの美学そのもの、今回の村上訳では妙に私はテリー・レノックスに
目が行ってしまいそんなことを思いました。
印象に残る洒落たせりふも良いのですが、マーロウ自身を作り上げてきた
さまざまな経験や何やらの中から凝縮し、抽出した行動そのものがやはり良いなあ、と。
読んでいると、理想だけでは生きられないのさ的な指摘も作品内で多々ありますが、
それでも貫くのがハードボイルドかと。
だから結構ばかばかしいことではあるのですが、やはり人生の美学はないとね。
村上訳ではマーロウが少し若返ったと言うか、ちょっと「青臭い」という
印象は残りましたが、清水訳とともにこちらなりの良さがありました。
きっと若い頃から、村上氏は何度も自分ならこう翻訳するぞ、という
シミュレーションを繰り返してきたのだろうということは感じます。
そして、やはり文章は「村上春樹」なのですね。
チャンドリアンとして名高い春樹くんが、チャンドラーの影響を受けて
今の村上春樹的文章を書いているのか、それともやはりこれも春樹流翻訳なのかが
私には区別がつきませんでした。
ただ村上作品の底辺に流れるものはなんとなく感じることは出来るかな。
気になったのが「はんちく」と言う言葉。
半端モノとかそういった意味合いがあるそうで、やくざの親分が何度も
マーロウに対して作品中で使用していましたが、先の私の印象と合わせるなら
青二才といった感じになるのかな。
でも現代ではほとんど使われることのない言葉を、村上春樹という人が
今になってあえて使っていることに興味を惹かれました。
この単語を使ったことが象徴する何かは、果たしてあるのでしょうか?
時間がかかってしまったこともあるけれども、ほかの作品以上に
ハードボイルドものの感想って書きづらいですね。
ま、これは自分で読んで感じていただかないと・・・と実も蓋もないことで
お茶を濁してしまうことにします。
巻末にかなり長い村上春樹のあとがきがあります。
この充実度はなかなかのもので、これだけでも読む価値はあると思います。
でも、やはりあとがきとか他人の感想は自分の書いた後で読むほうが
絶対に良いですね。
誰かのを見てしまうと、どうしてもそれが書くことに制限をつけてしまうような
気がします。
今回は海外のペーパーバックスを思わせるこの新書版で読みました。
ロング・グッドバイ (Raymond Chandler Collection)/レイモンド・チャンドラー
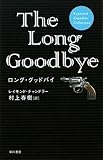
¥1,470
Amazon.co.jp
有名な「To say good-bye is too die a little.」と言うせりふの出所となった曲らしい。
が、その大モトはフランスの詩に・・・詳細は春樹くんのあとがき参照のこと。