岡本太郎の熱い「芸術論」なのですが、つきつめると結局どんなふうに
生きるべきか、という人生論になっているように思います。
理路整然として端的でわかりやすく、そしてブレのない主張はとても感動的でした。
もうひとつの生き方的な部分に関しては、しごく理想的ではあるけれども、
この思想はやはり岡本太郎として到達したものでしかないのですね。
だから、おおっ!すごい!私もそういう生き方をしよう、と思ったからと言って
たやすく実践できるものではないと思います。
1954年に書かれた古いものですが、今読んでも心に響くものは十二分にあります。
少し前に読んだ「陰翳礼讃」などに通じるものもありましたし、
古さを感じさせずむしろ新鮮であることは、彼自身が定義する芸術の条件を
十分備えている気もします。
文章の印象からすると、当時は孤軍奮闘していたように見えますが、
岡本太郎と同じような考え方をする方は、周りにいなかったのでしょうか?
だとするなら、多少なりとも時代は変わっているのかもしれないと思います。
私が好きで読んでいるの作家(小説家・漫画家ともに)の中にはこんな感覚を持って、
世間に対抗しようとしている方たちは何人かいますので。
いずれも権威を嫌い、慣れ合うことを否定している方たちのように見えるのは
太郎式に考えれば良い傾向と言えるのかもしれません。
でも出る釘は打たれるし、そういう方たちは徒党も組まないので
さぞや日々痛い思いをされていることでしょうね。
その痛い思いを私たちが読んで、共感したりするわけですが
だからといってその思想のシンパになることを求められているわけでも
ないだろうと思います。どちらも孤高なのですね~。
発表当時ベストセラーとなり美大生や芸術を志す多くの若者たちが読んだそうです。
皆様どのようにこれを消化され、現在どんな状況であるかがとても興味がありますね。
第3者を啓蒙するためのものではあるけれども、自分の賛同者や信者を
増やすことが目的で書いたものでは決してないはずです。
でも、たいてい(すごい!私もぜひ)と単純に思ってしまうのが感動した時の
人の常で、そしてまたそれをすぐに風化させてしまうこともやはり多いはず。
求められているのは束の間の同意や共感ではなく「実践すること」で、
机上の空論ではないのですよね。
芸術は爆発だ!とは岡本太郎の残した有名な言葉ですが、読中、読後に
爆発を繰り返したこの感動を、維持し続けると言うのは難しいものだと思います。
こんな風に哲学的な一面を持つものを読んだ後は、いつも楽しくも空しい
無力感のようなものが残ってしまうのでした。
なので最近はあまり読まないようにしていたのですが・・・なんとも強烈!
画家としてのこの方については、作品の色合いとかぬめっとした表現の質感が
あまり好みではないため、実作品は大阪にある「太陽の塔」を高速道路上から
何度か遠くに見ただけにすぎません。
マスコミで見かけるわずかな一面しか知らずに来ましたが、こういう人物や
思想にはものすごく惹かれるものがあります。
虚心坦懐、先入観を捨てる・・・などということを感じている読後の今です。
それがさめぬうちに県内にある彼の美術館で、作品を見てみようと思います。
今日の芸術―時代を創造するものは誰か (光文社知恵の森文庫)/岡本 太郎

¥520
Amazon.co.jp
本日のBGM。
Celts/Enya
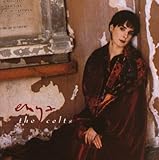
¥1,884
Amazon.co.jp