「華麗なるギャツビー」の作者「スコット・フィッツジェラルド」の短編集です。
5つの短編と、フィッツジェラルドについての村上エッセイ。
そして作品ごとの村上解説・・・と至れり尽くせりの内容でした。
私が村上春樹って意外といい!と思ったのは、昨年「グレートギャツビー」の
翻訳を読んだことがきっかけでした。
中学生の頃に、この映画を見て講談社文庫から出ていた「華麗なるギャツビー」と
「雨の朝、巴里に死す」の2冊を買って読みました。
もちろん14,5歳のころだったと言うのもあったと思うけど、読んでいて
何一つ楽しいところがなく、苦行のような思いで読んでいました。
一体、フィッツジェラルドという作家の何がアメリカ人を夢中にさせたのか?
まったくもってわけがわからなかった。
昨年もう一度、昔の本を実家から持ち帰り読もうとしたけど、相変わらず
話の中に入り込むことすらできない。
そこで村上春樹で読んでみようと思って、そしてそれは正解だったんですね。
好きな作家の好きな作品を心をこめて訳してある、という印象で
私が昔読んでいたものは、単に原文を訳しただけにすぎなかったのかも、と思いました。
今回のこの短編集はいずれも初見のはずでしたが、表題作の「バビロンに帰る」が
どうも私の記憶にある「雨の朝巴里に死す」と印象が重なるので調べてみたら、
まさにその通りでした。
フィッツジェラルドの小説を原作としてエリザベステーラーが主演した映画の
タイトルが「雨の朝、巴里に死す」で、日本では映画のタイトルを優先して
出版していたらしいということがわかりました。
「雨の朝、巴里に死す」として読んだ時は、映画を見ていたにも関わらず
やはり何が言いたいのかまったくわからなかった。
それはもちろん先に描いたように私が中学生だった、という事情が
大きかったにせよ、やはり翻訳小説としての出来栄えが明らかに違うと
思いました。翻訳者・村上春樹・・・恐るべしです。
大恐慌をきっかけに何もかもを失ってしまった人たちが主に描かれていて
それはバブルを経験した日本人の姿にも重なるし、またフィッツジェラルド
そのものでもありました。
いずれも物悲しさの残る作品でしたが、やはり表題作の「バビロンに帰る」と
「カットグラスの鉢」が怖いけど美しさの漂う作品でとてもよかった。
で、この本はフィッツジェラルドの短編なんだけど、ワタクシ的には
村上春樹とフィッツジェラルドの違いが実は不明確なんですね。
どこからが村上でどこまでがフィッツジェラルドなのかがわからないのです。
一体化しているといえばいいのか・・・とにかく、村上春樹の短編集と
言われても違和感がないと言う感じ。
そしてたとえば、私が山田詠美の本を読んでいるときには、あの感情を
こんな言葉で表せるのか、とかそんな感動を持って読むことが多いのですが、
村上春樹についてはそういうことがこれまで一切なかったのですね。
せっかく生まれてきたんだからこの本は読んでおいたほうがいいよ!というものと
読まなくてもいいけど、読んだら楽しいかも、そして読むに値しないものの3つが
大きく分けてこの世にはあると思うんだけど、フィッツジェラルドの小説も
村上春樹の小説も私にとっては、その2番目にあたるかも、と思います。
読んだ後はもちろん何かしら感じるものはあるけれども、別にそれは
なくてもあまり私の人生に関わりがない・・・でも読まずに終えるのも
ちょっともったいないよ、みたいな・・・う~ん、うまく言えないけど。
でもふたりの作品は私から見るとその点が良く似ているな~と思うのですね。
それはやはり村上春樹がそこに自分を位置付けようとしているからなのかな。
この感覚ご理解いただけるかなあ???
・・・いや、これはもうちょっとまとめないと、感覚的すぎてダメですね・・・。
でもとりあえず、本日はこれにて。
カフカ賞受賞時の春樹さま。
バビロンに帰る―ザ・スコット・フィッツジェラルド・ブック〈2〉/村上 春樹
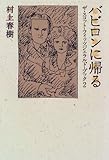
¥1,377
Amazon.co.jp