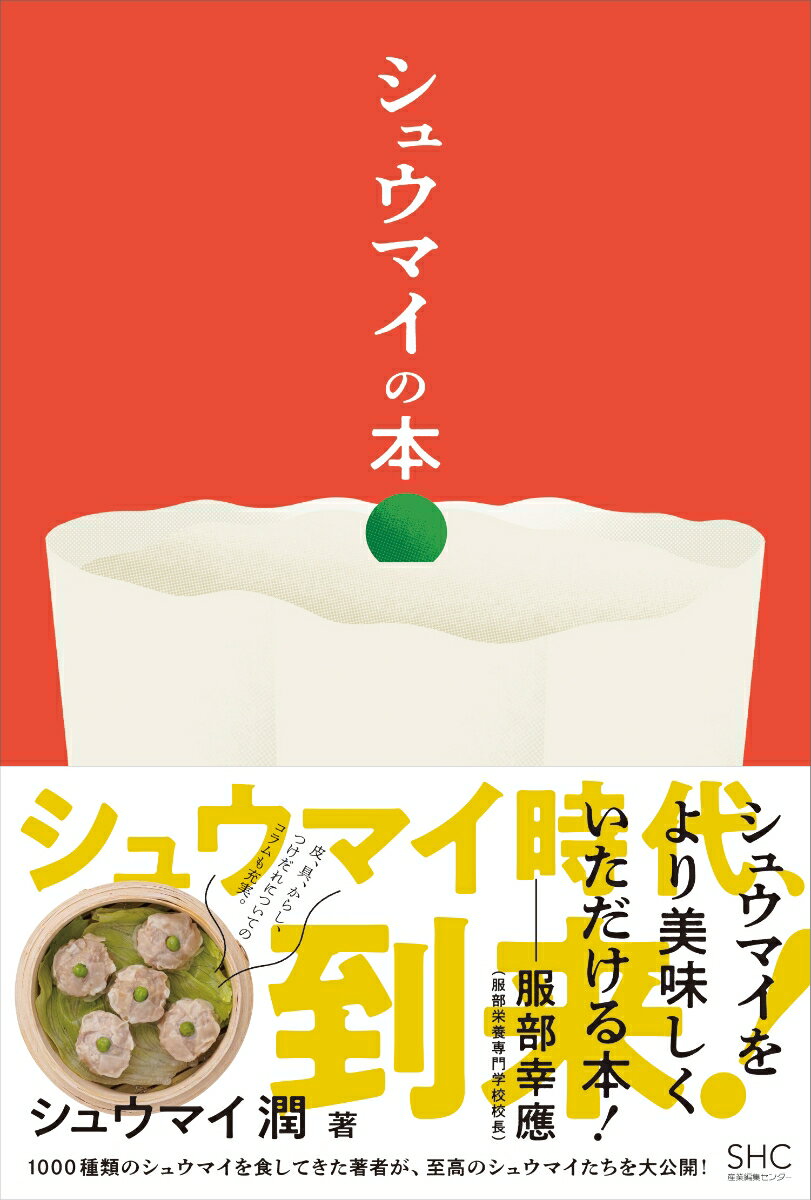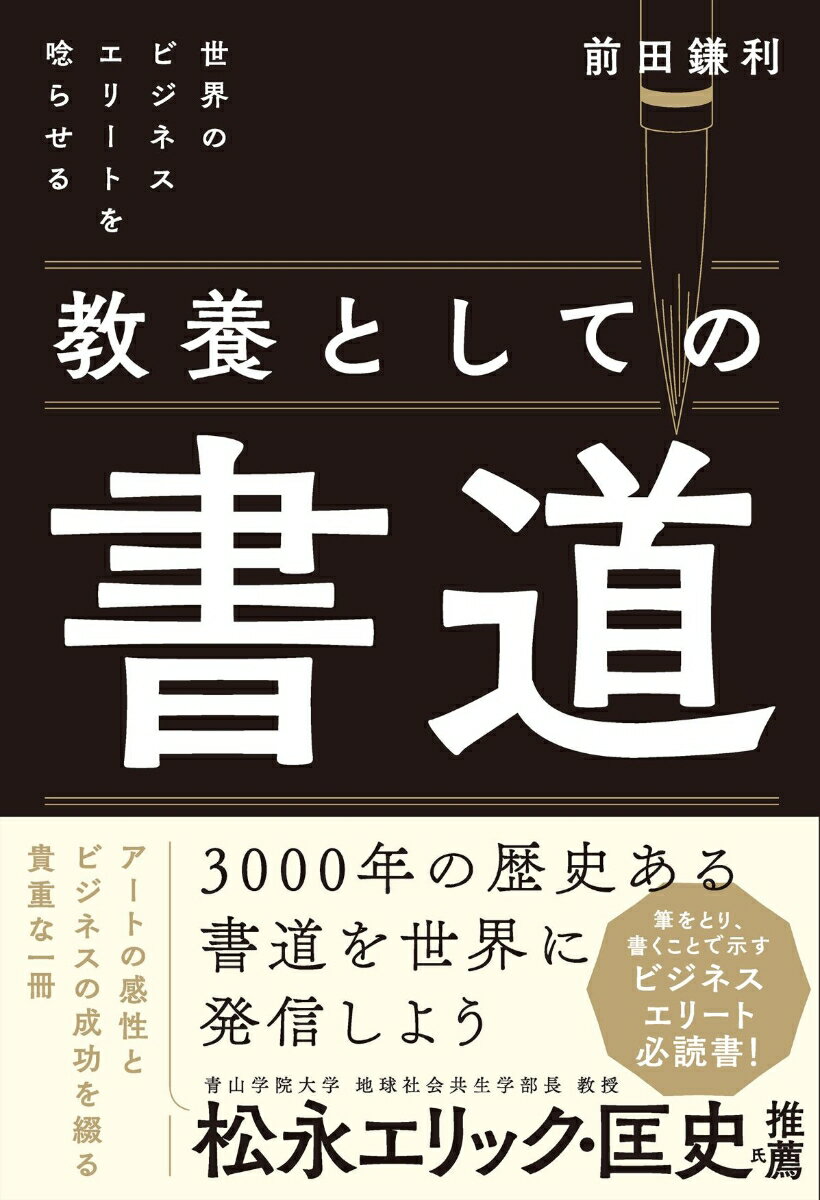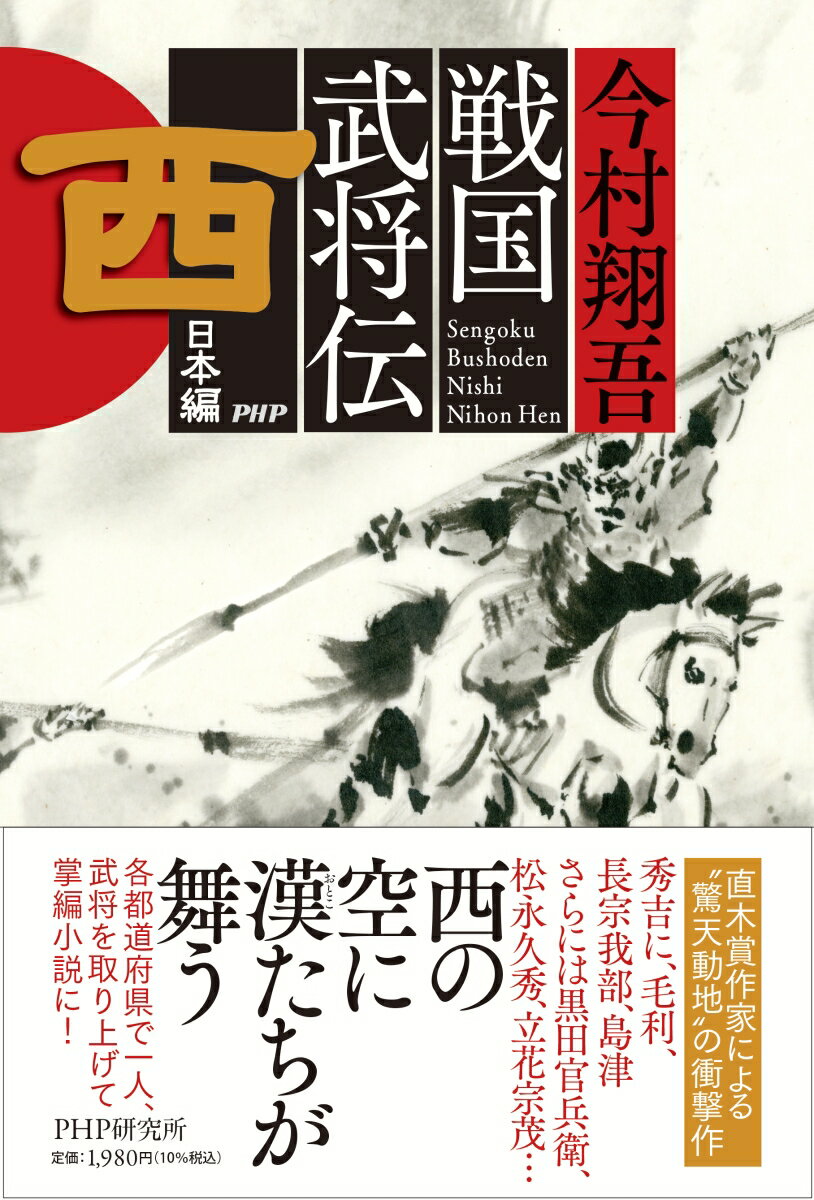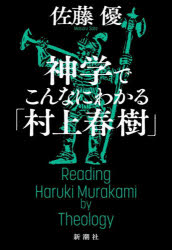「パンチライン」とは名セリフのことです。
誰もが知っている主に漫画作品を主に、その作品の名セリフを日本語の言語学
観点から考察するのが本書の内容です。
しかし本書の面白さはそれだけではありません。
その作品のキモとなる部分の解説には、思わずクスりとさせられるツッコミが
あり、「そういえばそんな場面があったなあ」と思い出に浸ることもできます。
あの「タッチ」の朝倉みなみによる「めざせ、カッちゃん、甲子園」はなぜ、
「カッちゃん、目指せ、甲子園」ではないのか。意味としては後者の方が通じ
るのになぜ?
ガンダムの終盤に登場するジオングの整備士はジオングの脚がないことについ
て、「偉い人にはそれが分からんのですよ」というセリフがありますが、実は
映画版では最後の「よ」が消えているのです。
この「よ」があるのとないのとでは、観る側にどのような印象を与えるのか。
などなど無意識に使っている日本語の奥深さを学ことができる一冊です。
クリックお願いします。