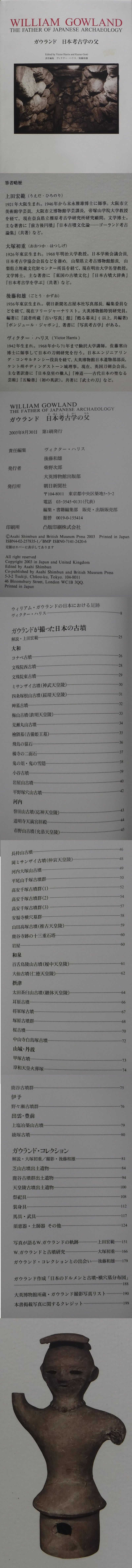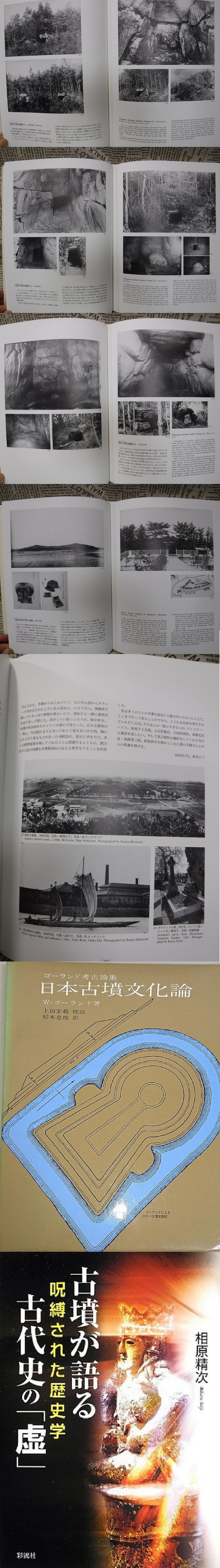・・・本当は、明治大学博物館での特別展を観に行きたかったのですが無理なので、本やDVDでガマンガマン。
《ガウランド日本考古学の父》刊:朝日新聞社 2003.8
https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=1739
編:ヴィクター・ハリス/1942年生まれ。大英博物館日本遺物部部長等を経て、英国刀剣会会長。
編:後藤和雄/1936年東京生まれ。朝日新聞社編集委員などを経て、フリージャーナリスト。
明治の「お雇い外国人」W・ガウランドが残した古墳研究の業績。その独自の史観と当時の日本にはなかった高レベルの考古学研究法を、未公開写真や古コレクションに解説を添え紹介。なかでも天皇陵の資料は貴重。大英博物館との共同出版。英訳付。
《参考》「長持山古墳の石棺」藤井寺市
https://www.city.fujiidera.lg.jp/kanko/kofun/furuichikofungunnoshoukai/koramu/1459337476616.html
藤井寺から出土した石棺としては、津堂城山古墳の長持形石棺と長持山古墳と唐櫃山古墳の家形石棺が有名です。最初に学会に紹介された石棺は、長持山古墳の家形石棺です。この石棺は、同じ長持山古墳からもう1基の別の石棺が見つかったため、2号棺とも呼ばれています。報告者は、イギリス人の★ウイリアム・ガウランドという人物です。ガウランドさんは、明治初期の日本政府が西欧の最新技術を積極的に取り入れるために招へいした専門家の一人だったのです。彼は明治5年に来日し、大阪の造幣局に冶金学の技術指導者として16年間日本に滞在しました。彼は公務のかたわら、日本の今でいう古墳時代の遺跡に大きな興味をいだいたようで、全国各地の古墳めぐりをしています。なかでも大和と河内にはたびたび出向き、詳細な観察記録を残しています。この記録は、イギリスに帰国後、いくつかの論文にまとめられて発表されました。長持山古墳の石棺は、「日本のドルメンとその築造者たち」(原文は英文)のなかで、道明寺近くの墳丘に石棺がほぼ全形を露出していて、まわりを丹念に調査したらガラス玉1個と少量の朱を見つけたと記されています。さらに当時としては貴重な写真が添えられています。この写真を見ると、石棺の3分の1ほどが長持山古墳の墳頂部からせり出しているところが写っています。また、蓋石の縄掛け突起も鮮明に写っており、2号棺の特徴がよくつかめます。2号棺の露出がいつごろ、どのような経緯で起こったのか、つまびらかではないのですが、長持山という古墳の名前もこの石棺に因んだようなので、かなり古くからであったようです。戦後になって、大阪府教育委員会と京都大学が長持山古墳を発掘調査しています。このときゴーランドさんの報告した石棺の北側で、もう1基の別の石棺(1号棺)が見つかったのです。この1号棺とすでに露出していた2号棺とは刳抜き(くりぬき)式であることは共通するのですが、形に違いがありました。一番違っている点は縄掛け突起のつく位置と個数です。2号棺は屋根形をした蓋石の屋根部分に二対計4個が造り出されていたのですが、新しく見つかった1号棺は、蓋と身の両方の小口に大きな突起が一対造られていたのです。(教育広報『萌芽』第7号:平成5年8月号より)
《参考》「岩屋山古墳」明日香村
https://asukamura.jp/chosa_hokoku/iwaya/iwaya.html
大字越に所在する終末期古墳です。周辺には牽牛子塚古墳や真弓鑵子塚古墳、マルコ山古墳等、多くの後・終末期古墳が点在しています。明治時代にはイギリス人★ウイリアム・ガウランドが来村し、岩屋山古墳の石室を調査して「舌を巻くほど見事な仕上げと石を完璧に組み合わせてある点で日本中のどれ一つとして及ばない」と『日本のドルメンと埋葬墳』の中で紹介しています。昭和53年には史跡環境整備事業に伴う発掘調査が橿原考古学研究所によって実施されています。調査の結果、墳丘は1辺約40m、高さ約12mの2段築成の方墳で墳丘は版築で築かれており、下段テラス面には礫敷が施されていることが明らかとなりました。埋葬施設については石英閃緑岩(通称、飛鳥石)の切石を用いた南に開口する両袖式の横穴式石室です。規模は全長17.78m、玄室長4.86m、幅約1.8m、高さ約3mで羨道長約13m、幅約2m、高さ約2mを測ります。壁面構成については玄室が2石積みで奥壁上下各1石、側石上段各2石、下段各3石で羨道部分は玄門側が1石積みで羨門側が2石積みとなっています。天井石については玄室1石、羨道5石で構成されています。こういった構造をした石室は岩屋山式と呼ばれており、奈良県内では小谷古墳(橿原市)や峯塚古墳(天理市)等でも確認されています。特にムネサカ一号墳(桜井市)の石室は岩屋山古墳と同じ設計図(規格)をもとに築造されたと考えられており両者の関係が注目されています。また岩屋山式とされる古墳に使用されている棺については小谷古墳で刳り貫き式家形石棺が使用されており、ムネサカ1号墳でも凝灰岩の破片が多く出土していることから岩屋山古墳でも凝灰岩製の家形石棺が安置されていたと推定されます。排水施設については玄室内の礫敷と羨道の暗渠があります。これは玄室内の水が床面に敷き詰められた礫を伝わって下層にある集水穴に集まり、そこからあふれ出た水が羨道の暗渠排水溝を通って石室外に排水される構造となっています。更に羨門部の天井石には一条の溝が彫られており外から天井石に伝わった水が石室内に入ることなくこの溝の部分で遮るように工夫がこなされています。石室内には古墳以外の遺構として長さ約2m、幅約90cmの中世の土坑墓が検出されており早くから石室が開口していたことが窺えます。このように中世から近世にかけて石室内を二次利用した例は仏塚古墳(斑鳩町)等でも確認されています。石室内からは土師器・須恵器・瓦器・陶磁器・古銭等が出土しており、築造年代については7世紀前半頃と考えられます。被葬者については斉明天皇や吉備姫王等が候補として挙げられています。
《古墳が語る古代史の「虚」呪縛された歴史学》著:相原精次
明治の早い時期に日本の古墳を精力的に調べてまわったイギリス人★ウイリアム・ガウランドが、つぎのようなことばを残している。
日本と似たドルメンに出くわすには、アジアを西に通り抜け、カスピ海沿岸まで行かねばならない。もっとよく似たものを見つけるには、さらに遠く西ヨーロッパまで足をのばさなければならない。
ガウランドは日本を去ったあとも日本の古墳について研究を続けており、イギリスでその成果を論文としてまとめ、さらに日本での経験を生かし、母国での★「ドルメン」を始めとした石造遺跡に関する第一線の研究者となっている。その人物が述べていたことの意味を私たちは改めて考えてみるべきだと思う。
《NHKスペシャル 知られざる大英博物館》2012/ナビゲーター:堺雅人(俳優)
全コレクションの99%が眠る収蔵庫。そこから、新たな歴史の扉がひらく。世界各地の文明が残した偉大な遺産を収めた、世界最大の博物館・大英博物館。しかし、800万点を誇る収蔵品のうち、展示室で公開されているのは、わずかに1%。残りの99%は収蔵庫に眠っています。そして、大英博物館のバックヤードでは、そうした未公開の品々の科学分析をはじめ、最先端の調査研究が、日々続けられています。今回、NHKは、2年半に渡る交渉の結果、大英博物館の知られざる舞台裏の全てを、本格的に取材する許可を得ることができました。そこからは、これまで謎に満ちていた、新たな古代史の真実が明らかになります。
●第1集『古代エジプト 民が支えた3000年の繁栄』
http://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?aid=20120624
古代エジプトの繁栄は、絶対的な力を誇ったファラオにより成し遂げたと言われてきた。しかしそれを覆すのが、大英博物館の収蔵庫に眠る、名もない庶民が残した大量の品々。3000年前のラブレター、子供たちの学習ノート、労働者の勤務表・・・。それらの調査分析から、謎に包まれていた庶民の歴史が生き生きとよみがえってきた。古代エジプト繁栄の鍵を握っていた庶民たちの、知られざる真実を解き明かす。
●第2集『古代ギリシャ “白い”文明の真実』
http://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?aid=20120701
紀元前7世紀に、突如エーゲ海で花開いた古代ギリシャ文明。真っ白い大理石の彫刻や白亜の神殿に象徴されるように、“白い”文明とされてきた。しかし、大英博物館の調査により、その常識が覆りつつある。真っ白だと思われていた彫刻や神殿は、鮮やかに彩られていたことが分かってきた。解明されつつあるギリシャ文明誕生の謎。そして大英博物館で起きた衝撃の大事件。白い文明、古代ギリシャの真実をひもとく。
★第3集『日本 巨大古墳の謎』
http://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?aid=20120708
ピラミッドや始皇帝陵とならぶ世界最大級の墓、巨大古墳。3世紀半ばから350年に渡る古墳時代は、文字資料がほとんどないため、未だ謎に満ちている。その巨大古墳の謎を解く鍵も、日本から遠く離れた大英博物館にあった。明治時代に来日した、一人のイギリス人が日本から持ち帰った膨大な古墳のコレクション。以来、120年以上も収蔵庫に眠り続けてきたコレクションの本格的な調査が、大英博物館と日本の合同チームにより、昨年から始まった。その結果、1500年ぶりによみがえった今はなき幻の古墳。そして、日本独自の進化を遂げた巨大古墳の知られざる実像も浮かび上がってくる。日本の未知なる古代史をひもといていく。
・・・まだまだ多くの事実が収蔵庫などに眠り続けているのでしょう。誰かが保管・保存してくれていたから、たとえ何百年経とうとも調査・研究できるのです。じっくり時間をかけて、コツコツしかないですね。