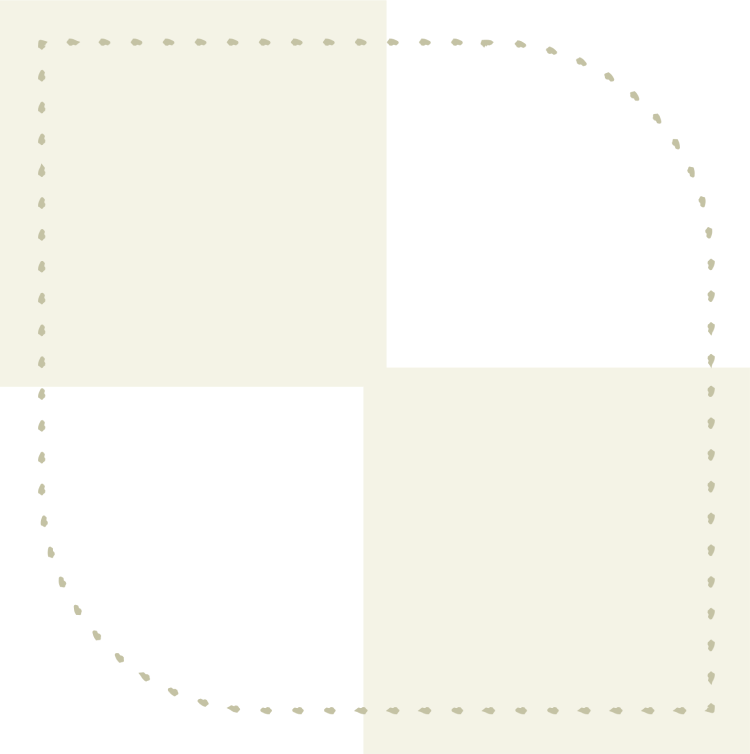初めて現とキスをしたのは、出会ってから半年ほど経った、冬の夕暮れだった。
クリスマスも終わって、人々は急に忙しなく、新しい年を迎える準備に追われていた。
私たちは、現のアパートのすぐ近くの、誰もいない公園のベンチで、学校帰りに寄り道をしている中学生のカップルのように寄り添いながら、遠くで聞こえるカンカンカンという乾いた踏み切りの音に耳を澄ませていた。
「寒いね」
「そうだね」
「もう今年も終わっちゃうね」
「そうだね」
どちらかともなく、こんな意味の無い会話を繰り返していた。
段々と暮れていく陽も、ふたりの間に流れる甘酸っぱい空気も、なんだが全てがくすぐったくて、私は、‘’本当に中学生の頃にでも戻ったようだわ‘’と、ずっとドキドキしていた。
こんなやりとりを一時間ほど繰り返した頃だろうか。現が私の耳元で何かを言った。
「今なんて言ったの?」
よく聞こえなかったので私がそう言うと、現は自分の足元を見つめて、「うん」と小さく頷いた。そして、意を決したように私の体に腕を伸ばした。
現はいつにも増して力強く私の体を抱きしめてから、ゆっくりと私の顔に自分の顔を近づけた。そして、一瞬戸惑ったような表情を見せたけれど、すぐにいつもの柔らかい顔に戻り、我が子を見つめる母親のような、優しくて温かい眼差しで、私の瞳と唇を交互に見ていた。
現の鼻先が私の頬に触れる。
震えている唇が意外で、現の口から漏れる吐息も、ゆっくりと忍び込んでくる舌の感触も、腰に回された手から伝わってくる驚くほど熱い体温も、今感じている現の全てを愛おしいと思った。
私たちは、お互い名残惜しさを感じながら家路についた。
家に戻ると、すぐに台所に立って夕飯の準備を始めた。キャベツをばりばりと剥きながら、私はなんとも言えない切ない気持ちに襲われていた。
現が私のことを大切だと思ってくれているのは、痛いほどによく分かっていた。今日だって、本当に愛おしそうに私を抱きしめてくれていたのがよくわかった。
でも、私が現のことを想うことで、どうすることもできないもどかしい気持ちを現に持たせてしまう。そのことが、現の首を締めているんじゃないかと心配だった。
そのせいか、現と会っている間中、現が私に言って欲しいと思っている言葉も、して欲しいと思っている表情も、全部分かっているのに、いつも素直にそれをしてあげることができなかった。
もっと抱きしめてあげればよかった。もっともっと優しくしてあげればよかった。
いつだって後悔するのは家に着いてからだ。
キスをしたからといって、そんな想いが綺麗さっぱり消えてしまったわけではないけれど、軽くなったのは事実だ。
「結婚しているなんて嘘よ」
重くならないようにさらっと言えばいいじゃない。どうして言えないの?どうして私は言わないんだろう。
真っ直ぐな現に、嘘をついてしまったことがうしろめたいから?本当は義理の両親のことを恥ずかしいと思っているから?
違う違う。どれもぴんとこない。
でも言えない。
簡単なことなのに、本当のことを言ってしまった方が絶対に楽なのに、現のことを心から大切に思っているのに、どうしても言えない。言えない理由が自分でも分からない。
いつもこんな風に自問自答している気がする。
私は、現の私への気持ちがこれからも変わらないでいて欲しいと願っているのか。それとも、本当は現の気持ちが冷めていってしまうのを待っているのか、分からないでいた。