墓を持たない終活の勧め
~そこに大切なひとは眠っていますか?~
健康とお金のこと以外にも生きとし生ける人が持ち続けている現代社会の根本的問題として、お墓と仏壇の継承が日常生活と深くかかわり、同時に、そのことが、将来地球規模で命運の要因をはらんでいることでしょう。マリブハウスでは、お墓と仏壇を持たない終活の勧めとしてその代わりとなる散骨と家系譜を提案しています。
仏壇の代わりの家系譜は下図を参考にしてください。
又、その私案の参考になる事例を紹介します。
お墓の継承事情に詳しい小谷みどりさんの著書『だれが墓を守るのか』の一節の中で、”墓に対する意識は1980年以降大きく変化している。”とあります。例えば、散骨については、1990年に当時の総理府が調査をしたときには「葬法としてはふさわしくない」と考える人が主流でしたが、昨今では、自分や家族の遺骨を海![]() や山
や山![]() などに撒くかどうかは別にして、散骨自体を否定する人は少なくなっています。これまでのお墓の在り方は見栄や世間体、家のしがらみなどに重きが置かれていたが、90年以降「どのように最期を迎えたいか」という自由な視点でお墓を考える人が増えてきたことも、お墓のかたちの多様化につながっています。
などに撒くかどうかは別にして、散骨自体を否定する人は少なくなっています。これまでのお墓の在り方は見栄や世間体、家のしがらみなどに重きが置かれていたが、90年以降「どのように最期を迎えたいか」という自由な視点でお墓を考える人が増えてきたことも、お墓のかたちの多様化につながっています。
昨今は無縁墓が増えており、その無縁墓の撤去も行政が税金で費用を出して撤去しています。お墓を作るのに高額な費用が掛かるのに、お墓を見る人がいなくなり無縁墓になって、行政が税金でお墓の撤去をする。考えてみると、おかしな話です。
また、井上文勝氏が著した『「千の風になって」紙袋に書かれた詩』の「1932年マリー・E・フライによって」と記した原詩を綴ってみました。
私のお墓の前にたたずみ泣かないで
私はわたしはそこにはそこにはいません 眠っていません
私は吹きわたる千の風のなかに
私は静かに舞い落ちる雪
私はやさしい雨のしずく
私はたわわな麦の畑々
私は朝の静けさのなかに
私は美しい鳥たちの優雅な上昇旋回のなかに
私は夜を照らす星光
私は咲き開く花々のなかに
私は静かな部屋の中にいます
私はさえずる鳥たちのなかにも
私は美しい物、ひとつひとつのなかにいます
私のお墓の前にたたずんで嘆かないで
私はそこにはいません 死んでいません
以上が原詩ですが、内容は「人類愛のたまもの」です。
「この詩がすこしでも誰かのなぐさめになるのなら」という純粋な思いだけだったと…。そして、素晴らしい献身的な方ではなかったかと…。井上文勝氏は著書の中に綴っています。この本が2010年2月7日発行された当時千の風になってという秋川雅史さんが唄う歌が大ヒット。その後、徐々に日本中で散骨が広がりをみせてきています。
以上のことから、総括して言えることは、人生の最期は全ての蟠りをなくして迎えるということです。
お墓を持たなくても「あなたの大切な人」は心の中で思っていればいつでもあなたの心の中で会えるとおもいます…
たまにはマリブハウスで、目の前に広がる広大な海を見ながらゆっくりとした時間を「あなたの大切な人」といっしょに過ごしてみてはいかがでしょうか?
120歳まで生き抜く人生を皆さんと共に目指してマリブハウスでは健康長寿のお手伝いをしています。
ぜひホームページをご覧ください。
メールでのお問い合わせもお待ちしてます。



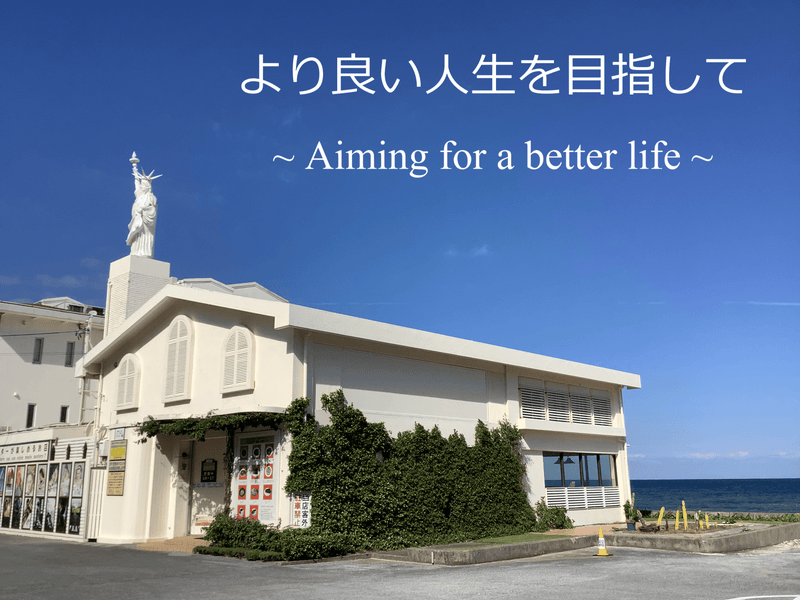
 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら