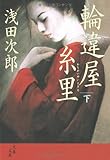浅田次郎先生の「輪違屋糸里」上・下を読破しました!
久しぶりに興奮しました!!
いろんな人物の視点が入り乱れて面白すぎる!
まったく退屈しなかった。
なぜこの本を手にとったかと言えば、この時代の芸妓さんに興味があったということと、京ことばを知りたかったという経緯です。
そしたらなんですか。
私がイメージするところの土方まんまだった!!!
これだよ、これッ!!!←大興奮
古高を前川邸の土蔵にて拷問するシーンで、
みんなが知ってる五寸釘より強烈なことをしてくれちゃってますわ。
ひとーつ・・・
ふたーつ・・・
みっつ!!
・゚・(;´゚д゚)・゚・
・・・こんな土方が猛烈に好き・・・(´Д`;●)
それはさておき、
タイトルからして主眼は糸里なのかと思いきや、
糸ちゃんだったり、吉栄だったり、菱屋お梅だったり、
八木邸の場面ではおまささんの心情が、
前川邸に移ればお勝さんの心の声が。
おまささんは芹沢一派を預かっているので、芹沢さんたちを庇うような発言を。
お勝さんは近藤派に感情移入していたりする。
この二人の認識の食い違いというのが面白い。
さらにはこの間に立って揺れる永倉新八の存在w
永倉はお喋りなもんで、この二人のお母さんらに派閥間で何が起きているのかうっかり口走ってたりw
永倉は神道無念流の遣い手だから、芹沢さんらに親近感を持っているけれども、試衛館で食客でもあった訳だからどちらにつく訳でもなく中立という態度なんですね。それが複雑で永倉自身も葛藤している。
実際、流派ってのは血縁のように強烈な同族意識を生むらしいので。
その中途半端な立場上、試衛館組に警戒されて作戦の仲間内には入れてもらえません。
もし、永倉が完全に試衛館の同胞たちと意を同じくしていたら、読み手もおそらく近藤土方両人の方へ同調してしまうでしょうが、人一倍正義感の強い永倉の視点が入ることで、両派の正しさも誤りもくっきりと浮かび上がってきます。
永倉の語りや心情に加えて、八木家のおまさと対をなすように出てくる前川のお勝の心の動きっていうのもミソですね。
読み進めるうちに感情が入り乱れて行ったり来たりします。
芹沢も横暴で酒癖の悪いロクデナシって思いがちですが、(←私はそう思ってないけど)
誰の目にも触れないところでは繊細だったり孤独だったりする訳です。
新見には新見なりの筋の通し方と水戸の仲間内を守るための算段を用意していたり。
水戸者でない平山も芹沢派の一人ではありますが、子分というよりはどっちかというと馬が合うから一緒にいるというようなもんで、言ってしまえば騒動の犠牲者のような書き方でした。
桔梗屋の吉栄と懇ろな平山さんも、質素だけどささやかな家庭を持つという平凡な夢を思い描いている。空想を思い描くように語る寂しさにグッときます。
元が百姓だった近藤・土方にしてみれば、水戸郷士の芹沢は威風堂々の立派な士であり、この人物を越えなければずっと家来のままだという卑屈さがあるんでしょうけど、芹沢もどこか欠落した不完全な人間であり、決して豪胆で怖いもの知らずという訳ではない。
その辺りの綻びみたいなものが、お梅という俄かな愛人の目を通して語られるのですが、これがまたしんみりしてしまうんですよね。世に打ち捨てられた可哀想な二人みたいな感じで。
みんながみんな、不器用なただの人間なんですよ。
身分だとか肩書きとか関係なく、心の暗い部分を映し出せば
ただただままならない人生を歩んでいる普通の人間で。
その中にあって心を殺しながら炯眼を光らせているのは土方独りですが、
この土方も心の内こそ語らないけど、
個の欲望のままに生きたいという正直な思いを最後に吐き出す。
それがもう情けなくってね・・・w
最後の最後でビックリしましたけどwww
あれだけ冷血漢であった男がこんなことを言い出すのかと目を疑いましたがw、
それはそれで面白かったwww
外側へ向かって表現する自分と、内側で思ってる自分との差異が激しすぎてw
そういう天邪鬼な土方にいいように使われて翻弄される糸ちゃんですが・・・
この子が健気でいけねぇやw
ここまで尽くす相手じゃないよ、土方さんはw
惚れた弱みとかそういうのを遥かに超えたような大きすぎる愛です。
でもね、糸ちゃんより吉栄やお梅さんに感情移入してしまった。私。
芹沢派と近藤派の苛烈な対立の中で女たちも荒波に呑まれるんですが、
糸里の愛し方(土方)、吉栄の選択(平山)、お梅の生き方(菱谷・芹沢)というそれぞれの視点があって、読み手はどれかに共感できる部分がある。
それは不幸の度合いを比べるというものではなく、ただ純粋に男を愛した結果おのおのが出した答えというところに帰結するんだけど、みんな失ったものは大きくて心にどっしりきた。
だけど潔く運命を受け入れるところに女の強さを感じました。
余談ですけど、
沖田総司の小説を怒涛の勢いで読んでいる私が
浅田先生の小説を読んで気づいたこと、
従来の総司のイメージを叩き斬ったねw
個人的には司馬先生や大内先生のところの総司が好きなので、
沖田が「俺」とかいうのに慣れてないw
それにこれまた個人的なイメージですが、
沖田はそうそう色事に手を出すタイプではない、むしろ晩生な奴です。
だから、芹沢とお梅が同衾して事に及んでいる
間ずっと塀の向こう側で息を潜めて原田と待機しながら、
「気を遣った後とやる前じゃどっちが(ry」なんて疑問を持つはずないしwww
そんなんよう言わんやろ!って思うw
いや、でもこういう総司も良いですけどね。
ただ、自分的には一人称は「私」が好きだし、丁寧語で時に土方を狼狽させるくらいの洒落っ気のある沖田が大好物なんでね。
他にも「俺」発言の小説はあったと思うけど・・・忘れた。
(↑戸部先生のとこの沖田でした。この作家さんの小説もすごーく面白い!)